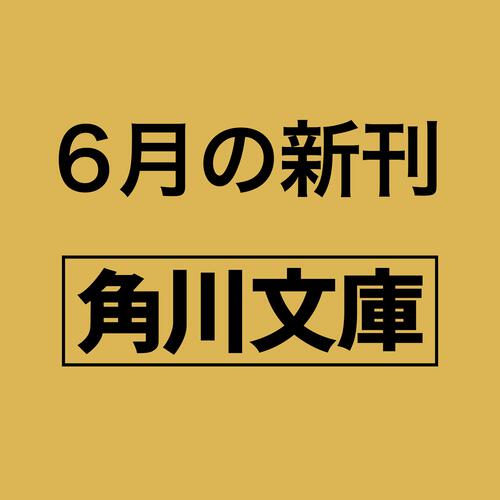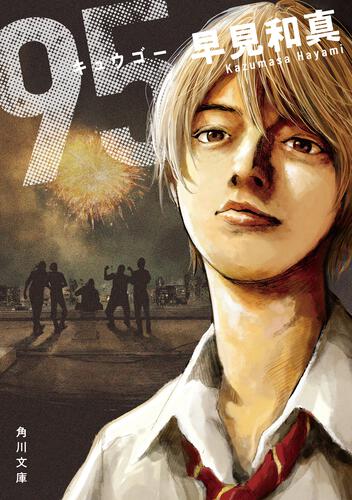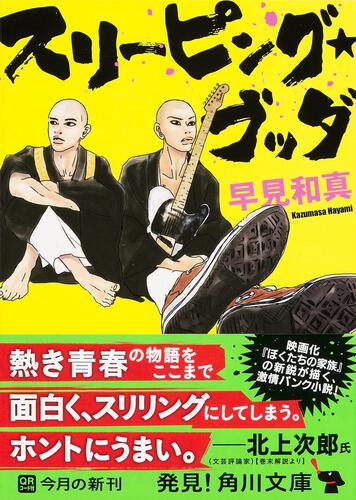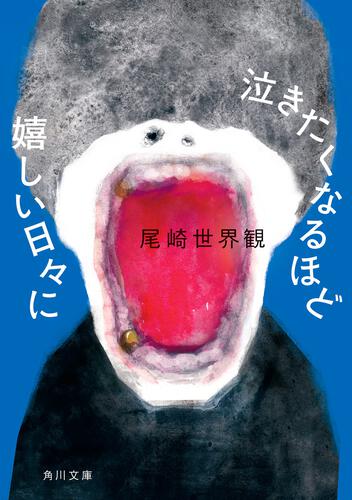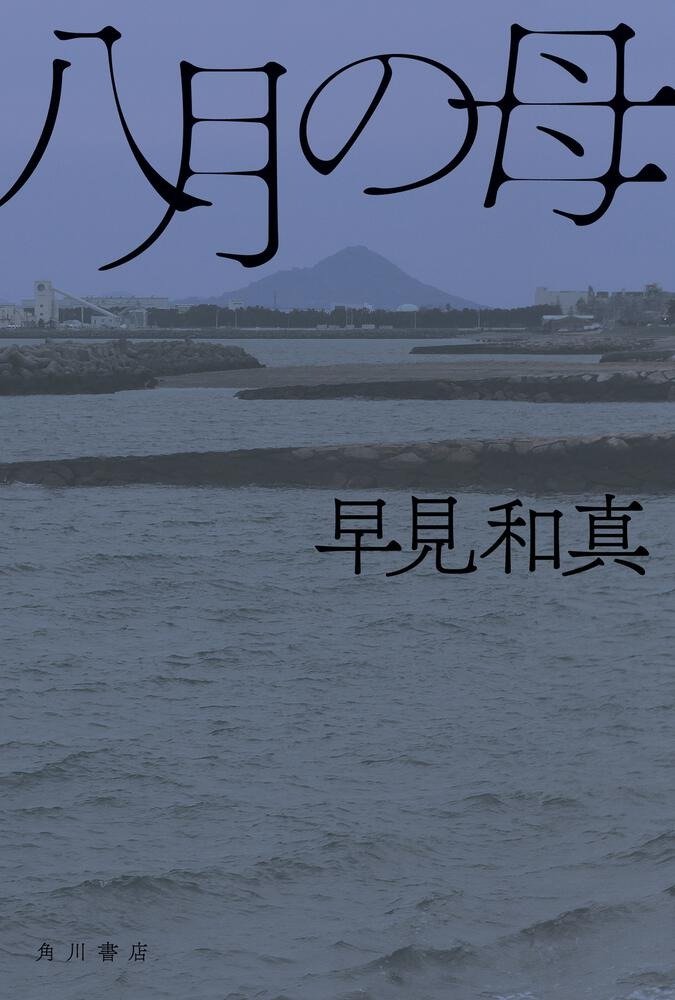愛媛県伊予市で起きた凶悪事件をもとに、押し付けられた母性を描いた早見和真さんの『八月の母』。文庫化を記念し、早見さんとミュージシャン・作家の尾崎世界観さんの対談をお送りします。なぜ早見さんは尾崎さんと『八月の母』の話をしたかったのか。そこには尾崎さんのデビュー作『祐介』への圧倒的な共感がありました。
構成・文/清 繭子 撮影/橋本龍二
早見和真×尾崎世界観 『八月の母』文庫化記念対談〈前編〉
何者でもない自分に戻って読めた
尾崎世界観さん(以後、尾崎):『八月の母』は久しぶりに純粋な気持ちで読めた小説で、それがうれしかったですね。今は本を読むことが仕事でもあるし、作者はライバルでもあるので、なんなら「つまらなくあってくれ」という気持ちで読んだりもしてしまうんです。でも、この小説は違った。まだバンドが売れていない頃、お金がないから図書館で本を借りて、それを自転車のかごいっぱいに詰めて、重みにふらつきながら家に帰った、あの頃の読み心地でした。
「この小説があってよかった」とも思いました。主人公が堕ちていくときに、でもきっとどこかで止まるんだろうという期待を裏切ってくれる。そうした残酷さがちゃんとあるし、それがないとたどり着けないところに連れていってくれました。ほんとに純粋に、この小説の読者になれてうれしかったですね。
早見和真さん(以降、早見):本当に、本当にうれしい感想です。今回、明確に「この人に届けたい」と読者を決めて書きました。それは、深夜2時、歌舞伎町のドン・キホーテにいた、キティちゃんのつっかけを履いて赤ん坊を抱えた女性。こういう人たちに届くものを書かなければダメだ、という思いは常にあるのですが、こんなに具体的に読者を定めたことは今までなくって。今回こそ、と思って書いたんです。でも、やっぱり理路整然とした論評ばかりが聞こえてきて、まさにあそこに届いてるっていう手応えが感じられなかった。だから、何者でもなかった尾崎さんに戻って、いち読者として読んだ、という今の感想がうれしい。
今回、なぜ尾崎さんとお話ししたかったかというと、尾崎さんのデビュー作『祐介』に圧倒的な共感を抱いているからなんです。たぶん日本の小説家のなかで僕がいちばん『祐介』に共感していると思う。当時、すでにクリープハイプとして成功していたのに、世の中に認められてない怒りや渇きをあそこまで書けることに興奮しました。
尾崎:デビューするまでは世の中に見つけてもらえないという悔しさばかりがあったんです。それが、デビューしてある一定のところまで届くようになったら、もっと上があるのが見えだしたせいで、デビュー前より具体的、立体的に足りなさが出てきました。それが結構しんどくて。そんな中、レコード会社の移籍問題、声の不調など、いろんなことが起こって、もう一回どうにか立ち上がるために書いたのが『祐介』でした。過去の自分、まだ何者でもなかった自分にもう一度縋ったというか。あのとき音楽に初めて行き止まりを感じたんですね。さらにそんな中でもある程度やれてしまえることが苦しかった。そこで、「小説」という自分ができないものを始めることによって、救われたんです。
早見:その気持ちが『祐介』にちゃんとにじみ出ています。僕のデビュー作は『ひゃくはち』という高校野球の話なんですけど、文庫版でかなり改稿しているんです。単行本版ではもう行間ごとに「俺はここにいる!」って叫んでいて、自意識過剰なだけだった。けれどやっぱり単行本のほうが好きだっていう読者も一定数いるんです。あの初期衝動が『祐介』にはそのままありますよね。
尾崎:自分の場合は、担当編集者さんに「直しちゃダメ」と言われました。これはそのまま残してほしいと。その代わり、文庫版には書き下ろしで新作を入れることになりました。
美輪明宏さんの忘れられない言葉
早見:僕、大学に7年も通って、しかもまた留年して、もらっていた新聞社の内定を取り消されているんです。そこから紆余曲折があって出版社でバイトしながら小説を書き始めるんですけど、そのときの周囲の視線が忘れられません。「あいつ小説とか書いてるらしいぜ」「やばくね?」って、ひょっとしたら自意識過剰だったのかもしれないけれど、冷ややかな視線を常に感じていました。その周囲の目にいつもイライラしていたし、ガワ(側)でしかものを見ない人たちだって憤っていて。
そんなあるとき、バイト先の出版社が瀬戸内寂聴さんと美輪明宏さんの対談集を刊行して、美輪さんのサイン本を作るのに駆り出されたことがあるんです。美輪さんがいらっしゃったパレスホテルの部屋の戸を開けたら、開口一番「あなたいい顔してるわね」っておっしゃって。呆気に取られていた僕に向けて、さらに「でも、社会に対して不満があるでしょ? 1つアドバイスしてあげる。あなたはこれから、いま自分の周りにいてほしいと思う大人になりなさい」って言うんです。
その言葉に僕はいまだに縛り付けられている気がします。たまに地方の高校に講演で呼ばれて行くんですけど、そこで出会う子たちの中には講演後も一定数連絡をくれる子がいて、その子たちからの連絡には真摯に対応しています。どんなに面倒くさい相談であったとしても、あの頃の僕が必要としていたのは「ちゃんと見てくれている大人」と思わせてくれる大人だったと思って。やっぱり美輪さんの言葉に縛られているんです。
尾崎:自分は10代の頃、こういう厳しい現実を突きつけるような小説にすごく救われていました。あの頃のような登場人物に、今回久しぶりに出会えたので、「あ、いるな」という懐かしさと安心がありました。そこから何が得られるんだって言われると、はっきりこれだとは言えないけれど、ただ、そういう世界が書かれていることで自分は留まれるというか。
そして『八月の母』では脅威として親が描かれている。それが当時読んでいた作品との大きな違いです。自分はそこまで親との関係に悩んだことはないのですが、親でなくても分かり合えない人っている。言葉ではどうしようもない獣と対峙するような。
最近、「ブレイキングダウン」(朝倉未来が主宰するアマチュア総合格闘技大会)のオーディションなんかを見ていると、もう言葉じゃどうしようもないんだなと思うんです。自分は言葉を使っているからこそ、この人たちの前では無力だって。そういう相手がいるのを知ることってすごく大事なんですよね。「ここから先は、どうしようもない」ということを。自分は読書でそういう体験をしたいんです。言葉じゃどうにもならないことが、言葉で書かれている……。そこにすごく惹かれるし、モンスターのように描かれた人物に対する救済でもあるように思います。
早見:ありがたいです。僕程度の書き手が物語で誰かを救おうとする傲慢性は常に感じていながら、それでもあのドン・キホーテにいる若いお母さんに自分が何を願ったかというと、「どうか少しでも俯瞰の目を持ってほしい」ということだった気がします。彼女たちはおそらく超近視眼的に生きている。小説にはやっぱり自分自身を一歩引いて見させる力があると信じているので。
そこで『祐介』に出てくる男性の暴力性、加害性の話につながるんですけど、僕は『八月の母』に出てくるクソ男はぜんぶ自分の分身だと思っています。なにかひとつ歯車が狂えば、俺はこいつにもなったし、こいつにもなった。書くたびそれを突きつけられて、自傷行為のように辛かったです。
尾崎:でも、男性側がすごくのっぺらぼうに見える感じが好きでしたけどね。あくまでも女性たちに委ねて、託していて、男性側からはその行為だけしか見えてこないというか。『祐介』でも、あえて主人公の顔が見えないように書いたんです。セリフもほとんどない。自分の中にはやっぱり女性の強さに対するあこがれや甘えがあって、バンドで作る曲も大きなテーマを書くときは女性目線で書くことが多いですね。男性目線では届かないだろうって。
たとえ今日だけの逃げ場所であっても
尾崎:あと、やっぱりこの団地の部屋の描写がすごかったです。自分も地元で毎日のように友達の家に入り浸ってて、あの頃をまざまざと思い出しました。ドアを開けた時の空気で、今どんな状況かをなんとなく察知するあの感じ。
早見:あの部屋は逃げ場所の象徴として書きました。べつに不良のたまり場でなくっても、ああいう場所は存在する。たとえば、引きこもっている中学生がいるとして、今日家を出て学校に行かなきゃ人生ダメになるって思ってる。だけど、今日だけ、もう1日だけここにいてしまう、その繰り返しだと思うんです。そんな「今日だけ逃げてしまう人たち」は僕を含めていっぱいいると思うんです。
尾崎:そうですね。それが本当の解決策ではないというのは、本人もわかっているんですよね。そのどん詰まりが色でも見えてくる。こう煙が充満していて、空気が重い感じというか。あれがわからない人ももちろんいるじゃないですか。
早見:「そんなとこ行かなきゃいいじゃん」って言えちゃう人たち。
尾崎:そう。後半はとくに、自分もその部屋にいるような感覚で読んでいましたね。自分はどこに座ろうか、どのポジションでいようか、と探しながら読んでいました。
早見:尾崎さんも歯車がひとつ狂ったら、あの部屋の地べたに座っていたと思いますか。
尾崎:はい。それはものすごく。でもやっぱりどこかで、そういうところにいる人たちに寄り添える限界もわかっています。
早見:これは本当に失礼な質問なんですけど、クリープハイプの曲はある種、若い子たちにとってあの団地の密室の役割を担っている面もある気がするんです。クリープの本質を掴まずに、歌詞の一節に単純化された「救い」という名前の逃げ場所を見出してしまっている可能性もなくはない。そことはどう折り合いをつけているんでしょうか。
尾崎:好きに捉えてもらって構わないと思っています。音楽って「足りない」んですよ。圧倒的に。メロディーがあって、リズムがあって、そこに短い言葉を乗せて吐き出しているので。そういう伝え方をしているこっちも悪いのかもしれない。一番美味しいところだけ食べて、苦手なものは残す人もいて、自分だってそうです。それで全く違う風に勘違いされていても、ほんとにその人が救われているのなら、逆にその責任を取りたいと思っています。
早見:腑に落ちました。その中にも本質的に尾崎さんの訴えようとしていることを受け取る子もいるに決まってますしね。僕は「また届かなかった」って、この15年、無力感を感じ続けているんです。だから尾崎さんがうらやましいし、かっこいいなって思う。
尾崎:届いていると思いますよ。『八月の母』を読み終わった時、寂しいと思ったんです。登場人物みんなに「お疲れさま」って、声をかけたくなるような気持ちというか。それだけ届く小説だと思っています。
プロフィール
早見和真(はやみ・かずまさ)
1977年神奈川県生まれ。2008年『ひゃくはち』で作家デビュー。同作は映画化、コミック化されベストセラーとなる。15年『イノセント・デイズ』で第68回日本推理作家協会賞(長編及び連作短編集部門)を、20年『ザ・ロイヤルファミリー』で第33回山本周五郎賞と2019年度JRA賞馬事文化賞を受賞。その他の著書に『スリーピング・ブッダ』『東京ドーン』『ぼくたちの家族』『小説王』『アルプス席の母』『問題。以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』『ラストインタビュー 藤島ジュリー景子との47時間』『さらば! 店長がバカすぎて』など。
尾崎世界観(おざき・せかいかん)
1984年東京都生まれ。2001年結成のロックバンド「クリープハイプ」のヴォーカル・ギター。12年、アルバム『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』でメジャーデビュー。16年、初の小説『祐介』を書き下ろしで刊行。その他の著書に『苦汁100%』『苦汁200%』『泣きたくなるほど嬉しい日々に』『私語と』など。2020年『母影』に続き、2024年『転の声』でも芥川賞候補に選出された。
〈衣装〉
・agnès b.のジャケット¥77,000 (11月発売予定)(アニエスベー / 0120-744800)
作品紹介
書 名:八月の母
著 者:早見 和真
発売日:2025年06月17日
連綿と続く女たちの「鎖」を描く、著者究極の代表作
八月は、血の匂いがする――。愛媛県伊予市に生まれた越智エリカは、この街から出ていきたいと強く願っていた。男は信用できない。友人や教師でさえも、エリカを前に我を失った。スナックを営む母に囚われ、蟻地獄の中でもがくエリカは、予期せず娘を授かるが……。あの夏、あの団地の一室で何が起きたのか。嫉妬と執着、まやかしの「母性」が生み出した忌まわしい事件。その果てに煌めく一筋の光を描いた「母娘」の物語。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000654/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら
▼早見和真『八月の母』特設ページはこちら レビュー・動画など関連情報が盛りだくさん
https://kadobun.jp/special/hayami-kazumasa/hachigatsu/
▼プロローグを一気掲載『八月の母』試し読みはこちら
https://kadobun.jp/trial/hachigatunohaha/eh3ibsm32hc8.html