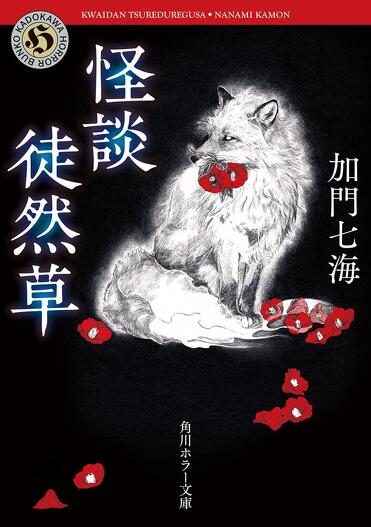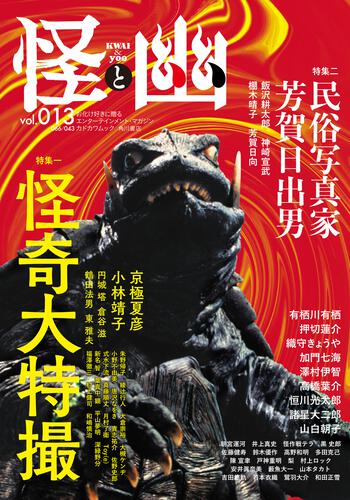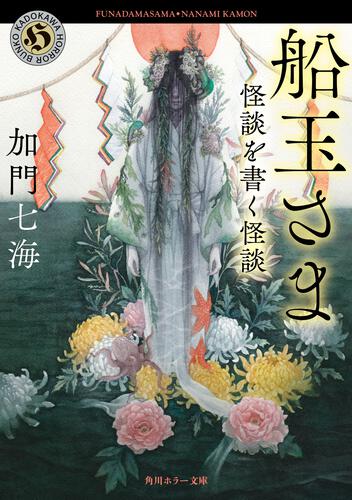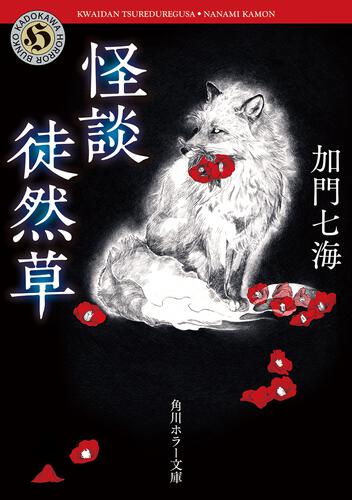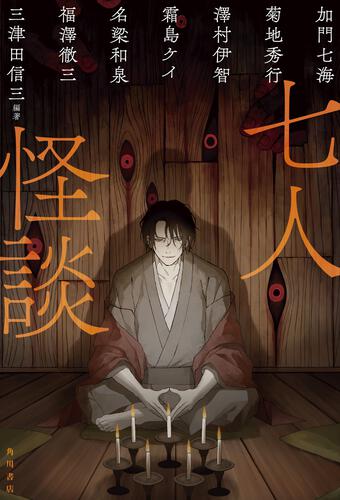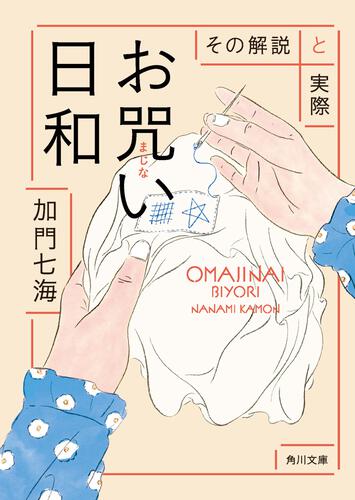平安後期、社会が変わり始めた頃に一人の俊英が現れた。その名は
取材・文:門賀美央子 写真:冨永智子
『神を創った男 大江匡房』加門七海インタビュー
「大江匡房? 誰それ? って思いますよね(笑)。平安時代の文学や歴史によほどの興味でもない限り、名前すらピンとこなくて当然です」
著者すらそう認める人物について、プロフィール風にまとめると次のような感じになる。
大江匡房(おおえ‐の‐まさふさ)[1041〜1111]平安時代後期の貴族。学者、歌人。博学で
頭が良く物知りだったおかげで出世をとげた貴族。大雑把にまとめるとこうなるだろうか。だが、本当はそれだけでは終わらない、と加門さんは言う。
「一見地味で、同じく平安期の俊才として名を残す菅原道真公や
加門さんがそう気づいたのは、もうずいぶん前になる。
「私は昔から伝奇や説話、さらに『
匡房の言動が後代にどれほど強い影響を残したのか、その点については第一章「神を創った男」と第二章「鎮魂の技術者」で詳らかにされる。書名にもなった「神を創った男」というのは、決して大げさな煽り文句ではないのだ。
「そのくせちょっとしたエピソードには妙な可愛げがある。なんだか不思議な人なんです。こういう男、好きだなとどんどん惹かれていって、気づけば虜になっていました」
政治的な安定期が比較的長く続き、国風文化が花開いた平安時代。匡房が生まれたのはちょうどその「終わりの始まり」の時期だった。長らく絶対権力をもって君臨していた藤原頼通は匡房33歳の年に死去し、藤原氏の全盛に陰りが見え始める。けれども、まだまだ朝廷を牛耳る存在であり、他の氏族は圧迫されていた。
そうした中、匡房は才知を武器に権中納言まで昇っていく。菅公のように藤原氏から目の上のたんこぶとして排除されてもおかしくなかったのに、うまく立ち回って着実に出世していったのだ。
「彼は行政官としてとても優秀で、難しい制度改革や治安維持などをきっちりやってのけました。でも、派手な表舞台には立たないんです。権力の脇にいることによって影響力を行使するタイプでした。昨年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』に大江広元という人物が出てきましたよね。彼は矢面には立たないけれど、要所要所でフィクサーとして重要な役どころを担っていましたが、あれと同様と思ってもらえればいいでしょう。この手のタイプは歴史上たくさんいたでしょうが、その中でも突出してるのが匡房だと思います」
だが、そこまでの人物がなぜあまり知られないまま現在に至っているのだろうか。
「一つは〝学問好きの文人〞としての立ち位置を崩さなかったのが理由だと思います。彼はやりたいことを自由にやって楽しめればそれでよかったようなんです。完全にオタク気質なんですよ。たとえば、出世してちょっとお金持ちになって最初にやったことが広大な土地を購入して文庫、つまり書物専用倉庫の建造でした。これって、本好きなら誰もが夢見るところじゃないですか。また、
匡房の道真オタクっぷりを熱く語る加門さんの匡房オタクっぷりがもっとも炸裂しているのが第三章「『野馬台詩』開封」だ。
『野馬台詩』とは、9世紀初め頃に中国から伝来したとされる十数行の漢詩なのだが、素直に読んだだけでは意味が通らない。そのため、近代に至るまで未来を予言する神秘的な詩と信じられてきた。そして、そのイメージ形成に一役買ったのが匡房だったのだ。
「古代史において篁や菅公に並ぶ秀才に
吉備真備が留学生として渡った唐で、時の権力者からひどい目に合わされるのを阿倍仲麻呂の亡霊とともに乗り切ったとする物語が『江談抄』にある。
「真備は、匡房さんにとって篁や菅公に並ぶお気に入りだったのだと思います。似た者同士の共感、でしょうか。でも、おそらくこの逸話はそれだけじゃない。私は『野馬台詩』そのものの謎を解く手がかりが隠されていると思うのです」
詩の内容自体は『江談抄』の中で一応読み解かれてはいる。だが、記述通りに文字を追っていくと、ある図形が浮かびあがってきた、と加門さんは言うのだ。それを見て直感した。『野馬台詩』は古人が仕掛けた数学的パズルではないか、と。
「気づいた時はもう本当に小躍りするぐらい嬉しかったですよ。でも、あまりにもマイナーなので人に言っても全く反応が返ってこない。その悔しさが本書を出す動機のひとつになったのは確かです(笑)。また、私が匡房さんってすごいよねって言ったときに、そうだよねって答えてくれる人が増えるといいなっていう気持ちもあります。つまり、本書は私にとっての〝匡房布教本〞なんです」
『野馬台詩』パズルがいかなるものか、それを限られた誌面で説明するのは相当困難なので詳細はぜひ本書を読んで確かめてほしいのだが、大江匡房という稀代の才人にして元祖オタクが仕掛けた謎には驚くばかりだ。
「歴史上に彼がいなかったら、後の文化はずいぶん変わっただろうと思います。私の好きなものって全部匡房さんが創ってないですか? みたいな感じで、すごくしてやられた感があるんですよ。それに、匡房さんを調べていくうちに、大江一族の秘密に迫れたところもありましたし」
史書や古伝をていねいに読み、断片を拾い集めながら、見えない背景を想像し、全体像を構築していく。一般的な学術研究では言えないことやそもそも研究対象にならないことはたくさんあるけれども、知的遊戯としてとてつもなくおもしろい。
「私は研究者ではなく、素人です。でも、その素人の視点からやれることをやれるだけやった自負はあります。もし本書がきっかけになって匡房さんに興味を持つ人が増え、研究が盛んになると嬉しいところです。選挙運動じゃないですけれど『大江匡房、大江匡房をよろしくお願いします!』って気持ちなので。ぜひミステリアスな歴史が好きな方々に読んでもらいたいですね」
※「ダ・ヴィンチ」2023年7月号の「お化け友の会通信 from 怪と幽」より転載
プロフィール
かもん・ななみ
東京都生まれ。多摩美術大学大学院修了。美術館の学芸員を経て、1992 年『人丸調伏令』で作家デビュー。著書に『呪術の日本史』『お咒い日和』など多数。また、モデルとなるコミックに『七海さんのオバケ生活』(みつつぐ作画)、『怪奇心霊語り』(JET 画)などがある。
書籍紹介
『神を創った男 大江匡房』
加門七海 笠間書院 2860円(税込)
秀でた官人で時代を代表する文人として活躍する一方で、呪術や陰陽道にも深い関心を示し、古人の伝説形成に関わった理由はなんだったのか? 滅亡の未来を予言するという『野馬台詩』の読解に込められた秘密とは? 謎多き人物に史実を元にした大胆な推理で迫る。
▼こちらも注目!
『船玉さま 怪談を書く怪談』
加門七海 角川ホラー文庫 792 円(税込)
怪談実話のパイオニアが綴る恐すぎる実体験。書かれた“怪”は“怪”を招く。「この手のものを書こうとすると寝た子を起こすごとく怪異は甦って禍を呼ぶ」(本文より)。書き下ろし含む全13 編。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322109000590/
amazonリンクはこちら
『怪談徒然草』
加門七海 角川ホラー文庫 880円(税込)
別格の恐怖。封印された三角屋敷の恐怖を再び―。「怪談の神髄は語りにあり」というコンセプトで編まれた本書。軽妙な語り口に騙されて読み進めると……真の恐怖、ここにあり。解説は東雅夫。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322204000278/
amazonリンクはこちら
『怪と幽』紹介
好評発売中!
『怪と幽』vol.013
KADOKAWA
特集1 怪奇大特撮
特集2 民俗写真家 芳賀日出男
小説:京極夏彦、有栖川有栖、山白朝子、恒川光太郎、澤村伊智、織守きょうや
漫画: 諸星大二郎、高橋葉介、押切蓮介
https://www.kadokawa.co.jp/product/322201000342/
amazonリンクはこちら