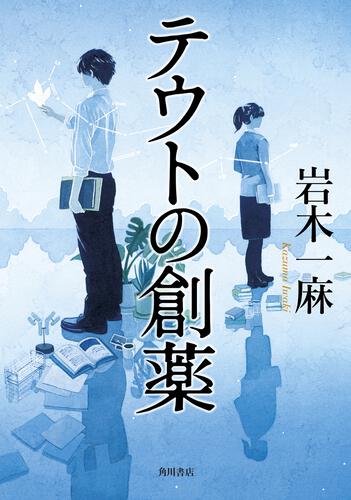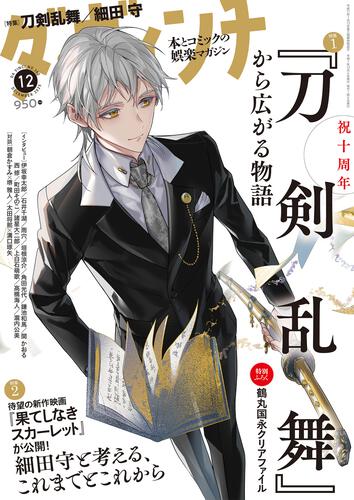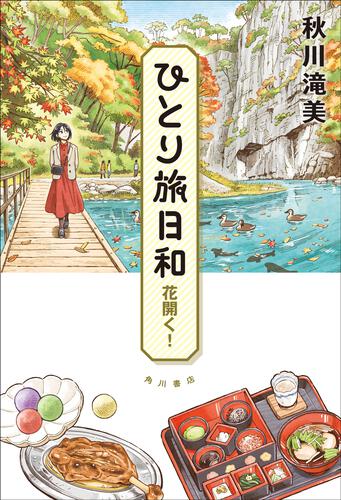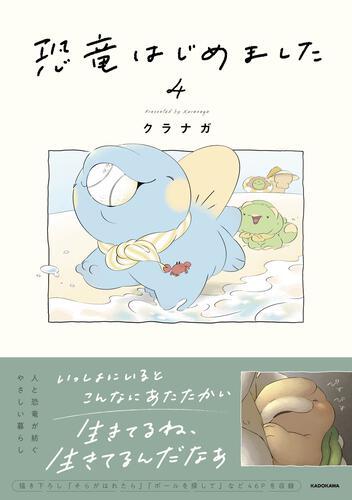「このミス」大賞受賞作家・岩木一麻の新刊、リアル創薬業界小説『テウトの創薬』発売!
著者特別寄稿「急成長するバイオベンチャーの見分け方」をお届け!
新型コロナウイルス感染症のパンデミックで世界的にも注目される創薬業界。このたび刊行の小説『テウトの創薬』は、その新薬開発に賭けるバイオベンチャー企業を舞台にした小説です。
第15回「このミステリーがすごい!」大賞受賞作家であり、国立がん研究センターでの実務経験もある著者・岩木一麻さんが、小説の主人公・進藤颯太郎の口を借りて「急成長するバイオベンチャーの見分け方」をコッソリ教えます。
急成長するバイオベンチャーの見分け方
執筆者:岩木一麻
はじめまして。バイオベンチャーを舞台にした企業小説、『テウトの創薬』(KADOKAWA)が二〇二二年三月に発売されました。僕は、作中に登場するバイオベンチャー企業「トトバイオサイエンス」研究開発部長の進藤颯太郎と申します。
作品は、実在するバイオベンチャーや製薬会社社員、医師への取材を通して、バイオベンチャーの魅力や、抱えている問題、新薬の種類や開発の仕組みなど、バイオベンチャーというホットでありながら実態がほとんど知られていない業種について、一通り理解できるように描かれています。
今日は、「急成長するバイオベンチャーの見分け方」というテーマでお話しさせて頂きます。もちろん簡単なことではありませんが、僕のこれまでの経験に基づいて、いくつかのポイントを押さえていきたいと思います。
製薬業界ではバイオベンチャー企業が、益々その存在感を増しつつあります。コロナ禍で誰もがその名を毎日のように耳にするようになった、ファイザーワクチンとモデルナワクチンのうち、ファイザーは世界最大の大手製薬企業ですが、ファイザーワクチンの起源会社であるバイオンテック(ビオンテック)はドイツ発のバイオベンチャー企業です。モデルナもアメリカのバイオベンチャーとして二〇一〇年に創業した、まだ若い企業なんです。
コロナワクチンは、ほんの一例に過ぎません。近年、世界で承認される新薬の多くがバイオベンチャーを起源とするもので、新薬のほとんどが大手製薬企業の研究室でその産声を上げていた一昔前とはずいぶん様子が変わりました。
バイオベンチャーは、どうして時代の寵児となったのでしょう。若い企業に勢いがあり、大手企業は年老いている、といった単純な話ではなく、技術の発展によって創薬パラダイムがシフトしたことが大きな原因です。昔は、患者さんの多い病気に対する高い安全性を持つ薬を開発するのが基本的なパラダイムでした。小さくて飲み薬に適していることが多い大量の低分子化合物の中から、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たると言ったら言い方が悪いですが、総当たり的に病気に効果のあるものを選び出していました。大規模な臨床試験によって有効性と安全性の確認が必要で、当然、開発には長い時間と多額の費用がかかる。大手製薬企業でなければ、新薬の開発は難しい状況がずっと続いていました。
ところが、分子生物学の発展により状況は変わりました。抗体医薬品や遺伝子治療薬を使って、最初から病気の原因となるタンパク質や遺伝子を狙い撃ちすることが可能になったんです。これにより、特定の患者群に対して、高い効果を発揮する新薬を目指す流れが生まれました。また、各国の規制当局も、オーファンドラッグと呼ばれる希少疾病に効く薬の開発を優遇する制度を次々と打ち出して、希少疾病に対する新薬が次々と世に送り出されています。こういった特定の患者さんに対する新薬の開発では、小回りの利くバイオベンチャー企業の方が、大手製薬企業よりも効率的に開発が進められることが多いんです。
大集団ではなく、より小さな患者集団や個人を見つめ、創薬に繋げる。これが、バイオベンチャー台頭の大きな原動力になっています。集団よりも個性に注目するという世の中の流れが、創薬にも生じているのは素晴らしいことだと思います。今は、バイオベンチャーの黄金期と言って良いでしょう。
革新的な技術はバイオベンチャーのキモです。では技術が優れていれば安泰なのでしょうか。『テウトの創薬』に登場する「トトバイオサイエンス」は、カイコを使った抗体医薬品の生産を技術基盤としています。昆虫の成長速度とタンパク質合成能力は桁外れで、カイコを用いることで高価な抗体医薬品を安価に大量生産できます。ところが、昆虫を利用した医薬品製造は前例がなく、医薬品の許認可を行う独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)はトトバイオの抗体医薬品の開発に対して慎重な態度を示しました。医薬品の安全性を考えればやむを得ない対応ですが、革新的な技術があるからといって優れた新薬の実用化につながるわけではないのです。現実世界でも、蛾の細胞を利用したインフルエンザワクチンの承認が下りなかったことがあります。また、カイコを用いた抗体医薬品の生産を目指すバイオベンチャーは実在しています。プレスリリースなどからはPMDAの慎重な姿勢に真摯に対応する会社の努力がひしひしと感じられます。「トトバイオサイエンス」はその会社をモデルにしてはいませんが、養蚕の復活でバイオ医薬品の貿易赤字が解消されるのであれば、素晴らしいと思います。
新型コロナウイルスのパンデミックは、バイオベンチャーにとっては腕の見せ所でした。多くの企業が新型コロナウイルス治療薬やワクチン開発への参入を表明しましたが、持続的な株価の上昇につながるような展望のはっきりしたものは多くはなく、相場は荒れがちです。プレスリリース後に飛びついて、懐を寒くした個人投資家も多いでしょう。
残念ながら、株価対策としてコロナ治療薬への参入を発表したのではないかと疑いたくなるような企業も多い中、業界を驚かせた不祥事がありました。がんの細胞治療を手がけているA社です。A社は新型コロナウイルスのパンデミック後に、B社と共同でコロナウイルスによる呼吸器障害の細胞治療の実用化を目指す臨床試験を、メキシコで実施すると発表し、市場はそれを好感しました。やがて一部報道が、臨床試験が行われていないのではないかという疑問を投げかけましたが、A社はすぐさまそれを否定しました。しばらくしてその細胞治療薬はメキシコのある州で承認され、メキシコ全土での承認を目指すと発表されたんです。ところが、その後A社から「B社によるメキシコでの開発の実態が確認できない」という衝撃的な事実が発表され、共同開発は解消されました。そもそもメキシコには州ごとに承認する制度そのものが存在しません。A社は特設注意市場銘柄に指定され、当時のB社社長は二〇二二年三月に金融商品取引法違反の容疑で起訴されています。
このように、バイオベンチャー業界を照らす光は眩しいですが、闇の深さも底知れないものがあります。
ほとんどのバイオベンチャーは、巨額の開発費を必要としているにもかかわらず、売り物がありません。企業も投資家も、将来的に上市するかもしれない未来の新薬に賭けなければならないわけです。日本ではバイオベンチャー企業の時価総額は低く、個人投資家の比率が比較的高い。そのため、市場は荒れやすく、多くの投資家が退場を余儀なくされています。
それでもバイオベンチャーには夢があります。投資先として、資金を増やせるということもありますが、新薬の開発支援を介して、人類の幸福に寄与できるかもしれないというのも大きな魅力だと思います。
僕は成功するバイオベンチャーを見極めるために重要なのは、技術ではなく人間だと考えています。最先端技術そのものは一般の人には分かりにくいでしょう。でも、既存の技術と比較して丁寧に説明をしてくれれば、その会社の優位性は理解できるはずです。素人を煙に巻くのではなく、真摯な姿勢でリスクと共に未来を語る経営陣には資金を託す価値があると思うんです。逆に、夢物語ばかりを語り、開発の遅延を繰り返して、増資による株式の希薄化が常態化している企業へは投資しない方が賢明です。バイオベンチャーに投資をするときには、どんな人間が経営しているのかをしっかりと見極め、その言葉が真実を語っているかどうか、注意深く見守りましょう。
『テウトの創薬』では創薬に対して、異なる想いを持つ人間たちがぶつかり合います。モダリティと呼ばれる、薬のタイプによる対立、問題解決のための手法の違い。官と民、ベンチャー企業と大企業の対立。過去と現在のせめぎ合い。そして一般にはあまり知られていない研究と開発の衝突。トトバイオはそれらの対立を乗り越えて、カイコによる抗体医薬品生産への道を拓き、貿易赤字の影の主役とも言われる医薬品貿易赤字を解消することができるのでしょうか。
『テウトの創薬』の帯には「誰も口にしない新薬の不都合な真実」という惹句が踊っています。煽り過ぎでしょうか。いえ、実際に業界関係者でも驚く人が多いのです。
「新薬の多くは既存薬に比べて優れていないかもしれない」、なんて話をすると。
作品紹介・あらすじ
『テウトの創薬』岩木一麻
テウトの創薬
著者 岩木 一麻
定価: 1,925円(本体1,750円+税)
発売日:2022年03月24日
地方発、世界行き! ホットな創薬業界の開発競争を描くエンタメ企業小説!
世界の新薬の6割を生みだす、創薬ベンチャ―の知られざる世界!
カイコを利用する新技術でバイオ医薬品の生産を目指すトトバイオサイエンスの研究開発部長の進藤颯太郎は、工場で起きた事件をきっかけに同社の科学顧問で上州大学医学部教授でもある加賀義武の本性を知る。事件後、加賀と袂を分かったトトバイオと進藤は、新たな科学顧問探しと新薬開発を進めるが、加賀の妨害工作でトトバイオの株価は下落する。さらに帝央製薬と手を組んだ加賀の狙いは――。
研究の理想とベンチャー企業の綱渡り経営の現実がせめぎ合う、リアル創薬業界物語!
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322111000493/
amazonページはこちら
こちらの記事もおすすめ!
病気になるのは自己責任? 医師が見たコロナ禍の医療と社会 『病気は社会が引き起こす』著者、木村知さんインタビュー
https://kadobun.jp/feature/interview/9bz3hdhwu70g.html
ウィズ・コロナ時代の必携三冊――海堂尊が選ぶ【コロナの時代の読書】
https://kadobun.jp/serialstory/car/6tell6c7d3k8.html
仮想通貨には本当に価値があるのか? 黒木亮『カラ売り屋vs仮想通貨』刊行インタビュー
https://kadobun.jp/feature/interview/6jy0yxlj0rk0.html
危機にこそ証券取引の場を――。コロナショックで株価が急落する今、歴史からなにが学べるのか。幸田真音『天稟』の刊行に寄せて
https://kadobun.jp/feature/readings/e8na5mj9hhws.html
科学に興味をもつ一般読者向けに編まれた、『柿の種』と双璧をなす寺田寅彦の代表作を初文庫化!――寺田寅彦『万華鏡』文庫巻末解説
https://kadobun.jp/reviews/entry-43697.html