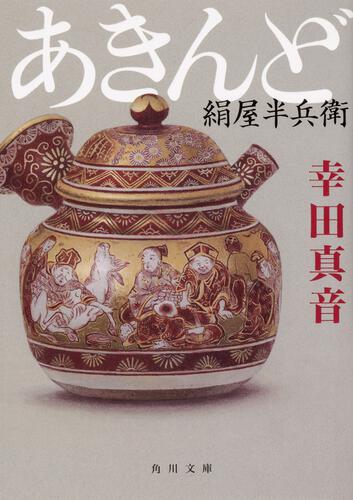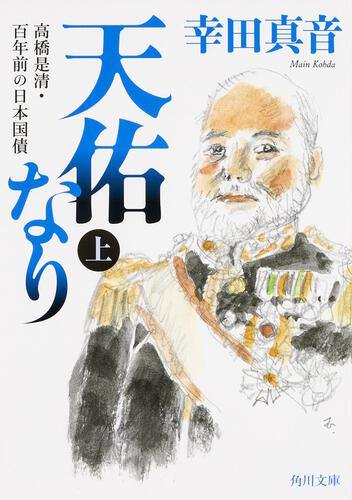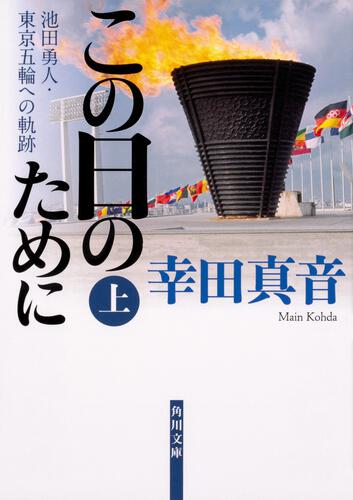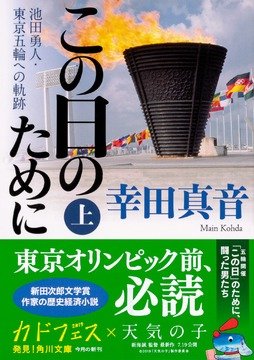今回のコロナショックにより、世界経済は大混乱に陥っている。過去の株価急落の局面同様、混乱を収束させるためには取引所を閉鎖するしかないのではないか、という声も聞こえるが、日本にはかつて、危機にこそ自由な株取引の場が必要だという信念のもと、戦後日本の復興のため、取引所の再開に尽くした男たちがいた。小説家として活躍する一方、米国系銀行や証券会社での債券ディーラーの経歴を持ち、現在も数多くの企業の社外取締役を務める幸田真音が、3月28日(土)発売の最新刊『天稟』に込めた思いを特別公開。
『天稟』の刊行に寄せて
歴史を、経済の視点で見つめ直してみると、これまでとはまったく違った景色が見えてくる。通り過ぎてきたはずの過去のなかに、驚くほどの現代との相似形を発見し、愕然とさせられる――。
そんな思いに駆られ、2002年から書き始めた歴史経済小説だが、今回の『天稟』は、その四作目となった。
一作目の『あきんど 絹屋半兵衛』では、幕末の彦根の城下に生まれたベンチャー・ビジネス「湖東焼」の窯を開いた絹屋半兵衛を主人公に、開国に踏み出した彦根藩主・井伊直弼との深い交流を描いたが、今年二月、第三次文庫としてKADOKAWAから刊行された。
二作目の『天佑なり』は、転職の達人(?)高橋是清が主人公。日露戦争の戦費調達のため、なにがなんでも外貨を得たいとする政府の命を帯び、果敢にロンドン市場に赴き日本国債の発行に成功した、型破りで波瀾に満ちた是清の生涯の物語だ。
三作目の『この日のために』は、かつて日本経済が二桁成長をしていた時代の1964年、東京で開催された一回目のオリンピックを舞台に描いた池田勇人と田畑政治の人生。敗戦から復興し、ついに高度経済成長期に突入した日本が、オリンピックに託したものがなんだったのかを、読者とともに考えてみたくて筆をとった。
膨大な資料はできるだけ原典にあたり、ご親族や関係者との思いがけない出会いにも恵まれて、史実を忠実に、しかも経済の視点から見つめ直すことに力を注いできた。
だが、前作『この日のために』を書き終えたとき、どうしても一点、書き残したのが気になって、ずっと頭を離れなくなったことがあった。
第二次世界大戦のまっただなか、ひたすら戦争継続を最優先させるため、節操なく国債を垂れ流し、どうしようもないほど積み上がってしまった政府の公的債務、つまりは溜まりに溜まった国の借金を、時の政府がどう処理したのかということ。
長引く戦争で、ことごとく軍需産業に転換させられてきた国内の産業は、敗戦でボロキレのように疲弊しきっており、頼みの青年男子の大半も戦地で失って、復興の担い手となるはずの産業も労働力も両方をなくした状態だった。
そんな政府が、八方手詰まりの財政の窮地で踏み切った究極の“出口政策”はなんだったのか。
それは「金融緊急措置」という政策の断行。流れが止まり、どうしようもないほどのへどろで詰まった管を一気に流してしまおうという、禁断の強い下剤にも似た強行策。すべての犠牲を国民に強いる施策であった。
まず、「財産税」という名のもとに、最高税率90%にもおよぶ過酷な個人資産への課税。さらには、敗戦直後にいったんは国民の預金を守ると宣言して、銀行に預金を集中させておいたあとの極端な引き出し制限。つまりは「預金封鎖」である。とどめは、それまで流通していた通貨を一切使えなくする「新円切替」の強行だ。国民生活の根本であり、経済活動の基本である通貨を、一瞬にして別のものに切り替えてしまおうとするあまりに横暴な措置だった。
それでも、人は生きていかなければならない。そして、生きていくためには金が不可欠だ。みずからを奮い立たせ、焼け野原で新しい仕事を始めるためにも、まずは資金が要る。
そんな市井の生き延びるエネルギーを裏で支えたのが手持ち株式の転売だった。
とはいえ、かろうじて焼け残った都心のおもだったビルは占領軍に接収され、証券取引所は非情にも閉鎖されている。自由な経済活動はその道を閉ざされていたのである。けれども、食料の闇市があちこちに生まれたように、株の内輪での売買も、自然発生的に始まっていく。人々の復興にかけるエネルギーはたくましいものがあった。
今回の『天稟』は、そんな戦後の証券取引所復活の物語でもある。
GHQ(連合国総司令部)が10年は禁じるとした取引所の再開を、わずか4年で実現させた男たちの軌跡の話でもあるのだ。立ち上がったのが、物語の主人公である山崎種二と清水浩。
売りからはいる相場を得意とし、値崩しに成功してきた名うての相場師・山崎種二は、「売りのヤマタネ」と恐れられてきたが、実はその真相は別にあった。貧しい育ちゆえ、人々の糧である米の価格が、儲け本位の相場の買い占めで吊り上げられていくのを黙って見てはいられなかったのだ。
清水浩は、独学で身につけた英語力を生かし、GHQに深く入り込んで日米間の交渉で活躍した人物だが、白洲次郎の存在に隠れてか、なぜかこれまでほとんど知られてこなかった埋もれた逸材だ。戦後処理における時代のヒーローである清水浩にもぜひとも光を当てたいと思い登場してもらったのだが、こよなく絵を愛する彼が、GHQと日本の金融界との交流に成功した裏に、日本を代表する画家の絵が存在したことも知ってほしかった。
そしていま、翻って現代の足許に目をやったとき、米中による「新冷戦」や、産油国を巻き込んだ「原油戦争」、頻発する自然災害、さらには新型コロナウィルス拡大による不安のなか、景気刺激策にいきづまり、金融政策には救いを見出せなくなった各国政府は、いずれは大規模な財政出動に頼らざるを得なくなるのかもしれない。
積み上がる国の借金は、出口のないまま崖っぷちに向かって進むしかないのだろうか。そのあげく、政府ははたしてどんな「下剤」を見つけ出すのか。
おりしも、中国がデジタル通貨の採用を議論の俎上に載せてきたが、抗いがたい時代の流れのなかで、やがては他の先進国の中央銀行も、デジタル通貨の発行に同調せざるを得ない時代がくるのだろう。
間違ってもそれが、かつてこの国が選択した「預金封鎖」や「新円切替」のように、われわれ国民に極限の犠牲を強いるものへと繋がることがないよう祈るばかりだ。
歴史を謙虚に見つめ直し、あらためてそこから教訓を得ることが、いまこそ問われる気がしてならない。
幸田真音
▼幸田真音『天稟』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321702000646/