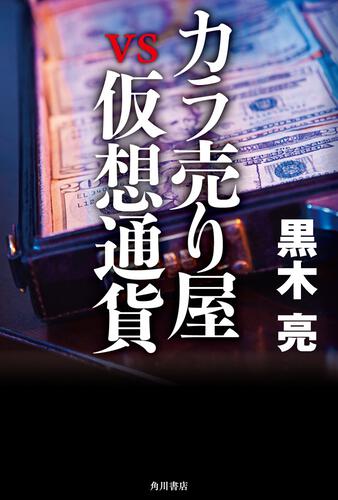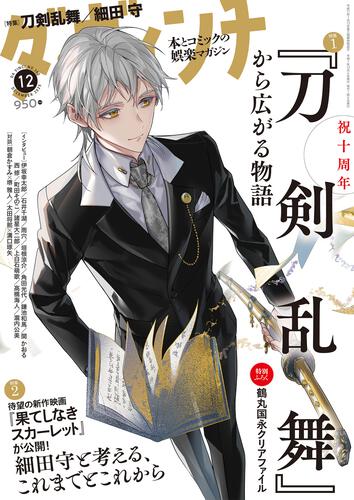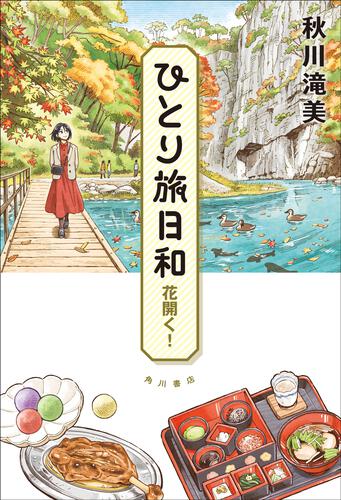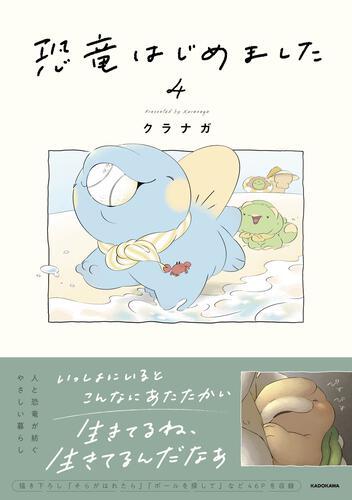今度のターゲットは、仮想通貨に電気自動車――。経済の動きのなかでも今、注目度が高いテーマの本質を、カラ売り屋が暴きます。シリーズ最新作『カラ売り屋vs仮想通貨』を刊行した黒木亮さんに、創作の裏側を聞きました。
黒木亮『カラ売り屋vs仮想通貨』刊行インタビュー
「カラ売り屋」とは、株式市場で実態より過大に評価されている企業を探し出し、株価が下がると見越して「カラ売り」を仕掛けて儲ける投資ファンド。ニューヨークを本拠地とするカラ売り屋「パンゲア&カンパニー」の北川、黒人のグボイェガらが日本に上陸し、獲物を狙います。『カラ売り屋vs仮想通貨』は「小説 野性時代」などで連載した「仮想通貨の闇」「巨大航空会社」「電気自動車の風雲児」の3編を収めています。
みんながいいって言うけれど、本当に価値あるの?
――仮想通貨をテーマにしたのはなぜですか。
黒木:ずっと「仮想通貨には本当に価値があるのだろうか」と思っていたんですよね。一度、突っ込んで勉強してみようと。細部のからくりがなかなか理解できず、連載時から書籍が校了するまでの1年半の間は、考えて、調べて、また考えての繰り返しでした。
――文中に「調べれば調べるほど、掴みどころがないという感じなんだよなあ」というカラ売り屋のセリフがありますが、これは黒木さんの気持ちだったんですね。
黒木:ずっとそんな感じでした。書きながら少しずつ理解を深め、ようやく尻尾をつかむところまではできたと思います。勉強してみて、やっぱり仮想通貨には価値がないと思いました。
それまでにない新しいものが登場する時には、たいてい初めは価値がないと思われますから、仮想通貨もそのような新しい価値の出現なのかと思って見ていたのですが、どう考えてもカジノのチップとしか思えない。ある仮想通貨取引所のハッキング流出事件をモデルにした物語の骨格の中に、得た知識を落とし込んでいきました。
どんな案件でもそうですが、カラ売り屋は価値の本質を突き詰めて考える投資家です。その意味では、仮想通貨のようなテーマを解説するには非常にいいキャラクターですね。
――ビットコインをはじめ仮想通貨は価格が急騰することがあり、値上がりすれば買い手が群がります。そんな仮想通貨を相手に、カラ売り屋も一時ピンチに陥りました。
黒木:相場は常にムードで動くので、理屈で説明できない価格がつくことがあります。それはそれで現実だと思います。日本ではもともと日銀の異次元金融緩和でおかしな市場になっていたところに、世界的にコロナ禍の給付金で過剰流動性に一段と拍車がかかり、金融市場にお金があふれて異常な相場になってしまいました。
ただ、株価はさすがに大元にファンダメンタルズ(企業の本質的価値)があるので、仮想通貨ほど乱高下しません。一方、仮想通貨にはファンダメンタルズがなく、価格が100%思惑で動きます。値段が動くものはなんでも投機の対象になる時代ですが、そのなかでも仮想通貨は唯一、本質的な価値がないものですから異常だと思いますね。
現在進行形で追った電気自動車
――一方、「電気自動車の風雲児」では、カラ売りした電気自動車会社の株価が予想に反して上がり続けるなか、カラ売りを手仕舞う(売っていた株を買い戻して撤退する)という、これまでにない展開です。
黒木:電気自動車についても、本当に優れたものなのか、世界にインパクトを与えるのかどうか、調べてみたいと思いました。モデルはテスラのイーロン・マスクです。初めから手仕舞うと決めていたわけではなく、現在進行形の状況を追いながら書きました。
2020年に連載を始める前は、テスラは株価が高いものの赤字続きで「この会社、本当に大丈夫か?」と思っていましたが、工場での生産が軌道に乗って株価が上昇してくると「こうなったらカラ売り屋は手仕舞うだろう」と筆が向きました。その後、リチウムイオン電池が安くなり、地球温暖化問題の追い風も吹いて、電気自動車は世界を席巻する勢いです。イーロン・マスクの宇宙ビジネスであるスペースXも宇宙船の打ち上げが成功しています。
――カラ売り屋が「『人類救済のために』という使命感に共感する部分もなきにしもあらず」とコメントするなど、これまでの作品のターゲットとは一味違う存在です。
黒木:カラ売り屋の面々とイーロン・マスクの生き方には共通している部分があります。どちらも、世間になんと言われようと自分が信じた道を突き進み、真実追求にあくなき執念を持っています。見ていて痛快ですよね。
ただ、イーロン・マスクはカラ売り屋とはレベルが違います。23世紀くらいになったら天才として語り継がれているんじゃないでしょうか。
知りたい気持ちが原動力
――仮想通貨も電気自動車も、ご自身が勉強したいと思うテーマだったんですね。
黒木:「これって何だろう」という知りたい気持ちが、作品を書くために取材する原動力になりますから、いつも大事にしています。ただ、それが自分一人の疑問ではなく、世間が思っている疑問と共通のものでないと本も売れません。
――世のムードに流されず本質を掘り下げる点が、作家としての黒木さんと、物語の主人公であるカラ売り屋に通じます。
黒木:カラ売り屋は逆張りが基本ですが、僕も昔からそういう人間なんですよ。「みんなはこう言っているけれど、違うんじゃないかな」って思うことがよくあります。みんなから「何を考えているんだ」と言われる人生を送ってきました。ただ、カラ売り屋が株価の動き次第で手仕舞うように、単に逆張りするのではなく、常に現実を直視して、逆張りが本当に正しいかどうかは考えなければならないと思っています。
銀行員時代の留学先も、みんな米国や英国に行きたがりましたが、「本当にそんなに面白いか?」と思い、アラビア語に手を挙げてエジプトに留学させてもらいました。ロンドン支店を最後に銀行を辞めて、英国に住み続けていることもそうです。
英国に住んでいると日本のことが客観的に見えますし、取材するには日本に来ればいい。日本で裁判を傍聴できていれば書けたかもしれないと思う題材はありますが、それ以外に出来ないことはそれほどないですね。
優れた航空機整備の現場、破綻に追いやった経営陣
――「巨大航空会社」は航空機をめぐる描写が緻密ですが、どう取材したのですか。
黒木:どことは言えませんが大手航空会社に長い付き合いの整備士さんがいて、話を聞くなかでいつか整備士の話を書いてみたいと思っていました。今回、取材のために整備工場を全部見せてもらったのですが、「ヒヤリハット」事例の掲示板があったりして、事故を防ぐために手前の段階での対応を徹底する航空機整備のすごさを感じました。
クライマックスの場面を書き込むために、飛行機のコックピットを再現したフライトシミュレーターでボーイング777の操縦を体験しました。インストラクターのチュニジア人のパイロットから通常運航時の離陸から着陸までに加えて、緊急事態対応の際のレバーやボタンの操作を教えてもらいました。
――経営の迷走と、真摯に機体に向かう整備士の姿が対照的です。
黒木:航空会社のモデルはJALですが、現場の人々は優れていて一生懸命やっているのに、上がダメというのは日本社会の縮図かもしれません。国民が額に汗して貯めたお金を、政治家がばら撒いてぶち壊しにしています。政治に関しては、昔は政治家がダメでも官僚がカバーしていましたが、今や官僚の質も劣化し、政治主導を掲げる政権は人事で官僚を恫喝しています。日本はもう行き着くところまで行かなければ、やり直せないのだと思います。
――英国のコロナ対応について黒木さんが各ネットメディアに寄稿された記事を読むと、ワクチンの取り組みをはじめ日本の対応に疑問を感じることが多いです。
黒木:英国政府は各社のワクチン開発計画に対し、新薬開発への投資手法を応用して段階ごとに前払金(マイルストーン・ペイメント)を支払うことでワクチンを確保しました。ワクチンが出来るかどうか分からないうちから接種ボランティアを育成して、ワクチンが出来ると一気に接種を始めたのは兵站作戦の成功ですね。日本はワクチン接種にしても戦略がありません。それでも最後は現場の人ががんばって、あと半年もすれば形を作るのでしょうが。
記事では日本の対応を叩くのではなく、日本で知られていない英国の動きを分かりやすく書くように心がけています。というのも、海外在住者が日本のことを批判すると、感情的に反発する人がいるんです。本業の小説ではない記事を書くのは、世の中に伝えたいことがあるからですが、入り口で反発を招くと読んでもらえません。胸にグサッと刺さり、考えてもらえる記事にするためには、書き方が大事だと思っています。
――カラ売り屋シリーズの次作は。
黒木:カラ売り屋は使い勝手のいいキャラクターなので、また書きたいと思っていますが、現場で取材できるのはコロナ禍が収まってからですね。それまでの間は、今の連載(味の素の海外市場開拓を描く「中央公論」の『地球行商人』、「青春と読書」の『イギリス国際金融浪漫』)や中断している作家・清水一行さんの伝記『
作家もカラ売り屋も、みんなが知らないことをガラス張りにするのが商売です。
『カラ売り屋vs仮想通貨』著者 黒木 亮
カラ売り屋vs仮想通貨
著者 黒木 亮
定価: 2,090円(本体1,900円+税)
仮想通貨は、夢の通貨か、悪魔のカジノか!?
元官僚の日本人と2人のアメリカ人が運営するウォール街のカラ売りファンド、パンゲア&カンパニーが、新たに3つの日本企業に照準を定めた。狙われたのは、濡れ手で粟の利益を上げる仮想通貨交換業者、グレーゾーンぎりぎりの会計手法で生き残りを画策する巨大航空会社、業界にEV旋風を巻き起こす新興電気自動車メーカー。財務諸表を徹底的に読み込み、株価を下げようとするパンゲアを、追い込まれた企業がマージン・コールで締め上げる――。金融ジャングルの勝者は、果たしてどちらか!? 「仮想通貨の闇」「巨大航空会社」「電気自動車の風雲児」三編を収録。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000158/
amazonページはこちら