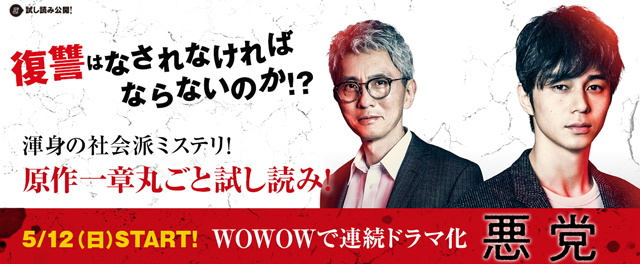
薬丸岳さんの衝撃と感動の社会派ミステリ、『悪党』がWOWOWでドラマ化!
5月12日の放送開始を記念して、『悪党』の冒頭部分を特別に公開します。
ドラマの前に、まずはこちらでお楽しみください!(全5回)(第1回から読む)
<<第3回へ
(承前)
「疲れたか」
坂上が訊いてきた。
仲間たちとの高級クラブでの宴が終わって帰路につこうかというときだ。
「疲れた」
私は正直に言った。
今日一日坂上と一緒にいて、細谷夫妻の依頼を受けた木暮を恨み、突っぱねなかったことを後悔している。
坂上が一万円札を差し出した。
「まだ試用期間だから給料というわけにはいかないが、今日はホテルにでも泊まれよ。二ヶ月ほど仕事をすればマンションを借りられるだろう」
「いや、大丈夫だ。まだたいして仕事をしてないし」
この金を受け取るわけにはいかない。
「良心が痛むか」
「そういうわけじゃない。きちんと仕事をしたときに、もらうものはもらう」
「律儀だな。そういう奴は初めてだ」
「そうかな。じゃあ、また明日」
坂上に別れを告げて、ネットカフェに向かった。
坂上の何を見れば、犯した罪を赦せると思えるのだろう。
狭い個室の中で、私はソファにもたれながら考えていた。
少なくとも、今日一日坂上のそばにいてその材料を見つけることはできなかった。
けっして、極悪非道な人間ではないと思う。昔はどうであったか知らないが、今の坂上は暴力で人を支配する人間ではない。それなりの気遣いもでき、仲間からの人望もある。
違う出会い方をしていれば、ダチになりたいと思ったかもしれない。
もし、坂上がまっとうな職に就いていたならば、細谷夫妻にとって赦せる材料になっただろうか。健太の墓に線香を供えて懺悔をすることが反省なのだろうか。坂上のどんな姿を見たときに、この仕事を終えられるのだろう。わからない。
無意識のうちに、自分の心の中に答えを探していた。
目を閉じると、今でも姉のゆかりの死に顔がまぶたの裏によみがえってくる。この世のものとは思えぬ苦悶の表情を顔中に残していた。
ゆかりを殺した犯人は二日後に逮捕された。地元でも素行の悪いことで評判だった榎木和也という十八歳の無職の男と、寺田正志、田所健二という十七歳の近所の高校に通っていた高校生だった。
もっとも、未成年が起こした事件ということで、新聞にもニュースにも犯人たちの名前や顔写真が出ることはなかったし、遺族が納得できる罰を与えられることはなかった。
主犯の榎木には懲役十年の刑が言い渡され、寺田と田所は懲役三年から五年の不定期刑というものだった。
ゆかりを殺した者たちをどうやったら赦せるというのだ。ゆかりを殺した三人はすでに刑務所を出て社会に戻っている。その者たちの今の姿を想像するだけで、その者たちが生きていると考えるだけで、どうしようもない激情が湧き上がってくる。
どんなことがあっても赦せない。たとえ刑務所で罪を償ってきたとしても、私たちの前で自分の愚かな行為に涙を流したとしても、社会的にまっとうな生活を送っていたとしても、赦すことなどできない。
細谷夫妻は私と違って、坂上のことを赦したいのだろうか。息子を殺した男のことを赦したいと思っているのだろうか。そのために、健太の命と引き換えにして得た金を私たちに託したのだろうか。
人を憎み続けることは苦しい。憎しみはやがて激しい焰となって、心の中を焼き尽くそうとする。そして、いつかの私のように、烈火を人に向けるのだ。
自分たちの息子を殺した坂上を赦せると思える日が来ることが、細谷夫妻にとっては幸せなのではないだろうか。
翌日、仕事が終わってから坂上に飲みに誘われた。
今夜は『ドール』ではなく違う店だ。おそらく、りさが来るあの店では、繕った話しかできないのだろう。
「だいぶ慣れてきたか」
今日は三時間ほどシナリオミーティングをやった後、実際に電話をかけて芝居をする坂上たちの様子を見ていた。
「役者にでもなれるな」
それは正直な感想で、あそこにいる人間たちは驚くほど話術に長けている。
「みんな、そんな度胸はない。見ててわかると思うが、意外と肝の小さい奴らがほとんどだ。相手の顔が見えないから、ああいうことができる。『おい、こら!』とすごんでる奴らも実際に会ってみるとそんなもんだ」
坂上が笑ってそう言う。
「ひとつ不思議だ」
「何が」
「ずっと一緒にいて思ったけど、あんたはそうとう頭が切れる。それにリーダーシップもある」
「リーダーじゃない。前にも言ったけどおれは管理職みたいなもんだ」
それはわかっている。坂上はこの組織の頭ではない。上の組織からグループの一部をまかされて仕切っているにすぎないのだろう。
「こんなリスクのある仕事じゃなくても通用するんじゃないか」
「まっとうな仕事ってことか」
「そう」
「おれもおまえと同じだ。十八から少年院に入ってた。出てきたら、親も、知り合いもみんなおれのことを避けて逃げる。そばにいてくれたのは昔のダチぐらいだ。ダチのひとりに誘われてこの仕事を始めたのがきっかけさ」
「何をやったんだ」
「中学の同級生を脅かしてたんだが、ちょっとやりすぎた。殺すつもりはなかったけど、ほっといたら死んでた」
坂上の口から初めて健太の話が出てきた。もう少し、坂上の気持ちを引き出したい。
十一年経った今、自分が犯してしまった罪をどんな風に受け止めているのだろう。
「遺族に会ったり、線香を上げにいったりしてるのか」
私が訊くと、坂上が何かを思い出したように時計を見た。
そういえば、三日後の四月二十五日は健太の命日だ。それを思い出しているのかもしれない。
「おまえは行ってるのか」
坂上が訊いた。
「何度か行った」
私は、あえてそう言った。
「そうか。それは偉いな。でもおれは、別に赦してもらおうなんて思わない。もう十分に罰を受けてる」
少年院に入ったことを言っているのだろうか。もし、そうであれば、大きな間違いだ。本当のダチならそう告げてただろう。
「ところで……さっき言ってた話、本当にそう思うか」
この話題はお開きにしたいのだろう、坂上が話題を変える。
「なにが」
「おれなら、まっとうな仕事ができるって」
「今の収入の何十分の一かで我慢できるんなら、できるだろう。そうしたいのか」
「いつまでも続けられる仕事じゃない。いい年してからムショに行くのは嫌だからな」
坂上が苦笑して言う。
「この前の女性だろう」
私が訊くと、坂上が虚をつかれたような顔をして見つめてくる。
「どうしてそう思う」
「なんとなく。別に聞き耳をたてていたわけじゃないけど、いろいろと聞こえてきた。介護ヘルパーをやってるみたいだな」
「過酷な仕事だし、給料も少ないし、どんなに一生懸命に働いてもなかなか報われない仕事だ」
彼女は老人の介護に精を出し、彼氏はそんな老人たちを騙して労せず金を搾り取っている。何とも皮肉な話だ。
「彼女は今の仕事のことを知っているのか」
意地の悪いことを訊く。
「知ってるわけないだろう」
怒気を含んだ口調で返してくる。坂上が初めて私に見せた苛立ちだった。
自分とは住む世界の違うりさのことを、そうとう愛しているのだろう。坂上の表情が語っている。
「りさには友人と会社をやっていると言ってる。おれの過去も知らない」
「どういうきっかけで知り合ったんだ」
興味があった。
「二年前にキャバクラで知り合ったんだ」
「へえ、意外だな」
りさの質素な外見を思い出した。
「ああ、向いてない。もともと生活のためにやってた。母親への仕送りもしていたし、介護ヘルパーの収入だけじゃきついからな。辞めさせてからは、おれが多少負担してる」
坂上の言葉を聞いて、複雑な心境になった。
もし、りさや、りさの母親が金の出所を知ったらどんな思いを抱くだろう。
「どうして、知り合ったばかりの奴にこんなことを話してるんだろう……」
坂上が呟いたとき、着信音が鳴った。ポケットから携帯を取り出して電話に出る。仕事に使うとばしではなく、自分の携帯電話のようだ。
しばらく誰かと話をしていた坂上が深刻な顔で電話を切ると、私に向き直った。
「頼みがある」
「なんだ」
何か面倒なことを頼まれなければいいがと願っていた。
「りさが仕事中に足を怪我して病院に運ばれたそうだ。行きたいところだが、おれはこれから上の人間のところに行かなきゃならない。病院に行って、タクシーで家まで送ってやってくれないか」
「わかった」
違法な頼まれごとではなくて安堵した。
「わかってると思うが、仕事のことなんかを訊かれても適当にごまかしてくれ。おれたちはりさの嫌いなタイプの人間だ」
坂上が一万円札を二枚差し出す。
「タクシー代だ」
バーを出て、タクシーを捕まえると板橋にある病院に向かった。
受付のソファに松葉杖を持ったりさが座っている。
「こんばんは。坂上さんはどうしても仕事を抜けられなくて、頼まれてきました」
りさに声をかけた。
「この前、『ドール』にいらした方ですね。彼の会社で働いてもらってるって聞きました」
りさに肩を貸して、タクシーに乗せる。
「お仕事のほうはどうですか」
本郷のマンションに向かっている車中でりさが訊いた。
「入ったばかりなのでまだよくわからないです。クビにならなきゃいいけど」
坂上の言いつけどおり、当たり障りのない言葉を返す。
「あなたのこと好きだと思うから大丈夫です」
思いがけない言葉を聞かされて、しばらくりさを見つめる。
「どうしてそう思いますか」
「なんとなく。私に会社の人を引き合わせるのは初めてだからかな。信用してるんだと思います」
胸の奥がうずいた。
私は信用される人間じゃない。坂上のことを調べている、ただの探偵だ。
「いつか仕事場での彼のことを教えてください。私には仕事の話なんか一切しないから」
「知りたい?」
私が訊くと、しばらくりさが考え込んでいる。
「知りたいような、知りたくないような……でも、私たちのために無理をしているんじゃないかと心配なんです。病弱な母のために仕送りもしてくれてるし」
「お父さんは」
「十年ほど前に亡くなりました。飲み屋でやくざの喧嘩に巻き込まれて刺されたんです」
りさが唇をきゅっと結ぶ。
思い出したくない過去に触れてしまったみたいだ。
「彼はもちろん、そのことを知っているんだよね」
「ええ。付き合い始めてしばらくしてから言いました。その話を聞いて泣いてくれました。ずっとクールな人だと思ってたのでびっくりしちゃった。人の痛みがわかる優しい人なんだなって……」
もう十分に罰を受けている──坂上が言った罰とは、もしかしてこのことなのではないだろうか。
りさを愛し続けることは坂上にとってはとても苦しいことだろう。いつまでも隠し通せるものではない。いつかは自分がしてきたことを話さなければならないのだ。
坂上は何を思って泣いたのだろう。
理不尽な暴力によって、自分が死なせてしまった健太や残された家族のことを思って泣いたのだろうか。
それとも、自分に近しい人の痛みだったから、理解できただけなのか。
いずれにしても、中途半端な悪党だ。
無性に腹が立ってくる。坂上のことを憎みきれない自分に、腹が立ってくる。
関連書籍

書籍週間ランキング
管狐のモナカ
2025年12月8日 - 2025年12月14日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
試し読み
-
特集
-
試し読み
-
特集
-
試し読み
-
特集
-
特集
-
特集
-
試し読み
-
レビュー



























