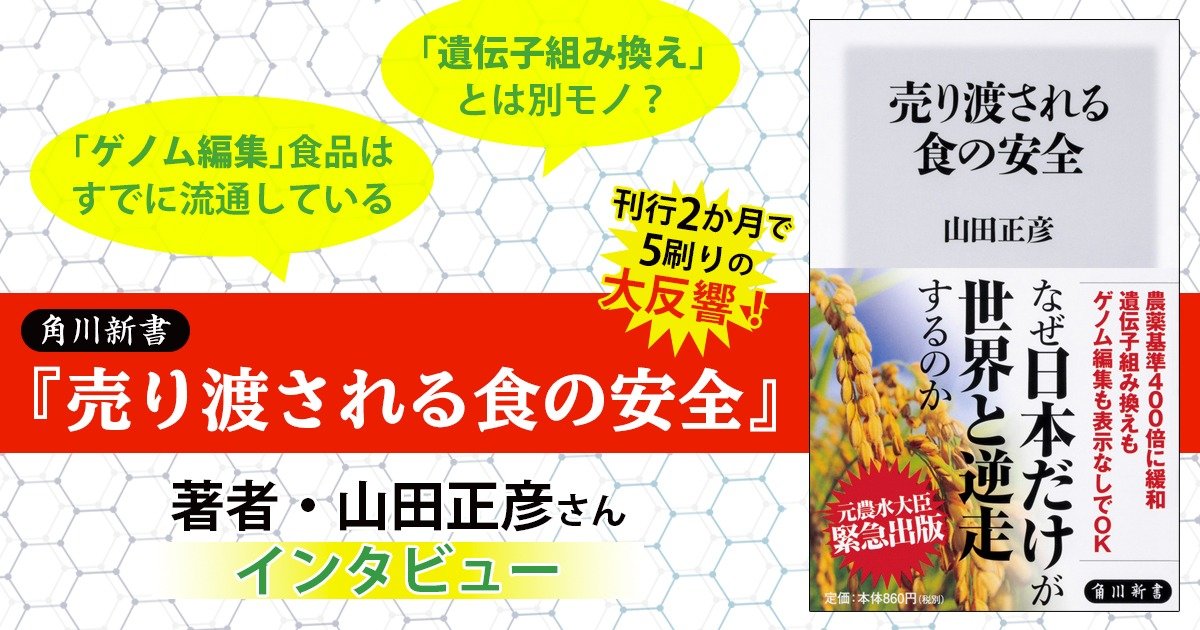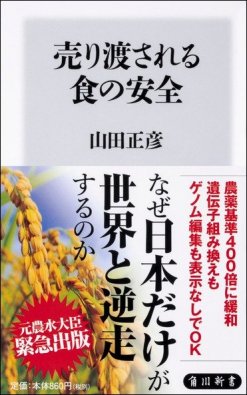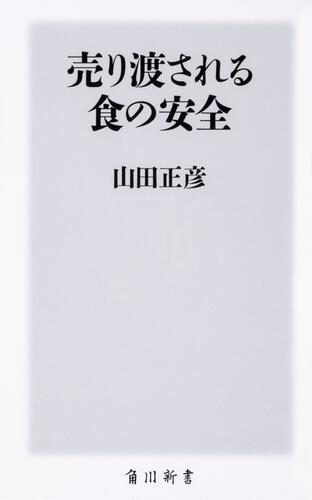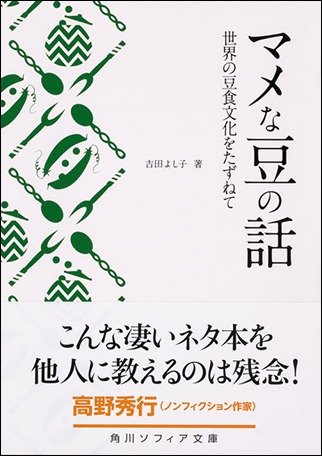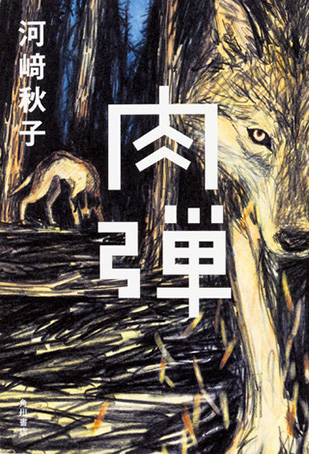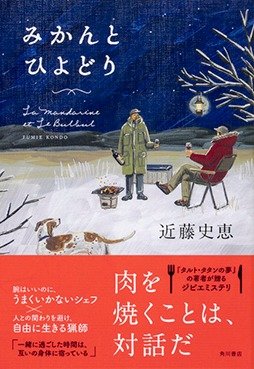角川新書『売り渡される食の安全』を刊行した山田正彦さん。刊行2か月で5刷りとなるなど、大きな反響を呼んでいます。
刊行後にはアメリカの食の状況を見に行ったという山田さんに、本書で伝えたかったことは何なのか、今の日本の食の安全はどのような状況なのか。お話をうかがいました。
ゲノム編集食品はすでに流通している
――日本ではついに10月からゲノム編集食品の届出で制度が始まりました。流通も開始しているとされていますが、今のところスーパーなどで見かけることもなく、ホッとしています。
山田:いえいえ、見かけることがないのは当たり前ですよ。「ゲノム編集食品」ということは表示しなくていい、というルールなのですから。表示しないまま、流通していると考えられます。
――どういうことでしょうか。
山田:環境省は2018年8月に「ゲノム編集は遺伝子組み換えではない」という見解を発表しました。今の法律では、遺伝子組み換え作物を5%以上使っている場合は表示が義務付けられていますから、その適用外だ、としたわけですね。
その後、厚生労働省の調査会が「ゲノム編集食品は従来の品種改良と同じで、安全である」という報告書を取りまとめました。報道も厚労省の発表をそのまま掲載し、問題点を指摘することもありませんでした。社会で問題になることもなく、今年の3月には、厚生労働省に届け出るだけで市場への流通を認める方針を固めたのです。表示は不要なのです。
――私たち消費者は、ゲノム編集された食品を食べたくない、と思っても判断できないということでしょうか。
山田:そのとおりです。なぜ表示しなくていいのかについて厚労省は「ゲノム編集のものとそうでないものを区別することができないから」と言っています。これは明らかに虚偽です。ゲノム編集で操作された遺伝子にはその痕跡が残るので、検出できる、と遺伝子組み換え情報室代表で分子生物学が専門の河田昌東さんは明言しています。
――ゲノム編集された食品としては、たとえばどんなものが考えられますか。
山田:日本で研究が進んでいるものとしては、京都大学では肉厚にした鯛が、大阪大学などでは毒素のないジャガイモが、筑波大学では栄養価が高いトマトなどがあります。「鯛を食べなければいい」という方もいるかもしれませんが、たとえばその鯛がすり身になってカマボコになっているかもしれません。いつも行くファーストフードのフライドポテトがゲノム編集されたものかもしれません。食べたくない、と思っても完全に除去するのは今の日本の食品表示の仕組みでは不可能です。
私がもっとも早く流通し始めると考えているのは、アメリカで栽培されたゲノム編集の高オレイン酸大豆です。アメリカでは消費者からソッポを向かれてしまっていますが、日本では表示義務がありませんから都合がいい。その大豆が「遺伝子組換えでない」として、豆腐や納豆、味噌などになってスーパーにすでに並んでいるかもしれません。
――「遺伝子組換えでない」という表示を選んで買ったけれど、ゲノム編集された商品の可能性があるということですね。
山田:そうです。非常に憂慮すべきだと思います。
――そもそもゲノム編集は危ないのですか、安全なのですか。
山田:まだわからない、というのが誠実な回答だと思います。ゲノム編集は1996年ごろから実用段階に入った新しい技術です。安全性の不備を指摘した論文も多く出ており、未解明な部分も多くあります。
現在の普及している技術は、クリスパー・キャス9というものですが、この技術はそもそも、遺伝子治療への臨床応用を目的としたものでした。開発者の一人、アメリカ人のダウドナ教授は「ゲノム編集を食物に施すのは危険です」と警告しています。
結論が出ていない技術であり、しかも施されるのは体の中に入る食品です。私は結論が出ていない以上、全面的に禁止すべきと考えますが、少なくとも消費者が選べるようにすべきでしょう。
――8月の日米首脳会談では、中国が輸入しないアメリカのトウモロコシを、日本が買う、と報道されました。それも何か関係があるのでしょうか。
山田:遺伝子組み換えのトウモロコシだと思います。飼料用とはいえ、最終的にその家畜を私たちが食べるのです。菅官房長官はトウモロコシが害虫で食い荒らされていて、飼料用のトウモロコシが不足する可能性がある、と言っていましたが、農水省は現時点では害虫の影響は出ていない、とコメントしています。情けない限りです。
――遺伝子組み換えとゲノム編集はどう違うのですか。
山田:遺伝子組み換えは、目的に適した遺伝子を見つけ出して、まったく別の生物の遺伝子を人為的に組み込む作業です。
一方で、ゲノム編集は、特定のある遺伝子をピンポイントで切断することで、生物の特徴を変える技術のことです。
遺伝子組み換えがまったく別の生物や植物の遺伝子を組み入れる技術であるのに対して、ゲノム編集は当該生物の遺伝子を切り取るという点で異なっています。
ちなみにEUでは2018年7月の段階で、司法裁判所が「ゲノム編集は遺伝子組み換えと同様に規制すべき」と判断しています。アメリカは農務省が「ゲノム編集は遺伝子組み換えに該当しない」とする声明を出しましたが、それは一部に限られており、改変の仕方によっては遺伝子組み換えであるとしています。
一方の日本ですが、ゲノム編集食品が遺伝子組み換えでない、としたばかりか、2019年9月から農水省やその関連機関では「有機JAS表示を認めるかどうか」も議論されていました。そんなことになれば、日本の有機作物は世界に輸出できなくなってしまいます。幸い、この決定は回避されましたが、今後どうなるかわかりません。目を光らせていきたいと思います。
「二度と国民を飢えさせない」――戦後の政府の覚悟がこもった種子法が廃止された
――2018年4月をもって種子法が廃止されました。恥ずかしながら、私は種子法という名前から農業界にかかわる法律だろう、と思って関心を持っていませんでした。
山田:多くの人がそうだと思います。私は若いころに牧場を経営し、その後、国会議員として農業政策に携わってきましたので、農家さんの状況や食の安全について、関心が高い方だと思います。そんな私でも寝耳に水でした。閣議決定までが非常に短期間でしたし、報道もほとんどされていませんでした。
――廃止されてしまった種子法とはどういう法律だったのですか。
山田:法律ができたのは1952年のことです。当時、戦後の食料難が深刻化し、餓死する人も出ていました。そうした状況下で制定されたのが種子法で、「食料を確保するには何よりも種子が大事だ」ということが明確に位置付けられました。そこには、「二度と国民を飢えさせない」という時の政府の決意と覚悟が反映されていると思えてなりません。
この法律によって、米、麦、大豆といった主要作物の種を、国が責任をもって育てる義務が生まれました。実際に種を育てているのは、各都道府県の農業試験場ですが、そこにかかるお金も、この法律に基づいて予算配分されていました。
今や、お米を食べることは当たり前すぎて、この法律の重要性に多くの人が気づいていない状況でした。廃止が明らかにされてはじめて、「これは大変なことになる」と声を上げたのですが、時すでに遅しでした。
――廃止されたことで、何が起こると考えられますか。
山田:まず考えられるのは、お米の価格の高騰です。からくりについては私の本を読んでいただければと思いますが、端的に言えば、これまで公共でまかなってきた種子事業を民間企業がになうことになります。企業は営利を目的としていますから、価格は企業の思い一つで上げられてしまいます。実際、三井化学アグロや日本モンサントなどの企業が販売している米の種子の値段は、公共の種子の8~10倍ほどもします。
また今、日本には私たちがふだん食べているうるち米だけで286種もの種類がありますが、これもみるみる淘汰されるでしょう。
都道府県の農業試験場も民間にタダ同然で明け渡されます。1952年の種子法制定以来、国民の税金を使って蓄積してきた種子の知見や研究施設を、なぜタダ同然で企業に渡さなくてはならないのでしょうか。
――TPPも発効し、日米貿易協定も国会で承認され2020年1月に発効することが決まりました。種子法も廃止された今、海外の企業にとって日本の農業市場は非常に参入しやすくなったといえるのでないでしょうか。
山田:そのとおりです。さらに政府は次の国会で「種苗法改定」を上げてくるはずです。種苗法は種子法と名前が似ていることもあり、ほとんど知られていない法律ですから、大きな議論にもならず、あっさり可決されてしまうかもしれません。ただこちらも非常に問題です。
――種子法と種苗法、名前が似ていてややこしいですね。何の法律ですか。
山田:名前は似ていますが、中身は大きく違います。
種苗法は、農作物や園芸植物を開発した人、および企業の知的財産権を保護する法律です。ただ、登録された品種であっても、その種子を購入して栽培した農家は、翌年採れた種をまいて利用しても構わない、としています。
しかし政府は、種苗法を改定することで、自家採種を原則禁止にしようとしています。つまり、自分の畑で採れた種を使ってはいけない、というわけです。私たちの感覚からしても違和感がありますよね。憲法で保障された財産権にも触れるのではとも考えられます。
――種苗法の改定で何が起こるのですか。
山田:自家採種が禁止されれば、毎年種を買わなくてはなりません。もし農家さんが、自家採種をして、その種で翌年も育ててしまうと、種苗法違反となり、10年以下の懲役刑と1000万円以下の罰金刑が併科されます。併科とは両方の刑が科されるという意味で、ほかの罰則と比べても非常に重いです。しかも種苗法違反は、いわゆる共謀罪の対象にもなります。採れた種を使っただけなのに、です。
種子法が廃止されたことによって、自治体の農業試験場は縮小し、最終的には大企業の種子を買わなくてはならなくなります。さらに種苗法の改定で、それを毎年買うことになるのです。
――種子を販売する企業に利益が大幅に流れ込みそうです。
山田:そのとおりです。種子法廃止、種苗法改定で潤うのはだれかといえば、種子を扱う企業です。農家は経費がかさみます。民間企業の利益を優先させるために、戦後の日本の農業を支えてきた農家の方々を犠牲にする究極の愚行としか思えません。ぜひみなさんには、国会を注視していただきたいと思います。
――日本の種子市場に乗り出すのは、どういった企業が考えられますか。
山田:種子を育てるというのは時間とお金がかかります。そういった事業ができるのは大手企業だけです。日本の企業では先ほど申し上げた三井化学アグロや豊田通商、住友化学などでしょうか。
海外の企業にとっても新たなビジネスチャンスといえます。多国籍アグリ(農業)企業と呼ばれる会社ですが、みなさんにはあまりなじみがないかもしれません。
今、世界の種子の70%をモンサント(2018年6月、ドイツのバイエルが買収)、ダウ・デュポン、シンジェンタ(中国化工集団傘下)の三社で生産していると考えられています。種子の市場の寡占化が進んでいるのです。そもそも、種子はどこかの企業のものなのでしょうか。祖先から受け継いできた、人類共有の財産ではないでしょうか。種子から公共性がはぎとられようとしているのです。
これらの会社は、かつて化学兵器を開発する会社でした。戦争が終わり、種子―農薬―化学肥料をセットで販売して、飛躍的に成長を遂げてきました。
ことにモンサントは、自社の除草剤ラウンドアップ(主成分グリホサート)に耐性を持たせた遺伝子組み換えの大豆、トウモロコシ、綿などの種子を開発して、農薬とのセット販売で世界の農業を席巻してきました。
世界を変えたモンサント裁判
――ラウンドアップというのは聞いたことがありません。
山田:庭や家庭菜園などで使う農薬を買ったことはありませんか。ぜひ裏の表示を見ていただきたい。ラウンドアップという名称ではないかもしれませんが、主成分が「グリホサート」とあるものは同じです。
日本ではホームセンターだけでなく、100円ショップでも売っているほど手に入りやすく、しかも除草効果が高い。安くて強力ということで、JAでも推奨しているところがありますし、学校や公園など、子どもたちが泥んこになって遊ぶような場所でも、当たり前のように使われています。
以前からラウンドアップは人体に甚大な影響を及ぼすとさまざまに言われてきましたが、そのたびにモンサントはあらゆる手段で否定し、「安全な農薬」の地位を保ち続けてきました。
――なぜラウンドアップと遺伝子組み換えがセットなのでしょうか。
山田:ラウンドアップは効果があまりにも強いため、雑草だけではなく、育てたい作物まで枯らせてしまいます。そこで、遺伝子組み換えを行い、ラウンドアップで枯れない大豆やトウモロコシが開発されました。
どんな遺伝子を組み込んだと思いますか。ラウンドアップを生産しているときに、排水溝からラウンドアップに耐性を持つ微生物が偶然発見され、その微生物の遺伝子を大豆に組み込みました。大豆の遺伝子に、まったく別の生物の遺伝子が組み込まれているのです。
――科学の進歩というのか、暴走なのか…。ラウンドアップに対して、海外ではどのような状況ですか。
山田:規制が進んでいます。オランダ、ベルギー、ポルトガル、デンマーク、カナダ、ブラジル、アルゼンチンなど、さまざまな国で禁止や規制が行われています。
さらに2018年8月10日は、大きなターニングポイントになりました。我が世の春を謳歌し続けてきたモンサントに対して、司法がノーを突き付けたのです。
悪性リンパ腫と診断されたカリフォルニア州在住の男性、ジョンソンさんが、がんを発病した原因は除草剤ラウンドアップにあるとして、モンサントを訴えました。サンフランシスコの陪審はジョンソンさんの訴えを認め、モンサントに対し320億円もの支払いを命じる評決を全会一致で決定しました。この判決以後、モンサントは世界で4万2700件もの訴訟を起こされています。ジョンソンさんの裁判は、まさに世界を変えた裁判だと思います。
――8月下旬にアメリカに行かれたとうかがいました。ジョンソンさんにもお会いになりましたか。
山田:はい、お会いできました。かなり体調がよくなくて、約束した日には来られませんでした。病院に行っていたそうです。私は予約していた飛行機をキャンセルして、ジョンソンさんを待つことにしました。
翌日、来てくださいましたが、腕はケロイド状で、歩くことも難しいとのことで車いすでした。
「モンサントに対してどう思いますか」と聞いたら、「怒りというより悲しい」とおっしゃっていた。その言葉がとても印象に残りました。
――ほかはどういったところに行かれましたか。
山田:モンタナ州の有機栽培を行っている大規模農場や一般のスーパー、研究者にもお会いしました。
アメリカのスーパーは表示が進んでいます。「NON GMO(遺伝子組み換えでない)」「ORGANIC(有機栽培)」「Animal Welfare(ストレスの少ない飼育環境で育てた牛や豚)」などのシールが貼られています。最初見たときはかなりのカルチャーショックでした。
野菜や精肉類、食パン、ケーキ類、牛乳やチーズ、ジュースやビール、ワイン、ドレッシングやマヨネーズなどの調味料、サプリメント、さらに洗剤などにも貼られています。
私が行ったスーパーでは日本のスナック菓子やお茶も売っていましたが、スナック菓子は何のシールもありませんでした。お茶には「NON GMO」のシールはありましたが、オーガニックのシールはありませんでした。農薬を使っているからでしょう。
私たちは知らない間に大量の遺伝子組み換え食品を食べている
――ただ日本では遺伝子組み換えへの拒否感も強く、それほど普及しているとは思えません。アメリカのような表示は必要でしょうか。
山田:「遺伝子組み換えでない」という納豆は見かけても、「遺伝子組み換え大豆を使用しています」という食品は見かけませんよね。ですが、日本は世界でも有数の遺伝子組み換え食品の消費国なんですよ。
「ラウンドアップ・レディー・大豆」「ラウンドアップ・レディー・トウモロコシ」(レディーは「準備ができている」という意味で、ラウンドアップに対して耐性を持つ)など、322種の遺伝子組み換え食品の安全性を厚労省が認め、輸入されています。322種類のリストは厚労省のホームページにありますから、ぜひ一度見ていただけたらと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000565437.pdf
――そうなのですか。輸入された遺伝子組み換え食品はどこで使われているのでしょうか。飼料用ですか。
山田:飼料用にももちろん使われていますが、私たちが普段口にしている食品でも使われています。
日本で遺伝子組み換えの表示が義務付けられている食品はほんの一部です。たとえば大豆であれば、豆腐や油揚げ、納豆などで表示義務はありますが、醤油や植物油に表示義務はありません。また、加工の方法によっては表示義務がなく、マヨネーズやマーガリン、コーンシロップなども表示しなくてOKです。
子どもが食べるスナック菓子は油で揚げているものが多いですが、その油も表示義務がありません。つまり、私たちは知らない間に大量に遺伝子組み換え食品を口にしているのです。このように、表示制度に非常に抜け道が多いのです。
ちなみに、ヨーロッパでは、外食のレストランのメニューにまで、厳格かつ詳細に表示が義務付けられています。私はその落差に目がくらんでしまうのです。
――逆にいえば、それほど食べていても問題ないのですから、大丈夫、とも言えないでしょうか。
山田:私の講演会などでもよくそういったことを聞かれます。煽りすぎではないか、と言われることもあります。
そうですね、すぐには影響はないかもしれません。ですが、かつてアスベストという物質がありましたが、影響がどのようなものかわかるのに40年もの年月がかかりました。その間、多くの場所で使われ、それによって多くの方が病気になりました。吸い込んで15~50年もの歳月を経て症状が現れることから、静かな時限爆弾と呼ばれていますね。
今は問題なくても、10年後、20年後、40年後は大丈夫でしょうか。私たちの子どもや孫たちはどうでしょうか。
遺伝子組み換え食品の危険性に関しては、さまざまな論文が発表されています。そのいくつかを私の本でも紹介しましたので、ぜひお読みいただけたらと思います。
――私もできれば、有機栽培の食品を選びたいと思いますが、やはり値段が気になります。普通のスーパーの価格の1.5倍はしますよね……。
山田:たしかに割高ですね。この話をアメリカの遺伝子組み換え表示を求める運動をけん引した主婦、ゼン・ハニーカットさんにたずねたことがあります。ゼンさんはこうおっしゃっていました。
かつては子どもたちが病気がちで、アレルギー症状もひどく、医療費が年間で100万円近くかかっていたそうです。いろいろ調べて、もしかして食事に理由があるのではないかと思い立ち、徹底してオーガニック食品にしたところ、家族が健康を取り戻し、今では医療費は10分の1以下になったそうです。
日本では有機栽培の食品を積極的に求める動きにはなっておらず、それもあって栽培している農家さんも少なく、価格は高騰したままです。もっと普及することで、価格が落ち着いていけばと思っています。
地方からのうねり
――今日、お話を聞いて、種子法というのが私たちの毎日の食事や食の安全を支えていた、大切な法律だったのだとわかりました。なくなったままで大丈夫でしょうか。
山田:もう中央には任せておけない、自分たちの食の安全は自分たちで守る、と地方が立ち上がっています。新潟、兵庫を皮切りに、11の道県で『種子条例』が成立しました。条例というと地方の取り決め、くらいにしか思わないかもしれませんが、実は刑罰も定めることができるほど強い権限を持ちます。
私は種子法が廃止されて以来、各地を回り、小さいところは5人くらいの勉強会から数百人規模の講演会まで、種子法の意味を伝えてきました。最初は「何しに来たんだ」「自民党がそんなことをするはずない!」と聞く耳を持ってもらえないことも多くありましたが、これは政党を超えた問題であること、あなたやあなたの家族の問題であることを伝え続けました。
――条例制定はすんなりいくものでしょうか。地方議会にもさまざまな政党があります。
山田:ある自治体では、自民党議員も野党議員も一緒になって全会一致で可決しました。そこには、住民の食の安全は我々が守らなくてどうするのか、という矜持を感じます。
だから、法律がなくなったからといって何も諦めることはないのです。今や大きなうねりとなって、全国に波及しています。今年度中に20ほどの道県で条例が成立するのではと見込んでいます。
私たちには権利があります。自分たちの生活を自分たちで守ることができるのです。安心安全なものを安価に食べたい。私は先人の思いが受け継がれた種子を後の世代にきちんと受け渡して行きたいと思っています。
書籍のご購入&試し読みはこちら▶山田正彦『売り渡される食の安全』| KADOKAWA