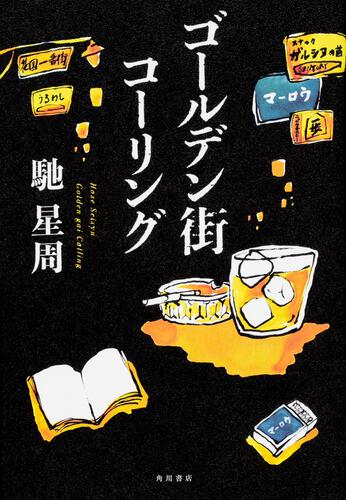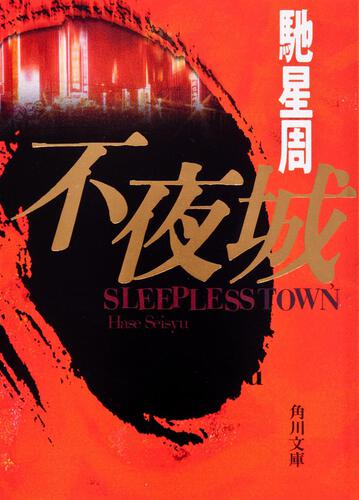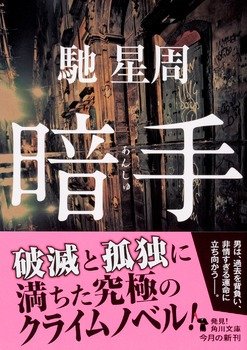馳星周が新宿歌舞伎町を舞台にした暗黒小説『不夜城』でデビューしてから二十二年。最近では、犯罪小説のほか、藤原不比等を主人公とした歴史小説『比ぶ者なき』、本格的な山岳冒険小説『蒼き山嶺』など、新たなジャンルに挑戦し続けている。
最新作『ゴールデン街コーリング』は、なんと自伝的青春小説だ。一九八〇年代中頃の新宿ゴールデン街を舞台に、作者の分身たる若者の青春が綴られていく。
自伝的青春小説という新しいチャレンジ
――今回、自身をモデルとした青春小説を書くきっかけとなったのは?
馳:編集者から、ゴールデン街にいたときのことを自伝的青春小説で書きませんかって提案があって、新しいチャレンジだし、おもしろいなと思ったんだ。もちろん、ほとんどはそのまま書けないことばかりなんだけど。もう陳さんもいないし、ある程度は書けるかなと。
――この小説に登場する新宿ゴールデン街〈マーロウ〉のマスター、斉藤顕とは、コメディアンにして書評家、日本冒険小説協会の会長、そしてゴールデン街の酒場〈深夜+1〉(通称〈深プラ〉)の主、内藤陳さんがモデルですね。実在した人物が名前を変えて登場している一方、そのまま実名で出てくる人たちもいます。作家では船戸与一、志水辰夫、北方謙三、書評家の北上次郎(目黒考二)、噺家の立川談志……。
馳:まず、〈深プラ〉に来ていた作家や有名人は、基本的にもう死んだ人しか出さない。そう自分の中で決めていた。
――なるほど。それはおもしろい。
馳:例えば船戸さんもそうだし、談志師匠もそうで、この小説に出てくる小説家や有名人は、みんな死んだ人たちなんです。もちろん北方さんとか志水さんとか、名前だけ出てくる作家はいるけど、作中に登場するのは亡くなった人だけ。例外は「本の雑誌」のエピソードで出てきた目黒さんくらいかな。いまも生きている人だと、いろいろさしさわりがあるでしょう。当時、店によく来ていた北方さんや大沢在昌さんのことなんか、全部は書けないから(笑)。
――主人公の坂本は大学生ですが、ストーリーはもっぱら〈マーロウ〉のマスター、斉藤顕との関係を中心に展開していく。つまり〈深プラ〉で内藤陳さんの下、アルバイトをしていた当時をそのままモデルにした部分がほとんどなんですね。
馳:やっぱり俺のゴールデン街の体験と内藤陳さんは、分かちがたいものがある。で、これを書くにあたり「自伝的青春小説」というフレーズに心を動かされたので、そこはやっぱり陳さんとの関わりをメインにしていかなきゃいけないな、というのは最初から思っていたかな。
――内藤陳さんが亡くなって、まもなく七年になります。いまだからこうして赤裸々に書けるわけですか。
馳:いまでも書けないことがたくさんあるけど(笑)。
――もちろん小説なので、フィクションとして脚色した部分も多く、実録的な部分をそれと融合させて描いていると思いますが、その辺の構想はどういうふうに?
馳:これは自分のいつものスタイルなんだけど、書きながら、考えては進めていく、という形で。 小説を書くうえで、まず頭にあるのが、フィクションを書くんだということ。すべてを事実として書く必要はない。ただ今回、実際あったことにフィクションを織りまぜて書いていくのは、おもしろいチャレンジだなと思った。基本は青春成長小説という枠組みがあって、舞台がゴールデン街、そして内藤陳という、とても複雑な人と、十八歳から二十二歳ぐらいまで付き合っていた自分がいる。あれで、ものの見方とかいろいろ変わったなとかとも思うし、その辺のことを物語にしていければ、うまく書けるなとは思っていた。
――この小説は一種のミステリ仕立てにもなっています。放火や殺人などの事件が起きる。物語の時代背景は、ちょうどバブル期の東京で、ゴールデン街にも地上げ屋が乗り込んでくるわけですね。
馳:最初は、そういう趣向はなくてもいいって思っていたんだけど、ちょっとだけでもひねりを入れたほうがおもしろくなるかなと。それはもう迷いながら書いていったんだけど、八五年当時の物語だから、地上げの話とも絡めなきゃいけないし。 あのころ、実際にもうバブルが始まっていて、ゴールデン街に古くからある飲み屋に行くと、地上げ屋が放火するという噂は、俺たちもよく聞いていた。詳しく覚えてはいないけれど、不審火の騒ぎがあったのは、なんとなく頭に残っていたな。氷を入れる発泡スチロールが燃えていたとかね。
――ひとつ奇妙に感じたのは、大学生なのに学校の様子がまったく描かれていないということ。
馳:大学、ほとんど行ってないから(笑)。もう毎日、〈深プラ〉にいた。で、大学二年生のとき、それまでは横浜にある学校の近くに住んでいたんだけど、引っ越して都内に移った。なるべくタクシー代が安くすむようにと。
――〈深プラ〉のアルバイトで心身ともにきつい思いをしながらも、都内に引っ越したあと、毎日のように新宿へ通っていた。それだけ惹きつけられるものがこの街にあったから?
馳:やっぱり猥雑で、あらゆることがデタラメだった。だって、酔っ払いだからしょうがないじゃん、というような空気はあったよね。やっぱりお酒を飲んで、酔っ払って、話しているのは楽しいから。 でも大学のクラスメートと呑みに行っても、つまらないんだよ。本の話や映画の話ができるのは、そういうところに行かなきゃできない、というのも大きかった。ゴールデン街に行くと、作家や編集者たち、文化人が多かったからいろんな話ができる。俺は新宿しか知らないけど、渋谷とか神保町とかにも同じような店があったかもしれない。でも、そんな多くあるわけじゃないだろうし、自分で探しにいかないと見つからない。
――新宿ゴールデン街だけではなく、区役所通り辺りのバーなども出てきますね。ちょうど『不夜城』の舞台とそのままかぶっている。
馳:この『ゴールデン街コーリング』に出てくる、ほかの酒場のロケーションは、俺が二十歳をすぎて、社会人になってから行っていた店とかがモデルになっている。それは普通の呑み屋だけど。 ふだん昔を思い出すなんていうことはほとんどない。そんなこと俺はしないタイプなんだ。でも、これを書いていて、あのとき、どうだったかなと思い出したりするのは楽しい作業だった。あと資料で、当時の歌舞伎町の地図は見つけてもらったな。けっこう変わっているから。実際に行って、ここ、前は何だったっけって、やっぱり思い出せないことがあるから。それぐらいかな。 ただ、当時の風俗的なことを資料で読んで、それをそのまま書き写すんじゃなくて、とにかく自分の記憶を掘り起こして書こうと思っていたんだ。
北海道の少年が馳星周になるまで
――この時代の多くの経験がのちの書評家としての坂東齢人を経て、作家・馳星周を生み出したところがあるのでは? いろんな意味で『不夜城』が出来るまで、という物語になっているようにも思えます。
馳:そうだね。その前段階の話というか。あと、これを書きながら、坂東齢人という田舎の少年が、馳星周的思考を身につけていく過程を書いてみようと思った、というのはあるんだよね。 それこそ、このなかにも書いたけど、最初はチャンドラーの小説が好きだったわけだけど、ずっとあそこにいるうちに、ちょっと違うんじゃないかと思いはじめた。それが結実していくのは、もっとあとのことなんだけど、やっぱりその辺りからが、正統的なハードボイルドや冒険小説に違和感を持ちはじめた時期でもある。そう思い返しながら、この作品を書いていくのは、自分の来し方を振り返る意味でも、おもしろかったかな。
――本作のなかに、あちこちで好きな作家の話が出てきますね。ディック・フランシスに志水辰夫。あと、平井和正……。
馳:これ、ほんとに偶然なんだけど、先月、大藪春彦賞新人賞の選考会が終わってから、今野敏さんや編集者たちと呑んでいた。そうしたら、〈ウルフガイ・シリーズ〉の話でめちゃくちゃ盛り上がったんだよ。三時間ぐらい、みんなで話していた。 でも、いまは書き手になったから、読む本の傾向が若いころと全然ちがう。要するにもう小説のための資料ばっかり読むという感じ。あと、ほかの人が書いた小説は、昔の純粋な読者だったときみたいに読めなくなった。俺ならこうするのにとか、なんかそんなことばっかり考えてしまう。
――最後に、いま振り返って、馳星周にとっての八五年のゴールデン街というのは、どういう場所だったと思いますか。
馳:愛憎相半ばする場所だな。この小説のなかで坂本も言っていたけど、好きだけど嫌い。嫌いだけど好きという、矛盾する気持ちが交錯する場所。
――良くも悪くも青春そのもの。
馳:そうだね。