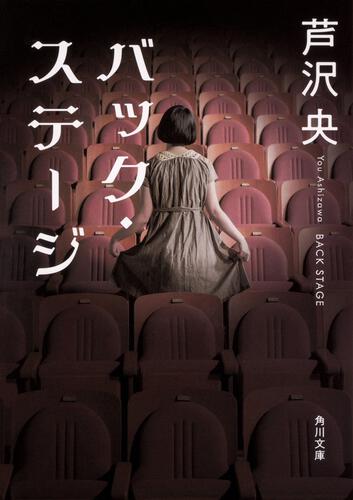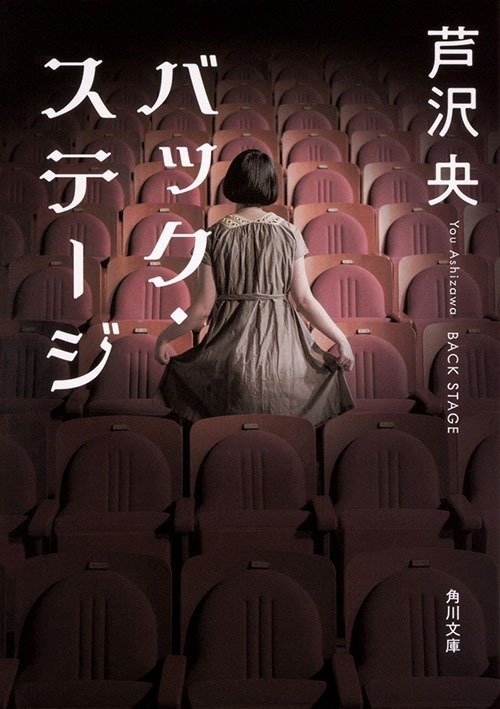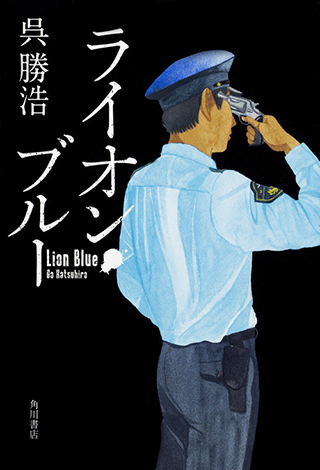「小説が大好きすぎて、その話がしたくてしたくてしょうがない二人」。
よりディープな小説論で盛り上がる後編に突入!
>>【前編】『カインは言わなかった』は気迫と描写力でねじ伏せてくる
関心が似ているけれど、アプローチが違う二人
芦沢:そういえば、担当編集者だったかな、呉さんが私のことを「関心が似ているけれどアプローチが違う」と言っていた、と聞いたのですが、どのあたりのことを思っているのかなと。
呉:『スワン』と『カインは言わなかった』は、演じること、演じさせられること、役割を選ぶことというあたりに、通じるものがあるという気がするんです。でも僕が『スワン』で結局やりたいなと思ったのは、社会と対峙するいずみが、自分が生き延びるために物語を捏造する選択肢を得ることなんです。それは現実に対応する上で仕方のないことだという前提で、でも、僕はいずみに「こうするのが賢い選択だ」と開き直ってほしくはなかった。それでもなお、彼女の中には負い目が残ってほしかったんです。嘘をつく、もしくは真実を明かさないっていうことは、負い目を抱え続けることなんだっていう。演じる時、その内側に本人がいるのかいないのかという問題がありますが、僕は本人がいる派なんです。一人の人の中にいろんな面がある、分人だと言ったとしても、核になるような本人はいるって僕は思っていて、そこをやっぱり書きたいというのがあります。
で、『カイン~』は若干違う気がする。なんか、本人が外からの圧力によって侵食されて、新しい形に変わっていく、みたいなものを感じるんです。外部からの圧力みたいなので自分が変形するみたいなのは、たぶん芦沢さんもテーマとしてあるんじゃないかっていう気がするんですけれど。
芦沢:ええと、分人であっても核になる自分があるということと、侵食されて変わるということは、相反することでしょうか。
呉:これが私だっていう核みたいなものが「ある」という前提に立てば、そこが侵食されることは、結構ハードな出来事だと思います。でも核が「ない」、つまり自己というのは相対的なところで形成される、という考え方もあり得ますよね。
芦沢:なるほど、なるほど。
呉:どちらがいい悪いの話ではなくて、『スワン』は乱暴に言うと、侵食してくる圧力に対して闘っている。『カイン~』の闘い方はまたちょっと違う。たとえばダンサーの尾上なんかは、むしろ侵食してくださいっていって、師匠に自分を差し出しているところがあるじゃないですか。他の人たちも、言い方が悪いけれど、いわゆる凡人たちが誉田なら誉田、豪なら豪に、「そっちに近づかせてくれ」っていっているように思えるんです。
芦沢:めっちゃ面白い指摘です! 実は裏テーマといいますか、尾上にしても絵画のモデルにしても、いかにして自我の輪郭が揺らいでいくかっていうところを、書きながら延々と考えていたんです。表現することやされること自体、自我の切り売りのようだけれど、でも自我って切れるものでもない。表現者というものを書く時点で、自我というものと侵食というものとが、切り離せない感覚がありました。それに、人は何かを創作する過程においていろんなことを言われるなかで変容するし、自分の創り出した表現物と相対するなかでも変容しうるし、外界からの評価とかでも変容するし。ということは私はたぶん、核がある派かどうかというよりは、変容していく派なんでしょうね。
呉:絶対に変わらないものなんて基本ないじゃないですか。それでも自分の中に「これは私であってほしい」という何かがあると僕は思っていて。もちろん、それを変えたいと思うモチベーションもありうるんですね。尾上はまさにそれで、自分に才能があるのかないのか分からずに自信が持ちきれなくて、誉田というスーパー外圧がかかってきた時に決して逆らわず、むしろ自己の核にある部分をそっちに寄せていこうとする。それは僕はやっぱり怖いなと思うし、ある意味、表現者が自分の核よりも別の何かに価値を置くというのが、面白いなとも思ったんですよね。
芦沢:たぶん、私自身とも関係しているのかも。私自身、そんなに自分自身を信じていないんです。自分がとんでもないものが書けるとか、みんなが思いつかないことを思いつくとか、それこそ核みたいなものをあらかじめ持っているという感覚が微塵もないんですね。微塵もないから、変容させていくしか手が届く方法がないと思っているのかも。
たぶん、豪は核がある人間なんですよね。だから彼だけがちょっと違う描き方になったのかもしれませんね。尾上は「誉田は神」と思ってすり寄っていっているというより、核がないからこそ変容している。ある意味、私や尾上のように核のない者にとっては、変容は希望なんです。いかにして外界の圧力をタコ殴りに受けていくかっていうのは、自分を変えさせる戦いでもあるんです。
呉:ああ、なるほど。今回、バレエを書くのは結構大変だったんじゃないですか。僕の『スワン』の場合は言っても女子高生が習い事の範疇でやっていることですけれど、『カイン~』は世界トップレベルの話だから。
芦沢:そうなんです。だからいろんな人に取材したんですよね。もちろんバレエやコンテンポラリーダンスも観に行ったし、振付家の方に話を聞きに行ったり、あと公演前のリハを見せていただく機会にも恵まれました。『カイン』ではバレエの他に絵も大きな軸としてあったので、画家や画廊の方にも話を聞かせていただいたり。自分の想像だけではたどり着けないような語彙や発見がたくさんあって、ものすごく刺激的でしたね。呉さんはどの程度取材をしますか。ロケハンをしたと言っていましたが、結構現地に足を運びます?
呉:なんとなくこのあたりかなと考えて、Googleマップで上から見て、「あ、ここに何かあるな」って。関西圏だったら見に行くんですけれど、さすがに東京とかだと難しい。だいたい直感で使うんですけど、あまりその土地に意味付けするのも微妙なんで。
芦沢:ああ、『スワン』は自治体の人に「小説に舞台にしてもらった」といって喜んでもらえるタイプの話じゃないから(笑)。私は今回、バレエに詳しい人に監修として読んでもらいました。それで、単語レベルでギリギリまで直しましたね。
ダンスはかじったことがあるし、これを書きながらレッスンにも行ったし、取材もして本も読んだのですが、知識を得れば得るほど、その知識の単語を書いてしまうんです。監修の人に見てもらったら、「こっちはアメリカ由来の言葉ですが、こっちはフランス語になってますよ」と言われて、それで、そもそも技の名詞に頼っちゃいけないと気づいて、最後の最後で技の名前を削って、自分の言葉で書き直す作業をしました。
自分の痕跡を消していくんです(芦沢)
呉:けっこう粘って原稿を直すタイプ?
芦沢:粘ります。
呉:僕もごちゃごちゃ粘るタイプ。語尾とかも直そうとしたらキリがない。点の打ちどころとかも。放っておいたら延々とやってしまうから締切って大切(笑)。
芦沢:大幅に書き直すことはありますか。
呉:僕は『白い衝動』を書いた時に全ボツを食らって、設定から書き直したんですよね。江戸川乱歩賞の授賞式にお祝いに行ったらそこにいた担当編集者に「あれはもう出すのやめましょう」って言われて。「ワンチャンください」と言って、そこから設定から何から、2週間で書き直しました。
芦沢:2週間で!
呉:まあ、元があるのでね。でも大変でした。あれはもともと違う舞台だったのを、学校を舞台に書き直したりして。大変だけど、実際に書いてみるっていうのはもう、どうしようもなく有効な手段ですよね。その労力を迷いなく捨てられるならね。
芦沢:私も考えるより、書いてみてそれを捨てるほうが早いですね。ぐずぐず考えていると、まったくやらないまま平気で日々が過ぎていく。朝、子どもを保育園に預けて戻ってきて「どうしようかな……あ、お迎えの時間!」っていうことは結構あります(笑)。迎えに行って、「ごめん、かあちゃん今日、何もできなかった。こんなことならお前と一緒にいればよかった」って泣きそうになります。
呉:僕の場合、そういう時はずっと漫画を読んでいます。一人でぼーっと漫画読んで3日経っていて「これは何かヤバイのでは?」ってなる。1週間、言葉を交わした相手がスーパーのおばちゃんだけっていう時もあるんです。「箸要りますか?」「はい」が1日の会話のすべて。最近、箸が自分で取れるようになって、もう話すこともなくなっちゃって。何か習い事をしたり、社会と接するように心がけていることってありますか。
芦沢:いいえ、特には。人と話すといえばインタビューを受けるとか。ただ、今日は対談ですけれど、普通のインタビューだと、私が90%くらい喋ってるんですよ。だから普通にママ友とかと喋る時、どうやって喋るんだっけ、ってなります(笑)。喋りすぎないように気をつけなくちゃ、って。
呉:それほんと分かる、マジで。
芦沢:書き直した話に戻すと、『カイン~』で大きく直した箇所があって。最初は有美という人物が豪の絵を画集で見るシーンがあったんです。でも、再校が出る前日くらいにホキ美術館に行ったんですね。前日に予習のつもりで美術雑誌に掲載されている絵の写真を見て「フーン」とか思っていて。で、美術展に行ったら、その「フーン」と思っていた絵が「これすごいわ!」ってなって、遠ざかったり近づいたりして何度も何度も見て、帰りにポストカードを買おうと思って見たら、また「フーン」って。やっぱり絵は実物を見ないと駄目だなと思い、その画集を見るシーンを、実施に個展を観に行くシーンに書きかえました。
呉:ああ、あの場面ですね。あれをギリギリでやるんだ、すごいね。
芦沢:もっと早くやれって話です。あとは、ある人物が犯人の動機について考えるシーンがありますよね。ミステリーの、「ここから解説の時間に入ります」みたいな部分。
呉:ああ、「今から伏線回収していきまーす」っていうところね。
芦沢:あそこがどうしても、登場人物が芦沢に言わされ始めたみたいにならないよう、いかに本人の体験から本人の言葉が出てくるようにするかは、最後の最後まで納得がいかなくて、何度も直しました。
呉:分かります。今回、僕は女子高生をメインの視点人物に選んでいるじゃないですか。で、わりと難しいテーマを扱っている。読者に伝わらなかったら嫌だから、女子高生にテーマ的なことを言わせたくなる。でも、それをシンプルに小説的に書こうとすると、装飾的になるんですよね。女子高生はこんなの知らないだろうという単語を使いたくなってしまったりして、これは登場人物の声なのか、作者の声なのか分からなくなる。特に自分と知的レベルや語彙力に差のある登場人物を選んだ時は難しいですね。
芦沢:私は第一稿では、自分の声がもろに出ちゃうんですよ。だーっと書いて、読み返して「おまえ、私じゃん」ってなるんです(笑)。
呉:それ、分かるわー!
芦沢:そこから、自分の痕跡を消していくんです。
呉:僕もバーッと書く時はそうなりますよ。でも、僕は結構、文章を直しすぎて分からなくなることがあるので、なるべく一発目でそれなりの言葉を出そうと考えます。そうすると執筆のスピードが超遅くなりますね。1日3枚とか5枚とかいけばいいほうで、それも5、6時間かかったりしちゃって。しかも、後からプロット上その部分が要らなくなったりするの。だってプロット決めないで書いているから。
芦沢:こねくり回した箇所を後で全部削除ってありますよね。私、『カイン~』で松浦という男性の視点人物は全部、差し替えました。
呉:へーっ。
芦沢:自分では、性別も年齢も考えていることも全然違う視点人物を書いているつもりでしたが、担当編集者に「全員トーンが似ている」と言われたんです。
呉:耳の痛い話だわ。
芦沢:全員追い詰められていて、みんな同じ緊迫感で、「声の大小が一緒です」って。「声を変えていきましょう」と言われてしばらく頭を抱えていたんだけれど、松浦に関しては心理描写はやめて、自分の声はあまり出さない人で、奥さんとか他の人の声を聞く人物にしたんです。だから漏水検査で水の流れに耳を傾ける仕事をしている、というのが描写に役立ちました。
呉:松浦の存在はいいアクセントになっていますよね。松浦が居酒屋で、元団員たちに対して「いいから食えよ」って思う、あの苛立ちの表現がいいよね。
芦沢:みんな「現役時代はこんなの頼めなかったよね」と言って注文しつつ、結局食べないっていう場面ですよね(笑)。
たぶん、演じることが大好きなんですよ(呉)
芦沢:呉さんは、いろんな人の声が書けますよね。それも、むちゃくちゃな倫理観や価値観を持っている人の台詞がすごくうまいですよね。『道徳の時間』で、恐喝者に対して主人公が「いらんスケベしとったら馬鹿見んのはそっちやぞ」って言うじゃないですか。「もうそのへんにしとけ」って意味で。ああいうフレーズが私からは出てこないんです。
呉:あれは、『ナニワ金融道』読んでたら出てくるようになりますから。
芦沢:(笑)。ヤクザな言葉も使えるし、女子高生の言葉も使えるし、なんかもうたくさん武器を持っていていいなと思って。
呉:たぶん、演じることが大好きなんですよ。実際に演技することじゃないですよ。たとえば、中学、高校くらいまで、通学中に頭の中で、既成のキャラを借りながら、ヒーローを演じる物語を勝手に作っていましたから。頭の中で演じるんです。
芦沢:ツッコミどころ満載な人を書く時、頭の中に自分が残っていて「いやおまえ、その論理破綻してるから」ってツッコんじゃうことはないですか。
呉:僕もそういうのは苦手ですよ。バカすぎる人間とか、あまりにも嫌なことだけするために生きているような奴を普通の一般人として書くのはできないです。そんなことを生きがいにしている奴の気持ち、俺も分からんし、あんまり自分が読んで楽しいと思えなかったりするし。そこに若干自分の世界の狭さがあるから、書けるようにならなきゃなって思う時はあります。書けない人っていますか?
芦沢:今聞きながら「めっちゃ同意」と思っていたんですけれど、私も、そういう思考をまったく持っていない人を書くのが苦手です。でも、松浦を書いた時に、こういう手札があるなら、もしかしたら今後は書けるようになるかもしれないなと思いました。
呉:次の小説は、どんな感じになるんですか。
芦沢:迷走中です……。
呉:同じくです……。じゃあ、未来に向けた話はやめておこう(笑)。
芦沢:なんか、今日の対談に向けて呉さんの作品を再読したり、未読だったものを読んだりして、改めて揺さぶられまくっていて、どうしようかと。私が持っていない部分をすごくいっぱい持って
いるから。
呉:その言葉はまあ、そのまま返しますけどね。
芦沢:『スワン』を書いたことによって、なんか変わったぞって思えるものがあるんじゃないですか?
呉:書けちゃった感はあります。だから、この後が本当に大変だなって思っていて。書けちゃったこと自体は嬉しいんですけれど、「これを超えねば」みたいな。あなたも一緒よ? 『カイン~』を超えなきゃいけないんだから。お互いに頑張りましょう。
芦沢:はい。今日は楽しかったです。私、はじめて呉さんにお会いした時、へべれけだけれども絶対にこの人真面目だなって思ったんです。「おまえさぁ」みたいなノリでも、本当に小説について真摯に考えて、小説が大好きすぎて、その話がしたくてしたくてしょうがない人だっていうのは感じていたので、今日素面でお会いしても、呉さんの印象は変わらなかったです(笑)。
呉:僕は小説に真面目じゃない人間とはあまり仲良くなれないんです。僕は前回の記憶がないので(笑)、芦沢さんがこんなざっくばらんに小説のお話ししてくれる人だったんだっていうのが嬉しいですね。
芦沢:前回もざっくばらんだったような気がするんですけれどね(笑)。
ご購入はこちら▶呉勝浩『スワン』| KADOKAWA
試し読み▷無差別銃撃事件の最中に少女が見た光景とは――。 2019年最大の問題作。呉勝浩「スワン」
芦沢央(あしざわ・よう)1984年東京都生まれ。2012年『罪の余白』で第3回野性時代フロンティア文学賞を受賞しデビュー。17年『許されようとは思いません』が第38回吉川英治文学新人賞候補。18年「ただ、運が悪かっただけ」、19年「埋め合わせ」がそれぞれ日本推理作家協会賞短編部門候補に。18年『火のないところに煙は』で第7回静岡書店大賞受賞、19年本屋大賞、第32回山本周五郎賞ノミネート。他の著書に『悪いものが、来ませんように』『いつかの人質』『雨利終活写真館』『バック・ステージ』など。最新刊は『カインは言わなかった』(文藝春秋)。
呉勝浩(ご・かつひろ)
1981年青森県生まれ。大阪芸術大学映像学科卒業。現在、大阪府大阪市在住。小学生の頃に読んだアガサ・クリスティの『アクロイド殺し』 でミステリーの面白さに開眼。2007年頃から小説の執筆・投稿を始める。15年『道徳の時間』で第61回江戸川乱歩賞を受賞し、デビュー。18年『白い衝動』で第20回大藪春彦賞を受賞。他にも吉川英治文学新人賞、山本周五郎賞、日本推理作家協会賞の候補になるなど、話題作を発表し続けている。
関連記事
・【レビュー】21名死亡の拳銃乱射事件。生き延びた少女が抱える秘密とは――。 乱歩賞作家が世に問う、10年代ミステリ最後の衝撃作!『スワン』
・【インタビュー】パワハラ上司の弱みを掴むべく奮闘する凸凹コンビ……。大注目作家の新境地!『バック・ステージ』