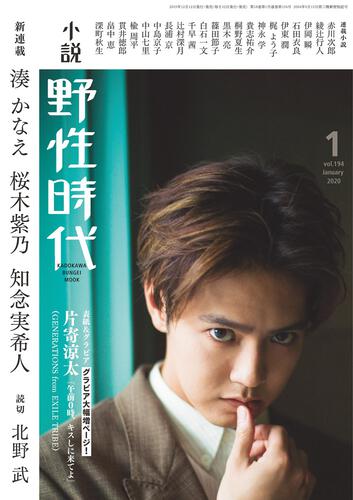「ミシュランガイド東京2020」で二つ星として掲載され、現在木村拓哉さん主演で大好評の連ドラ「グランメゾン東京」の料理監修をつとめている「INUA」を村田沙耶香さんが訪問!
その未知の食体験をエッセイで綴っていただきました。
私は「食べる」のが好きだ。
といっても特にグルメなわけではなく、食べることで、何か未知の感覚を獲得することが好きなだけだ。「食べる」ということは、私にとって、ある物体や物質を、「食べ物」という角度から改めて知る、ということなのだと思う。
けれど、それを美味しそうに書いたり、レビューしたりすることはまったく得意ではない。なので、最初にこの依頼を頂いたとき、とても悩んだ。書いてみたいなあと思ったのは、宣伝ではなく純粋に未知の食体験を私なりに言語化してほしい、というご依頼だったことと(たぶん)、INUAが遺伝子を引き継いでいるという「noma」があるデンマークが、個人的に思い出深い場所だからだった。
デンマークに行ったのは夏だった。ルイジアナの文学祭に参加するためで、そのときなにか特別な食文化に接したわけではない。けれど、私はデンマークに行って、世界に対しての感覚が少し変わった、と感じていた。
編集者さんのTさんとMさん、女性三人でレストランに出向いた。TさんとMさんは素敵で親切な女性お二人だが、いつもお仕事でお会いしていて、プライベートをご一緒したことはない。これもお仕事だが、なんとなく心細いので、こっそりと、小学生のころの私を連れていくことにした。
「デンマーク、行ったことある?」
と聞くと、小学生のころの私は首を横に振った。そういえば、このころの私は好き嫌いが激しく、違和感のあるものは決して飲み込もうとしなかった。それがいつからか、不思議なものこそ食べたい、感じたいと思うようになっていた。所在なげにしているので、「名前は?」と聞くと、「さゆり」と嘘をつかれた。子供のころ、憧れていた名前だった。
雨の日で視界が悪く、入り口のことはよく覚えていない。中に入ると、静かな細い空間で、食べ物の音も匂いもしなかった。Tさんが受付で予約名を告げ、奥のエレベーターへと案内された。少しダンジョンみたいで、わくわくする。横を見ると、さゆりは憂鬱そうだった。
私はレストランの「空間」が好きだ。元はコンクリートの何もない部屋だったものが、置かれる家具、壁の色、行き来する人の服装などで異空間になる。INUAは、リラックスするように計算されているようで、さゆりと同い年くらいの金髪の女の子もいた。
私は、美味しいレストランには二種類ある、となんとなく思っている。妊娠した友達に、子育てで忙しくなる前にレストラン巡りをしようと言われ、グルメな彼女が行きたいといういくつかのお店で食事をしながら思ったのだ。「意味がわかる美味しいお店」と、「意味がわからない美味しいお店」があるなあ、と。そんなふうに分類されていると知ったら、お店の人はがっかりするかもしれない。でも、私はなんとなく、「INUA」は「意味がわからない美味しいお店」の典型なのだろうなあと、決めつけていた。だから、さゆりをこっそり過去から連れてきて、テーブルに座らせようと、変なことを考えたのかもしれない。当時の私にとって、「意味がわからない美味しいもの」は、どんなに薦められても、口に入れられても、絶対に飲み込まない、世界で一番恐ろしいものだったから。
そうこうしているうちに、最初のお皿が運ばれてきた。メニューがどこにも置かれていないので、何が運ばれてくるのかは予測できない。最初にきたのは、スポンジに緑色の絵の具が載ったような、一目では甘いのか辛いのかもわからないものだった。
「溶けてしまわないよう、早めにお召し上がりください」
そう説明され、ついつい、あれ、溶けるものなのかな、とお皿を覗き込む。はっと顔を上げると、TさんとMさんも同じ体勢でお皿の中の物体を見つめていた。
この、「お皿を覗き込む」というポーズはこのときだけではなく、ここから先デザートとメニューにはないお口直しまで、十三皿全てのお皿が運ばれてきたときにとられた。姿勢を元に戻すと、お店の人が、なんだかおとぎ話でもするように丁寧に料理を説明してくださって、再び「へえー」と同じポーズになる。なので、最低でも一人二十六回、お皿を覗き込む姿勢になったと思う。
最初のお皿について、膝の上に置いていたメモにはこう書いてある。
「あんきも アイス
ふかふかふわふわ」
食後に頂いたメニューには、鮟肝テリーヌ、炭火焼きインゲン、ブナの実、とあり、半分も話を聞いていないことがわかる。不思議な食べ物を、ただ感じるのに夢中になってしまったのだ。その食べ物は、アイスクリームのように冷たくて、鮟肝の香りがしっかりと感じられ、でも、口のなかに入れるとすぐに消えてしまった。
「わー、すごいですね」
Tさんと、Mさんと顔を見合わせ、感動を伝え合う。私は、食べながら友達とお喋りをするのが好きなので、「お仕事だから」と少し緊張感のあった自分たちのテーブルの空気が、一気にほぐれた気がした。何か悪い商談をする人たちにはきっとすごくいいのかもしれない、なんだか油断するし、と失礼な想像をした。
ふとさゆりを見ると、口を閉じて、皿の中のものから目をそらしていた。あのころの私は、何がそんなに怖かったのだろう。「意味がわからない美味しいもの」には毒が入っていて、殺されると信じているみたいだった。
そこから連続して運ばれてきた、全てのお皿が、絵本に出てくるような、不思議な見た目だったと思う。けれど、物語のようにこのお皿が出来上がったいきさつを説明されると妙に腑に落ち、口に入れて体でも知ることになり、なんだか全身を、食べられる知識で支配されたような気持ちになるのだった。
一応、全てのお皿についてメモをとっていたのだが、後で見返すと、自分だけが「あー、あれね、あれあれ」と理解し、他の人にはうまく説明できない変な走り書きばかりだった。
「柑橘類 オリジナルの七味(トマト! ハイビスカス!) カシスの葉っぱ」
「キッチンの人が走ってきて、舞茸を見せてくれて、また去っていった」
「白海老 麹 ケーキ 発酵している 薔薇のペーストを塗ってある ちょっとお寿司っぽい」
「さっき見せられた舞茸 5日寝かせて3日薫製 ※ずっとやってるメニュー! これだけ! 桜の花の塩漬けをパラパラかけてたべる 液体は真っ黒、でもしょうゆは使っていない」
「プラムのジュースをシートにしてめくって手で食べる ※本物のフォトフレーム 一口でいろんな味 花びら きれい」
「手で食べるメニューが多いですね」
Mさんがふと言った。
そういえばそうだ。以前スリランカに行ったとき、「手で食べると味が違う」と教わったことを思い出した。熱くないものは、指先の感覚まで使って、より純粋な味で食べてほしいと思ってらっしゃるのかなあ……と勝手に妄想した。ヘッドシェフのトーマスさんは、この日はいらっしゃらず、なので私の中で架空のトーマスさんがどんどん大きくなっていった。カトラリーも、できるだけ軽いものにと非常にこだわってらっしゃる、と妄想でなければだれかが教えてくれた気がする。
「えだまめのシチュー ブーケでかきまぜる! きれい すてき」
が出てきたときは、「わー」と歓声をあげ、MさんとTさんと、ブーケの匂いを嗅いだり、花を見つめたり、顔を見合わせて微笑んだりした。そういえば、普通のレストランよりも、いろんな人の顔を見ている気がする。なぜだか、みんな笑っている。厨房というものはピリピリしたムードが漂い、真剣な怒鳴り合いが聞こえてきたりするものだとなんとなく思い込んでおり、オープンキッチン、正直胃が痛いなあと思っていたのだが、シェフの方々は笑顔で、食べ終わったお客さんと肩を組んで写真を撮ったりしている。
食べている私たちも力が抜けてきた。Tさんは真面目に私にいろいろな知識を教えてくれていたが、ペアリングで出てきた緑色のジュースが異常においしかったときから急に笑顔が増え、「私これ大好きです」「これはなんですか?」「緑のジュース美味しかったですよね」とずっと仰っていて、お仕事ではない楽しさを味わってくださっているのならうれしい、と思った。Mさんは普段からほんわかした方だと感じていたのだが、「この器、一人一人模様が違いますね」と、ふんわりした口調で意外なほどいろんなことを発見していた。
私はもっぱら、人の表情を見ていた。同じテーブルで食事をしていても、三人とも、違う眼差しでこの空間を、感じているんだなあと思った。このレストランの心地よさは、その小さな発見をお互い教えあって、「わー、ほんとだ」とはしゃぐことができる、無邪気でいられる空間を、わざと作ってくれているということなのだと思う。まんまと無邪気になっている自分がすっかりコントロールされているようで怖い気もしたが、真っ白なテーブルクロスが掛かったお店ですべての人がきりっと、うやうやしく振る舞っていたら。それはそれで、緊張感という非日常に包まれることになるわけで、そういう意味では、私たちはいつもレストランというものにコントロールされているのかもしれない。このレストランから差し出された非日常は、「奇妙なほどのリラックス」という異空間だった。
なんとなく、少しだけ天界に近い場所にいる気持ち。それは、私が夏にデンマークを訪れたときの感覚と、よく似ていた。海と空がいつもよりずっと近くて、一日中、青だけを眺めていた。服のまま砂浜に寝そべって海と空を見て何時間も過ごした、子供みたいな時間。「いつかまた行きたい」とずっと願っている遠い国で感じた空気が、このレストランの中にも少しだけ、発生しているような気がした。
デザートには、アイスクリームとともに、蜂蜜で漬けた松ぼっくりが出てきた。子供の頃拾い集めたあのかわいいものが「食べられる」ということもうれしかったし、「これを探してスタッフみんなで取りにいったんです」という話もあたたかかった。
デザートのワカメのミルフィーユも美味しく、「ワカメがデザートなんて想像つきます!?」と私もかなり砕けてTさんとMさんに話しかけており、気が付くと、目の前の人間たちに集中していて、妄想のさゆりはどこかへ走り去っていた。
あのころの私が、絶対に口に入れなかったもの。でも、デンマークで育っていたら、毎日あの海と空の間にいたら、きっと笑顔で手を伸ばして食べていたもの。幼少期の自分の潔癖さが、少し悲しかった。食べることは信じることだから、「意味のわからないもの」を信じることができなかった幼少期の私は、清潔な日本で必死に生きていたというだけなのだろう。私がさゆりに本当に食べさせたかったのは、デンマークに漂う空気、そのものだった。
高いお店だということはわかっていたが、どうしても大好きな友達とINUAに来たい、という気持ちになった。
「今日、仕事でINUAに行ってきたよ」
うまく誘うことができず、メッセージアプリでそう送った。
「わー、そうなんだね、美味しかった?」
「うん」
「よかったね」
どうしても、一緒にブーケでえだまめのスープをかき混ぜながら「わー、きれい!」と一緒に笑いたいと思ったのだが、うまく言い出すことができなかった。
ワインのせいだけではなく、なんだかふわふわ高揚していた。少しだけ、三、四時間だけ、あのへんなレストランで育った人、になった気持ちなのだった。子供時代ではなくても、人は育つ。世界を吸収して変化する。私の四時間は、日本でもデンマークでもない、あの変な場所に使われ、そこで食べ物を摂取し、少しだけ育ったのだった。そういうことを、今度友達に会ったら伝えようと思った。
寝る前、いくつかの顔が浮かんだ。厨房を案内してくれたシェフの男性が、料理を作る場所を「実験室」と呼んでいた。確かに、成功品を運んでくる人たちの表情は、なんだか全員、あどけないのだった。実験室では、失敗作ももちろんたくさん出るのだという。そこで成功したお皿を、「わー! 見て見て!」と走って持ってきてくれる、白衣を着た実験者たちが浮かんだ。その実験はとても無邪気で、無垢な喜びがこちらにまで感じられて、つられてうれしくなってしまう、そんな空気の余韻が、私を包んだ。眠っている間、また少し、変なレストランの中で私は生きて、育つのかもしれなかった。
INUA
所在地:東京都千代田区富士見 2-13-12 KADOKAWA富士見ビル 9F
営業日時:毎週火~土曜日 18時~(ディナーのみ)/日曜ランチ(月数回、不定期)
公式サイト:inua.jp
◎INUAが料理監修をつとめるドラマ「グランメゾン東京」(出演:木村拓哉、鈴木京香 他)はTBS系にて毎週日曜夜9時~大好評放送中!
ノベライズ版『グランメゾン東京(上)』も角川文庫にて好評発売中です。
追加情報!
村田沙耶香の最新刊『丸の内魔法少女ミラクリーナ』は2月29日発売予定!
魔法のコンパクト片手に、モラハラ&DV男を撃退するアラサーOL、
初恋を忘れるために、初恋の人を監禁する少女、
性別の壁がなくなった世界でのせつない恋、
”怒り”という感情がなくなりつつある社会に、適応できず焦る女性……など、
『コンビニ人間』以前から今最も旬な最新作まで詰め込んだ、
村田沙耶香ワールドの神髄が堪能できる短編集です!