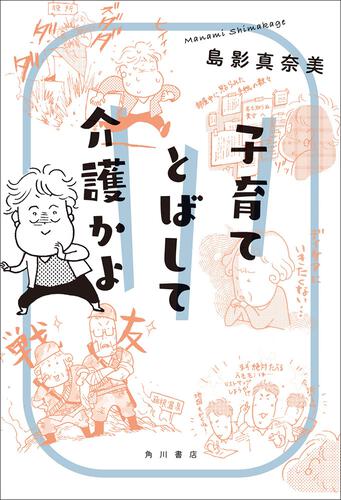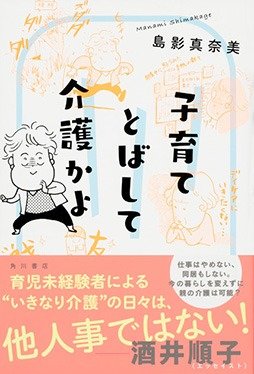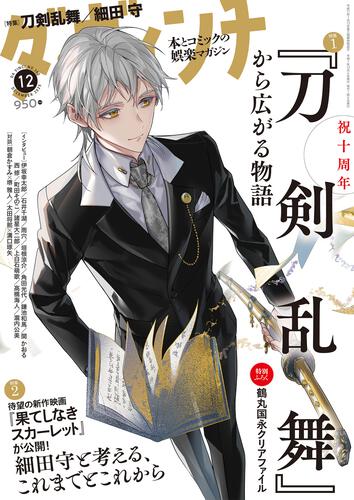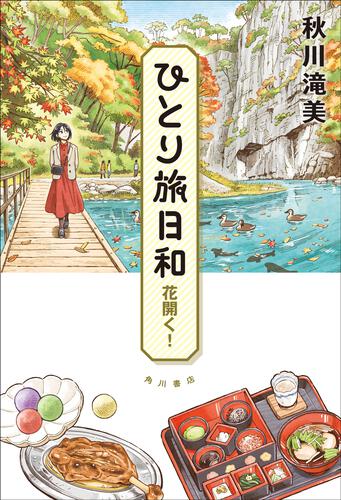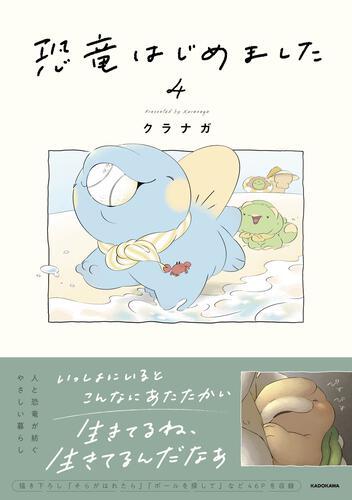見逃してしまった認知症の初期の兆候
前々から、うちの相方(『子育てとばして介護かよ』の著者・島影真奈美さん)に「(僕の)両親はご年齢もご年齢だから、いつか介護する日が来るかもしれない」と言われていた。が、数年前まではまったくピンと来ていなかった。もっと言えば、長く疎遠だったこともあって、そうした可能性から目を逸らそうとしていたし、「そうなったら難儀だなあ」とも思っていた。
なにせ、こちとらの父は銀行OB、母は教職出身。鬱陶しいくらいに口やかましく、指図がましい。ちょっと携帯に出ないだけで、スタッフのいる事務所の電話を鳴らすし、忙しいときにメールを放置すると「非常識だ」とセッキョーをお垂れになられる。
「えっと。自分たちが現役だった頃、職場である銀行や学校に個人的な電話をおかけになる文化、ありましたか?」「ていうか、零細自営業の忙しさ、なめんなよ」と内心では腹も立てていた。控えめに申し上げて面倒くさい。存在としては敬して遠ざけたく、関係としては「疎遠」そのものだった。
だから初期の兆候を見逃した。
僕は原則、仕事や遊びなど平時は理屈で動く。一方、災害などの非常時にはカンで動く。職業柄、情報収集の範囲は広く取るよう心がけているし、各方面のプロフェッショナルから学びを得る機会も多い。カンと言っても言語化できない経験則の積み重ねで、大まかな判断の精度は高いほうだと思う。いずれにしても、行動の土台には理屈がある。
だが、介護が始まる前、僕は「介護」「認知症」というものに対してまったく無知だった。僕個人は「医療」にあまり縁がなく、病院で治療を受けた経験もほとんどない。思い出せるのは歯の詰めものが取れて、交換してもらったときくらいだ。それさえも20年以上前のことである。
だから両親に「認知症の疑い」と聞かされても、家族としてどう行動すべきか思考が働かなかった。新聞で「認知症、社会で支えるには」というような見出しの記事を眺めることはあっても、それは傍観者の視点だった。僕自身が介護の当事者になったとき何をどんな順番で進めたらいいか、まったくわからなかったのだ。
最初に「あれっ?」と思ったタイミングは相方と同じ頃だったと思う。『子育てとばして介護かよ』にも書かれていた、「自宅の窓から女性が入ってきて、天袋を抜けて2階へ上がって」行くという“泥棒”の話に「なんだそりゃ」と思った。「寝ぼけまなこで夢の話と混ざったかな……」程度に軽く考えていた。「霊能力に目覚めた可能性も」と言ったのも、100%冗談というわけでもない。自分の知らない事実や常識は世の中にはたくさんある。
「何か理解を超えたことが起きている」ことだけはわかったが、安全な暮らしを脅かされているわけでもなさそうだ。「緊急性はさほど高くないだろう」、「折を見て確認しよう」と考えていた。それでも両親のことを気にかけてくれた相方のアドバイスで、両親そろって「もの忘れ外来」を受診することになった。そこから認知症という診断が下るまでの経緯は『子育てとばして介護かよ』に譲りたい。とにかく、両親の介護をレールに乗せて走らせるまでには、あれこれ紆余曲折があった。
良好だと思っていた夫婦関係
基本的に相方との夫婦関係はずっと良好だと思っている。互いにフリーランサーで、僕は地方出張も多く、彼女は大学院での研究も始めた。それでも話し合う機会は多いし、公私ともに共通の友人もたくさんいる。重要な事柄についてはもちろん話し合って決定するし、日常のよしなしごともよく話してきた。
彼女は地頭もよく弁も立つし、人として面白い。コミュニケーションのタイプは、僕と少し違っているけど、ウマは合う。強いて違いを挙げれば、僕の方が温厚で粘り強く、彼女は快活で突破力があるというあたりか。
付き合いはじめてしばらくは、人との付き合い方や物の見方が合わないところもあって、周囲に人がいたらドン引きされるような口喧嘩を何百回やったか数え切れない(実際、何度も友人たちにドン引きされた)。
その口喧嘩も口論とかディベートと呼んだ方がニュアンスは近かったかもしれない。理屈とロジックで相手を折伏するべく、自分の論における正義を主張し、反論も含めてバチバチにやり合う。そんな舌戦を夜10時に始めて、気づいたときには朝の8時。そのまま仕事に出かけるということも何度もあった(いま思えば「寝ろよ」以外の何物でもない)。
でも、それだけ全力投球のキャッチボールをしていると、互いの“常識”や暮らしにおけるルールのすり合わせができる。
例えば、日常の仕事や家事分担もそれぞれ得意分野で力を発揮して、苦手分野は相手に任せる。どちらも苦手なものは外注する。料理は僕が担当することが多いが、相方もやる。経理は数字に強い相方の担当。アイロンがけはどちらも苦手なので、クリーニングの手配はYシャツの枚数の多い僕、といった具合だ。ただし立て込み具合で、役割は適当に受け渡す。最小の人的コストで最大の結果を出す、ということでスタンスは一致していた。これは昔も今も変わらない。
介護という新しい課題に直面してもその姿勢と関係性は同じ、つもりだった。
俺、そんなこと言った!?
だから、彼女が介護のキーパーソンを引き受けてくれたことに感謝はしつつも、そう判断したこと自体に驚きはなかった。
きっかけは実家に遊びに行った介護経験のあるいとこが両親の異変に気づき、姉に地域包括支援センターに相談するよう、アドバイスしてくれたことだった。姉が面談の予約を入れた日時、相方も窓口に行くと言ってくれた。僕はどうしても外せない地方出張があったので、後ろめたさもありながら地方に滞在していた。
面談の日の夕方に連絡が入り「『医療とか介護の窓口、わたしがやります』って言っちゃった。ごめん」と言われて、「なんで、謝るんだろう」と不思議に思ったが、とにかく本によると僕は「文句があるわけないじゃん。賢明な判断だと思うよ」と返したらしい。
確かにそれに近い感想は抱いたと思う。彼女と僕(や姉)とでは、医療や介護についての予備知識のレベルがまったく違っていた。
彼女のご両親はふたりとも病院に勤務していた。とりわけお義母さんは病院で看護師長を務めたのち、ケアマネジャーの資格を活かし、介護施設でも働いていたという。そもそも相方も大学院で「老年学」の研究をしていて、誰に当たれば確度の高い情報を得られるか、アタリがつけやすい。本人の意に沿うのなら、彼女がキーパーソンを引き受けてくれるのが、最良の選択である。彼女もそう考えたから手を挙げてくれたと思っていた。
もっとも最初に本書のゲラ刷りを読んだとき、「俺、本当にそんな偉そうな言い方した? 意訳してない?」と思ってしまった。というのも、彼女がキーパーソンに最適任なのは間違いないが、内心「こっちの実親なのに……」と申し訳なくも思っていたからだ。そんな心持ちのときに、偉そうな言い方をするだろうか――。
そういえば過去のケンカでも、僕の言葉が額面通りに受け取られず、モメ事が炎上することがあった。いずれにしても、僕が伝えたつもりになっていた「申し訳ないな」という気持ちは届いていなかった。無念である。
妻の著書にあった「離婚」の二文字
さすがに本の中に「離婚を考えていた」という話が出てきたときには「マジで!?」と仰天した。「そんなそぶり、あったっけ?」と首をひねっても、思い当たるフシがまるでない。
出版後、その話になると、「本当、離婚届を取りに行かなくてよかったー」と本人は笑っていたが、こちらとしては「そこまで追い込まれていたのか」と言葉を失った。介護スタート当初から、散々「書け」と背中を押したエッセイのなかに、まさか「離婚」の二文字が書かれているとは思いもよらなかった。
そういえば当初は介護というものが、どんな体制でどう進むのか、その道筋も知らなかった。この数年の介護生活で、介護とは現実と折り合いをつけながら、本人にとって意味のある時間を過ごしてもらうサポートをすることだとようやく知った。
特に介護が始まった直後、キーパーソンである彼女のスマホには、連日たくさんの電話がかかってきた。両親の体の状態、物のありか、ケアチームの体制づくりなど、ありとあらゆる確認、連絡、相談が舞い込んでくる。電話の主もケアマネジャーに訪問看護師、複数のヘルパーなど、多ければ日に10本以上も電話でやりとりすることもあった。
周辺の介護者はもちろん両親や家族とのやりとりにも、大なり小なりストレスだってあったはずだ。それが頻繁なこととなればストレスは積み上がる。僕がそのフォローをできた日もあれば、取材や打ち合わせですれ違ううちに、ついタイミングを逃してしまう日も多かった。
それでも平日しか診療予約のできない、もの忘れ外来にも一緒に付き添っていたし、夫婦間でかなり突っ込んだ話もしていたつもりだった。「言う機会はいくらでもあったのに、追い詰められる前になぜ言わない」という腹立たしい気持ちも少しはあった。
でも、何からどう言えばいいかわからなくなるほど、彼女の負担は大きかったのだ。想像するとうなだれるしかなかった。
たとえ自分から手を挙げたとしても、実の親でもない老人2人の晩年の暮らしを支える窓口をつとめることがどれほどの疲労を伴うか。逆の立場にでもならなければ本当に理解するのは難しいのだろう。
それでも、昨年から入退院を繰り返している、父親の“看護”におけるキーパーソンを僕がつとめるようになってから、少しは近い目線で話をすることができるようになった気がしている。
当初は「目を逸らしたい」対象で「難儀だなあ」とさえ思っていた介護は、いつしか「時間をかけて、準備をさせてもらっている」と前向きに、ときには「あと何年続けられるかなあ」と楽しみに捉えられるまでになった。疎遠だった両親の黄昏時に伴走させてもらえることのありがたさも知った。そのことを教えてくれた彼女に、そして僕をこの世に送り出してくれた両親に感謝したい。
____________________
さて、ここまで書いた原稿を彼女に読んでもらった。
「少しエラそうにも見えるけど、わたしのことも含めてさすがによくわかってる。そしてわたし、われながらいい仕事してるよね! 介護のキーパーソン引き受けてよかった。本当、この数年でずいぶん親孝行になったねえ」
ちょっと待った。あなただって、けっこうエラそうである。
松浦 達也(まつうら たつや)
フリーライター、編集者。食にまつわる取材・執筆・コメントなどを幅広くおこなうフードアクティビストでもある。『子育てとばして介護かよ』(島影真奈美・著/KADOKAWA)には島影さんの夫として登場。
▼『子育てとばして介護かよ』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321901000063/