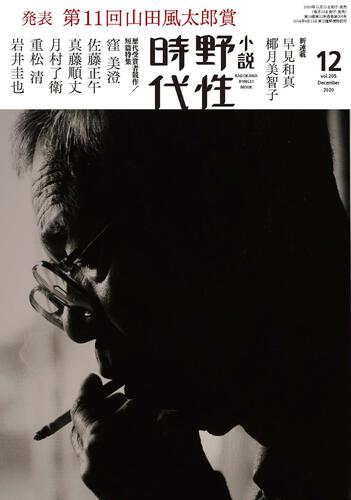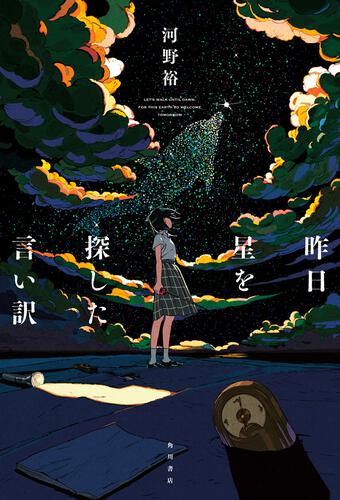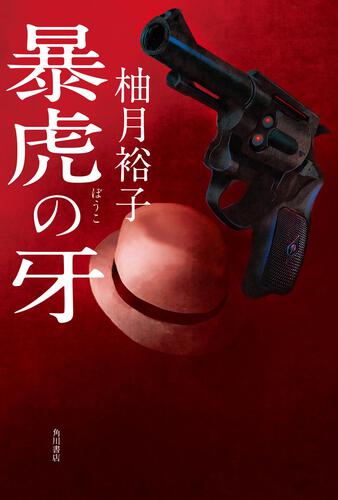山田風太郎賞概要
戦後日本を代表する大衆小説作家、山田風太郎。本賞は氏の独創的な作品群と、その作家的姿勢への敬意を礎に、有望な作家の作品を発掘顕彰するために創設されたものです。ミステリー、時代、SFなどジャンルを問わず、対象期間に発表され、最も面白いと評価された作品に贈られます。
対象作品
毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日 (奥付表記)までに刊行された日本の小説作品 (長編、短編集、連作短編集等)※刊行時の判型による除外作品はありません ※小説誌等の掲載段階では対象としません
賞品
正賞 記念品/副賞 100万円
選考委員
奥泉 光、恩田 陸、貴志祐介、筒井康隆、林真理子、夢枕 獏(五十音順・敬称略)
主催
株式会社KADOKAWA 公益財団法人 角川文化振興財団
選考経過
第 11 回山田風太郎賞選考会は、令和元年 9 月 1 日から令和 2 年 8 月 31 日までに刊行された対象作品の中から、上記 5 作品を最終候補として、令和 2 年 10 月 16 日午後 2 時より行われました。奥泉 光、恩田陸、貴志祐介、筒井康隆、林真理子、夢枕 獏(五十音順・敬称略)の選考委員 6 名による討議の結果、今村翔吾『じんかん』を受賞作と決定いたしました。なお、選考委員はお互いに距離をとりアクリル板を立て、新型コロナウイルス感染防止策を講じた上で選考を行いました。
候補作品(著者名五十音順)
- 今村翔吾『じんかん』(2020年 5 月刊 講談社)
- 河﨑秋子『土に贖う』(2019年 9 月刊 集英社)
- 河野 裕『昨日星を探した言い訳』(2020年 8 月刊 KADOKAWA)
- 凪良ゆう『わたしの美しい庭』(2019年 12 月刊 ポプラ社)
- 柚月裕子『暴虎の牙』(2020年 3 月刊 KADOKAWA)
受賞作 『じんかん』今村翔吾
受賞の言葉
「風太郎のいる空」今村翔吾
まず予備選考に携わられたKADOKAWA、関係者の皆様、何より選考委員の先生方に心より御礼申し上げます。
私が山田風太郎と謂いう作家に出逢ったのは、今から二十三年前の1997年のことだったと思います。当時の私は中学一年生。小学五年生から歴史、時代小説を読み漁り始めていた私は、何故、もっと早く知らなかったのかと悔いたことをよく覚えています。当時は山田風太郎先生がまだご存命。私が読んでいた本の作者は、すでに他界されていることが多かったこともあり、
「この世界に山田風太郎が存在し、同じ空気を吸っているのか」
と、不思議な気持ちで空を見上げたものです。
その時の私が、その名を冠した賞を受けると知れば何と言うでしょう。きっと無邪気にはしゃぐだけではないでしょうか。山田風太郎という名には、少年の心を無条件にときめかせる何かがあったのです。故に、この場ではその名に恥じぬ云々――と書くべきなのかもしれませんが、敢あえてこう言わせて頂きます。
今を生きる読者だけでなく、まだ見ぬ次の世代の胸を躍らせる。私もそんな作家になりたい。そのために今後とも誠心誠意精進して参ります。
選評
選考の指針 奥泉 光
とにかく面白い小説を選ぶ、というのが山田風太郎賞の理念なのだけれど、しかし面白いと思うのは読者ひとりひとりなのであって、小説の面白さなるものが普遍的に存在するわけではない。事実、今回の選考会でも、ある選考委員が「面白くて一気に読んだ」と述懐した作品を、べつの選考委員は「退屈して読むのに難渋した」と評する、そういうことがあったわけで、まあ小説とはそういうものである。文学賞の選考会では、「こういう読み方があるのでは」といわれて見方が変わることはある。しかし作品への評価は変わっても、退屈だったものががぜん面白くなって頁をめくる手がとまらなくなりました、とはなりにくい。山田風太郎賞の選考はなかなかむずかしいのである。
で、今回の候補作五作品のなかで、夢中になるとまではいかないが、自分がいちばん面白く読んだのは、河野裕氏の『昨日星を探した言い訳』であった。全寮制の中学高校を舞台にした一篇は、思春期の少年少女の心情を活写した、というのでは必ずしもなくて、虚構世界を緻密につくりこんだファンタジー小説というべきだろう。理知的な構成におかれることで人物たちは熱を放ち、端正な幾何学的文様をなす小説は過剰ともいうべき熱気を帯びる。脚本の結末をめぐって主人公の男女がすれ違う物語の結節点では、図形の線がやや乱れてしまった印象はあるものの、飽かず読み終えることを得た。
受賞作となった『じんかん』の、自由都市形成の萌芽とその思想化の可能性を戦国日本に見出し、それを虚構の形で展開する今村翔吾氏の姿勢には共感した。小説も、
凪良ゆう氏『わたしの美しい庭』は完成度が高く、まったく文句はない。これはこれでよいとしかいいようがない。広く読者を獲得しうる作品だろう。しかし自分はどうしても小説に過剰なものを求めてしまう。小説の真の面白さとは、ときに作品の均衡を破壊しかねぬほどの過剰性にあると考えるからだ。本賞が破天荒な作品を数多く書いた山田風太郎の名前を冠している点も、推しにくい原因となった事実はいなめない。
柚月裕子氏『暴虎の牙』の力感あふれる物語は、昭和五十七年および平成十六年の二部構成になっている。暴対法施行の前と後など、時代の変遷を踏まえた狙いがそこにはあるのだろうが、残念ながら不発に終わっている。そのせいで、全体の輪郭がぼやけ、楽しみにくくなってしまったのではないかと思う。
河﨑秋子氏の『土に贖う』は、エンターテイメントとしての結実度はおくにしても、舞台である北海道の大地や空の匂い、手触りが、もっともっと伝わらなければ、作品が力を得ることはできないのではないかと感じた。とはいえ近代日本の歴史に埋もれ、忘れられた人間の姿を描くという、小説というジャンルがぜひとも扱うべき主題の選択には共感できる。であればこそ鮮烈な描写がほしい。今後に期待したい。
心残り 恩田 陸
『じんかん』。タイトルが素晴らしい。「どういう意味なんだろう?」と読み始め、ああそういうことかと納得し、読み終えて改めてタイトルの意味が心に響く、という、小説のタイトルのお手本のようだ。
『土に贖う』。北海道の滅びゆく第一次・第二次産業というコンセプトで統一された作品集である。ひじょうに渋いこの題材を選び、なおかつ書けるというのはたいへん地力のある方だと思うが、いちばん不満に感じたのは、どれも使った資料が透けて見える点だった。資料にこういう写真があって、こういう記録があって、というのがみんな想像できてしまうのだ。読んでいてお勉強の跡が気になるのは、読者が小説に集中できていない証左である。著者の経歴を聞いていたので、さぞかし身体性のある描写なのだろうな、と期待していたせいか、意外にそういうところが感じられなかったのも残念だった。
『昨日星を探した言い訳』。黒い目の持ち主が緑の目の持ち主を差別している、という設定は不要だと思う。この設定がなくても、この話はじゅうぶん成立する。なぜ「イルカの唄」の悲劇的ラストを打ち明けなかったのか、どうしても納得がいかない。「愛しているから、傷つけたくなかったから」と説明しているのだが、むしろそれならば打ち明けるほうがよほど理に
『わたしの美しい庭』。たいへん気持ちのよい、欠点のない作品である。どの登場人物の心情も、共感できて愛おしくなる。そして、タイトル通りあくまでも「わたしの」「美しい庭」であって、その外に出るつもりがない。この作品はこれでよいと思うので、他の候補作と比べた場合、話が小さく感じられてしまうのは不可抗力というものだろう。
『暴虎の牙』。『孤狼の血』ファンの私は、改めてシリーズ第一作、第二作を読み直してからこの作品を読んだ。『じんかん』と『暴虎の牙』の二作受賞になればいいな、と推す気まんまんで読み始めたのだが、残念ながら、この小説単体でも、三部作のしめくくりとしても、成功していないと感じてしまった。
足腰が強くブレない物語 貴志祐介
今回から選考委員の末席に加わることとなった。おまえに書けるのかというブーメランも覚悟しつつ、一読者として選考に臨んだ。
『土に贖う』
緩やかな連作短編集だが、一本目の「蛹の家」を読み始めたときは、ホラー小説になるのかと誤解した。だが、読み進めるにつれ、作者の意図はあきらかになった。北海道を舞台に、隆盛を極めて消えていった産業、なりわいを描くことで、時代の流れに吞み込まれた人々の一瞬の思いをすくい上げようとしたのだろう。白眉は「うまねむる」で、埋葬される巨大な馬の死体の上に落ちた少年の感じた冷たさは、実体験ではないかと思うほど印象的だった。
ただ、作品によって、ばらつきも感じた。「南北海鳥異聞」は、ラストがすばらしいが、島に取り残された途中のエピソードが強すぎ、バランスを損なっている。表題作においては、不良品のレンガを自らに重ねる工員の述懐は書かずもがなだろう。
『昨日星を探した言い訳』
思春期の少年少女の感覚が、みずみずしく綴られている。他者と関わりたいと願いつつ、傷つきやすすぎる自我を守るために言葉で自らを
『わたしの美しい庭』
穏やかな時間と、優しい人々。この読み心地を愛する読者の気持ちはよくわかる。欠点らしい欠点がないという意見も多かった。しかし、私には、(ほとんど読んでいないのだが)少女漫画臭が強すぎるように感じられた。縁切り神社の参拝者には不気味な女性もいたので、一編だけでも怖めのエピソードを入れていたら全体が締まったと思うのだが、これは完全に好みの問題かもしれない。
『暴虎の牙』
この長さを一気読みさせる筆力は、さすがだろう。一方の主人公である大上という刑事は、魅力に溢れ、作者自身も大好きなのが伝わってきた。ただし、三部作の三作目というのは、ハンディになったかもしれない。一作目と比べて云々というのは、言いたくなかったのだが。
物語も、大上の死後は、やや失速したように感じられた。
『じんかん』
松永
第一章の孤児の時代のエピソードは躍動感に満ちており、選考委員全員が絶賛していた。史実に縛られる後半生は窮屈になったという意見もあったが、私の目には、第一章の少年が、そのまま成長したように自然に感じられた。戦国大名が「民主主義」の思想を持つことへの批判もあるだろうが、愛する多くの人たちを失ってきた悲しみから生まれた思いだとすれば、これも充分にうなずける。要は、物語の足腰が強く、ブレがないのだろう。
この作者は、筆力と読みやすさ、爽やかさを兼ね備えた、本物の大器だと思う。今後も、さらなる活躍を期待したい。
風太郎賞的な作品とは 筒井康隆
青春時代、多くの若者は自分の性格を勝手に規定し、自分なりのテーマや言動に忠実だと思い込む。それほどではないということを後で知ったりもするのだが、河野裕『昨日星を探した言い訳』では、そのあたりのことが繊細に、正しく書かれている。言わば大人の小説だ。差別問題も出てくるが、部落問題のように陰湿ではなく、黒人問題と同じく外見からそれとわかる差異だから案外明るくて、大きな問題を語っているぞという点数稼ぎでないこともはっきりしているので読んでいて不快感はない。ロマンチックで文章もよく、風太郎賞的ではないものの、候補作の中では一番よくできているので、これ以外に受賞作はないと思わせられた。
凪良ゆう『わたしの美しい庭』は、主要登場人物の大半が美化されて、美しい物語に奉仕している。
歴史小説には新しい視点が必要だが、今村翔吾『じんかん』の場合は「松永弾正久秀は悪人ではなかった」というものである。難しいのはそれ以外の歴史はよく知られていることばかりという点であり、このあたりをどう退屈させずに語っていくかという技術だ。一向一揆の盛り上がりは素晴らしいが、後半のよく知られた歴史の場面になると退屈になってしまう。ラスト、久秀が神も仏も信じないのであれば、なぜ大仏殿の焼き討ちを事故などとせず、『多聞院日記』などによる史実の通り、久秀が信念を持って焼き払ったことにしなかったのだろうか。その方が作品のテーマに沿う形になったのではないか。
柚月裕子『暴虎の牙』は、同じ作者による『孤狼の血』の続編であるが、前回と同じく警察組織や暴力団や不良グループのことなどよく調べられていて、ストーリイ展開もプロットもよい。ただ、登場人物のキャラもラストへの持って行き方も、常識の
河﨑秋子『土に贖う』は文章がよくない。のっけから「右手に桑の葉と一匹の蚕を乗せ」である。「右手に一匹の蚕を乗せた桑の葉を持ち」であろう。こういうのが一ページ、二ページごとに出てくるので読む気が失せる。実話が元になっている場合はもっと虚構性が必要だし、この賞ではそれが求められている。また、農民文学、労働者文学を目指しているのであれば、プロレタリア文学的な自然主義リアリズムがなければなるまい。
今村さんのパワーで決まり 林 真理子
今回の山田風太郎賞は、今村翔吾さんの『じんかん』で決まりだなと、選考会に臨んだ。
この作品にはいくつかの不満がある。前半のいきいきとした少年時代に比べ、後半の政治劇がやや退屈だ。あまりにも現代のヒューマニズムを前面に押し出しているのではないか、など。
しかしその存在感は、他の作品をはるかに圧していたと思う。かねがね言っていることであるが、私は山田風太郎賞というのは、エンタメどまん中、面白くてパワーがある作品に与えられるべきだと考えている。それでいくと、今村さんの『じんかん』は、まさにぴったりの作品だ。まだそれほどのキャリアではないのに、これだけの長篇を書いていける実力はたいしたものだと思う。まさに出版界のエースとして躍り出た。
次点というべき柚月裕子さんの『暴虎の牙』であるが、少々もの足りなさが残った。柚月さんの力を充分に知っている者としては残念だ。父を殺すほどの罪を背負い、暴力の中で生きていく主人公に、大上刑事がからむ。暴力団の世界を書かせたら、この方は本当にすごい。しかし誰でも知っているとおり、ヤクザはもはや滅ぶべき種族である。舞台は昭和の終わりから平成十六年となっている。だったらもっとレクイエムの要素を入れるべきだったのではないだろうか。
凪良ゆうさんの『わたしの美しい庭』は、のっけからキラキラネームの青年と少女が登場し、
反対に河野裕さんの『昨日星を探した言い訳』は、私の苦手な小説と言うしかない。この作品をずうっと手元に置いていたのであるが、少しも先に進まないのである。物語の中に入り込めないといった方がいいかもしれない。SFのにおいがする小説で、名門の学校が登場するのであるが、主人公のやりとりがもどかしく退屈であった。物語の最重要事項となる映画の脚本を、どうして必死で探していた少女に渡さないのかまるでわからない。そしてこの小説の不思議なキイワードになる「緑の瞳」「黒い瞳」の分類もまるで機能しなかった。
そして最後の河﨑秋子さんの『土に贖う』であるが、これは読んでいるうちにつらくなっていく小説である。短篇が七つ収録されているのであるが、すべてが北海道開拓に関しての失敗の物語である。北海道の厳しい自然によって、お蚕は失敗し、レンガの製造工場は失敗する。これをずうっと読んでいるうちに、次第に気が滅入ってくるのはあらがえない。
しかし馬の蹄鉄をつくる短篇と、アホウドリの短篇は、選考会でもとても評価が高かった。まるで神話のような味わいがある。この作者の持ち味をもっと生かした小説の構成を望みたい。
『じんかん』第一章でぶっとぶ 夢枕 獏
プライベートで、小説の新刊を読む機会がだんだんと減ってきている。手が伸びるのが、昔読みのがした気になる本になるということが多くなった。そういう状況にあるので、山田風太郎賞の選考で、新刊をまとめて読めるというのはたいへんにありがたく、また、おもしろい。
その年に出た本で、一番とんがっている場所にあるものを、五冊いっぺんに読むことができ、しかも、選考会というものがあるので、通常の読書とはまた違う読み方──評をせねばならないというプレッシャーの中で読むので、かなり気合いの入った読書になる。
今回は、今村翔吾さんの『じんかん』、柚月裕子さんの『暴虎の牙』、この二作品を同率トップで押すことにした。どちらか一作にしぼりきれず、あとは選考会という現場で判断しようと考えたのである。
では、まず、受賞作からだ。
『じんかん』今村翔吾
第一章
この章に出てくる子供たちの姿、生き方が
今村翔吾は、次作でさらにまた、ひとつ上のステージへ駆けあがってゆくのではないか──そんな気さえしたのである。
『暴虎の牙』柚月裕子
『孤狼の血』、『凶犬の眼』から続く大上シリーズ(?)とでもいうべきものの三作目だ。今、まさにのりにのっている作者の作品である。ガミさんこと大上の広島弁が板について、彼がしゃべり出すと、その声の抑揚や表情までが眼の前に浮かんでくる。作者は、よほどこのガミさんのことが好きなのであろうとわかる。後半、このガミさんが死んだ後、物語のテンションが、少し下がってしまったか。
これは、ガミさんのさらに昔の話も読みたくなってくるぞ。
『土に贖う』河﨑秋子
短編で、どれも北海道で、様々な産業に関った人物たちの話だ。どれも読ませる。ぼくが一番おもしろく読んだのが「南北海鳥異聞」である。アホウドリを捕ることから始まった
『わたしの美しい庭』凪良ゆう
なんともよい話のオムニバス。もしも、減点方式で採点したら、一番得点が高かったかもしれない。〝うつむきがちの猫背で歩いていく〟うすきみ悪いおばさんのことでもう一編増やしてもらえたら、予定調和の中に異物がまぎれ込むような感じで、またひと味違ったおもしろさが出たかもしれない。
『昨日星を探した言い訳』河野裕
本当は、この作品を一番に推すことも考えたのだが、迷いに迷って断念してしまった。
その一番の理由は、
受賞記念エッセイ
風太郎と見る夜景 今村翔吾
今年、山田風太郎傑作選江戸篇『
受けるべきか否か迷った。作家にとってその名は大きすぎる。だが二十三年前、中学一年生の頃からの読者としては、「やってみたい」という素直な気持ちが沸々と湧くのを抑えきれず、結局謹んで受けることにした。その時の帯の言葉は、
──古びないのではない。今なお新しいのだ。
と、いうものである。私にとっての山田風太郎はこれに尽きると思う。
今は漫画などでもお馴染みの「能力バトル」は、山田風太郎が起源だという方もいる。超人的な力を持ったキャラクターが活躍する作品はそれ以前にもあった。だが皆が超人的なのだが、能力の相性によって勝敗が決するようなものはなかったのではないか。それに読者は「くそ! 相手が悪かった!」などと一喜一憂する。これが素晴らしく面白いのである。
だがこうして考えてみると、これは現実社会にも大いに当て
人は生きる場所、出逢う人によって、良くも悪くも変わるものである。才が開花するかどうかも、詰まるところそれにかかっているのではないだろうか。そう聞けば、人生そのものが運次第だと取る方もおられるだろう。それは半ば正解であり、半ば間違いだと私は思う。残念ながら全ての努力が報われる世の中ではないが、努力が出逢いを、地縁を引き寄せる。運を引き寄せることはあると感じるのだ。
私は小学五年生の頃から歴史、時代小説を読み漁ってきた。それは中学、高校となっても変わらず、常に二冊は本を
今も決してがらの良い風貌とはいえないが、その頃の私は今以上に「やんちゃ」であった。金髪だけでは飽き足らず、青色、銀色にしていたこともあるし、すでにピアスも空いていた。今でも蓄えている
「兄ちゃん、それおもろいやろ」
と、声を掛けてくれる年配の、
その頃にはいつか小説家になりたいという夢を抱くようになった。高校の卒業文集の「将来の夢」の欄にもそのようにはっきりと書いている。だがそれは五、六十、少なくとも四十歳になってからのことだと思い極めていた。前述したように文芸誌も読んでいると、尊敬する歴史小説作家の対談なども掲載されており、多くの方が、
——人としての深みが出ないと歴史小説は書けない。
といったようなことを
だが三十歳になった時ふと気づいてしまった。忙しい日々の中、いつか、いつか、いつかと繰り返している内に、ただ
その瞬間、公募サイトを見ると、四日後に原稿用紙100枚程度の短編の賞の締め切りがあった。これに間に合わないくらいでは一生なれない。そう思った私はパソコンに向かい、初めての小説を執筆した。当時は7時から 23 時まで働いていたので、寝る間を惜しんでという状況であった。そして何とか脱稿し、それが何と受賞に至ったのである。
そこから多くの人の縁を頂くようになった。漫然と生きていただけでは
今でもこの作家という場所が私にとって最も良い場所なのかは解らない。ただこの場所に導いてくれた多くの方々の想いに応えるべく、これからも一歩、一歩進んでゆければと思う。そして死の間際に、やはり間違っていなかったと思える人生を送りたい。
そして今日という日が、その人生に挟まる
(いまむら・しょうご)1984年京都府生まれ。デビュー作『火喰鳥羽州ぼろ鳶組』(祥伝社文庫)で2018年、第7回歴史時代作家クラブ賞・文庫書き下ろし新人賞を受賞。同年「童神」で第10回角川春樹小説賞を受賞。「童神」は『童の神』(角川春樹事務所)と改題し単行本として刊行され、第160回直木賞候補となる。20年『八本目の槍』(新潮社)で第41回吉川英治文学新人賞を受賞。同年刊行された『じんかん』(講談社)が第163回直木賞候補となる。
●山田風太郎賞特設サイト
https://awards.kadobun.jp/yamadafutaro/