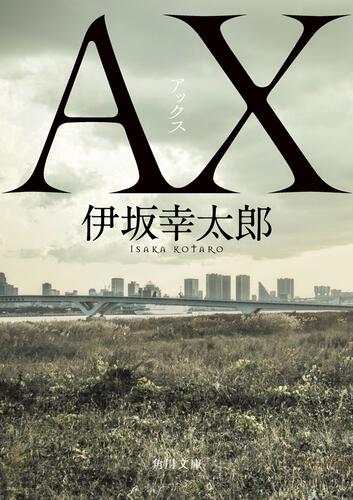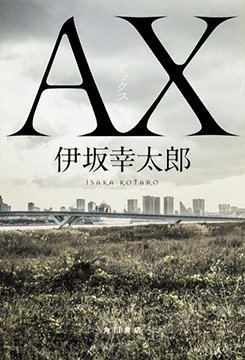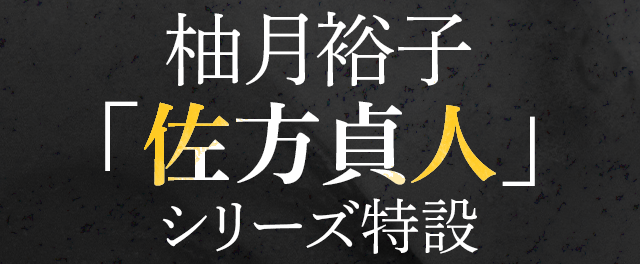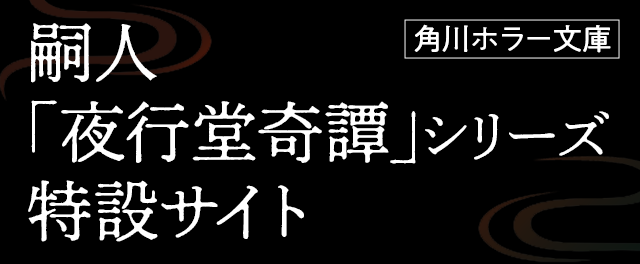突然、涙があふれて止まらなくなった。
そして思った。「2011年の震災がなければこの作品は全然違ったものになっていたのではないか」
『AX アックス』は、利害関係を異にする殺し屋たちが激突する“殺し屋シリーズ”最新作だ。
シリーズ前作『マリアビートル』の刊行が2010年。翌年の震災を経て、少しずつ書きためられた短編と書き下ろし作から成っている。
主人公は、超一流の腕を持つ殺し屋「兜」。愛する妻と高校生の息子がいる。息子の誕生を機に、彼は殺し屋稼業から足を洗いたいと願って来た。しかし、「足抜けすれば、家族の身の安全は保障できない」と業界のフィクサーから脅され、身動きができない。
“もう殺しはやりたくない”から、心のスイッチを切って手早く仕事をこなす。
そのため、ハードボイルド色の強いシリーズ前作と比べ、殺しのシーンは幾分控えめだ。
その代わり、執拗なまでに描き込まれているのが「兜」と妻との会話だ。
妻に頭の上がらない「兜」は、普段、彼女の機嫌を損ねないよう細心の注意を払っている。しかし、最終的には地雷をまんまと踏んでしまい、冷たい言葉を浴びる羽目になる。いわく「あなたは、わたしの話をいつも聞いていないわよね」「あれは何だったの? 生返事だったわけ? それともあれは別人だったの?」etc.…… 読者たる夫たちは、実際に陥りがちなそのシチュエーションに度々吹き出しながらも、自らの家庭生活を反省せずにはいられない。
物語の前半、外では感情を殺している「兜」にとって、唯一リアルに感じられるのは、妻との会話だけだ。しかし、いつしかぶっきらぼうな息子の中にも自分への心遣いがあることに気づき、ついには初めての友人ができる。「兜」が周囲へ共感を広げていくにつれ、まるで真暗な路地裏にあかりが次々に灯っていくように、登場人物ひとりひとりの個性が輝き出す。そして、作品世界を明るく切なく照らすのだ。
2011年、東日本大震災という想像を絶するリアルの前に、すべての創作が無意味に思える時期があった。伊坂幸太郎は、住まいのある仙台でそれを経験している。震災後、“殺し屋シリーズ”という大作に再び向き合った時、まずは家族の中のリアルを手掛かりに執筆を始め、一歩一歩、作品の世界を広げていったのではないか。
そしていつしか“殺し屋シリーズ”は、“暴力や死への恐怖すらもさらりと受け流すスーパーマン的な殺し屋たちが活躍する物語”から、“時に情けなく醜態をさらす等身大の男たちの物語”へと変容したように思う。
作品の中盤、「兜」は、敵対する殺し屋に共感してしまう。赤の他人にも守るべき家族がいて、必死に戦っていたのだ。物語はズドンと重力を増し、なおかつ一気に加速度を上げていく。読者は多くの登場人物への感情移入を余儀なくされ、もはやページをめくる手を止めることができない。
行き着いた最後の数ページ、「兜」がもっとも大事にしているある思い出が、鮮やかに切り取られる。それを読んで、涙を抑えることができなかった。
我々はこれからも閉塞感を増していく世の中を生きていかなければならない。
しかし少なくとも、伊坂幸太郎という小説家が共に時代を共有しながら歩んでいてくれる。そう思わせてくれる必読作だ。