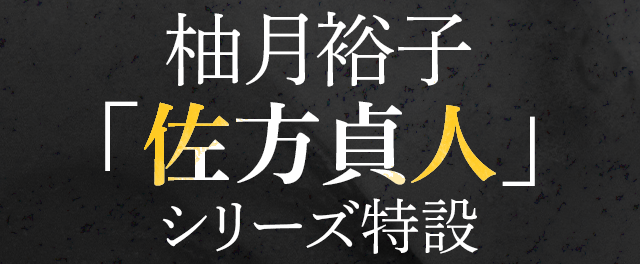文庫解説 文庫解説より
道尾秀介を瞠目させた、グロテスクで魅力的な「謎」の正体は!?『人間の顔は食べづらい』
※物語の結末に触れています。本編を未読の方は、そちらを先に読むことをおすすめします。
と、ミステリーの解説では書くようにしているのだけど、これがあまり意味をなさないことを最近知った。そもそもミステリーの巻末解説を先に読む人は、結末や展開をあらかじめ把握しておきたいからこそ、そうすることが多いのだとか。結末や展開を知っているとどうなるかというと、初読の時点で、伏線やミスリードといったテクニカルな部分を楽しめる。なるほど、たしかにそんな読み方もあっていい。省エネになっているし、人生こうも忙しいと、読書においても時短テクニックが必要だろう。たとえば大河ドラマなどは、観る人の多くが主人公や敵の行く末をすでに知っていながら楽しむわけで、その感覚に近いのかもしれない。
とはいえ、やはり本作については、物語を先に味わっていただければと思う。第三十四回横溝正史ミステリ大賞において、最終候補作として挙がってきたこの作品を読んだとき、僕自身が受けた衝撃を、なるべく多くの人にも体験してもらいたいので。
※まだ触れません。
ミステリーはレゴに似ていると常々思っている。どちらも、あらかじめ形が決まっている大小のパーツを組み合わせ、自分がつくりたいモノをつくっていく。どんな世界にもすごい人がいるもので、レゴでも小説でも、同じパーツを使ってよくもこんなすごい作品がつくれるもんだと驚かされることがしばしばある。「小さなブロック」を無数に集めて等身大の人間や車をつくってしまったり、「あり得ること」を積み重ねて大冒険や大犯罪を描いたり、あるいは読者を見事に騙したり。
が、ほかのあらゆるものと同じように、レゴもミステリーも進化する。レゴでいうと、たとえば「スター・ウォーズ」の戦艦や、日本のお城など、事前に決められた完成形を持つ商品というのがある。すべてのパーツが「それ専用」で、いわばプラモデルのように、定められたパーツを定められたとおりにしっかり組み合わせていき、最終的に作品が出来上がる。完成品を見てみると、細部の表現までとても丁寧で、すごいものだ。ただ、こうしたレゴセットに対しては、「これなら何でもできちゃうじゃないか。こんなのはレゴじゃないよ」なんていう意見もあるらしい。既存のパーツをいかに上手く組み合わせて作品をつくるかが面白いんじゃないか、と。確かにそうかもしれないけれど、出来上がった作品の美しさを見せられると、やっぱり素直に感心してしまう。
ミステリーにもそんな、無数のオリジナルパーツによって組み上げられた作品が存在する。「ある完成形のためだけに生み出されたパーツ」の集合が、一つの物語をつくり上げる。因果という言葉があるけれど、いくつもの「因」の関係性によって「果」がつくられるという、初期のレゴのようなものではなく、まず著者の頭の中に「果」が存在し、それに対する「因」を一つ一つオリジナルでつくっていくというものだ。たとえば不死者との戦いという「果」に対しては、不死者の存在という「因」をつくるし、超常的な能力によって事件が解決されるという「果」に対しては、超常的な能力の存在という「因」をつくる。ここで、「これなら何でもできちゃうじゃないか。こんなのはミステリーじゃないよ」と言われないために必要なのは、やはりレゴと同じように、完成形の美しさなのだろう。
前置きが長くなったけれど、白井智之さんの『人間の顔は食べづらい』は、完成形が本当に美しい。使われているパーツも徹底的にオリジナルで、自ら創作する小説世界において作者は神であるという言葉を、久々に思い出した。
※少し触れます。
さて、白井智之という神様がつくったこの世界、はっきり言って万人向けではない。もともと小説は万人に向けて書かれるものではないので、最大公約数を狙った作品よりも、むしろずっと小説的だと言えるのかもしれないが。
まずこの世界の入り口には、いきなり屈強な門番が立っている。墜落死による遺体が登場するシーンで「顔面には無数の小枝が突き刺さり、視神経ごと飛び出した眼球が提灯のように揺れていた」とあり、あまりに容赦のないこの描写に、思わず引き返す人もいるに違いない。そして、ひとたびこの門番の脇を抜けて世界に入ってみると、そこにはさらなる容赦ない世界が広がっているのだ。人間が自らのクローンをつくって食用とするという設定も、そのクローン肉の生産工場で繰り広げられる非人道的で残酷な光景も、まったく作者の頭はどうなっているのかと心配になるくらい、ドライブがきいている。さらに、この小説は多視点であり、複数の主人公が存在するので、いつ誰がどんなとんでもない目に遭うか予想がつかないのだ。予測不可能なその世界の中で、由島三紀夫というハイセンスな名前の人物が登場してくれたときは、「なるほど彼がこの事件を解決してくれる〝名探偵〟か」と思って少々ほっとしたのだが、そんな安堵も束の間、ページを捲っていくうちに惨死してしまう。「……さては、死んだと思わせておいて、あとで再登場して事件を解決するんだな」という一筋の希望を胸に、前を読み返したり後を読み進めたりしてみるのだけど、やっぱり完全に死んでいる。そうして物語は、謎と残虐性を次々に孕みながらふくらんでいくのだが、ふくらみきったその腹から、いったい最後に何が生み出されるのか、これまた予想がつかない。
この不安な読書を助けてくれたのは、僕の場合、チャー坊の存在だった。一人称が「おいら」、語尾が「……でございやす」というふざけたこのキャラクター、そこにいるだけでも異様に魅力的な上、檻の中でとんでもない推理力を発揮し、限定された情報から〝真相〟をバシバシ言い当てていく。最近読んだ小説の中で、このチャー坊というキャラクターは一番好きかもしれない。
ところどころにサラリと書き込まれている皮肉も非常に面白く、ページを捲る手を動かしてくれる。爆発事件によって満腹産業が混乱に陥り、自爆テロだ戦争だとわめく白樺執行役を、センター長である設楽がいさめる――「白樺さん、人命救助が先だ」。いやもう本当に、ここは声を出して笑ってしまった。また別のページでは、クローンを家畜として飼育している柴田が、大真面目にゐのりに言う――「人の命を屁とも思わないような、やばいやつに嵌められたんだよ」。
もう一つ、燃えさかる炎を前に由島が口にする台詞も印象深い。
「たとえ檻から出ることができても、クローンたちに居場所はないでしょう。人間社会が築く檻は、こんな代物よりずっと厄介ですからね」
しかもこの台詞、作品世界と現実世界に対する両方向的な皮肉であるとともに、伏線としても機能していたことに、あとで気づかされるのだ。
※触れます。
由島が言う「厄介な檻」を、クローン界のレクター博士とも言うべきチャー坊が、物語の結末で痛快に破壊してみせる。その破壊こそが、この物語のふくらみきった腹の中で息づいていた、グロテスクで魅力的な赤ん坊だったのだ。
この結末を読んだとき、僕は以前に聞いた哀しい話を思い出した。一七九九年にフランスの森で、十一歳から十二歳くらいだと思われる野生児が発見された。森の中で生き延びてきたその少年は、人語をまったく解さず、人々は彼を社会に適応させようと六年間も熱心に教育したのだが、ついに言語を習得することはなかったという。言語の習得は、脳の発達がある臨界期を過ぎると不可能になってしまうのだ。しかし、チャー坊たちクローンは違う。彼らは成長促進剤を打たれることで、猛烈なスピードで大きくなってはいるが、脳まで成長するわけではないので、まだ言語習得が不可能になる臨界期を過ぎていない。だからこそ人間がつくった檻を壊すことができた。つまり未発達が発達に打ち勝ったわけで、これもまた、なんと強烈な皮肉だろう。
前述したように、『人間の顔は食べづらい』は第三十四回横溝正史ミステリ大賞の最終候補作として挙がってきた作品の一つだった。なにしろ万人向けではないので、候補作となったのもギリギリだったと聞くし、選考会でも評価が大きく分かれた。けっきょく受賞は逃したが、僕と有栖川有栖さんがしつこく推していたところ、単行本で出版しましょうということになってくれた。選考委員としてなかなかいい仕事をしたと、いまも思っている。
その後、白井さんはプロとして精力的に執筆をつづけ、『東京結合人間』『おやすみ人面瘡』(ともにKADOKAWA刊)を次々に刊行した。前者では「身長二メートル以上で手足が四本ずつの人間」というオリジナルパーツが、後者では「誰かの咳を聞くと暴れ狂う人面瘡」というオリジナルパーツが使われ、どちらも美しい完成形がいま書店に並んでいる。作者いわく、『人間の顔は食べづらい』も含めて「人間」シリーズ。いずれも本書に負けず劣らず万人向けではないが、やはり面白い。
つぎはどんな作品を書いてくれるのか。僕は個人的に、白井智之版『守銭奴』である本書でチャー坊のファンになったので、いつか彼が再登場する話を書いてもらいたいのでございやす。
紹介した書籍
関連書籍
-
レビュー
-
試し読み
-
試し読み
-
試し読み
-
レビュー