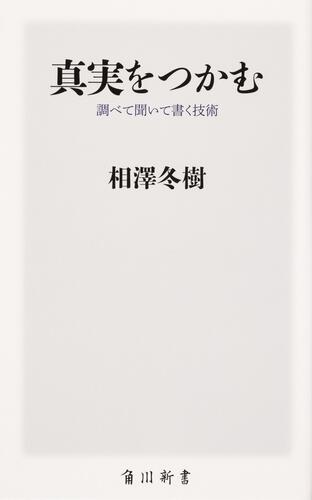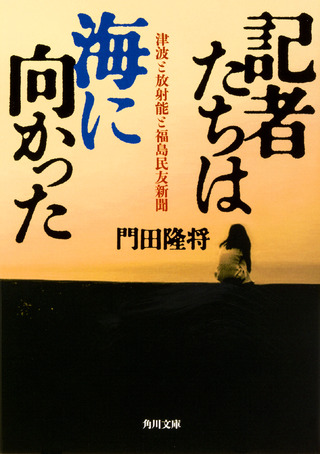森友学園問題の報道をリードしているジャーナリスト、相澤冬樹さんの書籍『真実をつかむ 調べて聞いて書く技術』が、角川新書から刊行されました。刊行を機に、フリーのジャーナリスト鎌田靖さんとの対談が実現! 実は鎌田さんも1月に『最高の質問力』をいう書籍を出版したばかり。第一線で取材を続けるお二人が、本に込めた思いや取材をする上で大切にしていることなどを語り合いました。
同時期の刊行という巡りあわせ
――角川新書から相澤さんの書籍『真実をつかむ 調べて聞いて書く技術』が刊行されました。
相澤:今日はありがとうございます。偶然ですが、ちょうど鎌田さんもテーマが近い本『最高の質問力』(PHP新書)を出されたんですよね。
鎌田:そうそう。今回、この対談の話をもらったときに一応、PHPにうかがいを立てたんです。ライバル社だから大丈夫かな、と思って。そうしたら担当編集者が、「ぜひ、受けてください」って。「書籍のことに触れてもらえるとありがたい」と言っていましたよ。他社のPRもやってくれるとは太っ腹ですね。
――いえいえ。相乗効果で盛り上げられたらと思います。初めにお二人の関係を簡単に紹介いただけますか。
鎌田:1993年から1995年の神戸放送局時代。僕が事件担当デスクで相澤さんは兵庫県警キャップでした。次が2003年から2005年の大阪放送局時代ですね。僕が報道統括で相澤さんは府警キャプ。相澤さんはずっと弟分みたいな感じですね。だから心配なんですよ。
相澤:鎌田さんは僕の6年先輩です。アニキと呼んで目標にしてきました。
――かなり長いのですね。お互いに、お相手の本を読んだ印象をうかがえますか。
相澤:パッと見て思ったのは、「俺、鎌田さんと同じこと考えるようになったんだな~」ということでした。私は「6年後に自分は、鎌田さんみたいに考えたり行動したりできるだろうか」と思いながら記者をやってきました。とても6年後にあんなふうになるのは無理だろうと思っていたし、実際6年たってもできていなかったと思います。でも今、記者になって30年ですが、読んでみたら同じことを考えている。私が鎌田さんと同じことを考えているんだ、と思って感慨深いものがありました。
鎌田:僕の本は1月に刊行されたのですが、お世話になった人に送ろうと思って相澤さんにも送ったんです。そうしたら「実は僕の本も間もなく出るんですよ」と言われました。妙な因縁を感じましたね。なんでまたここで同じような時期に、似たような本を書くんだ、と。
読んでみたら、冒頭に「この本はビジネス書である」とあったんです。実はぼくも担当の編集者から「メディア本はウケないので、一般の読者、学生やビジネスマンに分かるように書いてください」と言われていました。だから僕の本はテクニカルで、とっつきやすい内容になっています。僕は記者だけではなくて、キャスターなど、いろいろなこともやってきたので、その経験も踏まえて、仕事や生活など様々な場面で具体的に役立てばと思って書きました。
それにしても同じような本を、ほぼ同じ時期に書くというのは、相澤もようやく独り立ちできたか、と。それは冗談として、とてもうれしかったですね。
実は人と話すのが苦手?
――本に書かれていますが、二人とも最初は人と話すのが苦手だった、というところが意外でした。鎌田さんは人見知りだったということですし、相澤さんは思ったことを直球で言ってしまうところがあったとあります。それをどう克服していきましたか。同じことで悩んでいる人は多いと思うので、ぜひお教えください。
相澤:考えてみたら、僕、克服はしていませんね。今でも直球で言って、周りの人間に怒られたりしています。
僕も、鎌田さんの本に「人見知りだった」と書いてあって、とても意外でした。そういう印象はまったくなかったです。
たとえば、この『真実をつかむ』の中にも書きましたが、阪神淡路大震災のときに、僕らが働いていたNHK神戸局の建物が壊れて、小学校の跡地にプレハブを建てたことがありました。プレハブ建てですので、誰でも入ってこられる状態です。普通の放送局ではありえない状況です。
そのときに一人の男性が「話をしたい」とプレハブに入ってきました。僕はそのときに、ちょっとそれをためらったというか、「もうすぐ取材に出なくてはならないから」などと自分に言い訳をして対応しなかったのですが、鎌田さんはさっと立ち上がって話を聞いていました。その人が帰った後、鎌田さんから「ちゃんと話を聞け」と言われて。そういうところが、かなわないな、と思うわけです。
見知らぬ人が入ってきたときに、さっと立ち上がってお相手して、話を聞いて。そうしたら、相手の人はちゃんと納得して帰っていく。最初にも言いましたが、自分は6年後にあんなふうにできるのかな、ととても印象に残っています。だから「人見知りだったんですか?」と思ってしまいました。
鎌田:そう? 現役のときにもっと褒めてほしかった(笑)。
子どものころから本当に人見知りでした。とにかく人と会って話すのが苦手で、それを隠すために無理して友だちと話をしていました。今も子どのころとそれほど変わらない。でも、こういう人見知りの性格でも経験を積んでいけばなんとか仕事はできる。
だから思うんです。どんなキャラクターであっても経験値によって一人前になれるのではないかと。それは取材だけでなく、どんな仕事でも共通することではないか。そのことを伝えたいですね。僕でもできたのだから、ということです。
ビジネスマン向けに書いたと言いましたが、もちろん報道記者やディレクターなど、マスメディアを希望しているような若い人たちに読んでもらいたい。「人と会ったりするのはちょっと苦手、と思っている人にもこの業界は門戸を閉ざしているわけではない」ということを知って欲しい、そういう思いは強くありますね。
――NHKの記者職というのは狭き門ですから、そのど真ん中で働いていたお二人がそのようにおっしゃるのはとても興味深いです。
鎌田:僕の人見知りもそうだし、相澤さんの直球な物言いもそうですが、いろいろな個性が組織には必要だと思っています。ある決まった能力なりキャラクターだけが報道に向いているわけではないんです。もしそうだとしたら、同じような人間ばっかりが集まってきて、価値観が固定化してしまう。組織として決して健全ではない。
相澤:僕自身はもともと積極的に報道とかジャーナリズムを志望したわけではありませんでした。大学までは文学が好きで、出版社に行きたかったんです。この角川さんも受けて落ちましたけど、文春も講談社もあちこち受けまくって、結局全部、落ちちゃった。内定をもらえたのがNHKだけでした。
NHKを希望する人はだいたいディレクター志望です。こんな番組をやりたい、と。僕はもうそういうのはなくて、記者になったら社会勉強できるんじゃないかな、世の中のことを学べるんじゃないかなと思って選びました。
手ごたえはある日突然やってくる
――相澤さんは本の中で、失敗談も赤裸々に書いていますが、とくに新人のころになかなかネタが取れなくて苦しんだところは、読んでいてこちらも苦しくなりました。そういった状況の中で、自信がついてきた、上手くいってるなという手ごたえを感じ始めたのはいつですか。
相澤:今でも覚えているのですが、1年たった3月、ほぼ丸1年たったときのことです。ある殺人事件の被害者のご遺族の家でごはんをごちそうになりました。「もっと食べろ、もっと食べろ」って言われて、食べきれないくらいいっぱいごちそうになりました。帰る車の中でふと思ったんです。「これは天職だな」と。他人に受け入れてもらえた、ということを実感して、記者になってよかった、と心から思えたんですね。
僕は学生時代、友だちは多くなかったですし、あまり人と折り合うことができませんでした。記者になるとまず。人と会う人数、回数が桁違いに多い。そうすると、合わない人もいるけど、合う人も出てくるんです。合う人が出てきたことがすごくうれしかった。犯罪の被害者というとてもつらい立場でも、相手をしてくれる人がいるんですよね。
その食事の直前に、本でも書きましたが、上関原発の特ダネを出すことができたことも大きかった。僕の記者としての初めての特ダネでした。偶然が左右したというところもありますが、でも人から話を聞いて出すことができた。
記者になって1年たったら、もう天職だと思っていて、そこからほぼずーっとそう思っていますね。
鎌田:僕は天職といえるほどの自信はない。こういう仕事に就いて良かったのかと今でも思うことはありますが、もう遅いですね。
私は最初の赴任地が名古屋で警察を担当しました。大きな都市なので、大手新聞社の中部本社があり、競争相手の記者は、支局を経験してきた数年先輩の記者ばかりでした。それも各社市内のサツ回りに3人から6人を配置して。一方、NHKは僕1人だけ。
警察担当記者というのは特ダネ、つまり、他社が知らない情報を取ってこないと話にならない。その是非については後で少し話せたらと思いますが、とにかく夜討ち朝駆けを繰り返してネタを取らなくてはいけない。でも取れるわけないでしょう(笑)。他社には経験値が高い人たちが大勢いて、こっちは1人で。3か月くらいして気づきました、いやこれ全然ダメだよ、と。
そのころには、警察幹部と話すことには慣れてきたのですが、まったくネタが取れません。僕が落ち込んでいたんでしょう。あるとき、市内のある警察署の生活課の警部補が、「おまえ、どうしたんだ」と声をかけてくれて。「いやもう、クビですよ……」というようなことを言ったら、「そうか。こんな話があるんだけど」と教えてくれました。同情してくれたのでしょう。
地方から名古屋にやってきた少年が市内で多額の盗みをして補導された、という話だったと思います。大きな事件ではないですが、NHKのニュースで放送したところ、それまで優しかった他社の先輩記者が急に冷たくなりました。ようやく僕も一人前と認められたのでしょう。それがささやかな自信というか、これならやっていけるかもしれない、と思ったきっかけでした。
そういう経験を一つ積むと、ワッと局面が開くということはありますよね。一点突破全面展開です。そうしたことがそのあとも何回かありました。
――一生懸命やっていたから警部補の方も声をかけてくれたのでしょうね。
鎌田:そういうことなんでしょうね。相当、真剣に悩んでたんじゃないかな。
相澤:今のとちょっと違うけど似ている話を思い出しました。私の同期の北澤くんという記者がいました。私の本にも登場します。
彼の初任地は前橋でした。当時は日航ジャンボ機の墜落という大きな事故がありました。群馬県警が墜落の原因究明や責任追及をしていましたが、これが記者にとっても大問題です。ネタを取ってこないとなりません。彼も一生懸命取材しましたが、全然追いつかない。群馬は上毛新聞という地元紙がめちゃくちゃ強いから、上毛新聞に毎回抜かれまくっていました。当時の上毛新聞の群馬県警サブキャップが有名作家になった横山秀夫さんですよね。
横山さんに毎回抜かれまくるから、1年生の北澤くんが記者クラブの自席でちょっと涙していたそうです。多分、デスクに怒られたのでしょう。そうしたら横山さんが近づいてきて、「北澤、どうしたんだ」と声をかけてくれたそうです。「泣くなよ、人生良いこともあるよ」と。それでちょっとほっこりしたら、翌朝の上毛新聞でまた抜かれていた、と(笑)。
「同情するならネタをくれ」というのがすごくよくわかります。北澤くんはこれを持ちネタにしていますね。
最終的に日航は不起訴になりましたが、この不起訴にするというのは鎌田さんの特ダネでしたね。これも、北澤くんとしては地元の記者として本当は頑張りたいところだったんだけど、最初は他社の上毛新聞に抜かれて、最後は同じ会社の先輩に抜かれたっていう。ダブルでオチのある話です。
上司と部下の関係
――一般の読者の目線で読めば、上司と部下の関係というところも興味深かったです。
相澤:今でも忘れられないのは、神戸に着任した私に鎌田さんが言った言葉です。「相澤、大丈夫。俺、3か月待つから」と。
鎌田:そうだっけ? 半年と言ったと記憶してるんだけど。
相澤:3か月も半年も同じです。3か月待つ、つまり、3か月しか待たない、もしくは半年しか待たないということです。半年たったらしっかり成果出せよ、と言われているのと同じですから、「いや、これは厳しいな……」とそのときは思いました。
そこからがむしゃらにやりましたが、実際には3か月たっても半年たってもそんなに成果は出せませんでした。でも、鎌田さんは「おまえ、どうなってんだ!」ということは言わなかった。1年たっても状況は変わらなくて、自分に自信も持てなくなっていて、いろいろな人からいろいろなことを言われていたから、異動させられるかな、と思っていました。でも異動はなかった。それで神戸の2年目、調子が出てきたんです。そのあと、震災が起きました。
上司というのは、最初はガツンとかますけど、それで追い込まずに、見守ることが大切ですよね。そのときは思いませんでしたが、自分がデスクになったときに思いました。
――鎌田さん、この3か月待つっていうのは、どういうお気持ちで言ったんですか。
鎌田:僕は神戸に行く前は東京で検察の担当をしていましたので、神戸への異動をあまり前向きにとらえられていませんでした。でも、だんだん、伝えられることを全部伝えるのが今の自分の仕事なのかもしれない、と思うようになっていきました。
東京の事件取材の水準はこれくらいで、記者たちはこういうことを求められているんだ、ということを記者たちに教えました。かなり具体的にたとえば夜回りの仕方などもね。こちらは高い水準を求めていたから、すぐに成果は出ないだろうと思い、3か月待つと言ったのだと思います。
神戸の記者たちが特ダネを出せば、彼らにとって東京へのアピールにもなるという思いもありました。鎌田が行って神戸局、がんばってるじゃないかとなれば、結果的に僕にとってもプラスになります。いやらしい話ですけど。せっかく自分がいるのだからという思いはありましたね。
相澤:鎌田さんが最初に来たころ、「なんで俺が」という雰囲気は感じました。
鎌田:鬼デスクと言われていたようで、それを本にも書きましたけど、とはいえ、僕自身は胆力があるわけでもないし気が強いわけではないので、けっこう部下に気を使ったり、指導法を悩んだりしたんですよ。「強く注意したけどあいつ、落ち込んでるんじゃないか」とかね。
僕自身、細かいことを言う上司が好きではなかったから、細かいことを言うつもりはありませんでした。大きな流れというか、広い見方、そういうことをアドバイスしたほうが、彼らにとってプラスになるのではないかと思っていました。
相澤:たしかに鎌田さんは細かいことは言わなかったけど、仕事に対する要求水準はすごく高かった。ご自身が特ダネをとるなど、ずっと第一線でやってきたという思いはあったのではないでしょうか。要求水準が高い上に、すごく短気なんですよ。すぐカーッとなって怒っていましたよね。
――そうなんですか。それは想像できません。
相澤:すごく怒るんですけども、冷めるのもすごい早くて。尾を引かず、カラッと終わるんですよね。だからこちらも、それほど落ち込むことはなかったですね。落ち込む暇もなく、鎌田さんの怒りも収まっていた、という感じでしょうか。
だから、鎌田さんというのは本当にある意味、理想の上司だったと思います。要求水準は高いし、仕事は厳しいんだけど、それができなかったからといってボロクソに言うわけではなくて。怒るときはワーッと怒るけど、すぐに解消して終わらせて、次の話に入っていく。
だから当時の神戸にいた記者はみんな鎌田さんのこと、兄貴分だと思っていると思います。
あの後、私は社会部行って、徳島行って、大阪府警キャップとして大阪に来たとき、鎌田さんが大阪の報道のナンバー2でした。私自身はとても意外でした。「俺、社会部で事件記者をやってないのに、なんで大阪府警キャップにするんだろう」と思ったんです。で、これは僕の想像ですけど、そのときの大阪の報道のナンバー2が鎌田さんで、その上の報道部長は大宮さんという神戸時代に一緒だった人でした。そういう人間関係なんだろうな、と思いました。
鎌田:僕としては、能力があって、サボらない人材がほしい。相澤さんはまさにそうでした。長い付き合いでそれはよく知っている。相澤さんの東京での評判がどうだったなど、僕にとって関係ない。どうでもいいことでした。
相澤:要するに、どういう上司だと部下はやりやすいっていうか、くじけずにやっていくことができるかという共通項をもっていたんですね。それを鎌田さんと私は別の側から見ていたように感じます。鎌田さんは上司として、だれが部下ならやりやすいかを考えていたでしょうし、私は部下として鎌田さんが上司ならやりやすいと感じたわけです。これは記者や報道の世界というよりも、どんな職場にも通じることですよね。
〈後編へつづく〉
書誌情報ページ
- 相澤冬樹『真実をつかむ 調べて聞いて書く技術』:https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000813/(KADOKAWA)
- 鎌田 靖『最高の質問力』:https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-84829-7(PHP研究所)