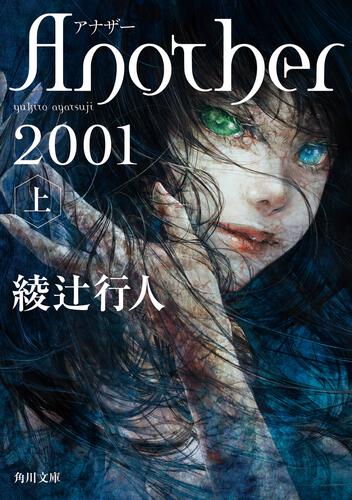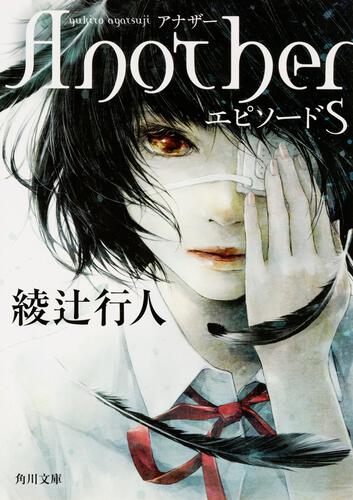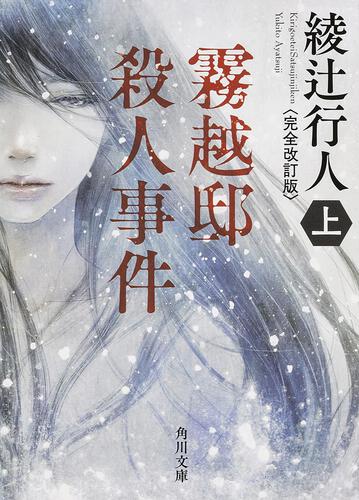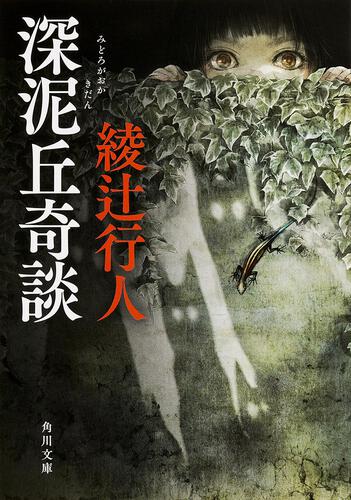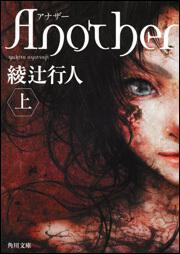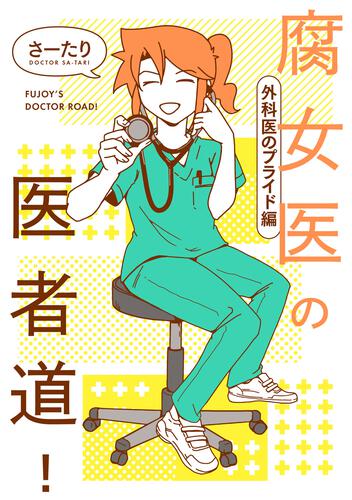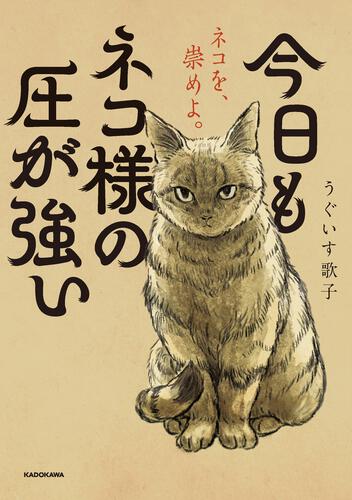第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈大賞〉と〈カクヨム賞〉をW受賞した綿原芹の『うたかたの娘』。奇妙な人魚伝説のある若狭を舞台に、美しき化け物・人魚とそれに翻弄される人間を描いた物語だ。「ミステリ的なセンスの良さも感じる。そして、怖い」「選考会では迷わずこれを推した」(選評より)という選考委員の綾辻行人と、著者の綿原芹が、執筆の経緯や作品の魅力を語り合った。
構成/千街晶之 撮影/橋本龍二
『うたかたの娘』刊行直前特別対談 綿原 芹×綾辻行人
謎の言葉「へしむれる」は造語?
綾辻:受賞、おめでとうございます。
綿原:ありがとうございます。選評で、ミステリ的なセンスがあって、しかも怖いということを言っていただけたのが嬉しかったです。
綾辻:選考のために応募原稿を読むときは僕、先に梗概を読まないようにしています。だから『うたかたの娘』も、一話目を読み終えた時点でやっとオムニバス形式の作品だと気づいたわけですが、これは幸運な読み方だった気がします。
一話目も二話目も、わりと軽い読み味でありつつもしっかりと“怖さ”があって、ひねりも効いていて面白い。悪くないなあと感じながら読み進めたところが、三話目に入ってのあの、壮絶で異様な展開。思わずページをめくる手に力が入りました。すっかり物語に飲み込まれてしまった、ということです。その三話目のタイトルにもなっている「へしむれる」という言葉、これは綿原さんの造語なんですか?
綿原:江戸時代に、人魚の骨のことを「ヘイシムレル」とオランダ語で言っていたらしいんです。「ヘシムレール」とも表記するようですが、それをもじったものです。
綾辻:そうでしたか。選考委員はみんな、「へしむれる」には心を掴まれていましたね。意味不明で、語感がなんだか気持ち悪くて、そのくせちょっと滑稽味もあって、という絶妙なワードです。加えてやはり三話目のインパクトは強烈だった。この調子でさらにいくつかのエピソードを読みたい、という気持ちにもなりました。
四話目では、大きく時代をさかのぼったりもしながら、物語全体を通して見え隠れしていた謎も解かれていきます。なかなか難しいパートだと思うんですが、とても面白く書けていて感心しました。
綿原:ありがとうございます。
綾辻:ミステリを読むつもりで読んでいなかったせいもあってか、各話の展開や結末にはどれも驚かされました。意外な展開と結末、しかもそれぞれに良い案配で伏線が張られている。どこまで意識されたかはわかりませんが、書き方がフェアなんですね。最後に意外な真相を明かされても、いきなり空中から未知の物体を取り出されたようなアンフェア感がない。そういう意味で、ミステリ的なセンスの良さを感じたわけです。
綿原:いわゆる本格ミステリはそんなに読んできたわけではなく、論理的思考も得意ではないので(笑)、ミステリは書けないかなと思っていたのですが、町田そのこさんの『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』という短編集がありまして。女による女のためのR-18文学賞を辻村(深月)さんに推されて受賞・デビューしたと聞いたんですけど、ヒューマンドラマでありつつミステリ的な仕掛けをちりばめた話を集めた短編集なんです。それが好きで、こういうのをやりたいと思ったことがありまして。今回もホラーではありますけど、伏線は回収したいし、叙述的な仕掛けも作りたいし、そのあたりは意識して面白く思ってもらえるよう書きました。
綾辻:それは正解でしたね。ところで、高橋留美子さんの〈人魚シリーズ〉は読んでおられますか。『人魚の森』『人魚の傷』『夜叉の瞳』の三冊が出ている傑作漫画ですが。
綿原:受賞前は読んでいなくて、選評で米澤(穂信)さんが触れていたのでこのあいだ読んだんです。
綾辻:ということは、この作品における人魚の、あの不老不死のシステムは独創なのですね。
綿原:そこは完全に自分の創作です。
綾辻:素晴らしい。高橋さんの〈人魚シリーズ〉を思い出させながらもまた違う、新しい「人魚像」「人魚観」の提示。“美しき異形”がもたらす恐怖だけではなく、そんな存在であるがゆえの哀切や苦悩にまで筆が及んでいるところも優れています。
身近にあった人魚伝説
綾辻:もともとはノージャンルというか、ホラーでもミステリでもない小説を書いておられたのですか。
綿原:創作自体は子供の頃からしていたんですけど、小説みたいなかたちになったのは十四、五歳くらいからで、ジャンルは広い意味でのヒューマンドラマですね。そのときに地方文学賞をもらったり、某社の新人賞の最終候補に残ったりしていたんですけど、落ちた次の年に編集者に新しい作品を見せてと言われて、読んでもらったら酷評されまして(笑)。大学受験とかもあったので、それで小説を書くのを十五、六年くらいやめてたんですね。また書き出したのが四、五年くらい前です。
綾辻:「野性時代新人賞」に出したことがあるそうですね。選考委員を務めている辻村さんから聞きました。
綿原:そちらでは辛い評価をいただいたのですが、今回は褒めていただいて嬉しかったです。
綾辻:辻村さんも嬉しそうでしたよ。今回の作品を読んで、綿原さんの文章は肌に合うというか、僕にはとても「いい文章」に感じられました。読みやすくて、かといって軽すぎず、ちょっとした描写で情景が浮かんできます。
『うたかたの娘』というこの物語は、そもそもどこから思いついたんですか?
綿原:これを言うとどうかしている人と思われるかもしれないんですけど、娘がディズニーのキャラクターのアリエルが好きなんですが、すごくかわいいので、人魚はこんなにかわいいものじゃないのになと……。出身が福井で、小浜の人魚伝説も身近にあったので、人魚は結構怖くて、簡単に触れちゃいけないものというイメージだったので、そのへんはギャップがあるんだなあと。昔からずっと語り継がれているので、ロマンは感じますね。そこからかもしれないですね、人魚を題材に書きたいと思ったのは。
綾辻:日本の古い伝承などはもともとお好きなんですか。
綿原:西洋のホラーって入りきれないところがあって、日本の怪談とか民俗学的なところが好きですね。妖怪も好きで、水木しげるとか手塚治虫の影響があると思います。
綾辻:ホラー小説で好きな作品は?
綿原:森見登美彦さんの『きつねのはなし』や、恒川光太郎さんの『夜市』です。ああいう不気味な日本の情景を描いた雰囲気が好きです。『きつねのはなし』のほうは謎は謎のままですが、『夜市』は綺麗に回収していますね。
綾辻:なるほど。ミステリで好きなものはありますか。
綿原:芦沢央さんは好きですね。一番読んだのはヒューマンドラマで、江國香織さんとか、吉本ばななさんとか、川上弘美さんにはまっていた時期があって、それが土台になっていたと思います。
綾辻:それは強みかもしれませんね。本格ミステリまわりには「ミステリひとすじ」みたいな作家も少なくないから。僕なんかもそうで、たとえば恋愛小説方面はまったく知らないというか、興味がなかったりする(笑)。ジャンル外のさまざまな作品を、自身の土台として持ち続けるのは悪くないことだと思います。
テーマを語りすぎずにエンタメに昇華
綾辻:ルッキズムについてはどのくらい意識して書かれたのでしょう?
綿原:テーマ先行で書いたわけではないので、最初からルッキズムの話を書こうと思ったら人魚の話にはならなかったと思うんです。書いているうちに熱くなっていくというか、説教臭いことを書いてしまうたちがありまして、それは絶対駄目だからエンタメ小説にしなくては……と自分を抑えたところはありますね。自分が思うことはあまり語りすぎずに、読者に考えてほしいところなので。
綾辻:エンタメの場合、その辺をむやみに語りすぎないのは正着でしょう。この作品はちょうどいいバランスをキープしていると思います。時代や社会によって当然、“美”の捉え方や基準は変わっていくわけですが、それでもなお「美しい」とは何なのか、「美人」とは何なのか。そういう視点もきちんと保持されています。
綿原:美醜の話は人間が営みを始めてからずっとあると思うんですが、やっぱりSNSが広まってから一気に苦しくなった人が多いのかなとは思っていて。ルッキズムという言葉も浸透したのは最近で、モラルは上がってると思うんですけど、可視化されるものの多さが反比例してるというか。
綾辻:ホラー小説が扱う“恐怖”という感情は、ある部分でどうしても美醜と深く関わってきます。切り離しては語れない。たとえば異形の怪物や妖怪に人間が恐怖を覚えるのは、原理的にはまず見た目が逸脱的で怖いからでしょう。「アップデートした」とされる近年の価値観や規範意識などを踏まえながら、それをどう捉え直していくのか。答えはそうそう簡単ではないと思いますが。
綿原:ずっと考え続ける問題ですね。
綿原さんらしいホラーやミステリを
綾辻:初めからこういった連作の構想があったんですか?
綿原:最初は連作として書くつもりはなくて、一話目は短編として書いて、そこから着想が拡がりまして。一話目は少し前に書いたものなので、文章を手直しするのが大変でした。
綾辻:確かに一話目だけ、ちょっと毛色が違いますね。それも含めて僕は楽しめました。ホラーにも当然いろんなタイプのものがあって、たとえば前々回の受賞作である北沢陶さんの『をんごく』はすごく完成度が高くて読み応えのある長編でしたが、受賞作のすべてがあのようである必要はない。今回のようなオムニバス形式の変化球であっても全然OKだし、むしろそれで賞に“幅”ができて良いと思うんです。まあ、選考会ではいろんな意見がありましたけれども。
綿原:なかなか電話が来なかったので、紛糾しているのかと(笑)。
綾辻:必ずしも全員の意見が一致しなくて。でも、三話目の「へしむれる」は良いね、というのは誰もが認めるところでした。辻村さんは「完璧」とまで言っていた気がします。受賞の知らせを受けたときは、どんなお気持ちでしたか。
綿原:あの日は(午後)五時から七時に電話かかってくると聞いていたんですが、一番忙しい時間帯で(笑)、子供二人のお迎えとか、ごはんの支度とかあるんでどうしようと思ってて、遅れてむしろ良かったんですけど、やっと、というか……若い頃に最終まで残ったのはまぐれで、同じところに行くことはないだろうと思っていたんですが、去年、野性時代新人賞とポプラ社小説新人賞に応募して最終で落選した記憶が濃かったので、あ、受賞することもあるんだなあと(笑)。
綾辻:ホラーやミステリを意識して書いたのは、今回が初めてだったのでしょうか。
綿原:そうですね、今まではヒューマンドラマだったので、長編では初めてです。
綾辻:「受賞の言葉」に「好きなことを好きなように書いた」とありました。だったらこの方向性でしばらく書いてみて、そこにいっそうの楽しさを見いだせたらいいですね。「好きなことを好きなように」というのは経験上、すごく重要なことですから。
綿原:非常に幸運だなと思っていて。巷では書きたいものと評価されるものは違うからみたいにおっしゃってる方が多いので……。
綾辻:ケースバイケースですよ。かつて「新本格」と呼ばれた僕や僕の友人たちはみんな「書きたいものを書く」という基本姿勢を堅持して、それで道を拓いてきました。京極夏彦さんなんかもそうですね。今の売れ筋をマーケティングして書くよりも、自分の作品で新たなマーケットを作るぐらいの気概でやるべきだろう、というのが、少なくとも僕の考えです。
綿原さんの場合、ヒューマンドラマを書きたいという土台を大事にしつつ、綿原さんらしいホラーやミステリを書いていかれればいい。ミステリといってもさまざまな形があって、アプローチの仕方も多様ですから。芦沢央さんがお好きなら、たとえば連城三紀彦さんの作品などもお読みになれば良いのでは? 良い刺激と参考になるかもしれません。いろいろなものを吸収しながら、「好きなことを好きなように」書きつづけられる力を養っていってください。
綿原:ありがとうございます。
綾辻:最後にひとつ。「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」でデビューされるわけですから、当面は賞の名前を意識して書いてほしい、というのが選者としてのお願いです。僕はこの賞が「横溝正史賞」だった頃からずいぶん長く選考委員を務めているのですが、“探偵小説の鬼”であられた横溝先生の名を冠した賞で世に出るからには、今後の長い作家生活の中でいつか、一作でもいいから「これが綿原芹の本格ミステリだ」というような作品を書いてほしい、とも願っています。
綿原:これが噂の……。
綾辻:いわゆる「本格の呪い」ですね(笑)。ご存じでしたか。
綿原:呪いをかけていただいてありがとうございます。これから本を沢山読んで勉強して、いつか書き上げることができたら読んでいただければと思います。
著者プロフィール
綾辻行人(あやつじ ゆきと)
1960年京都市生まれ。京都大学教育学部卒業、同大学院博士後期課程修了。87年、大学院在学中に『十角館の殺人』でデビュー、新本格ミステリ・ムーヴメントの契機となる。92年、『時計館の殺人』で第45回日本推理作家協会賞を受賞。2009年発表の『Another』は本格ミステリとホラーを融合した傑作として絶賛を浴び、TVアニメーション、実写映画のW映像化も好評を博した。他に『Another エピソードS』『Another 2001』『霧越邸殺人事件』『深泥丘奇談』など著書多数。19年、第22回日本ミステリー文学大賞を受賞。
綿原 芹(わたはら せり)
福井県出身。2025 年「うたかたの娘」で第45 回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈大賞〉〈カクヨム賞〉をW受賞し、デビュー。
作品紹介
書 名:うたかたの娘
著 者:綿原 芹
発売日:2025年10月01日
第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞〈大賞〉受賞作
道に佇む不気味な人物をきっかけにしてナンパに成功した「僕」。相手の女性と雑談をするうちに故郷の話になる。そこは若狭のとある港町で、奇妙な人魚伝説があるのだ。そのまま「僕」は高校時代を思い出し、並外れた美しさで目立っていた水嶋という女子生徒のことを語る。彼女はある日、秘密を「僕」に明かした。「私、人魚かもしれん」幼い頃に〈何か〉の血を飲んだことで、大病が治り、さらには顔の造りが美しく変化したのだと――。
詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322505001050/
amazonページはこちら
電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら