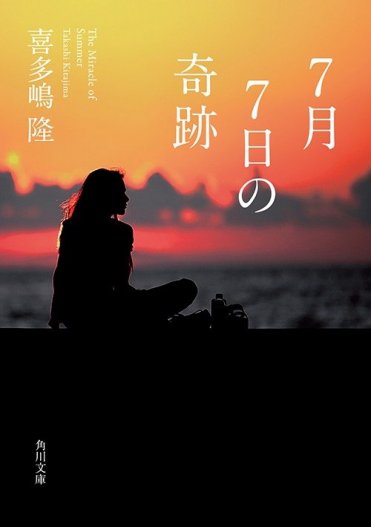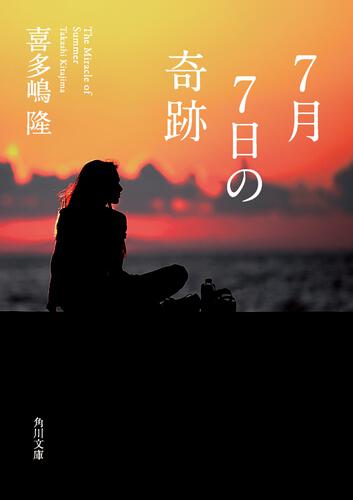読書の秋、本番! 喜多嶋隆さんの『7月7日の奇跡』が刊行されました。このカバー写真の目に染みるような夕焼け空は、1万枚以上の写真を見て、喜多嶋さんが「これしかない」と確信をもって選んだもの。
抜けるような青い空と、爽やかな湘南の海を舞台に物語を紡ぎつづけてきた喜多嶋さん。本書のテーマは、喪失を経て本当の愛を見つける男女の姿と、生きているだけで摩耗し、傷ついていく心の脆さ――。しっとりした、より奥深い「愛」の形が描かれます。
発売直後から、編集部に「これまでの喜多嶋作品とは一味違う」という熱烈なコメントがぞくぞく届きはじめました。角川文庫編集部のTwitter(@KadokawaBunko)でも一部ご紹介していますが、ここでは、その全文をお届けします。
あらすじ
彼女は、少年の姿で僕の前に現れた――。
友人の自殺のため、船員学校を休学した雄次は、ある日、ショートカットが似合う野性的な少年に出会う。だがひょんなことから彼の秘密に気づき……。海辺の町を舞台に、傷ついた心が再生する姿を描く感動作。
編集部に届いた熱烈な感想
■物語にある、「人の心は壊れもの」という言葉。
人は皆、葛藤の中で生きている。他人からは見えない、心の奥底に抱えている様々な感情。
「何処にでも居る特別な人々」の人間模様が複雑に絡み合いそして道となる、儚く美しい物語。
海の香と波の音。オーディオから流れる音楽。毎年、7月7日が近づく度、私はこの物語を思い出す事でしょう。(CHITAA)
■いつもながら楽しみに、でも読み終わってしまうのがもったいなくて、ゆっくりゆっくり読みました。
きらきらと移り変わっていく葉山の季節のなかで、様々な「過去の事情」を抱えた人たちがいろんな角度から接点を持つことによってそれぞれの状況を認めて、克服し、明日に向かって進んでいく物語です。7月7日にまつわる本当に素敵なできごとに期待して、各所にちりばめられている素敵なBGMと爽やかな風景を味わいながら、楽しみにお読みください!(J・M)
■なんだろう、この読み終えてのさわやかな気持ちは。
つらいと思えるできごとを胸に秘めながらも、真夏の暑さにも負けず、凛と咲くひまわりのように、日々を生き抜いていくノブ。
彼女をとりまく人たちが、もっと良く生きようと変わっていったように、私も毎日一歩でも進んだなと言えるように生きたいと思いました。(K・K)
■男装の少女と、友人を亡くした青年。
そんな二人が出会い、娘の死から表舞台から姿を消した料理人、苦しみを抱える精神科医も交えながら、心を開き、立ち直っていく、清々しい作品である。
そこには、人間誰しも心に傷を抱えて、それでも前を向いて生きているんだ、生きていきたいと願っているんだ、という思いがあるんだと思う。
前半読んでいる途中で、頭の中に浮かんだ言葉は、「TOMBOY」「男装の麗人」。作者の作品によく出てくる、ボーイッシュな女性である。異常に女性であることを隠す、その心の闇にあるものは何であろうと、読み進めた。
主人公も他の作品よりも比較的若い21歳の設定。今までの作品とは異なり、作者の新たな視点を感じる。あいかわらずモデルのような、いい男そうだ。ちょっと妬けるけど。(K・A)
■これまでの喜多嶋作品とは、ちょっと違ったテーマではないでしょうか。
今回の作品は恋愛小説とも言えるが、登場人物が交流を通して、それぞれが抱える問題を乗り越えていく物語と言っていいと思う。
様々な現代社会の問題が随所に出てきます。
それにより心に傷を負い、それに苦悩する様子が綴られています。
同様の傷を負った方にはこれから生きていくヒントになるかも。(出川徳見)
■喜多嶋隆という作家のイメージは、ずばり『青春小説』だと思います。
ただしそれは数年前までの印象です。
このイメージがだんだん変化してきたのは、より深い『愛の形』を描いているように感じるからです。
本書は、喜多嶋さんの小説で僕の求めていた、『さわやか』な小説です。
ここ数年の中では一番読みやすいと思います。
読後感も心地よかったです。
これからも、さわやかな小説を期待します。(林谷昭治)
■それぞれトラウマを抱えた雄次とノブ。
はじめは異性としては意識しあってはいなかった2人は、徐々に惹かれ合いながら互いにそれぞれの傷を癒やし合っているのでしょう。
読み終える頃には感情移入して、伸びた髪でポニーテールを結ったノブを見たくなりました。
海辺での田舎暮らしをしてみたくなる、そんな小説です。(永井明)
■いつもは憧れのヒロインやシチュエーションで非日常を満喫していたけど、今回は自分に置き換えて読める部分も沢山あった為に新鮮かつ親近感が持てた。喜多嶋さんの作品は楽しめて知らないうちに身についているような私の教科書になりつつある。読後は、今こうして生きていられる事の奇跡に改めて感謝する事ができた! 喜多嶋作品を知らないまま人生を過ごしている人は勿体無い! 可哀想だと思う。(佐藤ユリ)
■喜多嶋作品はいつも明るくて爽やかな文章なので、軽くて読みやすい。
今回の登場人物は心が壊れかけた人たちが多く、迷いながらそれでも前に進んでいく、そんな姿にすっかり感情移入してしまいました。
読み終わったあとは、まるで海辺の潮風に吹かれたような感覚になります。(三沢栄樹)
■喜多嶋小説を読み始めると瞬く間に小説の世界に入っていった気がするのはいつものことなのだけど、今回も、葉山のちょっと小高くなった場所に建つ家をまるでドローンの目になったようにみてる自分がいた。
風の香りや話し声、喧騒など、まるでその場で聴いている気分になるのは、なぜだろう? いつも不思議に思うことである。ちょうど映画館で圧倒的な映像に出会ったときのよう。その世界にどっぷり浸るのである。
今回の物語は、少しシリアスな内容も含んでいる。現代病とも言える「心の病」は、コロナの蔓延を境に、どんどん顕在化してきている。そんな心の傷を抱えた主人公たちが、日々の人間関係の中で、癒され、励まされ、再生していく物語のように感じた。
今回も物語に出てくる料理やお酒のうまそうなこと。作ってみたいと思ったし、食べてみたいと思った。葉山の豊富な海の幸をシンプルに調理した主人公の作る燻製は、読んでいるだけで、もう食べたくてたまらなくなる逸品だった。
喜多嶋小説は、いつ読んでも心にビタミンを与えてくれる。この小説も、期待通りの読後感であった。(松本典子)
■今作もHappy Endで良かったです。ちょっと変化球のシンデレラ・ストーリーのような。人間、つらくても生きていれば、きっといつか『生きてて良かった』と思える日が来る!のかな。(Y・T)
■本作品は妹のような存在のノブが、心に傷を負って、その再生物語がベースにあります。喜多嶋隆は、女医の雅子に言わせているように「私たちが生きている世の中って、一種の戦場じゃないかしら……見えない弾丸が飛び交っている」「あの子も戦場で負傷してしまった一人なのかもしれない……16歳の負傷兵……」「やはり世の中は戦場ね……。で、うちのようなクリニックはいわば野戦病院……」というメッセージを読者に伝えたかったのではないでしょうか?
コロナ禍で、つらい人が多い現在ですから、ノブや雅子といった存在を通して『頑張れ!』と喜多嶋隆は言いたかったのではないかと思いました。
今までの喜多嶋作品には、海、妹のような存在が、欠かせない基軸ですが、それに「心の病」というテーマも加わった印象があります。その始まりのような作品です。 (S・I)
■心が傷ついても、人生を投げやりにはできない、純真な気持ち。
それこそが、誰もが望む奇跡の種なのかもしれない。
奇跡の種を育てるには、自分が嫌になるような格好悪い姿を、人に見られてしまうこともある。
でも、それで良いんだよと、ポンと背中を押してくれる物語。
喜多嶋作品の中でも、特に、ずっと手元に置いておきたい1冊です。(熊谷みゆき)
■喜多嶋さんの作品はいつも、挫折を経験したり、心の傷を負った人間への理解、共感、そして応援する気持ちのこもったものですが、今回は特にその気持ちを強く感じられた作品でした。
長年の読者としては、明確に書かれたハッピーエンドより、物語が終わった先も続く、登場人物たちの人生を想像できるようなエンディングの物語が、今後も読みたいと思います。(K・I)
■1度読んで、涙が出る。
2度読んで、勇気が出る。
何度でも読みたいラヴ・ストーリーです。
湘南の鮮やかな色彩と、豊かな香りに包まれて、主人公ノブの生命力の回復と共に、自分の心のすり傷が癒されて行く……。
こんな奇跡なら、起きて欲しい……。
そんな気持ちで、3度目のページをめくっています。(柴田知実)
■ぶっきらぼうなノブと、親友を失い「眠れない」という戦場にいる雄次。二人の心と身体の距離が縮まっていく様に、のめり込んでしまっていた。海の恵みを受けながら、トラウマと向き合い懸命に生きるノブ。彼女のひたむきな言動は、“戦場”で生きる自分に勇気を与えてくれた。(網代布美子)
■喜多嶋隆を読むと、ほっとするのはなぜだろう。それはたぶん、大人による大人のための青春小説だからだ。物語に出てくるちょっとしたキャラクターがすべて、きちんと自分の人生を生きていて、自分の言葉を持っている。だからいつも、優しい気持ちで読み続けて、最後には前向きな気持ちになれる。
『7月7日の奇跡』は、LGBTや小児虐待、サラリーマンの鬱の問題、女性の自立の問題などの課題を扱いながら、それを前面に出して、声高に誰かを責め立てたり、正義を振りかざしたりする小説ではない。主人公のユウジも、ヒロインのノブも、社会がかかえる「どうしようもなさ」に対して、泣き叫んだり、怒りを爆発させたりしない。ただ一生懸命、「自分が成長する」という一番誠実だけど手間がかかるやりかたで対峙する。だからほっとする。その態度は、完全じゃない者に対して常に優しく、完全ではない自分もまた、許されている感じがする。
今の時代、ネットを開けば、声高に正義を叫ぶメッセージや、誰かを非難したり、悪を糾弾するメッセージがあふれている。完全な正義のヒーローは、悪を許さない。しかし、大人である限り人は、立場により、見方により、「悪」にもなりうる。だから、私もまた、きっと「彼ら」には許されないだろう。正義でも悪でもない中間を描くのが小説であれば、この小説は、本当の小説だ。ひとは不完全であり、その不完全さを許すから、ほっとするのだ。
矛盾にあふれた仕事に疲れて帰ってきて、喜多嶋隆を読む。そこには、ゆるぎない、変わらない、大きな海のような、あたりまえの大人の世界があって、すべてを包み込む。だから、前向きな気持ちになれる。葉山の海の、静かな潮騒の音の夜のようなにおいがする。
ちなみに私の誕生日は、7月7日でもあり、そんな意味でも、嬉しい小説だった。(吉森大祐)
▼喜多嶋隆『7月7日の奇跡』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322006000152/