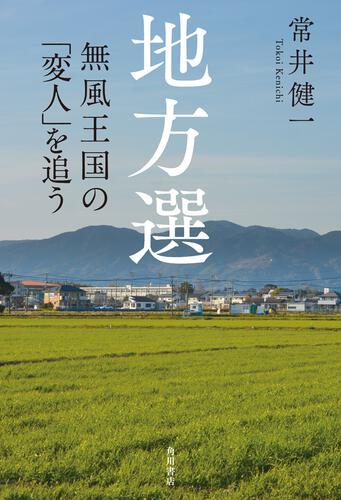ノンフィクションライターの常井健一氏が、全国の町村長選の現場を歩き、候補者と有権者、そして選挙戦の鍵を握る地域の“キングメーカー”らの心理を巧みに描いた異色のノンフィクション『地方選 無風王国の「変人」を追う』(KADOKAWA)。21年3月に佐賀県上峰町で実施される町長選は、現町長VS新人という、本書が取り上げた17年選挙と同様の構図での一騎打ちとなる公算が大きくなっていると報道されている。本記事の前編では、菅義偉氏の肝入り政策であるふるさと納税で潤った町で、かつて「全国最年少町長」ともてはやされた、現町長の人物像とバックグラウンドに迫る。(*本記事は『地方選 無風王国の「変人」を追う』第7章を一部改変して掲載したものです)
「サティの町」からふるさと納税へ
佐賀県
南北は12・5キロ、東西はわずか1キロしかない。いかにも山々に囲まれていそうな地名なのに、見渡す限りの平らな土地に一戸建て住宅と田畑が混在している。隣町には誰もが子どものころに学校で習った「
人口約23万人を抱える県都の佐賀市と福岡県
2010年代半ば、大きな曲がり角を迎えた小さな町に、1995年のショッピングセンター誘致に続く、「第2のゴールドラッシュ」が到来した。
トリガーとなったのは、2008年に始まった「ふるさと納税」だ。
総務省の統計によると、ふるさと納税による上峰町への寄付は2015年度で約21億円も集まり、全国の自治体の中で堂々の9位となった。16年度には約46億円に倍増し、さらに順位を上げて全国5位。受け入れ件数で見ると27万件(前年比約3倍)を超え、宮崎県
2013年度は20万円、14年度は40万円に過ぎなかったのである。それが一気にブレークしたわけは、15年後半に仲介サイト「ふるさとチョイス」に登録したことと、同年の税制改正で税額控除限度額が2倍に増やされたことが重なったためだ。上峰町は高額寄付者に最高級の佐賀牛一頭分の精肉を贈るなど、納税者の「肉」欲を満たす豪華な返礼品を他の市町村に先駆ける形で取り揃えたことによってブームに拍車をかけた。
平成末期、こうして西九州の名もなき小さな町は「ふるさと納税」「高級和牛」というバズワードのおかげで、知名度も全国区になったのである。
財政破綻寸前の町を襲った汚職
その仕掛け人こそが、この章の主役である上峰町長の
人口が1万人にも満たない小さな町に巨額のあぶく銭が転がり込んだことで、町民の暮らしは変わった。
町内では、中学生までが対象だった医療費助成が、「18歳以下」までに引き上げられた。
さらに、2015年からは小学校高学年を対象とした英会話授業と、中学校の補習指導がオンライン化された。
これには、佐賀県そのものがわが国屈指の「ICT教育」先進県だという背景もある。教育用コンピューター1台当たりの児童生徒数(2019年3月時点、文部科学省まとめ)は、全国平均5・4人のところ、1・9人というダントツの首位。第2位の高知県でも3・6人、東京都は5・2人、福岡県は7・1人だ。
県教育委員会は2014年から、県立高校の生徒を対象にタブレット端末の購入を義務付けた。同じころ、県西部の
一方、2015年12月には、隣町の小学校で佐賀市内の業者が手掛ける給食に、ボタン電池が混入するという問題が起きた。上峰町はその業者との取り引きをすぐに停止したものの、町内には給食が作れる自前の調理室がなかった。そこで、1億円を投じて閉鎖中の施設を改修し、民間の運営で地産地消メニューを提供する態勢を整えた。
即断、即決、即実行だった。
まるで意識の高い先進自治体のようにも見える上峰町だが、ふるさと納税で有名になる前までは、実は財政破綻寸前の地方公共団体であった。
平成に入ってからの「失われた20年」の間、バブル崩壊以前に計画された大規模な公共事業が続行された。その結果、町の借金は2003年度で117億円まで膨張。以後、約30億円の年間予算の3~4倍にも当たる借金を抱え、九州最悪の財政状況になった。そのせいで「平成の大合併」では、西隣の町からも東隣の町からも嫌われ、孤立を余儀なくされたのである。
そんな
出直し町長選は2009年3月に行われた。大川の後継者である副町長(選挙当時53)と、当時29歳の武廣の二者択一となった。町民の多数派は、若いほうの武廣に地元の再建を託した。
ロスジェネの「全国最年少町長」
町議会議員の抵抗に遭いながらも、財政再建は進んだ。ひたむきな改革姿勢は町民に支持され、2013年には、町の歴史で初めての無投票再選を果たす。14年度には町独自の判断で起債が認められる水準にまで財政状況が改善し、就任から5年ほどで「県内最悪」の汚名を返上したのである。
小太り、ふっくらしたほっぺ、クリッとした目。私は武廣のポスターを見て「ビッグボーイ」というファミリーレストランのマスコットを思い出した。
生まれは1979年。中学校から近所の公立校ではなく、自宅から約20キロ離れた同じ三養基郡の
武廣は、大量のワーキングプアを産み落とした就職氷河期の
「『勇平は東京では役立たんから帰ってきたんだ』と言って、おじが嘆いておったとよ」(町の有力者)
2009年3月、ビッグボーイは、人生大逆転の
当時は、民主党政権前夜。同じ九州の宮崎県では「
非自民陣営で政治家修業を積んできた武廣が、東国原ブームにどれだけ心動かされたのかは定かではない。だが、同じ九州で、同じ出直し選挙という条件下で、中学から故郷を出たという「よそ者」の経歴を逆手に取り、東国原さながらに「しがらみゼロ」とアピールした。
武廣の選挙を支えたのは、地元で無双の勝負強さを誇る原口一博ら民主党の関係者だった。武廣は政権交代の追い風にも乗る形で、相手陣営を支える自民党との対立軸を鮮明にし、275票の
ロスジェネの29歳は、その日を境にマスメディアから「全国最年少町長」と持て
「原口一博」という後ろ盾
あれから8年経った2017年。
3期目に挑む町長選を迎えた武廣は、町内で最も交通量が多い交差点のそばに選挙事務所を構えていた。
以前はファミリーレストランがあったという街道沿いの空き店舗の屋根には、今回のスローガンが田んぼの向こう側の町役場に見えるように大きく掲げられていた。
〈いよいよ実現のとき! わくわくすること 全力で。〉
事務所の机の上に置いてあった選挙公報を手にしてみたら、「8年間の実績」と銘打って三つの数字が誇らしげに躍っていた。
〈借金(地方債残高) 30億円 削減!〉
〈貯金(基金残高) 20億円 増加!〉
〈ふるさと納税 43・7億円 増収!〉
事務局長を名乗る男(取材当時74)は強調する。
「今回は、これまでと違って自民党の応援も受けているんですよ」
佐賀県では2015年の知事選で、地元の保守勢力が分裂し、自公推薦候補が敗れた。旧民主党系の武廣は内紛に乗じ、どうやら自民党支持層の一部を取り込もうとしたようだ。当時5人いた自民党国会議員の中では、復興相(当時)の
事務局長に据えられた人物は、ある集落で区長をした経験があるだけで「選挙の手伝いは初めてよ~」とおどけている。地元紙の佐賀新聞は、実働部隊の正体を「商工会青年部」と書いていたが、ユーレイ部員を差し引けば5~6人しかいない弱小組織に過ぎない。やはり陣営の中核にいるのは、原口を長く支えてきた選挙のプロたちだった。
その1人は、「原口の幼なじみなんです」と言う50代の男性である。もらった名刺には町内にある福祉施設の責任者という肩書きが書かれていたが、東京から突然やってきた不詳のライターを相手に、作り笑顔を絶やさずに抜け目なく対応する。
私はその時点で「プロ」だとわかった。
武廣と原口の深い関係は、お互いの先代までさかのぼる。
20代で造園業を起こした武廣の父は、地元選出の自民党衆院議員の
原口はこの取材をした2017年春時点で、7回連続当選。彼と争ってきた自民党と言えば、元大蔵官僚の
一方、武廣の父は1999年に町議になった。冒頭に紹介したサティが西九州随一の賑わいを見せていたころに、町の商工会長にものし上がった。2003、07年には町長選に出馬したが、2連敗を喫している。その時の対抗馬こそが、町議会多数派を従え、後に選挙違反で逮捕される大川であった。
「財政難を乗り切った総務課長です」
大川の一族は、長い間、上峰のキングメーカーを担ってきた名門である。
町屈指の大地主だった大川の祖父は昔、町議会議長を務めている。その末っ子も議長を務めた後、県議になった。大川家は中選挙区時代、大坪と別系統の自民党衆院議員も支えてきた。
町の図書館で1979年に発行された「上峰村史」をめくっていると、
町村合併の相手を西側の町にするか、東側の町にするかで二つの派閥が長らく争った時代もある。それが大川の登場以来、町政では大川派と反大川派に分かれ、国政では保守分裂で自民党VS民主党という構図になった。
取材当時69歳だった大川は町長失職後、3年間の公民権停止が明けた2013年に自民党上峰町支部長として復権を果たしていた。町議会で大川派と武廣派が拮抗する中、2017年の町長選で大川は一種の分断工作を仕掛けた。武廣の同級生で彼の側近の1人だったはずの最年少町議を擁立し、骨肉が争うような「同士討ち」を演じさせようと画策したのである。
だが、その町議は土壇場で出馬を断念し、大川の謀略は
「武廣町長とは人間の太さ、経験値が違いますよ」
てんやわんやの末、告示日の50日前になって大川派から対抗馬に名乗りを上げた
丸刈りの小柄だが、体格は良い。決して人も悪くない。だが、近くで話してみると、独特の薄ら笑いと、言葉の端々からにじみ出る感じのエリート臭が妙に気になった。
公務員の家庭に生まれた鶴田は上峰の小中学校と隣町の県立高校を出て、福岡大学経済学部を卒業後、1973年に当時の上峰村役場に入った。就職した動機については「戸籍がまだ手書きの時代。(役場職員が書く)達筆な文字に
以後、38年間、あらゆる課長職を経験した。役場時代の先輩でもある大川は鶴田の働きぶりを絶賛する。
「どんな仕事もソツなくこなす。ボクの町長時代に、財政難を乗り切ってくれた総務課長ですよ」
武廣が町長に就任した2009年、ベテラン職員だった鶴田は町の会計責任者兼出納室長という大役を任された。
東日本大震災が役人人生を変えた
鶴田は30歳下の新町長の下で1年間だけ勤め上げると、あっさり定年退職した。
その後、東日本大震災の被災自治体に役場のOBを助っ人として派遣する公募に手を挙げた。宮城県の
鶴田は語る。
「被災地で働くうちに、私の人生はずっと裏方だったなあ、と。1度は町のトップをやりたいなあと思った」
3月中旬、田んぼには短い雑草が青々と生い茂り、新しい春が到来していた。
「私は行政経験38年の恩返しをできればという思いで、この戦いに挑んでいます」
ライムグリーンのジャンパーの上にスーツを羽織るという不自然な着こなしをした鶴田は、碁盤の目状の新興住宅地を選挙カーでくまなく回った後、自衛官が暮らす5階建ての官舎前で演説を行っていた。
隣の吉野ヶ里町には陸上自衛隊
私は目の前にあるコンクリートの建物に多くの自衛官が住んでいるということを知ると、そこに来る直前に立ち寄った武廣事務所で2枚の為書きを見かけたのを思い出した。自民党参院議員の佐藤
自民党の2人は自衛隊員の家族やOB団体の応援を受ける全国比例選出の組織内議員である。なのになぜ、非自民の原口一博系町長のために、わざわざ武運を祈願するのか。私は町に自衛隊の拠点があることを知り、ようやく合点がいった。彼らは、上峰町のように自衛隊施設を受け入れ、騒音被害などを負う自治体と円滑に対話できる関係を保つため、現職首長の陣営に対しては党派を超えてもエールを送ることを慣例としている。
平日の午前10時だった。陽当たり良好のベランダには人影も見えない。時折、駐屯地に飛来する戦闘用ヘリが上空で
そんな環境の中で鶴田は訴えた。
「私も2年間、南三陸町に単身赴任で出向いていました。地元町長が自衛隊の復興支援に感謝していました。私の子ども2人も、海上自衛官として頑張っています」
1分30秒のアピールをお揃いのジャンパーを着た男女7人が静かに見守っていた。ウグイス嬢2人と
鶴田の事務所は、閑静な住宅地の中にあった。築30年程度の立派な日本家屋と同じ敷地内に2階建ての納屋がある。典型的な農家の屋敷だ。普段は車庫に使っているという木造の納屋の1階に大きな机を入れ、窓のサッシに神社のお札が立て掛けてあるだけ。活気に沸く武廣事務所とは対照的な
鶴田は告示後、毎日2度のミニ集会を企画した。各地区の公民館で自ら政策を説明する。約20人を前に30分以上、小役人っぽい棒読みで、私にとっては退屈極まりなかった。
長寿祝い金の充実など老壮年の有権者を意識する政策を強調していたが、若い参加者から次世代向けの支援について問われると、その場で具体策を示せず口ごもってしまった。
一方、本人到着まで大川派の町議たちが行う「前座」には、
▼常井健一『地方選 無風王国の「変人」を追う』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/322004000829/
◉合わせて読みたい:幻の町長選ルポ〟群馬県草津町長選(あとがきより)