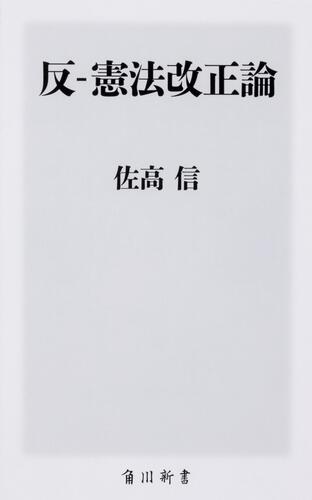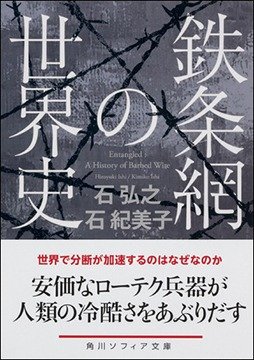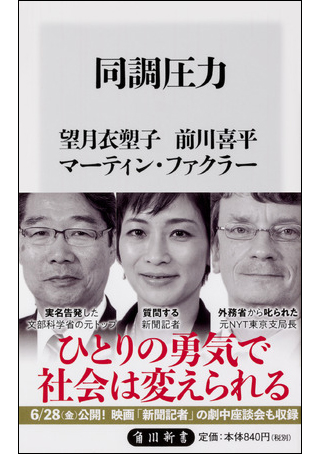2019年12月4日、アフガニスタンで用水路の建設や医療活動など、人道支援に取り組んできた中村哲医師が銃弾に倒れました。中村医師への取材をもとにまとめた『反-憲法改正論』第12章について、著者である佐高信氏と相談のうえ、哀悼の意を込め、全文公開いたします。
【中村哲氏追悼文】
日本国憲法が撃たれた――。佐高信
中村さんはいつも、自衛隊派遣が自分たちの活動を邪魔していると言っていた。アフガニスタンで井戸を掘り、用水路を拓くことで築いた信頼関係が、自衛隊の派遣で崩されるからだ。
私は、そんな中村さんを、「歩く日本国憲法」と言っていた。平和憲法の下でこそ、日本人であることが安全保障になるからだ。
その日本国憲法が撃たれた今、なおさら「平和憲法」が必要だと強く思う。
中村さんのご冥福を心からお祈りするとともに、彼が生前語っていた平和憲法への思いについて紹介した『反-憲法改正論』「第12章 アフガンを歩く日本国憲法、中村哲」を、追悼の辞としたい。
「第12章 アフガンを歩く日本国憲法、中村哲」
「週刊金曜日」の対談で中村と会ったのは二〇〇二年の春だった。アフガニスタンから一時帰国した中村とのそれは同誌の五月十七日号に載っている。
一眼見て魯迅に似ていると思ったので、そう言ったら、中村は、
「うわあ、それは光栄だな」
と目を細めた。
その中村が二〇〇五年元旦の「高知新聞」で鶴見俊輔と対談していた。
小さいころから論語の素読をさせられ、割と保守的な中村は、昆虫が好きで、虫の宝庫の山に登るようになり、アフガンへも最初、山岳隊員として行った。
そして、昔の日本と同じじゃないかと思い、ホッとした。中村はクリスチャンだが、儒教をベースにした儒教クリスチャンである。
鶴見との対談で中村は「国際貢献」という言葉が嫌いだ、と告白している。強いて言えば、自分たちのやっていることは「地域協力」だというのである。そこには平和憲法を改変しようとしている国家、つまり日本への不信感がある。
二〇〇一年に中村は国会のテロ対策委員会に参考人として呼ばれ、自衛隊派遣は有害無益だと断じて、自民党議員らからの強烈なブーイングを受けた。しかし、悠揚迫らずといった感じで、そのときのことをこう語る。
「テロ特措法で、バター味(米国)がしょうゆに入ってきて、バターの側の敵までしょうゆが引き受けてしまったということでしょうね。日本というと、やっぱりアジア諸国の人にとっては大きな心の支えだというのは現地の人の通念だと思うんですよね。ところが、米国支援で、いろんな敵をつくってしまった」
私は中村のことを〝歩く日本国憲法〟と言っているが、日本人の世界観は欧米からの借用だと語る中村は、それを次のように解説する。
「私たちがメディアで見聞きするアフガン像には、貧者の姿は映されていません。貧富のうち、富の声だけが届いている。富者のほうは英語を流暢に喋り、国連職員に雇われ、NGOで幅をきかす。九九・九九%を占める貧しい人たちは、依然として病や死と隣あわせにあるわけです」
言うまでもなく、これはアフガンに限らない。
中村たちは、国連もNGOも行かない山間辺境の無医地区に足を運ぶ。
「皆がわっと行くところならば行かない。だれかが行くところは、だれかにまかせておけばいい。それよりだれもが行きたがらないところ、だれもやりたがらないことをする。これが私たちの一貫した基本方針です」
しかし、はじめから使命感をもって途上国にかかわらなくても、物見遊山でもいいという中村の、力まない姿勢がいい。
そう言ったら、自分も最初はそうだったから、と中村は笑った。
『花と龍』で有名な玉井金五郎の孫である。その俠客に抱かれて育った。
「映画館のチケットを買うのに殺到する群衆の中には入りたくないですね。流行に乗るのはどことなく軽薄な感じがして、どうもついていけない」
〝歩く日本国憲法〟の魅力紹介に、つい、ペンが先走ったが、二〇〇七年に共同通信の依頼で書いた中村の『医者、用水路を拓く』(石風社)の書評を、重複を恐れずに引こう。憲法は〝危険地帯〟でこそ光を放っているのである。
〈「外国人によってアフガニスタンが荒らされた」という思いは、官民を問わず、党派を超えてアフガニスタンに広がっているという。そんな中で、井戸を掘り、用水路を拓く著者の試みは、例外的に支持を受けている。それはなぜなのか? まさにいま問題になっているテロ対策特別措置法が国会で審議されていた時、参考人として招かれた著者は、
「現地の対日感情は非常にいいのに、自衛隊が派遣されると、これまで築いた信頼関係が崩れる」
と強調し、自衛隊派遣は有害無益で飢餓状態の解消こそが最大の課題だと訴えた。
しかし、この発言に議場は騒然となり、司会役の自民党の代議士は取り消しを要求する始末だった。時計の針を六年前の著者の発言時点に戻せば、日本はどこでまちがったかが明らかになる。
その意味でも、この本は実に「タイムリー」な本である。
自衛隊派遣は著者たちのようなNGOの活動を危険に陥れるだけであり、まさに「有害無益」なのだ。「給油活動」なるものもその延長線上でしか捉えられないことは言うまでもない。
評者は著者を〝歩く日本国憲法〟と言っているが、平和憲法の下でこそ、「どんな山奥に行っても、日本人であることは一つの安全保障であった」という著者の指摘は成り立つのである。
喜ばれないものを派遣して、喜ばれているものを危うくすることが「国際協力」であるはずがない。医師である著者が「百の診療所よりも一本の用水路」を合言葉に現地で奮闘する姿は、これこそが国境を越えた協力の姿だということを示す。
一つひとつ地に足が着いた言葉で綴られる「報告」に読者は粛然とさせられると思うが、著者が病気で次男を喪う場面には、思わず、神はどうしてそんな試練を著者に与えるのかと叫ばずにはいられなかった。幼い子を亡くして著者は、空爆と飢餓で犠牲になった子の親たちの気持ちがいっそう分かるようになったという〉
人材育成コンサルタントの辛淑玉は、『日本国憲法の逆襲』(岩波書店)所収の私との対談で、日本国憲法が求めた人間像に、ペルーの日本大使公邸人質事件のときの国際赤十字のミニグを挙げ、
「あのとき、ほんとうに人質の命を助けたのはミニグさんです。権力の銃口とゲリラの銃口の間をバギーバッグひとつひきずって何度も往復して、人質を励まして、医者を連れていき、食糧を与え、しかも飄々と威張ることもなく、〝赤十字〟というゼッケン一枚つけて、あの紛争のなかを入っていったのです。
国際紛争のなかに、日本国憲法というゼッケンひとつつけて日本は一度として入っていったことがあるのか」
と問うているが、中村こそ、まさにその人だろう。
残念ながら、二〇〇〇年の時点で、辛の視野に中村は入っていなかった。憲法についての辛の次の解説も鮮やかである。
「弱い男ほど暴力を使うでしょ。戦争というのは口できちんと対応できない男たちのなれの果てだと思うんですよ。日本国憲法というのは、つまり、巧みな外交によって国際社会を啓蒙し、口だけで国を守れといったわけ」
なぜ、中村のような医者がアフガニスタンで井戸を掘っているのか?
「とにかく生きておれ! 病気はあとで治す」
中村はこう言って井戸を掘ってきた。
中村を立派な人と讃える声は充ち満ちているが、私は、中村が賽の河原の石積みにも似た医療と井戸掘りをやりながら、
「訳もなく哀しかった」
と述懐する場面に共感した。
『医者 井戸を掘る』(石風社)によれば、その日が中村の五十四歳の誕生日だったというのである。
「こんなところでウロウロしている自分は何者だ。……ままよ、バカはバカなりの生き方があろうて。終わりの時こそ、人間の真価が試されるんだ……」
と中村は思った。
もちろん中村は立派な、頭の下がる人間だが、それ以上に深い魅力を湛えた人間である。医学から出発して、人間の暮らしそのものを考えるようになったという点で、魯迅に似ている。同じような経歴をたどったチェーホフにも似て、独特の静かさとユーモアを体得しているのである。
「思うに、希望とは、もともとあるものだともいえぬし、ないものだともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には、道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ」
この魯迅の言葉を、中村も幾度か口ずさんだことがあるに違いない。
あるいは、魯迅がのちに妻となる許広平に宛てた手紙の次の一節も……。
「あなたの反抗は、光明の到来を望むからではありませんか? そうにちがいないと思います。だが私の反抗は、暗黒ともみ合うだけです」
私は竹内好他訳の『魯迅選集』(岩波書店)に拠りながら、『魯迅烈読』(岩波現代文庫)を書いた。中村は生き方において魯迅を実践していると言える。
魯迅が好きだという中村は、孔子と老子が出会う場面を描いた魯迅の「出関」も印象深く憶えているだろう。老子が別れぎわにつぶやく。
「同じ一足の靴であろうとも、わしのは、流沙を踏むもの、彼のは、朝廷へ登るものだ」
なぜ、中村は中村になったのかを知りたくて、私は一つ年下の中村に、
「どんな学生時代だったんですか」
と尋ねた。
「佐高さんと同じで、大学紛争。佐世保港が近くて、入学した翌年にエンタープライズ号が来て、九州大学の教養部が基地になったりして、それからゴタゴタに巻き込まれたりした。たまたま自治会の役員をしていたので、お巡りさんの厄介になったり。一時は、大学をやめたりしました」
やめたときは肉体労働をしていたが、一生これをやるのはと思って大学に戻ったら、まだ籍があった。
こう語る中村の気質の根本には儒教がある。
「うちの父は戦前の筋金入りの左翼でしたけど、メンタリティは右翼以上に封建的でしたね」
と笑う中村は、学生活動家になじめなかった。
「私の道徳感覚からいって、自分たちの先生を集団暴行でつるしあげるのは大嫌いだった。自分の恩師がつるしあげられているのを助けに行ったこともある。そんなこともあって、こんな人たちと一緒にいると命が縮むという消極的な理由で、実のない政治思想から離れました」
ペシャワール会にサポートされてアフガンに行っている中村は彼の地で撃たれそうになったこともある。
「実際、現場に立たされると案外そっけないものです。丁半で決められるようなもんですから。生死はわれわれが決定するものでもないというか。生きるものは生きるという妙に楽観的な気持ちが湧いてくるものです」
私はその死生観をただ聞くだけである。
「死ぬときは立派に死ねばいいですね。だめだと観念するときは、時間が非常に長く感じます。実際は数秒間でしょうけど。まず連れ合いのことを考えたり、生命保険であとの家族が暮らせるかとか。恐怖心とは違いますね」
反米親日だったアフガンの人たちの空気も、これだけ日本がアメリカの属国化してくると、変わってくる。中村によれば、しかし、一時はこんな〝誤解〟があった。
「あれはお人好しの日本人がアメリカにだまされているんだ。かわいそうだ」
日本人としては苦笑いするしかない〝誤解〟だろう。
それにしても、いわゆる治安の悪いアフガンで「地域協力」をしている中村が、平和憲法こそが大事と強調するのは説得力がある。
「あれだけの犠牲を払った上でつくられたものだから、一つの成果じゃないかと思います。それを守らずして、国を守るもないですよね。だから、それこそ憲法というのは国の掟、法の親玉みたいなもんじゃないですか。憲法をあやふやにして国家をどうのこうのというのはおかしい。それで靖国の英霊がどうのこうのというのは、結局彼らをテロリストにしちゃうんですよね。日本国憲法というのは、本当は戦争の犠牲の上にできたものですよ。それを改憲を言う人はコケにしたんだ。道徳的な心棒もそれでなくなっていく。非常に悪いですよね」
平和憲法は世界中の人が憧れている理想だから守る努力をしなければという中村は、
「ブッシュは(九・一一を)第二のパールハーバーだと言っていますからね。小泉(純一郎)は靖国をテロリストの墓地にしてしまった」
と慨嘆する。アフガン爆撃もそうだが、その後のイラク空爆を真っ先に支持した小泉を批判した中村は、
「職業軍人だからと言って彼らを悪いとは思いません。彼らは彼らで国に尽くしたわけで、職業軍人と一般国民の犠牲の上に平和憲法ができた。決してアメリカが押しつけたのではなくて、日本国民がそれを受け入れた。それが戦後の原動力だった。それを壊すようなことをしたら、日本の国はどうなるのかというのが私の率直な感想です」
と語る。
「とにかく軍隊を持てば次には戦争をしたくなるわけです」
と私が言うと、中村はこう答えた。
「指導者はね。軍隊が一つの利権団体でもあることは、どの国でもあります。それは医療でもそうだし、あらゆる分野がそうだと思いますね。一つの確立した組織があると、かならず利権がある。経済的な動機と大義名分がごっちゃになってしまうのは、世界中そうじゃなかろうか。医者が患者を助けるのが何が悪いと、過剰な診療をやる。大義名分としては反対できない。けどそういう形で薬品会社、医療機械産業の利害が関わってくる。経済的動機と大義名分が一体化するとこわいですよね。軍隊は特にそれが起きるとおそろしい」
この中村の何か役に立ちたいと考えたのが作家の澤地久枝だった。それで澤地が聞き手となった中村との共著『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る』(岩波書店)が生まれる。
「はじめに」に澤地は書く。
「ホテルの一室でやっとお目にかかれたのは、二〇〇八年八月十一日の午後。
小柄な、やわらかい物腰、静かな声でゆっくり話す人であった」
澤地が連絡をとってから二年後だった。
「そんな無理をつづけていたら、いのちが危いじゃないか」
と澤地が本気で思うきびしいスケジュールで中村は動いていた。
澤地の掘り起こしたいろいろな逸話がある。
アフガンにも、けっこう若い人が助っ人に来る。彼らは、ボランティアの意義だとか、国際問題だとか、いろいろ言う。
「それはあとで話そう。ともかく明日は、あそこの溝を掘ってくれ」
と中村が言うと、
「はあ」
と答えてツルハシを持つが、使い方もわからない。そこで「役に立たない自分」というのを発見する。しかし、一カ月もすると、
「先生、あそこの岩盤は硬いけど、発破作業でやりますか。ツルハシで起こしますか」
と具体的に聞いてくる。
「先生、水が出ました」
そんな喜びも味わって、理念の空中戦はなくなり、たくましくなっていくという。
アフガニスタンの首都カブールには、銀座顔負けのきらびやかなアーケードができている一方で、凍死する人がゴロゴロいる。国外からの援助で政治家や商売人が潤っている一方で、餓死者が出ているのである。
「片や、大金持ちが庶民では生涯できないほどの贅沢をして、それを外国軍が守るという、この構図。これが崩れないわけがない。そのなかで、テロ特措法だのなんだの、むこうで聞いてると、トンチンカンなものを議論しているという気がしてならないです。みんなまだ、食っていくのに一生懸命なんだ」
ペシャワール会についての澤地の解説を引く。ハンセン病患者の治療に始まって、水路建設の土木工事の指揮者になる中村を支えてきたのがペシャワール会である。
「六年間キリスト教系の派遣医師としてペシャワールで医療にあたったとき、この会の方針にしたがって自らを支える後援組織を作った。数すくない友人知己が発起人となって、中村医師の現地での事業を支えるためにペシャワール会が生まれる。このNGOには、若者をふくむ多くの日本人がボランティアとして、中村医師とともに働いてきた。
記録映像を見ると、水路建設の作業をする人々の頭上に何機もの低空飛行する米軍ヘリコプターの姿がある。機銃掃射の標的にされて攻撃され、外務省を通じて米軍に抗議をし、非を認めさせたということもあった。
一触即発の大地で、丸腰こそが事業達成の最大前提であると、ゆるぎない意志を語るが、その声が激することはない。全国で『中村哲先生報告講演会』がもたれ、ペシャワール会会員の会費と寄付によって、十六億円の水路建設費用はまかなわれている。日本人はこの事実を誇りにしていいと思う。カネが万能の退廃した社会にあって、ペシャワール会のサポーターとなった日本人の『善意』を」
終章で、また澤地は書いている。
「厄除けめいて日の丸を車のボディに描いてきた中村医師たちは、日の丸が危険防止の方法たり得ない状況に立ちいたったとき、日の丸とJAPANの文字を消す。自衛隊のアフガン介入の予測によって、日本人ボランティアの安全性はいちじるしくおびやかされるに至ったのだ」
世界において平和憲法を掲げる日本こそが尊敬され、親しまれているのである。それを改めることは、まさに日本を壊すことになる。中村はそれを日々の暮らし、生き方において教えている。
二〇一三年六月六日付の「毎日新聞」夕刊でも、中村はこう言っている。
「憲法は我々の理想です。理想は守るものじゃない。実行すべきものです。この国は憲法を常にないがしろにしてきた」
憲法九条が変えられたら、自分はもう日本国籍なんかいらないという中村は、九条の現実性を次のように強調する。
「アフガニスタンにいると『軍事力があれば我が身を守れる』というのが迷信だと分かる。敵を作らず、平和な信頼関係を築くことが一番の安全保障だと肌身に感じる。単に日本人だから命拾いしたことが何度もあった。憲法9条は日本に暮らす人々が思っている以上に、リアルで大きな力で、僕たちを守ってくれているんです」