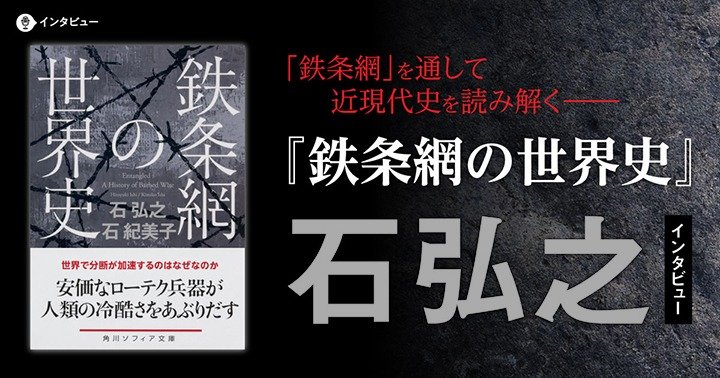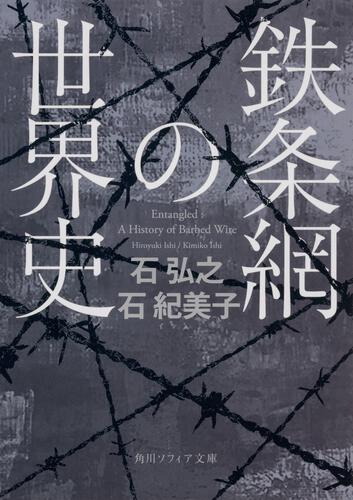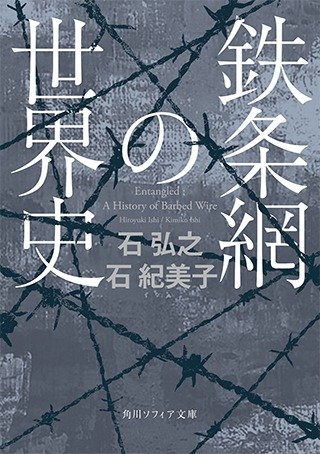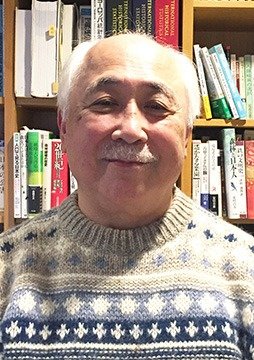平等や自由がうたわれる現代でなお、世界の各地で分断が続くのはなぜなのでしょうか。人間の強欲が視化される過程を追ったユニークな書『鉄条網の世界史』を刊行された石弘之さんにお話をうかがいました。
◆鉄条網が可視化させる「分断」
── : 今回のご本は、鉄条網を通して近現代史を読みとく、というものですが、そもそもなぜ鉄条網だったのですか。鉄条網に目をつけるというのはユニークです。
石: はじめて鉄条網の存在を意識したのは、約二十年前にケニアの国連機関で働いていたときでした。あるときに、首都ナイロビから北西部一帯に広がる農業地帯の「ホワイト・ハイランド」で調査をしていました。この呼び名があるのは、植民地時代に白人が占有していたからです。調査が終わって、近道するために茂みを通って道路に戻ろうとしたとたん、下半身に巻き付くものがありました。雑草に覆われて見えませんでしたが、錆びた鉄条網が絡み合った大きなかたまりでした。 身動きするとジーンズを通して鋭いトゲが皮膚に食い込んでくる。クモの巣に捕まった虫のように哀れな姿になりました。大声で助けを求め、やっとはずしてもらいました。鉄条網がこれだけ自由を拘束できるとは思ってもみませんでした。このときに、はじめてまざまざと鉄条網を見ました。それまでも、いくらでも見る機会があったのに、意識したことはなかったのですね。 調べてみると、鉄条網はもともと1860年代に米国中西部のカンザス州とフランスで、ほぼ同時に発明されました。畑への家畜や野生動物の侵入を防いだり、家畜を逃がさないように飼ったり、外敵から財産や家畜を守るという、開拓時代の西部では願ってもない機能を兼ねそろえていたんです。西部開発の強力な脇役になり、爆発的に普及していきました。 そして、畑と放牧した家畜を分け隔てる機能が、またたくまに人と人を「分断」するという役割を担うようになります。敵味方、人種、民族、宗教、貧富……さまざまな違いを、安易に安価にそして強力に隔てる道具になってしまいました。
── : 当初の目的からずいぶん変わってしまいました。
石: アフリカで働いていたときには、植民地の歴史なども調べていたのですが、鉄条網がひんぱんに出てくるんです。アフリカに乗り込んできた宗主国は、なるべく現地民と摩擦や戦争を起こさないで、土地を占領したい。そこで土地を鉄条網で囲ってしまう。鉄条網はこん棒やペンチ1本で壊すこともできますが、囲いこまれた鉄条網の中には心理的にも入れなくなってしまう。 ホワイト・ハイランドは、アフリカでもっとも土地の肥えた一帯でしたが、やってきたイギリス軍が鉄条網で囲い込むことで簡単に占領することができました。 そんなとき「分断」というキーワードが浮かんできたんです。今、「分断」ということばが世界中をうろついていますね。たとえばトランプ米国大統領のメキシコ国境の壁、メイ英国首相のブレグジット、中東では政治、宗教、宗派が絡み合って複雑に分断されています。「分断」の問題は実は古くて新しい。冷戦時代には深刻な分断が地球の各地で起きました。それがふたたび力を得て新たな装いで広がりはじめました。むろん、トランプ大統領の影響は大きいと思います。 「分断」を「鉄条網」というキーワードで眺めると、世の中が別の角度から見えて新しい発想がわいてきました。分断という抽象的な概念が、鉄条網を通すと非常に具象的になり、可視化されることに気づいたのです。
── : アメリカ‐メキシコの国境をはじめ、ベルリンやサラエボなど、さまざまな分断の地が紹介されます。
石: 僕がそんな構想を娘の紀美子に話したんです。娘は当時、テレビのディレクターを辞めて内戦終結後のボスニア・ヘルツェゴビナの国連和平機関で働いていました。旧ユーゴスラビアは超複雑で、「7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家」を統合していたのですが、それが内戦でばらばらになり最終的に6つの国家に分断されました。この過程でいたるところに鉄条網が張り巡らされたんです。娘も鉄条網ではさんざん苦労していたので、いっしょに本を書こうということになったわけです。
── : 鉄条網の歴史を調べるために、かなり大変な思いをして資料を集められたそうですね。
石: そうなんです。鉄条網の資料なんかほとんどなくてね。集めるのに10年ほどかかりました。ある文献を読んでいるときに言及されていた著作があったのだけど、販売もされていないし図書館にもない。米国の著者にメールして送ってもらいました。南米やアフリカから取り寄せたものもありました。もしも、鉄条網の研究をされたい方がおられたら、そっくり差し上げたいと思います。
◆世界各地の先住民は風前の灯火
── : 石さんは環境問題の専門家として、アマゾンなどの南米地域やアフリカでも現地に足を運んで来られました。記者や大学の研究者だけでなく、国連機関や大使としても働きましたね。そういった現場感覚も大きかったのではないでしょうか。
石: そうですね。僕は記者時代から熱帯雨林の森林問題を長く追いかけてきたのですが、それを通して先住民の問題に関わってきました。その一つにアマゾンの先住民の問題があります。ブラジルに600万人いるといわれた先住民ですが、今はわずか20万人ほどしか残されていません。 熱帯雨林の調査で奥地に入り込むと、先住民たちと出会うことがありました。彼らは失礼ないい方かもしれないけど、物乞いのような状態で暮らしていた。

牧場を追われてわずかな土地にしがみついて生きるカイオワ族
もちろん、最初からそうだったわけではないでしょう。かつて彼らは生活資材をすべてジャングルから得て暮らしていたはずです。
そこに征服者がワーッと入ってきて鉄条網で土地を囲い込み、先住民の暮らしていた土地を奪い、森の木を片っ端からチェーンソーで切り倒して、あっという間に大豆やトウモロコシの畑にしてしまいました。生活の基盤を失った彼らは当然生活できず、貧しさに拍車がかかりました。自殺が増え、集団自殺も起きています。
先住民への迫害に対して国際的には批判が高まり、1970年代にはすでに「先住民が住んでいる場所を開拓してはならない」という法律がブラジルでできたのだけど、「じゃあ先住民さえいなきゃいいんだろ」と、先住民を殺す人が出てきた。
ひどいのになると「あなたも人間を撃ってみませんか?」という殺人ツアーまで組まれることもありました。
── : 信じられません。人間の残虐さを思い知らされます。さまざまな先住民が、征服者により虐げられていくことも本書で記されています。
石: 先住民の迫害は世界のどこでもありましたし、現在進行形の問題でもあります。アメリカ、ブラジル、オーストラリアの先住民など、枚挙にいとまがありません。 日本も例外ではありませんよ。明治32年(1899年)に制定された悪法「北海道旧土人保護法」は、1997年のいわゆる「アイヌ文化振興法」の制定まで、実に100年近くも生き続けました。アイヌは「旧土人」として、土地の没収、固有の習慣風習の禁止、日本語使用の義務、日本風氏名への改名などが義務付けられてきたのです。
── : 迫害や同化政策もあり、先住民はかなり減ってしまいました。
石: コロンブスがカリブ海に来たときに上陸したイスパニョーラ島というのがあります。そのときにその島だけで住民は100万人以上いたと言われています。私が1974年に行ったときには3人になっていました。その1人のおばあちゃんに草で編んだ帽子をもらって、今も僕の家に飾ってあります。 その後まもなく3人とも亡くなりました。その種族は全滅してしまったわけですね。そういう話はほかにもたくさんあります。ちょうど20世紀の半ばから後半にかけて、先住民は世界中で次々に絶滅していきました。
── : 征服者とともに、先住民にとってのもう一つの大きな脅威が感染症だというのも驚きました。
石: インフルエンザ、はしか、天然痘など、僕たちにとっては予防も治すこともできますが、彼らはそれまでそういった病気に接したことがないから免疫がまったくありません。僕がアマゾンにいたときも、石油の探査チームがある先住民の村を通って奥地へ入って石油探査して同じ道を戻ってきたら、2週間前に通りすぎた村の全員が死んでいた、ということが起きました。
── : 感染症といえば、石さんは前著『感染症の世界史』のなかで、さまざまな感染症にかかったことを紹介されています。
石: さまざまな熱帯病の洗礼を受けましたね。マラリア4回、コレラ、デング熱、アメーバ赤痢、リーシュマニア症、ダニ発疹熱各1回、原因不明の高熱と下痢数回……人間ドックのときに渡された書類の「既往歴」に書いたら、看護師さんに「忙しいんですからふざけないでください」と叱られました。よく生き残ったと思うこともあります。 こんな話を聞けば、アマゾンやアフリカには、おっかないばい菌がいっぱいいると思うでしょう。ところが調べてみると、彼らから私たち文明人がもらう病気よりも、私らが彼らに移した病気の方がはるかに多く、しかも死亡率が高いんです。
(後半へつづく)
後編はこちら▶鉄条網が促す劇的な自然の回復