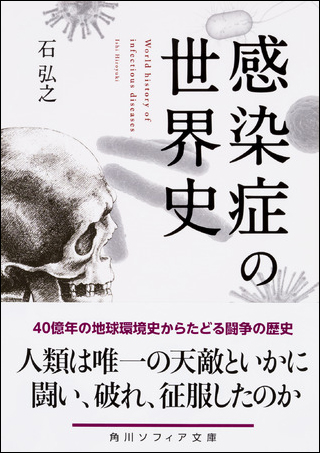人間の持つ外的排除の心理を可視化させてきた鉄条網。そんな負のイメージのなかで、清涼剤となることもある、というのが後編です。どういうことでしょうか。
<<【前編】世界で分断が続くのはなぜか。人間の外的排除の心理を見つめなおす。
◆鉄条網が強欲と結びつく
── : 本書ではほかにも鉄条網が引き起こした地球規模の環境変化や、戦争なども描かれています。
石: 鉄条網ができて土地の囲い込みが容易になったことで、アメリカではそれまで家畜を放牧させていたのが牧場になりました。囲い込まれた土地で家畜は草を食べつくし、土を踏み固めます。草地だったところの荒廃が目立つようになります。また農地も大型農業機械の導入で掘り返され、酷使され、土壌がやせ細っていきました。 こうした土壌が悪化したところに干ばつが起こり、「黒いブリザード(吹雪)」と呼ばれるすさまじい大砂塵が巻き起こり、各地を砂で埋めました。

一瞬にして街を飲み込んだダスト・ボウル(1934年、アイオワ州)

ダスト・ボウルが収まった後、村は砂塵で埋まっていた(1936年、サウスダコタ州)
1934年5月12日のニューヨークタイムズの紙面には「高さ数千フィートにも舞い上がった大砂塵が、1500マイルも離れた西部から押し寄せ、昨日は太陽の光が5時間もかすんで見えた」(1フィートは約0.3m、1マイルは約1.6㎞)、と報じました。映画にもなったスタインベックの小説『怒りの葡萄』のテーマでもあります。
── : 鉄条網によって安易に囲い込めたために大災害にまで結びついてしまったということですね。
石: もっと家畜を出荷したい、もっと収穫を多くしたい、という人間の強欲が鉄条網と結びつくと思いがけない災害を呼び起こしてしまいます。強欲という点では、戦争も同様でしょう。
── : 第4章で記されていたナチスドイツの強制収容所なども鉄条網がなければ、と思わずにいられませんでした。
石: その前から戦争で鉄条網は大きな役割を果たしていましたが、第二次世界大戦のころには拘束施設に欠かせないものとなっていました。その究極がナチスの強制収容所でしょう。政治犯や共産主義者、ユダヤ人、同性愛者、エホバの証人の信者など、反政府、反社会とナチスが決めつけた人たちを次々と送り込みました。 このほかにも旧ソ連の強制収容所、太平洋戦争直後にアメリカやカナダにつくられた日系人の強制収容所などは、鉄条網抜きには存在しえなかったでしょう。 人間を狭い空間に押し込めて無力化し、家畜のように扱うことを可能にしてしまう。鉄条網がなかったら、ナチスの強制収容所があれだけ大規模な殺戮ができただろうか、と思います。
── : こう見てくると、私たち人間はだれもが心の奥底には分断したいとか差別してしまうという心理を持っているのでしょうか。
石: 常にあるのでしょう。分断する、差別する、というのは人間の欲や自衛本能に結びつく面もあるでしょう。鉄条網は発明から150年たっても現役を続け、ほとんど進化していません。こんなローテクですが、人間の欲望が続く限り第一線を退くことはないでしょう。
◆鉄条網が促す劇的な自然の回復
── : この本の最終章では一転して、鉄条網が自然を保護しているという話題が記されます。
石: 朝鮮半島を分断する軍事境界線やチェルノブイリ原発の周辺などです。鉄条網で囲い、人が入れないようになっているがために、自然が劇的に回復しているというわけです。
たとえば朝鮮半島の軍事境界線は、幅が30~40㎞あり、囲われた面積は22万平方㎞、朝鮮半島の全面積の0.5%を占めています。朝鮮戦争で71%あった朝鮮半島の森林の割合は35%まで落ち込んでしまいました。
その後、軍事境界線が設けられると、目に見えて自然が回復し、近年は78.3%までになりました。

森林に覆われたプリピャチの街(ウクライナ政府チェルノブイリ原発省提供)

チェルノブイリの制限区域内に現れた、巨大な角を持つヘラジカ
動植物にとっても天国となり、韓国では最も豊かな生物多様性を誇る地域になったのです。
チェルノブイリでも、原子炉の近くは今も高濃度の放射線を出し続けているにもかかわらず、ワシミミズクやオジロワシなど、絶滅危惧種がみられるようになりました。ある報告書では、「皮肉なことに、制限区域はまれに見る生物多様性の保護区になった」と結論付けるほどです。さらにこのエリアに希少動物を導入し、保護増殖を図る試みまで始まり、実際に効果が見えた動物もいます。
── : 人が入らないことで自然が回復するとは、たしかに皮肉めいていますね。
石: 日本でも、東日本大震災のあと、鉄条網で区切られた帰還困難区域で植物が生い茂り、野生動物が増えたことが確認されています。また、ヒラメやナメタガレイなどの海産資源量が増えていることがわかりました。震災の影響で漁獲量が減ったことが逆に資源を守る結果になったというわけですね。 とはいえ、放射能汚染の影響が自然界にどのように出るのかはまだまだわかりません。今後の研究を見ていきたいと思います。
── : 鉄条網という地味ながら脅威の存在を触媒にすることで、人間の深層心理や歴史の必然があぶり出されることにおどろきました。今の世界の現状を考えるときにも新しい視点をもたらしてくれました。
石: 時間はかかりましたが、この本をまとめながら、この変哲もないトゲ付き鉄線が環境や戦争、ときには個人や種族の運命を大きく変えてきたことに気づきました。 なぜ今、世界のあちこちで「分断」が起きているのかを考える一助にもなると思います。