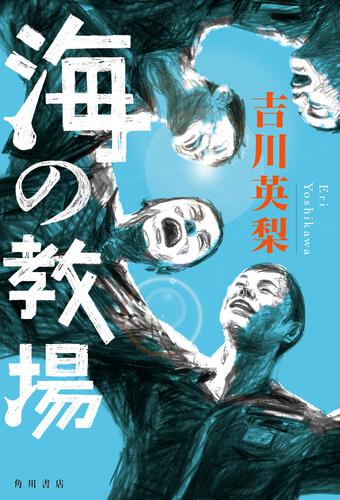2022年7月4日に吉川英梨さんの新刊小説『海の教場』が発売されました。『海の教場』の舞台となるのは、京都府舞鶴市にある海上保安学校。海の安全を守る海上保安官になるために、学生たちが必要な教育や訓練を受けるところです。
発売前の7月2日、海上保安学校のオープンキャンパスイベント「
前日の市長と校長への表敬訪問の様子とあわせて、イベントのレポートをたっぷりとお届けします!
7月1日 多々見舞鶴市長を表敬訪問
舞鶴の多々見良三市長はもともと、海上保安学校で校医をされていた方で、海上保安学校のこともよくご存知です。吉川さんとは2度目の対面ということもあり、話が弾みました。
吉川さんから『海の教場』のサイン本と共に、舞鶴の名所・五老岳から舞鶴湾を望む風景が描かれた連載挿絵(画=西川真以子さん)の原画を贈呈し、市長と舞鶴市役所の方々にも喜んでいただけました。
多々見市長「海を守っている海上保安庁の7割の人が舞鶴で1~2年修行していることを誇りに思っています。生まれも育ちも違う人間が共同生活をして、船の上での業務に備えているんですよね」
吉川「取材で訪れたときからなんだか懐かしい感じがしたのですが、舞鶴の方言は私が縁のある北陸に近いからかなと感じました。父方の祖父がシベリア、母方の祖父が満州の引揚者ということもあり(ユネスコ世界記憶遺産となった)舞鶴引揚記念館も訪れました」
歴史ある海上保安学校
海軍の街・舞鶴で、創立71年目を迎える海上保安学校。『海の教場』でも、実際の学校の様子がふんだんに取り入れられています。
趣のある校舎に入ると正面には、小説の中でも存在感を発揮する、昭和19年から設置されている重鐘式巻き時計が見えてきます。
7月1日 彼末海上保安現学校長に挨拶
4月に学校長に着任された
校長室には歴代の校長名が書かれた木札がずらりと並んでいます。4月に着任した彼末校長の名札はまだ日に焼けておらず、木の色が鮮やかでした。
彼末校長「まずは単行本の完成、おめでとうございます。「日刊ゲンダイ」に連載されていた時から読んでいましたが、だいぶ加筆されたんですか?」
吉川「ありがとうございます。連載は、本当は「海のもしも」の電話番号と同じ数字の118回で終わる予定だったのですが、数え間違いで119回になったのが残念でした(笑)。新聞連載は1回あたりの文字数が決まっているのと、次が読みたくなるように書かないといけないため、そのまま単行本にするとつながりが悪いところもあり、かなり加筆しました」
彼末校長「取材内容がだいぶ小説に織り込まれているようで、連載時から反響があったとお聞きしています。単行本も楽しみです。明日の五森祭は、コロナ禍もあって3年ぶりにお客さまを入れての開催となります。市民の方やオープンキャンパスに訪れる方も楽しみにしているようです」
吉川「取材時は、当時の校長の江口さんや、事務局の方が本当に親切に対応くださいました。学生さんや教員の方だけでなく看護師さんなどもご紹介いただいて、登場人物の造形やエピソードにはまったく困らなかったです。とても楽しく書くことができました」
彼末校長「海上保安学校は18歳から30歳まで本当にいろいろな学生がいるのでモデルには事欠かないですね。海上保安庁創設時からの伝統「正義仁愛」の精神の下、共同生活を送る中でいろいろなドラマが生まれます。ぜひまた小説に書いていただけると嬉しいです」
7月2日 いよいよ五森祭 トークイベント
全国から参加者が集まる五森祭のトークイベントは、39度にも達した暑さの下、海上保安学校の講堂で行われました。制服を着た音楽隊の演奏で吉川英梨さん、前海上保安学校長江口圭三さん、宮野直昭海上保安協会常務理事が入場します。
客席には、前日に表敬訪問した多々見舞鶴市長、彼末校長の姿もありました。
世界初? 海上保安学校を舞台にした『海の教場』について
吉川「海上保安庁に取材した小説を書いていた際、元教官の方と、警察学校を舞台にした小説はあるけれど海上保安学校を舞台にした小説はないよね、という話になったんです。ちょうどドラマで警察学校を舞台にした「教場」をやっていたこともあり、「海の教場」というタイトルが生まれて、執筆するご縁となりました」
宮野「まさにその「海の教場」という言葉が生まれた瞬間に立ち会いました。吉川さんは取材の行動力がある方で、実際に学校を訪れて見聞きしたことをこうして物語にしているのに感動します。この『海の教場』でも、海上保安庁に関する特殊用語、専門用語もわかりやすく書いていただいている。
また、複数のエピソードがつながって物語が変化していき、それでも通底した一つのストーリーが紡がれているという構成が素晴らしいです。海上保安庁の現場では何一つ一人ではできなくて、仲間と一緒にやっていく、その正義仁愛の精神や心が小説を通してひしひしと伝わってくる。くすっと笑うところもあり、感動して涙を流すこともあって、読み応えがありました」
江口「新刊のおすすめコメントの依頼を頂き「生きることの意味を考えさせられる秀逸な作品。自分の進むべき道を探している人に是非読んでもらいたい」と寄せました。教官や学生のドラマで、教官自らも成長していくという小説は、これから海上保安官を目指す方だけでなく、いま自分の道を探している人にも参考になる本だと思います。
吉川さんの取材にも立ち会いましたが、本当によくご覧になっていて、舞鶴のことも学校のことも詳細に書かれていると思いました。生活や訓練を巧みに表現いただいています。舞鶴の湾と半島の形について、両腕を上げた格好になっているなんて言う描写は素晴らしいと思いました」
取材の思い出について
吉川「コロナ禍だったのでなかなか来られず、何度も計画倒れになってやっと去年の五森祭に来られました。ところが、ちょうど熱海の土石流災害があった時で新幹線が停まってしまい、お昼ご飯のカツカレーをふるまっていただくのを15時くらいまでお待たせしてしまいました。お腹が空いていたこともあったんですが、本当においしかったです」
江口「去年はコロナ禍で、来場者を入れず学生だけで五森祭を開催したところに、吉川さんに見に来ていただきました。学生の主計課程の取材をしてもらって、巡視船の中での生活を簡単に説明しただけなのに、非常によく理解されて小説の中で実にリアルに描写されていて驚きました。ただ、ありのままの状態をご覧いただいたのでひやひやする場面もありました」
吉川「「ここは書かないで」って言われたところですね(笑)」
江口「五森祭の前夜祭に「私の主張」というイベントがあって、学校生活の疑問や教官の文句なんかを叫ぶんです。最後に出て来た教官が号令をかけて、吉川さんがいらっしゃるのに全員上半身裸になって万歳するという場面があって……そこは書かないでください、とそのとき申し上げたんですが(笑)」
吉川「作家としては書かずにはいられない貴重な場面を拝見できたので、ちらっと書かせていただきました(笑)。前夜祭はコロナ関係なく、ふだんから一般の方には公開していないようなので、ぜひ読んで頂きたいですね。
遠泳訓練も心に残っています。翌日に主計のクラスを見学させていただきました。遠泳訓練が終わった学生さんたちは普通に授業を受けているんですが、日焼けの後がくっきり残っていて、なんだかたくましくなっている。指揮官・教官が目じりを下げてその日焼けの跡について言及しているのを見て、その優しいまなざしがとても印象に残っていて、学生と教官の深いつながりを書けるのではないかなと、ひとりでうるっときました」
主計科の教官を主人公にした理由
吉川「『海蝶』は潜水士の話、『感染捜査』は特殊警備隊の話で、ヒーロー・ヒロイン的な強い人が主人公だったため、ふつうの海上保安官も描きたいと思ったのが理由です。船の中でも縁の下の力持ちといわれる主計科の人を主人公にしました」
江口「学校に取材にいらっしゃるのだから厳しい訓練教官を考えておられるのかなと思って、そういう教官を選んだんですが、ことごとくイメージをはずした変化球で人物造形がなされていて面白かったです。
取材してもらったのはシュッとした教官ばかりだったんですが、メタボの中年という形に置き換えられていましたね(笑)」
吉川「学園ものは登場人物が多いので、かなりひとりひとりに特徴をつけ、読者に印象付けようとしています。極端な人物描写になっているところもあるかと思います」
小説の舞台となった海上保安学校について
江口「海上保安学校は海上保安庁の聖地といっても過言ではありません。これからの長い仕事の礎になる、基盤をつくる場所であって、教官と生徒が切磋琢磨しながら高めあっていくところです。そうした学校が持っている絆みたいなものを『海の教場』ではしっかりと描いていただけました。
私自身、海上保安庁職員となっていろいろな仕事をしたけれど、一番悩んだのが教官時代でした」
宮野「主人公の教官が成長していくのもこの小説の読みどころで、「キョウイク」と言いますが「教え育てる」のではなく「共に育つ」。学生を育てることで教官自身も成長していくところが、『海の教場』に描かれていると思っています」
吉川「またひとつ、海保のことを好きになったなと思いました。もともと警察小説を多く書いていまして、海上保安庁小説を書いてくれないかというお声を受けてからこの世界に踏み入ったのですが、取材に行くたびに面白い方々との出会いもあって、本当にどこに行っても歓迎してくれて私を楽しませてくれる。
人間が豊かになれる部分は海の上で育まれるところが多いのかなと思いました」
江口「海上保安官というのは世間で認知されていない分、説明したがりが多いのかもしれないですね。巡視船、航空機では一人では何もできないということもあるかもしれないです」
海保小説三部作の年
吉川「実は、出版業界では「よく書くね。海の小説は売れないんだよ、みんな海を知らないから」なんて言われます。私も海保小説三部作を書きましたが、海を知らない人にはハードルが高いのが事実です。どうやって読者のハードルを下げていけばよいのかというのが悩みどころでした。取材の現場で聞く専門用語はカタカナでいうより漢字のほうがわかりやすいので、表記で工夫したり、わかりやすくかみ砕いた表現にしたりもしました。海保の方から見るとリアリティが損なわれるかもしれないところも、わかりやすさを優先して書いているところもあります」
宮野「私も昔オレンジの服を着ていたことがあって(特殊救難隊)、沈没船の中で迷子になったりしたこともありました。そういった経験の後、PTSDになりそうになることもありました。仲間たちに失敗談を話すことによって、克服していったところもあります。吉川さんの海保小説を読んでいると、そういった現場が思い出されてジェットコースターのように気持ちが動かされます。しんみりと泣かせるところもあり、ぐーっと気分が上がるところもある小説です」
江口「『海の教場』は海保をよく知らない人が読んでも面白いと思います。海上保安官の人も自分の立ち位置、スタンスが振り返れるような内容です。
私がドキッとしたのは第三章。悩める男性学生を、主人公の教官が竹島の国境域に連れて行って迷いを吹っ切らせるところ。我々が国境で頑張ることで平和が保たれていれば、国民が知らなくてもいいという描写があります。自身も警備などの仕事が多かったので、これは自分のことかなと思うくらいドキッとさせられました」
吉川「警備部門のことは教えてもらえないことが多いので、あれは私が考えて書きました。作品の肝になる部分は取材で手に入るものではなく、作家自身が見つけなければならないんですよね。主人公の目線になって絞り出した一言だったりもします」
『海の教場』でおすすめの章は?
吉川「全部なんですが(笑)前夜祭を描いた第四章。主人公が想いをよせている女性にプロポーズしているところです。あとは第五章「溺れる猿」。実際に遠泳をみせてもらったときのひとつひとつのことばなどを活かしました」
江口「女性の海上保安官が女性ならではの生き方で悩むシーンもあるのでぜひ参考にしてほしいです」
上記はイベントのごく一部。
会場の学生さんからも熱い質問が飛び出るなど、拍手に包まれてトークイベントは終了しました。
『海の教場』は全国の書店で発売中。ぜひお読みください。
(寄稿:アップルシード・エージェンシー)
プロフィール
吉川英梨(よしかわ・えり)
1977年、埼玉県生まれ。『私の結婚に関する予言38』で第3回日本ラブストーリー大賞エンタテインメント特別賞を受賞し2008年に作家デビュー。「女性秘匿捜査官・原麻希」シリーズ、「新東京水上警察」「警視庁53教場」「十三階」「海蝶」の各シリーズ、『雨に消えた向日葵』『感染捜査』など著作多数。(アップルシード・エージェンシー所属)
おしらせ
・海上保安学校のHPはこちら。
https://www.kaiho.mlit.go.jp/school/
・イベント出演の江口圭三さんは現在、日本水難救済会の常務理事。
日本水難救済会は、海難救助に駆けつけるボランティア救助員を支援しています。
7、8月は、「青い羽根募金」の強調運動期間。ぜひご注目ください!
https://www.mrj.or.jp/donation/index.html
https://twitter.com/Qsuke_MRJ/
・宮野直昭さんが所属の海上保安協会は、海上保安活動に関する普及啓発を図るために、海上保安新聞を月3回(原則)発行しています。
キャラクター「うみまる」のグッズも展開中。
https://xn--p8j1fc3cznsc6g4e.jp/index.php
https://twitter.com/JCGF_umimaru/
関連記事
吉川英梨 最新作『海の教場』の舞台へ~海上保安学校 卒業式&巡視船みうら 訪問記~
https://kadobun.jp/feature/readings/4bku5sndc2kg.html
使命と私情の両立に新時代のステージを感じさせる海上保安官小説――吉川英梨『海の教場』レビュー【評者:門賀美央子】
https://kadobun.jp/reviews/entry-46272.html