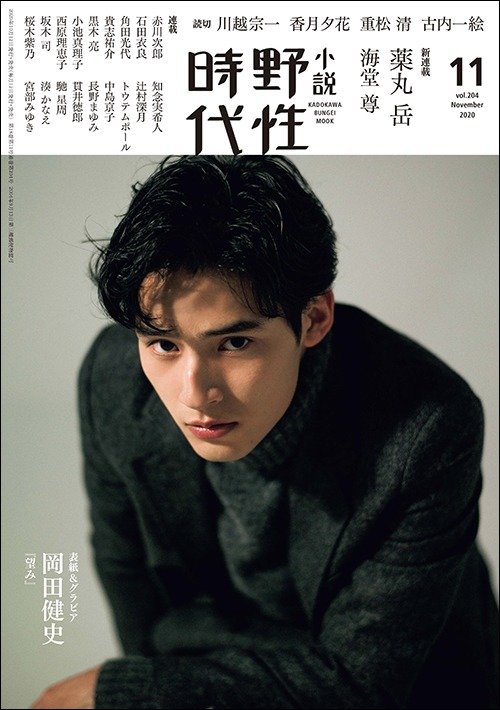殺人犯と、娘を殺された父。
死刑執行が迫るなか、二人の命懸けの対話が始まるという話が展開される、薬丸岳さんの新刊『最後の祈り』。動機なき殺人の闇に迫った本作について、話を伺いました。
取材・文:タカザワケンジ
写真:橋本龍二
『最後の祈り』刊行記念 薬丸岳さんインタビュー
一晩で骨格までできた作品
――娘を殺された父が、娘を殺した死刑囚と向かい合い、復讐を企てる。大変難しいテーマに挑まれましたね。
薬丸:本が出てからずっとそうなんですが、読者から受け入れられるのかどうか、不安でしょうがないですね。これまで書いてきた作品の比ではないくらい。
――着想はどこから?
薬丸:「小説 野性時代」で連載を、と以前から言われていて、何年も前からまったく違う、もっとエンタメ寄りの話を考えていたんです。これでいこうと決めた頃に、ある晩、寝る間際に、急にこの話がパッと思い浮かんだんです。僕としては珍しいくらい、ある程度までの骨格が一晩くらいでできあがりました。
どうしてもこれをやりたいという思いが強くなり、編集部にA4で2枚くらいのプロットを出して了解してもらい、急遽、連載を始めることになりました。
――では、すんなりと書き出せたんですか?
薬丸:それがそうでもなくて。書くにあたって、クリアしなければならない問題がいくつかありました。
一つは僕の知識面です。キリスト教や教誨師の仕事、死刑についてなど、書き切るだけの知識が足りてないな、と。
もう一つは設定に関して。自分の大切な人を殺された牧師が教誨師になって犯人に復讐する、というアイディアをどうやってリアリティのあるものにするか。家族や恋人を殺された人がその犯人の教誨をできるわけがないですから。
考えれば考えるほどハードルが高かったんですが、これはもうスタートするしかないなと腹を決めて連載を始めました。万全の準備をしてスタートしたというよりも、書きながら調べ、考えながら書いていったという感じでした。
――死刑について、そのプロセスも含めて緻密に描写されていますよね。まずそのことに驚かされました。
薬丸:冒頭が死刑執行の場面ですからね。死刑については、巻末の参考文献の数倍を読みました。挙げているのは実際に参考にさせてもらったものです。死刑に関する本はそれなりの数が出ているんですが、本によって書かれている内容がかなり違うんですね。
僕が読んだ本は元刑務官の方が退官後に書いたものが多かったので、情報が古いこともあるし、拘置所によって違うのかもしれない。でも、たしかめようがない。情報の取捨選択が難しかったですね。
日本では、死刑について法務省が公式に発表していることがごくわずか。クローズドなものなんです。
――教誨師についてはどうですか。
薬丸:教誨師の連盟があるので、取材を申し込むことも考えたんですが、しませんでした。教誨師が犯人に復讐するというストーリーだけを見ると、とても取材協力はお願いできなくて。読んでいただければ理解してもらえると思うんですが、まだ書く前なので誤解されるんじゃないかという危惧がありました。直接取材はできなかったので、数少ない資料や本を読んで、探り探り書いていきました。
――巻末に牧師の方に謝辞がありますね。
薬丸:この方は教誨師ではなく、一般的な牧師をされている方です。ふだんのお仕事や、日常生活、お給料などの生活面について、貴重なお話をお聞きしました。礼拝に参加させていただいたり、教会の中を見学させていただいたりお世話になりました。
舞台はほぼ拘置所。逃げ場がなかった
――主人公の保阪宗佑は刑務所に通い、教誨師の仕事もしている牧師です。かつて罪深い行いをした彼は、いまは信仰の道に入って穏やかな暮らしをしています。しかし、事件が起きたことでその生活が一変してしまいます。キリスト教の「赦し」という概念が、これまで薬丸さんがお書きになってきた罪と罰というテーマにダイレクトにぶつかり、保阪自身の「許し」と葛藤が生まれる。『最後の祈り』は薬丸さんの作家としてのキャリアの中でも重要な作品だと思いました。
薬丸:自分でもチャレンジだったと思います。いままでは個人としての罪と罰を書いてきました。しかし今回は、神の前では罪人も赦されるという教えを説いてきた牧師が、自分の大切な人の命を理不尽に奪った人間の前で同じことが言えるのか、という問いです。
信仰をお持ちの方は、一般の人よりも罪に対して寛容なのかもしれない。そうだとするとこの話を成立させるのは難しいのかなと思ったこともありました。
しかし、『デッドマン・ウォーキング』という映画を見て少し考えが変わりました。以前にも見たことがあって、もしかしたら近いかもと思って見直したんです。
――1996年の映画ですね。ショーン・ペンが死刑囚。スーザン・サランドンが彼を支えようとするキリスト教のシスターでした。
薬丸:映画の中でスーザン・サランドンが死刑囚に寄り添っていると、同じ信仰を持つ仲間にあんなクソ野郎を助けようとするなんて、と罵倒されるシーンがあるんですね。それを見て、クリスチャンだからと言って、犯罪者に寛容なわけではないんだな、と。聖書の教えがあるから、ということにこだわりすぎず、一人の人間としての苦悩を描いてもいいんだなと思いました。
――『最後の祈り』がエンタテインメント小説として開かれていると感じたのが、キリスト教の描き方です。キリスト教の精神性を踏まえた上で、主人公を同じ現代の日本に生きる普通の人として描いています。多くの読者が自分事として想像できる物語にしていると思いました。
薬丸:ありがとうございます。中盤までは自分でも自覚できていなかったんですが、後半になってきて、やっとこれがやりたかったのか、こういうことだったのか、ということが見えてきたんです。
でも、連載の最中はきつくてきつくてしょうがなかったですね。逃げ場がないって言うんでしょうか。ちょうど『罪の境界』と『刑事弁護人』『ブレイクニュース』とこの『最後の祈り』の連載期間がかぶっていて、それだけでも大変だったんですが、ほかの三作と比べても『最後の祈り』がきつかった。ほぼ拘置所の中だけの話で、ホッとするような場面を入れづらいんです。唯一、若い刑務官の小泉のパートだけは、家族がいるので多少の息抜きはできたんですけど。
「許す」「許さない」の二択に悩んだ日々
――『罪の境界』は罪のない人が通り魔に殺されるというお話ですけど、あちらは事件を追いかけるのが当事者とはいえ生き残った人。ところがこちらは死刑に関わっている人ばかり。死に向き合い続ける人たちの心のうちを描くのは本当に大変なことだろうと読んでいて思いました。
薬丸:『罪の境界』は『最後の祈り』とは真逆で、あまり話を決めずに書き始めたんです。通り魔にあった女性が、自分の身代わりになってくれた男性のことを思う、くらいは考えていたんですが、その後の展開は書きながら考えていきました。どう展開するかを選ぶ余裕があったんですね。
ところが『最後の祈り』は、ストーリーができてしまっていて、結末は保阪が死刑囚の石原を許すのか許さないのかの二者択一しかない。許すとしたら、石原が改心して被害者に贖罪の念を持つというのがいちばん腑に落ちる結末ですが、そうは絶対にしたくなかった。ご都合主義になってしまう。じゃあ、どうすればいいのか。後半になればなるほど悩みました。
――読者としてもドキドキしました。だからこそ、結末とエピローグに心を打たれたわけですが。
薬丸:考えて考えて考えて、やっと見つけた着地点ですね。読者からは賛否両論あるかもしれないのは覚悟の上で書きました。
――これはもう読んでもらわないと伝えられないので言いませんが、薬丸さんの人間観が出ているなと思いました。
薬丸:人間って白と黒だけじゃなくてグレーの部分もあると思うんですよ。物語は終わっても登場人物たちの苦悩が終わるわけではない。納得した、の一言で片付けられない、済ませられないことを示すのも小説の力じゃないかなと思います。
読者のみなさんからどんな反応が来るかはまだわかりませんが、一度読んで納得できなかった人でも、数年後に読み返したら、わからなくもないかなと思ってもらえるかもしれない。読者の方々を信じて書いた作品になったと思います。
プロフィール
薬丸岳(やくまる・がく)
1969年兵庫県生まれ。2005年に『天使のナイフ』で第51回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。2016年に『Aではない君と』で第37回吉川英治文学新人賞を、2017年に短編「黄昏」で第70回日本推理作家協会賞〈短編部門〉を受賞。『悪党』『友罪』『Aではない君と』『死命』など作品が次々と映像化されている。他の著作に『アノニマス・コール』『ラストナイト』『刑事弁護人』『罪の境界』などがある。
作品紹介
『最後の祈り』薬丸岳
2023年4月21日(金)発売
KADOKAWA 刊 2,090 円(10%税込み)
四六判上製 416 頁
殺人犯と、娘を殺された父。
死刑執行を前に、 命懸けの対話が始まる。
東京に住む保阪宗佑は、娘を暴漢に殺された。妊娠中だった娘を含む四人を惨殺し、死刑判決に「サンキュー」と高笑いした犯人。牧師である宗佑は、受刑者の精神的救済をする教誨師として犯人と対面できないかと模索する。今までは人を救うために祈ってきたのに、犯人を地獄へ突き落としたい。煩悶する宗佑と、罪の意識のかけらもない犯人。死刑執行の日が迫るなか、二人の対話が始まる。動機なき殺人の闇に迫る、重厚な人間ドラマの書き手・薬丸岳の新たな到達点。
詳細はこちら:https://www.kadokawa.co.jp/product/322009000359/
amazonページはこちら
楽天ブックスページはこちら