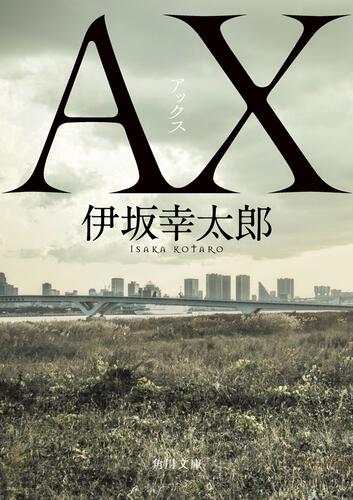伊坂幸太郎『マリアビートル』ハリウッド映画化記念インタビュー
伊坂幸太郎『マリアビートル』がなんとハリウッドで映画化、日本でも9月1日公開となる。映画のタイトルは「ブレット・トレイン」。主演はブラッド・ピット、監督はデヴィッド・リーチ。日本のエンタメ小説がハリウッド映画になるというビッグプロジェクトに、原作者は何を思うのか。
『マリアビートル』がハリウッド映画になるまでの経緯
――そもそも、『マリアビートル』がどうして、ハリウッド映画になったのか、その経緯を教えてもらえますか?
伊坂:すごく簡単に言ってしまうと、アメリカの映画関係者に、僕の小説を紹介したところ、面白いと思ってくれた人がいた、ということなんですよね。とはいえ、もちろん、実際に簡単なわけではなくて、いろんな人たちの尽力があって実現したのですが……。
――『マリアビートル』はその時、英訳されていたんですか?
伊坂:まだ、英訳出版はされていなかったんです。というよりも、そこが発端と言いますか。
十年くらい前から、英語圏でも僕の小説を出版したいと頑張ってくれているエージェントがいるんですね。もともと出版社の編集者だった人と、別業種から来た人の二人で。
エージェントとはいえ、僕と知り合った時はほぼ、実績はなかったと思うんですが、彼らも、日本の小説がもっと国外で読まれてほしい、という気持ちで頑張っていて。
それまで僕の場合は、作品ごとに出版社が窓口をやってくれていて、それはそれで助かる部分も多かったですし、問題もなかったんですけど、ただ、彼らのチャレンジ精神とか、小説への思いみたいなものに共感して、お願いすることにしたんです。
――海外の読者に読まれたい、という気持ちは強かったんですか?
伊坂:いやあ、僕はほんと、そういう気持ちはなくて(苦笑)。日本の読者が楽しんでくれて、それで自分が生活できれば充分ありがたいですし、海外進出したいという気持ちもあまりなくて。
ただ一方で、良くも悪くも、「伊坂幸太郎は、どうせこうなんでしょ」という先入観を持たれている気持ちもずっとあって、先入観のない人たちに、「面白い」と言われたいなあ、という夢はずっとあったんですよね。そんな時に、彼らが現われて、だから、お願いしてみたんです。
日本の出版社も理解を示してくれて、彼らが、海外出版の窓口をやってくれるようになったのが十年くらい前で。その流れの中で英語圏への売り込みもしてくれていたんですが、ただ、壁が厚いと言いますか、うまくいかなくて。
――英訳出版が、ですか?
伊坂:イギリスでは、出版したいと言ってくれる人が現われたんですが、アメリカでは全然で。向こうが求めているものではなかったんでしょうね。自分の作品は通用しないんだな、と落ち込みましたし、日本の僕の読者に申し訳ないな、と思いました。
その中でエージェントの彼らが、映画という方向から出版に結び付けられないか、とも考えてくれて。特別なことをしたわけではなく、正面突破というか、映画関係者に会いに行って、小説の説明をして、というのを何度も繰り返してくれたんです。
『マリアビートル』が日本で映像化されていない理由
――たくさんある作品の中から、どうして、『マリアビートル』にしたんですか?
伊坂:これは僕の場合に過ぎないのかもしれないのですが、すでに日本で映像化されているものは、アメリカで映画化するのは少しハードルが高かったんですよね。権利とか、大変なことが多い感じで。前に、日本ですでに映像化されているものをハリウッドで映画化したい、という監督が現われたことがあって、僕は実現してほしかったんですが、結局うまくいかなかったんです。なので、まだ日本で映像化されていないものがいいな、と。
――『マリアビートル』は、新幹線の中で殺し屋たちがぶつかり合う、という設定からして非常に映像化に向いていそうですね。
伊坂:もともと、『マリアビートル』は、エンターテインメントとして映画や漫画よりも面白い小説を書きたいな、という思いで書いたものなんです。
遡ると、同じ世界観で書いた『グラスホッパー』という小説が、発売された後はほんとうに評判が悪かったので、そのリベンジで書いたという(笑)。
――『グラスホッパー』は初期の代表作と紹介されたりもしますが。
伊坂:今でこそ、そう言ってくれる人もいるんですけど(笑)、当時は、「よく分からない」「面白がり方が分からない」みたいに書評家の方や知り合いに言われちゃって、「そんなに面白くないのかなあ」と編集者と言い合うくらいだったんですよね。
もちろん褒めてくれた人もいましたけど、それにしても悔しくて。だから、「つながりのある小説で、絶対面白いと言わせたい」と書いたのが、『マリアビートル』だったんです。
――日本で映像化されていなかったのは理由があるんですか?
伊坂:ありがたいことに、小説が出た後、日本で、映画化したいと言ってくれる人が多かったんですよ。ほかの小説の時以上に。映画監督さんでもすごく熱意のある方がいらっしゃって。ただ、『マリアビートル』に関しては、日本で映画化すると、小説とそれほど変わらないものになっちゃうような怖さがあったんですよね。
「小説は面白い!」と読者に思ってほしくて書いた小説なので、「映画を観れば、小説は読まなくていいや」と思われちゃったら寂しいな、と思ったりして。
ほんと贅沢な話ではあるのですが、声をかけてくれた方には、そういう気持ちを説明して、映像化はしないでいたんです。
もし万が一、ハリウッドとか海外で映像化されることができたら、小説とは違うものになるでしょうし、お願いしたいなという話もしていたんですよね。まあ、そんなことはないだろうな、とは思ってましたが。
――まさか本当に、ハリウッドで映画化されるとは、という感じですね。
伊坂:僕は直接やり取りしていないのですが、ハリウッドのソニー・ピクチャーズのプロデューサーが興味を持ってくれて、こっちが用意していた英訳もすぐに読んで、「面白い!」と連絡してくれた時は、嬉しかったです。
向こうは、伊坂幸太郎なんて知らないわけですし、単純に、中身を面白がってくれたんだ、という気持ちがあって。そういう人に出会えたということが、ありがたかったです。日本の読者にもようやく顔向けできるような、そういう感覚でした。
僕の勝手な思い込みかもしれないんですが、日本だと、売れている小説とか、人気がある小説とか、もしくはよっぽど監督が思い入れのあるものが映画化されるように思っていたんですけど、『マリアビートル』の場合は、英語で本も出ていなければ、知名度がまったくなくて、それなのに、映画にしたいと言ってくれたんですよね。
面白いストーリーやアイディアをとにかく求めているんだなあ、と感じましたし、だから、今回は僕の小説が映像化されましたけど、日本の作家っていろんなアイディアとかストーリーをたくさん出しているので、どんどん広がっていく可能性はあるんじゃないかな、と期待したくなりました。
映画「ブレット・トレイン」の監督と主演について
――『デッドプール2』などで知られるデヴィッド・リーチ監督ですが、決まった時はどう思われましたか。主演はプラッド・ピットさんになりましたが。
伊坂:直接、制作に関わるわけではないですし、誰が監督するのか、どんな映画になるのか、楽しみにしているだけだったんです。ただ、想像以上に、ソニーのプロデューサーさんは僕たちに仲間意識を持ってくれているような、そんな印象を受けました。
ハリウッドとかになると、権利を買ったらあとは、こっちには何の連絡もなく進めていくんだろうな、と考えていたんですけど、話せる範囲ではいろいろ報告してくれて、それはすごく嬉しかったです。
デヴィッド・リーチさんは、『アトミック・ブロンド』も恰好良かったですし、『ワイルドスピード/スーパーコンボ』『デッド・プール2』も楽しくて好きだったので、まさか監督してくれるとは、という感じですよね。ブラッド・ピットさんにいたっては、もはや現実味がないと言いますか、こんなことがあるのかな、と。
ただ、もともと心配性なので、そんなに規模が大きいことになって大丈夫かな、とか胃が痛くなってますけど(苦笑)。
――胃が痛いんですか(笑)。
伊坂:僕自身は、向こうのプロデューサーさんが最初に、「面白いよ。映画にしたい!」と言ってくれた時点で、完結しているというか、それでもう充分なところはあるんです。
実際、映画が公開されたりすると、ただ無邪気に喜んでいられないことは、日本で映像化してもらった時も経験していますし、規模が大きくなればなるほど、心配です。
映画の舞台は架空の日本
――舞台は日本ですけど、だいぶ違いますよね。
伊坂:せっかくハリウッド映画になるなら、日本にこだわらなくてもいいんですよ、と映画制作側には最初、伝えていたんですよね。
外国の映画で描かれる日本、というのはどこか違和感があるじゃないですか。むしろ日本以外を舞台にしてくれたほうがいいな、と。『マリアビートル』は日本が舞台じゃなくても成立する話ですし。
――確かに、そうですね(笑)。
伊坂:日本じゃないと成り立たない作品だったら、日本を舞台にしないと良くないかもしれないですけど、まったく架空の話で、そもそも僕の小説に出てくる登場人物は、日本人かどうかも分からない、ファンタジーの存在なので。
これまでも韓国や中国で、僕の小説が映画化されていますが、それも全部、日本とは関係ない映画になっていますし、そういう感じでいいのではないかな、と。
ただ、ハリウッドの制作側の人たちが、日本の新幹線を舞台にしたがっていたんですよね。最初からずっと言われていたのは、「いくつもの駅に停車して、時間をきっちり守る電車は、日本くらいなんだ」ということで(笑)。
ほかの国にもあるんじゃないかとは思うんですけど、僕は日本のそういう、ちゃんとしているところが好きなので、そう言ってもらえたのは少し嬉しかったです(笑)。
ただ、それだったらアメリカとかで、日本の新幹線みたいな架空の列車を作っちゃえばいいのでは、とも思ったんですよね。
映画「ブレット・トレイン」の感想は
――実際にご覧になって、どういう感想を持たれましたか?
伊坂:面白かったです! かなり、はちゃめちゃで(笑)。一流の人たちが集まって、こんな遊び心に溢れた映画を作ったなんて、ほんと楽しかったです。なんか、観終わった後にもう一度観たくなっちゃって。ジャンクなお菓子を食べた後みたいな(笑)。
でも、想像以上に、小説のアイディアを使ってくれていることに驚きました。
正直なところ、「新幹線の中で殺し屋が戦う」という部分だけ使われるのかな、と考えていたんですよね。ですので、かなり小説のままという部分が多くて、嬉しかったです。
個人的には、仙台に住んでいて、東北を舞台にした小説をたくさん書いているので、盛岡行きの新幹線から京都行きに変わっちゃったのが残念、といいますか、東北のみなさんに申し訳ない気持ちになっちゃうんですが、実際の新幹線を誘致するとか、そういうのとは違うので、許してほしいなと思っています。
――小説では新幹線ですけど、映画では超高速列車という乗り物なんですよね(笑)。
伊坂:あ、そうでした! 違うものなんです。実際、まったく違いますからね(笑)。
ちなみに正直なところ、僕自身は、「ハリウッド映画で描かれる、違っている日本」というのが少し苦手だったんですよね。理解されていないのかなあ、と寂しくなっちゃいますし。ただ、今回、分かったんですけど、当然、映画制作側も、「これが日本だ」と思っているわけではないんですよね。
情報化社会ですし、さすがに、日本に来たことがある人も多いですし、映画の中で日本のトイレが印象的に登場するみたいに(笑)、いろいろ知っているんですけど、ただ、あくまでもフィクションの世界の舞台として、全部でっち上げているんだなあ、と分かりました。
だって、東京を夜に出て、朝方、京都に到着するんですよ(笑)。距離感ももはや歪んでいます。
だけど、これって、さっきも言いましたけれど、最初に映像化が決まった時に思った、「まったく架空の新幹線を作ればいいのに」ということ、そのものなんですよね。僕はアメリカを舞台にした架空の列車を、と思ったんですけれど、それを架空の日本に持ってきたと思うと、「何だそうか」と感じたというか、細かいことが気にならなくなりました(笑)。
小説を書いている時には、鉄道に詳しい人に細かい指摘をされないかな、とびくびくしていたんですが、今回の映画はもう、大きい指摘しかできないというか(笑)、ここまで違うとたぶんみなさん、現実とは違うものとして受け止めてもらえるんじゃないかなあ、と。
あとそれとは別に、現実の日本や、現実の新幹線と違っているのは、良かったなと思っているところもあるんですよね。
――それはどうしてですか。
伊坂:『マリアビートル』のあとがきに「架空の新幹線の、現実とは違う世界の話と思っていただけるとありがたいです」といったことを書いているんです。
リアルな感じになると、列車での物騒な事件とかと関連付けられちゃう怖さがありますし、それはつらいし、嫌だなと思っていました。
できるだけ一般の人に危害が加わっている印象にならないように、と思いながら書いてはいたんですよね。フィクションはあくまでもフィクションなので、だから、まったく違う、架空の世界だと考えてほしい、とは強く思っていましたので、こうして、現実とは違う、時代設定もよく分からない、「日本っぽさのある架空の国」「架空のお話」みたいな雰囲気になったことで、現実と重なりにくくなっていますので、これはすごくホッとしました。
とはいえ、もちろん、「日本がこんな風に描かれるなんて」とつらい気持ちになっちゃう人もいると思いますし、そういう方には申し訳ないなあ、という気持ちなんですが。
原作小説と映画の設定の違いについて
――「王子」は、原作の男子中学生という設定から、若い女性に変更になっていますよね。
伊坂:「王子」に関しては、小説を書いた時から言っていますが、「嫌な少年」とか「少年法に守られた、ずるがしこい少年」というつもりではないんですよ。
悪の象徴、比喩みたいな気持ちなんですよね。
世の中の恐ろしいことが起きる要因には、「同調圧力」や「集団心理」があると思っているんですが、そういったことを仕掛けてくる存在という感じで。「人間の弱点」を狙う悪魔的な存在の擬人化と言いますか。殺し屋たちは、人間の弱点に翻弄されていく、みたいにしたかったんですよね。ですので、映画で、強面の男とかに変更されているよりは、一見、怖くなさそうな女性になったのは、間違っていないと思いました。
ただ、映画では、「王子」が小説よりは、分かりやすい感じの嫌な人間になっているので、そこが原作とは一番大きな違いだと思っています。でも、小説のままだとかなり不快感が強いので、エンターテインメント性を重視して、そうしたのは良かったんじゃないかな、と感じています。
――ほかに、小説との違いで気になっているところはありますか?
伊坂:小説では、ある人物の素性をいかに隠すか、読者に驚いてもらうか、かなり苦労したんですね。映画だとそこがかなり分かりやすくて、たぶん、もともと隠す気がなかったんだと思うんですよ(笑)。ですので、驚きたい人は先に小説を読んでもらいたいなあ、という気持ちはあります。
あ、あと、原作にはまったくない会話や場面なのに、なぜか、僕の小説的と思えるものがいくつかあるんですよね。僕が別の作品で使った固有名詞が、映画の中に出てきたり、とか。たまたまではあるんですけど、僕の熱心な読者は、「全然違うけれど、伊坂幸太郎的だな」と思う部分が何ヵ所もあるような気がしています。
――最後に、読者や映画を観る方たちに伝えておきたいことはありますか?
伊坂:現実社会ではいろいろつらいこと、暗いニュースも多いので、この映画を観ている時は、「どこの列車なんだよ!」とか、「どうしてここで、その歌が流れてくるんだよ!」とか(笑)、ありがたがる必要はないと思いますけど、突っ込みながら笑って、楽しんでもらえればいいなあ、と思っています。
何より、素晴らしい役者さんたちがみんな魅力的ですし、僕の小説が好きな人も嫌いな人も、面白がってくれればいいなあ、と今は祈るような気持ちです。
プロフィール
伊坂幸太郎(いさか・こうたろう)
1971年千葉県生まれ。東北大学法学部卒業。2000年『オーデュボンの祈り』で第5回新潮ミステリー倶楽部賞を受賞しデビュー。『アヒルと鴨のコインロッカー』で第25回吉川英治文学新人賞、短編「死神の精度」で第57回日本推理作家協会賞を受賞。08年『ゴールデンスランバー』で第21回山本周五郎賞、第5回本屋大賞を受賞。著書に『グラスホッパー』『マリアビートル』『AX アックス』『重力ピエロ』『逆ソクラテス』『マイクロスパイ・アンサンブル』など多数。
映画「ブレット・トレイン」原作小説『マリアビートル』
2014年大学読書人大賞受賞
英国推理作家協会賞(ダガー賞)翻訳部門 ショートリスト作品(最終候補作)(英題『Bullet Train』)
著 者:伊坂幸太郎
定 価:836円(本体760円+税)
ISBN:9784041009772
発売日:2013年9月25日
https://www.kadokawa.co.jp/product/321302000007/
幼い息子の仇討ちを企てる、酒びたりの殺し屋「木村」。優等生面の裏に悪魔のような心を隠し持つ中学生「王子」。闇社会の大物から密命を受けた、腕利きの二人組「蜜柑」と「檸檬」。とにかく運が悪く、気弱な殺し屋「天道虫」。疾走する東北新幹線の車内で、狙う者と狙われる者が交錯する――。
小説は、ついにここまでやってきた。映画やマンガ、あらゆるジャンルのエンターテイメントを追い抜く、娯楽小説の到達点!
『グラスホッパー』『AX アックス』に連なる、殺し屋たちの狂想曲。
<殺し屋シリーズ>とは
角川文庫より発売中の『グラスホッパー』『マリアビートル』『AX アックス』の3作が、通称 <殺し屋シリーズ> 。毎回個性的な”殺し屋”が登場し、各作品は関連するものの続きの物語ではなく、それぞれ独立した作品として楽しめる。<殺し屋シリーズ> は伊坂幸太郎屈指の人気を誇り、シリーズ累計300万部を突破。今なお売れ続けている。
▼「殺し屋シリーズ」特設サイトはこちら
https://kadobun.jp/special/isaka-kotaro/koroshiya/
映画情報
タイトル:『ブレット・トレイン』
(原題: BULLET TRAIN)
日本公開情報:2022年9月1日、全国の映画館で公開
原 作:伊坂幸太郎「マリアビートル」(角川文庫刊)
監 督:デヴィッド・リーチ
脚 本:ザック・オルケヴィチ
オフィシャルサイト:https://www.bullettrain-movie.jp
オフィシャルTwitter:https://twitter.com/BulletTrainJP
オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/BulletTrainJP/
こちらの記事もおすすめ
【会員限定】伊坂幸太郎 幻の短編「マリアビートル・イントロダクション」
https://kadobun.jp/feature/readings/entry-45957.html
伊坂幸太郎『マリアビートル』試し読み
https://kadobun.jp/trial/mariabeetle/128f8x1jgvv4.html