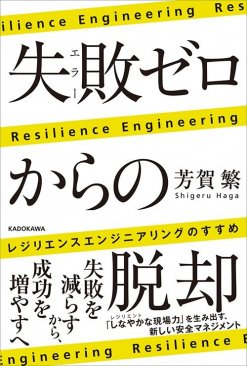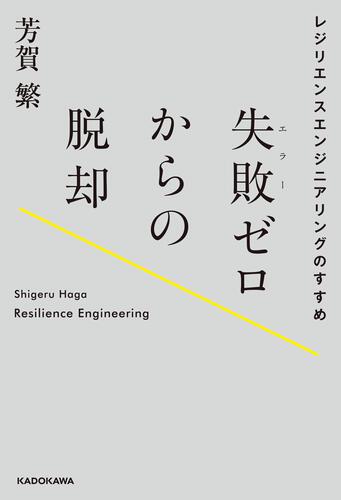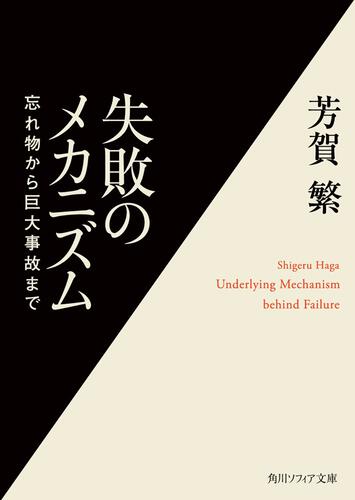労働災害・交通事故・医療事故など、ヒューマンエラーの最前線を研究し続けてきたからこそ見えてきた、「事故ゼロ」「失敗ゼロ」を目指す安全対策の弊害と限界とは。『失敗ゼロからの脱却』著者の芳賀繁先生にお話を伺いました。
事故原因は「不注意」、安全対策は「注意喚起」!?
――芳賀先生は、ヒューマンエラー、ヒューマンファクター研究の第一線で長く活躍されてきました。つまり、ずっと「失敗ゼロ」を目指してきたのではなかったのでしょうか?
芳賀:私は1977年(昭和52)に国鉄(日本国有鉄道、現・JR)に就職したのですが、当時は国鉄だけで毎年100人以上の人が労働災害で死亡していました。全産業では3千人くらい。交通事故で死ぬ人は1万人近く。世界に目を向けると大型ジェット旅客機はあちこちで落ちるし、化学プラントでの爆発や有毒物質の漏洩も後を絶ちませんでした。
――それほど多かったのですか。
芳賀:そんななか、社会や産業界ではヒューマンエラーやヒューマンファクターズに対する関心が高まっていきました。大学で認知心理学を勉強して国鉄の研究所(鉄道労働科学研究所)に就職した私は、注意やヒューマンエラーの研究で事故防止に貢献したいと考えたのです。
鉄道でも、信号を見間違えて事故が起きたり、停まるべき駅を通過してしまったりするトラブルがちょくちょく起きていました。当時はヒューマンエラーで事故が起きると、原因は「不注意」、「漫然作業」、対策は「注意喚起」「確認の励行」などと報告書に堂々と書かれていました。だからまず、ヒューマンエラーを科学的に理解して背景要因を解明すること、それに基づく効果的な対策をうつことの重要性を、多くの人に理解してもらう必要があったのです。
過剰な安全対策が現場を疲弊させる
――実際、先生のご著書『失敗のメカニズム 忘れ物から巨大事故まで』(角川ソフィア文庫)はロングセラーになっています。つまり、先生がおっしゃったような状況やヒューマンエラーに対する関心は、現在も少なからず続いているのでは、と感じます。
にもかかわらず、なぜいま『失敗ゼロからの脱却』という逆説的なタイトルの本を書こうと思われたのでしょうか?
芳賀:『失敗のメカニズム』の初版から約20年の間に、ヒューマンエラー対策はずいぶん進みました。日本の安全水準もずいぶん上がりました。そんな状況で、ぐりぐりと安全対策を進めて「事故ゼロ」を目指すだけでは、却って弊害が目立つようになったのです。
労災関係の国のある会議では「小さな事故でも報告書に必ず再発防止対策を書いてください」と安全担当者に呼びかけています。先日、ある大きな工場の安全大会に出席したのですが、工場長が1年間に起きた労災事例を紹介していました。カッターで指を切ったとか、階段で足を踏み外して捻挫したとか、そんな話ばかりです。それでも、労災をゼロにするため「みんなで頑張ろう」と檄を飛ばしていました。
結果としてどういうことが起こるか。カッターで手を切るのを防ぐ対策としてカッターナイフの使用を禁止するとか、階段で足を踏み外さないために階段昇降時に必ず手すりを持つルールを決めるとか、そういう対策が大真面目に行われるのです。現場は仕事がやりにくくて仕方がない。
――つまり、安全対策をやりすぎている、ということですね。
芳賀:ええ。小さな事故を防ぐために過剰な対策が行われ、仕事がやりにくくなっています。本来、仕事をする目的はよい製品を作ること、よいサービスを提供することです。事故を起こさないことやトラブルを起こさないことではありません。現場第一線はよい仕事をしようと頑張っているのに、失敗を避けることだけを考えている安全マネジメントが足を引っ張っている。
安全マネジメントだけではありません。経営も、教育も、行政も――日本社会はあらゆる側面で「失敗を避けること」に汲々として、しなやかさを失っていると思います。
現場の仕事は99.9パーセント以上うまくいっている
――「しなやかさ」とはどういう意味ですか?
芳賀:本書の副題を「レジリエンスエンジニアリングのすすめ」としました。レジリエンスとは「弾力性」「復元力」といった意味です。ダイナミックに変動する環境の中で果たすべき機能を維持する力、機能が損なわれたときには素早く回復する力がレジリエンスです。
システムのレジリエンスを高めるにはどうすればよいか。それを考えるのがレジリエンスエンジニアリングですが、システムがレジリエントであるためには、現場第一線もレジリエントである必要があります。現場第一線のレジリエンスを、私は「しなやかな現場力」と呼んでいるのです。
――現場では、つねに想定外の事態も起こり得ます。個人も組織もガチガチでは、対応しきれなくなりますね。
芳賀:これまで、安全はリスクの少なさや、事故の数の少なさで評価されていました。たとえて言えば、これは料理の美味しさを表現するときに「不味くない程度」を使うようなものですね(笑)。
レジリエンスエンジニアリングでは、安全を「うまくいくことが可能な限り多いこと」と定義します。この新しい安全の定義が、本書のなかで述べている「セーフティII」という概念です(本書59P以降)。
――なるほど! 「事故が半減して安全になった」と言うのは「不味さが半減して料理が美味しくなった」と言っているに等しいとすれば、かなり違和感がありますね。
芳賀:安全管理者は失敗ばかり調べています。そして、安全マネジメントは事故や事故のもとになるエラーの数を減らすことを目標にしています。でも、現場の仕事は99.9パーセント以上うまくいっています。
どのようにして現場はうまくやっているのか、よく見て、そこからもっと学ぶべきです。そうすれば、現場第一線が変化する状況に柔軟に対応して成功を続けていることが分かるでしょう。そして、それをもっと続けもっと増やすにはどうすればよいかも見えてくるはずです。
3.11で気づいたプロフェッショナルたちの仕事
――ところで、先生が最初にレジリエンスエンジニアリングと出会ったとき、どんな印象を持たれたのですか?
芳賀:初めて聞いたときは、従来のヒューマンファクターズの考えとあまりに違うので戸惑いました。
――そうでしょうね。ずっと「失敗ゼロ」を目指してきたわけですから(笑)。
芳賀:これまで、エラーは結果であり、システムの設計を改善することで人のエラーを減らし、人がエラーをしても事故が起きないシステムを作るべきだと言い続けてきました。それなのに、人の柔軟性がシステムを守っている、システムの機能を維持するためには人や組織の力を付けなければならないなんて、古い考えのように思えたんです。「しなやかな現場力」などという言葉を当時の私が聞いたら、「そんな精神論ではダメです」と一喝したでしょう。
――何か転機になる出来事があったのでしょうか?
芳賀:じつは、2011年3月11日に東日本大震災を経験して考えが変わりました。私は東京の池袋で地震に遭遇し、おなじ池袋にある勤め先の大学に戻って一夜を明かしたあと、電車が動き始めるのを待って駅に向かいました。運転本数が極めて少なかったので、大変な混雑だったし時間もかかりましたが、迂回ルートを経由してとにかく帰宅し、家族の無事を確認することができました。
その後も東京では計画停電があったり、福島原発の状況も不安定だったりして大変な状況でしたが、首都圏の鉄道は運転本数を減らして走り続けていました。あとで聞いた話ですが、担当者は毎日の列車ダイヤを編成する作業で、徹夜続きだったそうです。震災から数日間、あるいは数週間、あるいは数ヶ月間、日本の様々な会社や役所で、その道のプロフェッショナルたちが、彼らが担っているシステムの機能を回復させようと、あるいは可能な限り高い水準で維持しようと努力していたのです。
――余震も頻繁でした。また何が起こるかわからない不安が続くなか、たしかに首都圏のインフラやライフラインは保たれていたように思います。
芳賀:そうです。それに気づいた私は、エラーを防ぐこと、失敗から学ぶことばかり強調していたことを反省しました。
電車を走らせなければ事故は起きません。地震の翌朝に無理をして電車を走らせなくてもよかったのです。駅は人であふれていて、電車を走らせると人身事故が起きるかも知れない。線路か路盤のどこかが痛んでいるかも知れない。強い余震が来るかも知れない。つまり「安全」だけを考えれば、復旧はもっと遅くてもよかったのです。
それでも鉄道会社の社員たちは、一刻も早く都心に残った人たちを帰宅させようと頑張ってくれました。そしてもちろん鉄道だけでなく、同じように頑張った人たちは、空港、道路、海運、警察、病院、薬局、福祉施設、工場、店舗、役所、学校など、ありとあらゆる業種に存在したのです。
レジリエンスエンジニアリングは、このようなプロフェッショナルの誇りとやりがいを支え、想定内でも想定外でも変化する状況に対応してシステムの機能を高い水準に維持するのに貢献する、新しいマネジメントのパラダイムだと確信しました。以来、レジリエンスエンジニアリングの研究と、企業や学会での紹介に取り組んできたのです。
コロナ禍に求められる「しなやかな現場力」
――新型コロナウイルスの脅威が続いています。一方で「自粛」「延期」「回避」等が長引くほど、実生活や社会経済が立ち行かなくなるというアンビバレントな問題に直面しています。
コロナ禍の現在こそ、まさにレジリエンスエンジニアリングの発想が求められているのではないでしょうか。
芳賀:感染対策のため、今までとは全く違った仕事のやり方、働き方が突然あらゆるところで必要になりました。
緊急事態宣言の解除後、あるニュース番組を見ていたら、「早くガイドラインを決めてくれないと店を開けられない」と取材に答えている方がいました。一方では自分で対策を考え、政府や自治体のガイドラインを待たずに店を開けた方もたくさんいました。
――政府や自治体の対応自体も、遅々として一律には進みませんでしたね。
芳賀:1人10万円の特別定額給付金を私がやっと受け取ったのも、7月中旬でした。
でも北海道東川町は、国会での補正予算成立を待たず、早くも4月30日午前に、申請のあった一部町民に対し金融機関を通じて10万円の先払いを実施しました。後日、国の特別定額給付金を充てる形で町が本人に代わって返済したのだそうです。人口の多い町では手続きに時間がかかっているところが多いのですが、人口74万人の練馬区では、6月末までに85パーセントが支給されたそうです。先手先手を打って準備を進め、担当職員を柔軟に配置して対応したのが功を奏したらしいのです。
――先生が「あとがき」で挙げられていた「人知れず任務に励む人たち」という言葉を思い出します。一人ひとりが発揮するプロフェッショナリズムこそが、仕事に対する責任と誇りを生み、実社会を支えていくのですね。
芳賀:一つの会社の中でも、あらゆる部門で新しい方法を模索しなくてはならないとき、いちいち会議を開き、部長や社長がそれを決裁して、などとしていたらキリがない。
求められるのは、現場第一線、それは個人であったり、作業グループであったり、一つの課や部だったり、支店だったりするのでしょうが、そういう末端組織で、できること、やるべきことを考えて実行していく――これからの社会には、まさに本書で述べた「しなやかな現場力」が必要なのです。
本書の最後(第7章)に、現場第一のレジリエンスを高める教育・研修・経営施策の実践を紹介しています。ぜひ、ご覧下さい。
▼芳賀繁『失敗ゼロからの脱却 レジリエンスエンジニアリングのすすめ』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321811001066/
>>ヒューマンエラー研究の第一人者が、行き詰まりを迎えつつある安全対策に警鐘を鳴らす『失敗ゼロからの脱却』を試し読み!