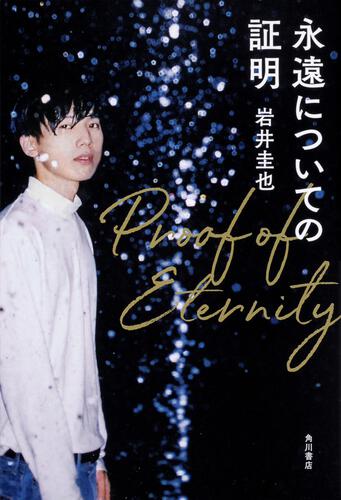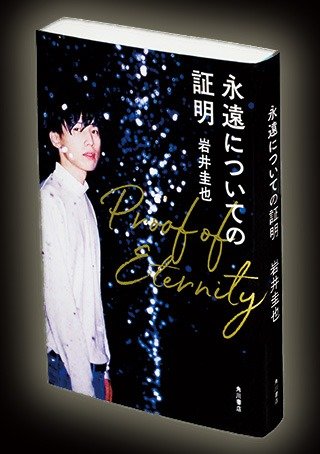冲方丁さん、辻村深月さん、森見登美彦さんの三人の選考委員が絶賛し、圧倒的な高評価で野性時代フロンティア文学賞を受賞した『永遠についての証明』。選評の公開に続き、冒頭部分の試し読みを2日連続で実施します!
すぐには信じてもらえないだろうが、しかたない。
熊沢勇一は話をどう切り出すべきか迷っていた。にわかには信じられない話だ。妄想と一蹴されてもおかしくない。説得するには、心情に訴えかけるしかなかった。
中庭に面した壁は一面ガラス張りで、赤く咲き乱れるツツジが見えた。残りの三方は純白の壁に囲まれている。無菌室。そんな言葉が似合う部屋だった。
「国数研はきれいでうらやましいですよ」
熊沢がつぶやくと、テーブルをはさんで向かいに座る小沼は穏やかな表情で前髪をかき上げた。いつもの癖だ。
小沼とは昨年の年会で会って以来だ。この数年で白髪の割合が急に増し頰の肉もこけ落ちた。五十代もなかばに差しかかり、老いの輪郭がはっきりと見えている。それでも貧相にならず、むしろ品性を備えているように見えるのが、熊沢にはずるく思えた。
「最近、改築したからね。前はびっくりするほど古い建屋だったけど。ここ何年か行ってないけど、理学部棟は今でもあのまま?」
「壁なんかもう、元が何色だったのかわからなくなってます」
「私立大学であそこまで建物が古いのもめずらしいよねえ」
穏やかな顔つきとは裏腹に、瞳に宿った切迫感は隠しきれない。明らかに小沼は焦れていた。
「クマと会うのも久しぶりだから色々話したいけど、こっちもそんなに時間はない。まさか准教授の就任挨拶のためだけに来たわけじゃないんだろう?」
小沼は数学の才能だけでなく、人間を見抜く目にも長けていた。研究者として優秀なだけでは国数研のフェローは務まらない。それでなくとも熊沢は小沼の教え子だ。考えていることなど、おおかた見破られている。熊沢は腹を決めた。
「先日、部屋を整理していたら変わったものが出てきまして」
「埋蔵金でも出てきたかな」
ある意味では埋蔵金に違いない。もしくはガラクタかもしれないが。
「瞭司の……三ツ矢瞭司の研究ノートです」
小沼はわずかに顔をしかめた。六年も前に亡くなった教え子の名だ。不審に思うのは当然だろう。しかし、すぐに平静に戻って話をうながした。
「研究室に置いていったのか」
「いえ。個人的に家族から譲り受けたものです。帰国やら移動やらでバタバタしていて、目を通せなかったんですが」
それにしても六年は長すぎる。熊沢は自分の言い訳に恥じ入った。
「それで?」
「そのノートがこれです」
熊沢は紙袋から分厚い大学ノートを取り出した。三百ページ以上に及ぶ冊子は、ちょっとした辞典ほどの重量がある。無地の表紙には茶色い染みや折れ曲がった跡があり、長年使われていたことがうかがえる。熊沢が表紙を開くと、記号と英単語でびっしりと埋めつくされたページが現れた。癖のある右上がりの字体。余白にまでメモや走り書きがあふれ、手垢やインクでところどころ汚れている。
小沼は手渡されたノートを幾度かめくっただけで閉じてしまった。急速に興味を失ったらしい。悲しげに首を振る。
「申し訳ないが、私には意味がわからない。彼の晩年については、熊沢君もよく知ってるだろう」
瞭司の晩年。熊沢にとっては思い出すのもつらい。変わり果てた彼の姿が痛ましいからというより、自分の言動を後悔するからだ。しかしこのノートを見つけたことで、当時の記憶は嫌でもよみがえる。
「元はといえば私が推薦したせいだからね。悪いことをしたと思っている」
「そんなことを話したいんじゃありません。ここを見てください」
熊沢はあらかじめ付箋を貼っておいたページを広げ、文頭を指さした。
〈以下にコラッツ予想の肯定的証明を示す〉
小沼は身を乗り出し、食い入るようにノートを見つめた。そこに記述された記号は、ほとんどが現代数学に存在しないものだった。未知の言語で記されたノートをたっぷりと凝視し、やがて小沼は顔を上げた。
「本当か」落ち着きを失った小沼は泡を食って詰め寄った。今度は熊沢が首を振る。
「残念ですが、私にもここに書いてある証明の意味は理解できません」
熊沢はこの一文を最初に読んだ瞬間を、鮮明に記憶している。部屋の整理中に発見したノートを開くと、最初に飛びこんできたのがその一文だった。証明の意味がわからないにもかかわらず、それが誤りではないと直感した。
瞭司にコラッツ予想の証明をみせられるのは二度目だった。あの薄暗いマンガ喫茶で手渡された証明とはまったく違う。今度こそ成功したのだ。十七年の時を隔てて。
コラッツ予想は名高い未解決問題のひとつである。一九三〇年代にドイツの数学者コラッツが提示した問題で、数学を研究したことのある者なら誰もが耳にしたことがある難問。問題そのものは子供でも理解できるほど平易だが、いまだ証明の手がかりすら見いだされていない。
――数学はまだこの種の問題に対する準備ができていない。
そう言ったのは二〇世紀の伝説的数学者、ポール・エルデシュだった。破格の数学者にそう思わせるほど、この問いの壁は高い。
小沼は躊躇しつつ、勢いを失った声でつぶやいた。
「瞭司を疑うわけじゃないが、その証明は……その、正しいんだろうか」
熊沢はそれには答えず、ふたたびノートを開いた。
「コラッツ予想の証明にたどり着く前に、二百ページ以上も使って理論が構築されています。証明を理解するには、先に理論そのものを理解しなければなりません」
「つまり、理論が妄想なら、証明も妄想だということか」
小沼は眉をひそめた。落胆の色が濃い。
「たしかに、彼は長いこと新しい理論に取り組んでいるようだった。たしか……」
「プルビス理論。そう呼んでいました」
口にするだけで胸が苦しくなる。
紙上に残された瞭司の筆跡を見ると、若かった日の記憶が生々しくフラッシュバックする。学生時代に住んでいたアパート。ままならない難問を相手に格闘した日々。恋人との甘く苦い記憶。それらが塊となって正面から襲いかかってくる。
瞭司を殺したのは俺だ。熊沢は奥歯を強く嚙んだ。
「小沼先生」熊沢の声に、小沼の視線が引きつけられる。
「本当に、この証明が妄想だと思いますか。瞭司が死ぬ直前まで研究していた理論が妄想だと、本気で思っているんですか」
小沼は答えを選んでいた。腕を組み、中庭を見やる。
「検討してみないことには何も言えないよ。クマはどう思う」
「証明に間違いはないと思います」
「根拠は?」
数学的な裏付けなどない。根拠と呼べるものはひとつだけだ。
「これを書いたのが、三ツ矢瞭司だからです」
小沼はこめかみの辺りを搔き、ふたたび窓の外に視線を逃がした。
この反応は予期していたが、実際に目の当たりにすると少なからずショックではあった。赤の他人ならいざ知らず、瞭司の恩師までもがこんな反応をすることが。
気まずさをとりなすように、小沼は一転して明るい口調で尋ねた。
「それで、これからどうするんだ」
「解読して論文にします」
「この分厚いノートをすべて?」
「数百ページならどうにかなります」
不安はあるが、熊沢は本気だった。それが瞭司に対する責任であり、せめてもの償いだと確信していた。
「気持ちはわかる。本当にコラッツ予想の証明に成功しているなら、とてつもないビッグニュースだ。世界中がひっくり返る。だが、そんなことが本当に……」
「先生もご存じでしょう。瞭司は並の数学者じゃありません。証明は正しいはずです」
これまでに、熊沢はおびただしい数の天才たちと会ってきた。アメリカ時代には目がくらむような才能たちと交流し、帰国してからも日本が誇る頭脳と呼ばれる人々と出会った。それでも、瞭司以上に〈数覚〉に恵まれ、明確に数の世界を見ることができた人間はいない。いつかマスメディアが名付けた〈二十一世紀のガロア〉というレッテルは、決して過剰な誉め言葉ではなかった。
瞭司は普通の天才とは違う。数理の子とでも呼ぶべき存在だった。
熊沢にも、一流の数学者だという自負はあった。恩師のおかげとはいえ、三十代なかばという早さで准教授に就任し、数論幾何の分野では若手の筆頭格と称されている。それでも、不世出の天才が作り上げた理論にたったひとりで挑むのは怖かった。
「小沼先生にも協力していただきたいんです。私ひとりでは太刀打ちできないかもしれない。先生の力を貸してください」
小沼の視線は室内をさまよっている。演技ではなく、本当に迷っているようだった。熊沢はひたすら返答を待った。小沼は戸惑いを隠さなかった。
「これが現役最後の仕事になるかもしれないと思うと、さすがに躊躇するな」
熊沢が出会った時には若き教授だった小沼も、すでに還暦が見えている。この年齢で論文を量産する鉄人ですら、老化には抗えない。それは数学者にとって永遠に克服することのできない敵だった。
愛着のあるテーマを脇に置いて、得体の知れない新理論を研究しろと迫るのは、熊沢にとっても心苦しいことだった。小沼の岩澤理論への思い入れを知っているだけに、なおのことつらかった。
しかし頼れるのは小沼しかいない。家族にも同僚にも学生にも相談できず、この数週間、孤独に思い悩んでいたのだ。普段は思わないが、この時ばかりは妻が数学者だったらと思わずにいられなかった。
「この歳になって先生に甘えるのは申し訳ないと思っています。でも、学生や他の数学者ではきっと手に負えません。瞭司と正面から向き合いたいんです。部分的にでもいい。それだけの価値があるんです」
熊沢は椅子を引いて立ち上がった。直角に腰を折り、深々と頭を下げる。「お願いします」
その頭に小沼の声が降る。
「価値があるというのは、数学界にとって? それとも、熊沢勇一個人にとって?」
わがままに付き合わされるのはごめんだということか。耳が痛い質問だった。
「両方です」
偽りではない。プルビス理論によってコラッツ予想を証明できれば、数学の風景は一変するはずだ。もっとも、本当に理論として成立していればの話だが。小沼はまだためらっているのか、返事をしない。
「先生。本当に瞭司の死に責任を感じているのなら、協力してください」
このひと言が切り札になった。小沼は長いため息を吐いてノートの表紙を見下ろした。
「わかる箇所から読み解いていくしかないな」
「協力していただけるんですか」
「趣味として。こんな意味不明の研究じゃ、予算申請もできないし。それよりクマはどうするつもりだ。数論幾何の範疇に入るのか、このテーマが」
「解決の目処が立ち次第、大学に相談してみます。世紀の未解決問題の証明と言えば、予算も融通してくれるかも」
妙な沈黙が流れた。その解決の目処はいつ立つのか。小沼から、そう言われているような気がした。
お互い、次の予定が近づいている。ろくに世間話もできないまま、熊沢はノートのコピーを送る約束をして部屋を去ろうとした。ガラス窓を背にした小沼が、ふと思い出したように言った。
「そういえば、斎藤さんには声をかけたのか」
熊沢は動揺が表に出ないよう、慎重に答えた。
「彼女はもう数学を離れて長いですから」
触れられたくないという熊沢の気配を察したのか、小沼はもう詮索しなかった。
斎藤佐那と最後に会ったのは六年前。瞭司が亡くなった直後だった。友人の死に打ちひしがれる彼女の横顔を、不謹慎ながら、熊沢は美しいと思った。
中庭のツツジが風にそよいでいた。色濃い花が密集して咲いている光景は、目の裏に焼きつくような鮮やかさだった。
春はまだはじまったばかりだ。
四月の陽を浴びながら、三ツ矢瞭司は協和大学の正門をくぐった。茶色がかった頭髪が陽光にきらめいている。
バックパックを背負ってあたりを落ち着きなく見渡す姿は、中学生にしか見えない。童顔はコンプレックスだったが、叔母さんからは「二十年後には親に感謝するよ」と言われていた。
門を抜けてすぐの場所に、キャンパスの案内図が掲げられていた。協和大学は理系の名門として知られるだけあって、理系学部が充実している。キャンパスには医学部、薬学部、工学部、農学部の各棟が建ち並び、中央には学内でのヒエラルキーを体現するかのように、理学部棟が傲然とそびえている。
瞭司は案内図で立ち止まり、道筋を確認する。ここに来るのは昨秋の入試面接以来、二度目だった。その時も理学部棟を訪れたはずだが、道はすっかり忘れている。
入学式当日だというのに、学生たちの姿はまばらだった。それもそのはずで、この時間まだ入学式は終わっていないし、会場は学外のコンベンションセンターだった。部活やサークルの勧誘部隊も入学式の会場に集結している。瞭司はそんなことも知らず、人気のないキャンパスを歩きはじめた。
広々としたキャンパスでは、風が吹くと住宅街よりも寒く感じる。ジャンパーでも着て来ればよかった、と後悔した。地元では四月になれば誰も上着なんか着ていないが、東京は長袖のトレーナー一枚では寒い。せめて中にシャツでも着るべきだった。
関係のない工学部棟や厚生棟を行ったり来たりしながら、ようやく理学部棟にたどりついた。歴史ある建造物らしく、外壁には長年の風雨に耐えた痕跡が刻まれている。今度はここから研究室の場所を探し当てなければならない。面接で来た時はとにかくあわただしかったせいで、ほとんど記憶に残っていない。
入口の脇に警備員の詰所があり、還暦を超えているであろう警備員がいた。小沼の研究室の場所を訪ねると、口の端から息をもらしながら場所を教えてくれた。中央の階段で二階に上がり、西側に曲がってすぐの部屋。
教えられた通りに行くと、たしかに学生たちの居室らしき部屋があった。隣接する教授室には小沼の名前が書かれた札が下がっている。閉ざされたドアをノックしたが、室内からの反応はない。ノブを引いたが鍵がかかっていた。小沼は不在らしい。
仕方なく学生居室を訪ねた。ドアは開け放されていたので、すいません、と言いながら足を踏み入れた。デスクに向かって何か読んでいたふたりの男が同時に振り向く。ひとりは小柄な長髪で、もうひとりは背の高い坊主頭。顔はそろって無精ひげにまみれている。年齢は二十代にも見えるし、四十代にも見える。長髪のほうが口を開いた。
「え、誰」
人と話すのは苦手だが、侮られるのも嫌だった。
「僕、小沼先生に呼ばれてるんですけど、どこにいるか知ってますか」
変声期前の名残りがある、かすれた高い声。今度は坊主頭が言う。
「入学式じゃないの。まだ十一時だし、終わってないでしょ」
「それより、きみ誰? 新入生? 高校生? 中学生じゃないよね?」
長髪のうわずった声は、明らかに動揺していた。
「あ、新入生です」
「入学式、出なくていいの」
「親には出とけって言われたんですけど、場所がよくわからなくて。面倒だし」
「面倒って……」
絶句した長髪に代わって、坊主頭が尋ねた。「もしかして特推の新入生?」
「トクスイ?」
意味がわからないまま反復すると、教えてくれた。
「特別推薦生のこと。小沼先生、今年度の指導教官だから」
それなら聞き覚えがある。はい、と答えると、二人そろって感嘆の声をあげた。
瞭司には特別推薦生という立場が今ひとつわかっていない。ただ、小沼に勧められたから従っただけだ。
もともと大学の格になど興味はなかった。数学と英語以外で点数を取れる自信はなかったから、試験が面接だけなのは好都合だった。それに、特別推薦生は四年間の学費が全額免除される。瞭司にとってはちょっとした親孝行のつもりだった。
「特推って、実績ないと合格できないんだろ。数オリとか」
「なんですか、それ」
「数学オリンピック、知らんの」
「あ、聞いたことあります。でも僕、そういうの出たことないんです」
「じゃあ何も実績ないの」
思い当たることはあまりない。瞭司は面接で聞かれたことを思い出した。「論文の内容は
色々聞かれました」
「論文? きみが?」
「はい。ムーンシャインの別解について」
「高校生で論文書いたってこと」
「噓でしょ」
二人の先輩は目を剝いた。瞭司はあわてて手を振る。
「でもまだ受理されてないんです。もう半年も経つのに。国内の雑誌に投稿しとけばよかった、って小沼先生は言ってるけど」
論文を投稿したのは昨秋、面接の直前だった。面接官のなかにトポロジーの専門家がいて、重箱の隅を突くような質問をいくつもされたせいで疲れてしまった。
おそるおそるといった様子で、長髪が問う。「名前は?」
「えーっと。『ジャーナル・オブ・マセマティック……』」
「いや、雑誌じゃなくて。あなたの名前」
「あ、三ツ矢瞭司です。先生が来るまで待っててもいいですか」
どうぞ、と言いかけた坊主頭を長髪が制止した。
「あの空き部屋がいいんじゃない。俺たちと一緒だと気まずいでしょ。ほら、教授室の逆側に使ってない小会議室があるから。あそこ鍵かかってないし。物置きみたいになってるけど、気にしないで。先生が来たら呼ぶから」
長髪の手元をのぞくと、論文のコピーの下に派手な表紙の雑誌が隠れていた。パチンコ、の文字が見える。なるほど。新入生がいないほうがサボるには好都合というわけか。瞭司は二人に礼を言って居室を出た。
教授室をはさんで逆側の部屋には〈小会議室〉という札が下がっていて、教えられた通り施錠されていなかった。正面の壁は腰から上が窓で、残りの壁は本棚で埋まっていた。古い書籍や雑誌、卒業論文などが押しこまれている。たしかに物置きらしい。部屋の中央には円卓があり、パイプ椅子が無造作に散らかっていた。
瞭司はパイプ椅子を引き寄せ、腰をおろした。入学式はたしか十時開始だから、正午までには終わるだろう。家を出る前に菓子パンを食べたから、昼までは腹も持つ。
本棚に収められているのは、数学に関する書籍や雑誌ばかりだった。この部屋なら何日でも時間をつぶすことができそうだ。瞭司は目についた整数論のテキストを手に取り、目を通した。
退屈な公式の羅列が続く。緊張がほぐれたこともあって瞭司は眠気をもよおした。しかし別の本に移ろうとした寸前、視線がある問題に釘付けになった。
(第2回へ)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
>>岩井圭也『永遠についての証明』書誌ページへ