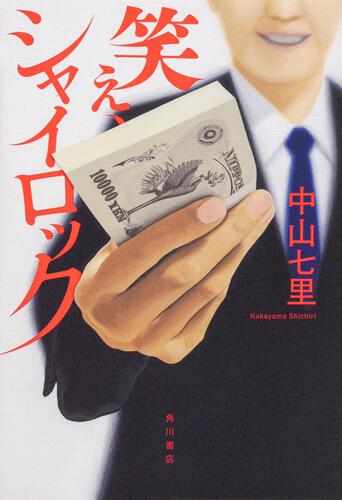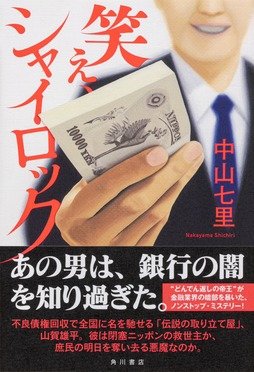本日7月12日(金)発売の「小説 野性時代 2019年8月」では、中山七里さんの新連載「ラスプーチンの庭」がスタート!
カドブンではこの新連載の試し読みを実施します。

娘の沙耶香を病院に見舞った犬養は、祐樹という少年を知る。
彼もまた、長い闘病生活を送っていた。
現代医学の限界を前に、見出した光の先は――。
「刑事犬養隼人シリーズ」待望の最新作が開幕!
一 聖痕
1
「ちょっと寄っていく」
ステアリングを握っていた犬養隼人は、インプレッサを帝都大附属病院へと向ける。勤務中だが、昼休憩の時間を見舞いに回しているという体裁なので怠業には当たらない。問題は同行している者が付き合ってくれるかどうかだが、助手席の高千穂明日香はすっかり心得た様子だった。
「どうぞ。その間、わたしはどこかでランチを摂っていますから」
了解を確認しながら、犬養は明日香の視線に気づく。
「何か言いたそうだな」
「他のことはともかく、沙耶香ちゃんの見舞いだけはマメなんだな、と思って」
明日香にしてみれば憎まれ口なのかもしれないが、犬養本人は何の痛痒も感じない。今まで家庭を顧みなかった父親としては、娘の見舞いを欠かさないのはせめてもの罪滅ぼしだった。
「高千穂も家族が病気になったことくらいあるだろう」
「ないですね」
明日香は事もなげに言う。
「両親とも健康過ぎて、わたしが物心つく頃から入院経験がありません」
「息災で何よりだ」
皮肉でも冷やかしでもなく、犬養は純粋にそう思った。病は家族の心を萎えさせ、貧しさは犯罪を呼び込む。健やかで貧しくないというのは、それだけで大きな幸福だ。
クルマを駐車場に停め、待ち合わせ時間を決めてから明日香と別れる。以前は病室の外までついてきたが、最近は放任してくれるので助かる。おそらく気を利かせてくれているのだろうが、本人に確認したことはない。
通い慣れた病棟は自分の庭のようなものだが、これとて自慢できる話ではない。素人ながら腎臓疾患に詳しくなったのも同様だ。娘が腎不全を患っていなければ、どうして刑事風情が医療知識など蓄えるものか。
沙耶香が入院してから既に数年が経過している。定期的に人工透析を受けなくてはならず、極端な体力の低下が理由で通常の学生生活は望めなくなった。通常なら高校受験に向けて補習受講なり塾通いなりに勤しむ時期だが、沙耶香にはそれも許されない。
娘がどんな進路を考えているのか。父親なら本人に訊くべきことなのだろうが、己の不義を理由に別居していた手前、父親面することに抵抗がある。煩わしい相談は別れた女房に丸投げしたいという卑怯な計算も働いている。不甲斐ない父親にできるのは、こうして定期的に娘の機嫌を伺うことくらいだ。時折自己嫌悪に陥るが、世の父親たちも多かれ少なかれ子供の進路は母親任せらしいという噂で自分を安心させる。
沙耶香の病室の前まで来ると、中から話し声が洩れてきた。主治医か看護師と喋っているのかと思ったが、洩れ聞こえる内容からするとどうもそうではないらしい。
『だからさ、y=ax²の場合、aは比例定数なんだよ。aが3と分かっているんだったらxの値-2を代入してyを求める。y=3×(-2)²で12。じゃあ次の問題はどうすればいい?』
『y=ax²にxとyの値を代入して比例定数を求める』
『オッケー。何だ沙耶香ちゃん、あっさり解いたじゃんか』
『説明、分かりやすくて。ひょっとして家庭教師でもやってたの』
『中学三年で誰の家庭教師するっていうのさ』
『でも、向いてそう』
ドア越しでも和気藹々とした雰囲気が伝わってくるので、部屋に入るのが躊躇われる。それでも回れ右で引き返すのは沽券にかかわるような気がして、ドアノブを回した。
「俺だ。入るぞ」
洩れ聞こえた声で承知していたが、病室は沙耶香と祐樹の二人だけだった。
「お父さん」
「あ……お邪魔してます」
「こちらこそ悪かったね。勉強中だったみたいで」
和気藹々が一瞬にして気まずくなるが、これはもう仕方がないだろう。祐樹も慌てているようだが、不意に現れた犬養に驚いただけで別に咎められる理由はない。その証拠に、ベッドの上には数学の教科書とノートが広げられている。
庄野祐樹は沙耶香と同じフロアに入院している少年だ。以前から沙耶香とは顔見知りだったが、数学が得意だったので院内教師を買って出たらしい。病人には不似合いな小太り体型で、眼差しが優しい。慢性糸球体腎炎という原因不明の難病で、沙耶香と同じく長期入院を強いられている。感心なのは長患いであるのをいささかも感じさせない態度で、いじけたり拗ねたりといった素振りを見せたことがないらしい。医師や看護師からの評判もよく、沙耶香の友人としては申し分ない。その上、家庭教師代わりにもなってくれるので父親としては喜ばしい限りのはずなのだが、犬養はどうにも面白くない。
「いつも沙耶香が迷惑をかけて申し訳ないね」
社交辞令を口にする時は、自分が父親であることを自覚できる。我ながら卑屈だと思うが、元より父親らしいことをした覚えがないので致し方ない。
「人に教えると、自分でも理解できた気がするんで……」
祐樹は少しはにかんで言う。真っ直ぐこちらの顔を見ようとしないのは生来気が小さいのか、それとも犬養を怖れているのか。
「人に何かを教えられるというのは才能だと思うよ。祐樹くんは、その、将来の夢とかあるのかい」
「お父さん」
沙耶香が呆れたような声を上げた。
「もうちょっと気の利いた質問できないの。わたしたち、まだ中学生」
中学生でも将来の希望くらいはあるだろうと言いかけて、やめた。沙耶香の抗議には、二人とも闘病の身という事実が言外に含まれている。碌に登校もできない者に将来を語らせるなという訳だ。夢を持つのも語るのも、それが許される土壌があっての物種で、可能性の低い人間に強いるのはかたちを変えた虐待でしかない。
「ああ、うん。悪かった。どうも若い人とは喋り慣れてなくてね」
「刑事だったら、不良学生とかも相手にしてるんじゃなかったの」
「中学生相手だったら生活安全部に少年事件課とか少年育成課とかがあって」
「あーっ、もううるさいっ」
沙耶香は強引に犬養の言葉を遮る。
「お父さんってホントに骨の髄まで刑事なんだから」
「そう言うな。これでも昔は俳優養成所に通っていたんだ」
「それ聞き飽きたって。折角俳優目指していたのなら、どうしてそっち方向に頑張ってくれなかったのよ。もし俳優になってくれてたら、今頃この病室はアイドルとか仲間のイケメン俳優とかの見舞客で一杯だったかもしれないのに」
へえ、と意外そうな顔で祐樹が沙耶香を見た。
「沙耶香ちゃんのお父さんって、そうだったんだ」
「うん。過去形なのがすっごく辛い。やっぱり刑事より俳優だよ。誰が何と言おうと」
「そうかな。僕は刑事の方がカッコいいと思うけど」
祐樹は遠慮がちに応える。犬養に対するおべっかでないのは口調から分かる。犬養にしても中学生に持ち上げられても、あまりいい気はしない。
「えー、どーして。あのさ、自分の親だから言う訳じゃないけど、刑事って地味だし、いつも殺伐としてるし、おまけに危険と隣り合わせだし」
「危険と隣り合わせだからカッコいいんじゃん。それに犯人を逮捕するなんて一般市民じゃできないんだぜ」
祐樹の言うのは正確ではない。一般市民でも犯罪者を逮捕できるのだが、機会と制圧力に恵まれないだけだ。しかし折角、刑事という職業を買ってくれているのだから、注釈を差し挟むまでもないだろう。
「祐樹くんは刑事に興味があるのか。もしよければ」
「お父さん、はっきり言って邪魔。出てって」
「今きたばかりだぞ」
「関数問題ができない人は帰って」
犬養はひと言も返せない。情けないが、今の犬養が教えられるとすれば男の嘘の見分け方くらいだ。
「まだ三ページも残ってるんだから。少なくともお父さん、数学の勉強では何の役にも立たないどころか、いるだけで目障り」
いつもより五割増しの舌鋒は祐樹がいるのも手伝っての照れ隠しなのだろうと思った。そうでなければ犬養もやっていられない。
「またくる」
そう言って病室を出るのが精一杯だった。
▶▶このつづきは、「小説 野性時代 第189号 2019年8月号」でお楽しみください。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。