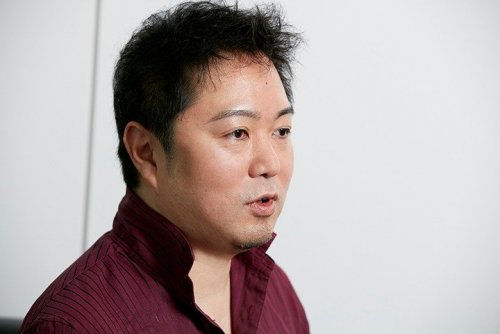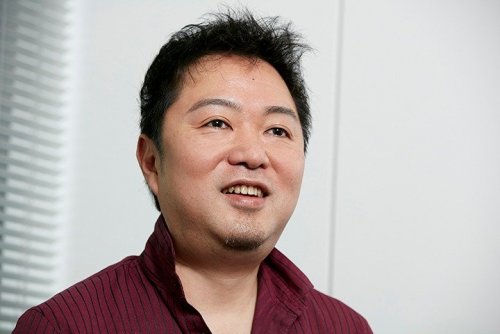第二次世界大戦の米軍の沖縄上陸作戦ですべてを失った一人の女性。
南米に移り、激動の時代を生き抜いたその波瀾の生涯を、当代きっての奇才が描ききる!
なぜ、ボリビアなのか?
――四年ぶりの新作『ヒストリア』は、第二次世界大戦の沖縄戦ですべての家族を失った少女、
池上:発端は僕が二十七歳の時、帰省中に、NHK沖縄放送局制作の情報番組をたまたま見たんです。
子どもたちが三線を弾いていて、どこか離島の学校かな、と見るともなしに見ていたら、インタビューに応えて喋る子どもたちの言葉が、古い沖縄の、祖父やその上の世代が喋っていたきれいな首里方言で。「えっ?」と思って。集中しようと意識を向けると「以上ボリビアからでした」と終わってしまった。
「いまのがボリビアかあ」と頭に刷り込まれて。僕らの世代が聞くことはできるけど、喋ることはできない言葉を喋る子どもたち。ウチナーグチの舌下音も声調も完璧で、これはどういうことなんだろう、もっと知りたいなと思ったんですよ。ボリビア移民について詳しく知っていそうな研究者に聞きに行くと、いい反応をしてもらえない。はっきりとは言わないんだけど「やめとけ」「彼らのことはそっとしておいてやれ」ってニュアンスです。
そうなるとさらに知りたくなるじゃないですか。自分なりに調べていくと、戦後の沖縄で、多くのボリビア移民が海を渡っていた。まるでパラダイスに行くかのように移民を勧める、移民局の資料も残っていました。
沖縄では、ブラジルとかハワイに移民した親戚がいるのは割と普通のことです。けれど、戦後の、基地をつくるために農地の強制収用とセットで行われたボリビア移民のことは、忘れた、もしくはなかったことのようにされていた。当時の沖縄の論調というのは、自分たちは真っ白な被害者なんですよ。生きるうえで加害に与した部分もあるのに、そういう歴史は隠蔽してしまっている。そういう複雑な感情が、ボリビア移民に対してはあるんだと思う。
作家になった当初の僕は、表層の沖縄しかとらえることができなかった。アメリカナイズされたものと伝統文化がまじった、キッチュな沖縄。そういう作品を書いていくうちに、意識がどんどん歴史の古層に入っていって、琉球王朝(注『テンペスト』)みたいなところまで一回、行くんです。でも、それは言ってみれば自分たちの誇りになる表の歴史であって、自分たちが見過ごしてきたもの、無視してきたものも含めて歴史で、そちらも書かないとバランスがおかしいという気持ちになったんですね。
ただ、書きたい気持ちはありつつ、軽い気持ちで書けるものではない。スペイン語もできないし、そもそもボリビアってどこにあるの? というレベルで、まあいつか書くんだろうな、と思っていました。それに、ボリビアを書きたいというのは各社の編集者にも言ってきたけど、「やりましょう」と言ってくれる人は誰もいなかった(笑)。
――いなかったんですか。
池上:やっぱりそれは、売れ線を書かせたいとかいろいろあるんじゃない? ボリビアをやりたいというと否定的な反応をされることに慣れてしまって、じゃあ、ますますやろう、って気になりました。手に入る資料はすべて集めました。
中南米の移民の中で、ボリビアだけが日本的なアイデンティティーを死守しているんですよ。ブラジルもペルーもアルゼンチンもチリも、すべて同化の道を選んで日本語を捨てているんだけど、ボリビアは違っていた。コロニア・オキナワでは、第一言語を日本語にして、スペイン語は中学を卒業してから学び始めるんです。
行ってみてわかる、南米に対する誤解
――ボリビアにも行かれたそうですが、どんな印象でしたか。
池上:現地を見ないうちはいろんな誤解をしていて、アンデス山脈だから、山の斜面にある道を横ばいになって進むんだろうか、とか(笑)。実際に行ってみると、想像とぜーんぶ違っていて、見渡す限りの大平原です。「めんそ~れ オキナワへ」という看板を見てから、車で時速百二十キロで十分ぐらい走ってもどこにも着かない。「さっき見た看板は幻なの?」って。
コロニア・オキナワだけで東京二十三区ぐらいの広さがあって、九十九%が耕作地です。表記は日本語だし、日本を彷彿させるものもいっぱいあって、鳥居の奥に教会があったりする。ネガティブな情報をいっぱい聞かされていたけど、悲惨な暮らしどころではなく、いわゆる富豪も誕生していました。私立の日ボ学校(注・日系の学校)は近代建築の校舎で、バスケットボールコートと体育館があって、一方で現地の学校はひどい有様で、ものすごい経済格差を目にしました。華僑ならぬ、日僑。マイノリティーというよりスーパーパワーだから、スペイン語を習得しなくてもやっていけるぐらいの存在感があります。 南米というと政情不安の国が多いイメージで、常に内戦が起きたりゲリラがいたり、って思ってたんです。行ってみると、これも様子が違っていて、きわめて小さな部族の社会がいっぱいあり、国家というのは一応あるけどそんなものは誰も信用していない。自分たちのコミュニティを壊そうとする動きがあると彼らは蜂起するんですよ。警察より自警団のほうに信用がおけたりする。ボリビアという国全体をとらえたくて、包括するイメージを探ろうとすると、逃げ水のようにどんどん逃げていく感じでした。
――事前に抱いていたイメージと違うボリビアを目の当たりにしたことは、小説の構想に影響しましたか。
池上:絵を描くときに、初めにキャンバスに十字を描くじゃないですか。この十字がズレてるって気づいて、何度も何度も描き直すようなことはしましたね。どこが中心かわからない感じです。それに、ボリビアの日系の人たちは、部外者に歴史の裏の部分を話したがらない。気持ちはわかるけど、それではこの小説が単なる辺境の郷土史になってしまう。
「ボリビアってどういう所なんだろう」と最初に思った二十七歳のときに書き始めていたら、たぶん『
自分の中にずっと抱えてきた違和感というのがあるんです。もちろん、戦争反対というのは前提です。だけど反戦のスタイルっていうのは戦後ずっと更新されず、陳腐化しているとも思っている。じゃあ、あなたは何を提示するのよ、って聞かれると答えに窮するんです。
そういうときに、戦災孤児で移民せざるをえなかった女性の目を借りて、彼女の目から沖縄をもう一回のぞいたら、「何も変わっていない」ことが描けるんじゃないかと思った。表層的には復帰後、本土化がうまくいって、ある程度豊かにもなった。政治も、ファッションも変わったけれど戦争は終わっていない、ということを。
タイトルに込めた思い
――『ヒストリア』――歴史というのは壮大な構えのタイトルです。
池上:最初は『コロニア』というのを考えていたんです。実際、そうなるはずだったんだけど、ボリビア移民の人たちが開墾に苦闘する姿を書きつつ、当時の世界情勢、キューバ危機も含めた国際政治のダイナミックな動きを背景に置くことで、周囲と隔絶された移民の姿も立体的に浮かび上がるんじゃないかと思い、このタイトルにしました。
――屍体の衣を剥いだり、青年将校をだまして背嚢を奪ったり、知花煉はいわゆるヒロインぽくないキャラクターとして描かれています。
池上:沖縄に「ミヤラビ」って言葉があって、そこには処女性みたいなことも含まれているんです。それに対して、知花煉はビッチですよ!(笑) こすっからくて男も利用する。ミヤラビだけじゃない、ビッチな女の子にも弾が飛んでくるのが戦争なんです。
一片たりとも染みがないように生きるなんて、そんなのは死後の世界で十分と思うから、僕はダーティーな部分を持っている人を描きたい。生きるってそういうことだから。ただし、できるだけ憎めない感じにしたかった。バカかこいつ、って思われるほど、着飾ったり化粧したりね。読者が「知花煉、何しとんねん!」と思いながらも、読むのが止まらないような、リーダビリティーのためのしかけはいっぱい入れました。戦争をテーマにするなら、面白くなくてもいい、ってなったら創作を放棄してるでしょ。
煉って、負けのほうが多いんです。よく読むと、十回のうち、三回ぐらいしか勝ってない。負け越しても立ち上がる。自分より明らかに強い相手にも一矢報いようとする。そのためにさらに痛い目に遭ったりもするんだけど。煉のああいうところは理想です。「いい女だよ」って思う。
――知花煉はモデルとなる人物がいるんですか。ああいうタイプの女性は沖縄によくいるんでしょうか。
池上:いません。沖縄の人は、もっとおっとり、のんびりしているタイプが多くて、ぼくみたいに闘争心の激しい人間は例外です。
『ヒストリア』を書き始めてすぐ、圧倒的に足りない、と気づくんですよ。もちろん書く前は、資料にしろ現地取材にしろ、できる限りのことをしましたけど、でも足りない。だけど途中でやめるわけにいかない、なんとかこの作品をものにしたいと闘争心が出てくる。足りないのは百も承知。だけど限られた時間で、少しでも勝ち越したい。連載中は、どこに物語のポイントがあるのか、目隠しされてさまよっている感じでした。
――ということは、煉の闘争心には、小説を書くときの池上さん自身の気持ちが投影されているということですね。煉がマブイ(魂)を落とす、というのも、この小説の核であり、小説を動かしていきます。マブイ落ちというのは池上さんの他の小説の題材にもなっていますが、これは沖縄独特のものですよね。
池上:僕、何回も落としたことあるんだけど……。不思議に思われるかもしれないけど、「この前あんた石垣島いたってね」って言われたり、いないはずの場所に「見たってよ」って言われたりする経験はこれまでに七、八回はあります。自分が規定する自分、っているじゃないですか。それと同じぐらい、他者が規定する自分というのもあって、それは自身が規定する私とは全然違う。だから、他者が規定する私が存在する可能性はあるんですよ。
似たようなこと、「魂は分離する」「生きているうちに分かれる」ということを、インディオの人も言っているんです。古代インカってやたらと生贄による祭祀が多くて怖いけど、生と死の境界があいまいというか、連続線上にあるような感じなんじゃないかな。キリスト教が入ってきてからはだいぶ変わっただろうけど、それまでは、生と死も、昼と夜みたいに一日のうちに同時に起きうるもの、ぐらいの認識だったんじゃないかと。このあたりはもっと詳しく彼らに聞いてみないとわからないけど。
チェ・ゲバラは本当に英雄か?
――煉の恋の相手として、本の表紙にも肖像が使われているチェ・ゲバラも登場します。
池上:たとえていえば、『ヒストリア』という小説の主旋律はマイナーなんですよ。けれど、伴奏はメジャーにしないといけないと思うから、できるだけメジャーコードになる音を探す。ゲバラもそのひとつです。 ただ、あれほど拍子抜けする人もいないと僕は思っていて。
――え? どういうことでしょう。
池上:ゲバラは、ジミ・ヘンドリックスみたいなもので、イケメンで、ナイーヴで、医者のエリートで、若くして死んだっていうのが広く喧伝されちゃってるでしょう。
ボリビア取材では、ゲバラが殺害されたイゲラ村まで、はるばるアンデス山脈の峠を越えて行ったんです。視界が十メートルぐらいしかない険しい山道を車で八時間ぐらいかけて登って、這う這うの体でたどりついた瞬間、膝カックンされた気持ちになりましたよ。高校生が文化祭でつくったような胸像があってそれで終わり。ここが簡易裁判が行われた教室です、って木の椅子を見せられて。もう立ち上がれないかと思いましたよ。芳名帳を見ると、日本やブラジル、アルゼンチン、アメリカ、ヨーロッパ、キューバの人も来ていたけど、ボリビアの人は一人もいない。
遺体が運ばれたというバジェ・グランデまで戻って博物館も見たけど、写真がいくつかあって、五、六メートル進むと旧石器時代の土器や鏃に替わるんです。空前絶後の粗末さ。それでも何かつかめないかと、そのへんにいたおばあさんに拙いスペイン語で「ゲバラ知ってる?」って話しかけたら、ものすごい警戒心で、「あん?」ってガン飛ばされて(笑)。これは自分の持っているヒーローのイメージを捨てないとゲバラの実像を正しく理解できないな、と悟りました。
もしボリビアに行ってなかったら、日本人が大好きな、カッコいいゲバラのイメージでこの小説を書いた気がします。行く前は、ゲバラを出すからにはゲバラに負けない魅力的な主人公を書かないと、と思ったの。だってゲバラが出た瞬間に全部ひっさらっていくから。ゲバラが登場する第四章までに、何とか知花煉を魅力的にするべく、着飾らせたりいろいろしたら、結果、「知花煉、勝ったわ」。真実のゲバラで十分、と思った。
いろんな資料を読んだんですけど、知れば知るほど、ゲバラの言ってることは理解できない。要するにやんちゃしたいだけじゃないかと。カストロは必死でキューバのことを考えているけど、ゲバラがキューバ人を愛していたとは思えない。ボリビアも愛してない。愛してないから、ボリビア人からも愛されてない。そういう前提で読み直すと、すごく筋が通るんです。
――結末は意外で、衝撃的でもあります。
池上:二〇一五年までを書くつもりだったけど、書きながら、ここで終わればいい、とわかった。だってこれ以降、何も更新されていないんだから。いまこの小説を読む人に「ハッ」としてもらいたい。言葉によるショックを与えるつもりで書きました。