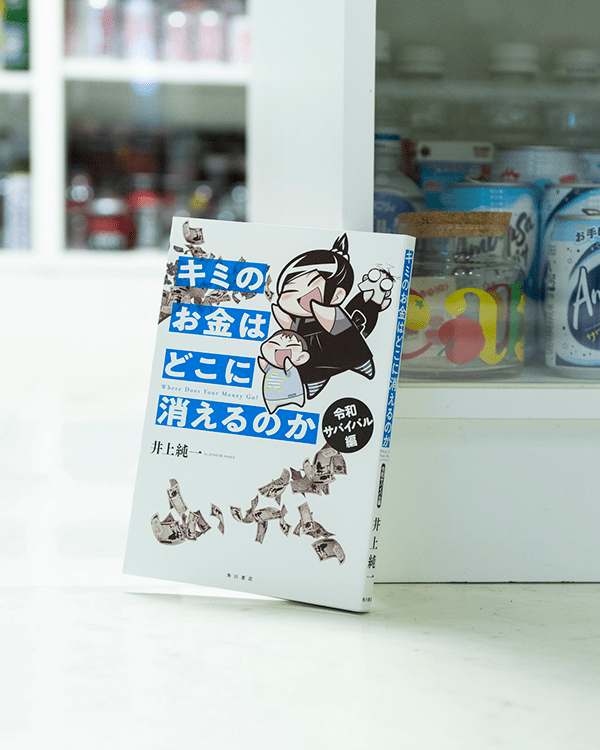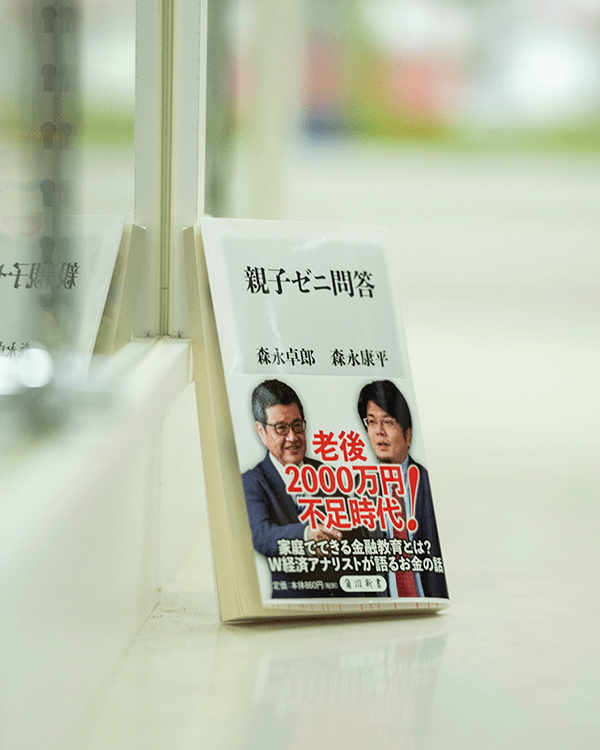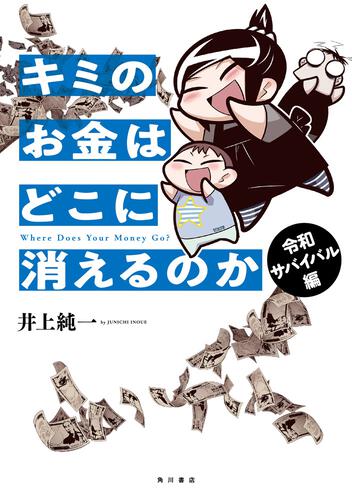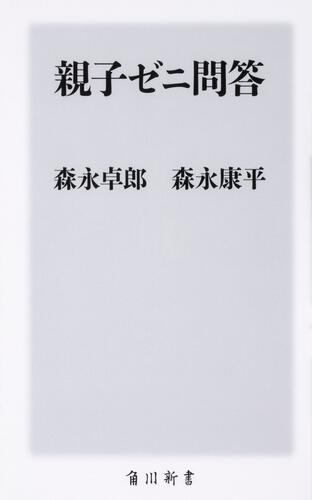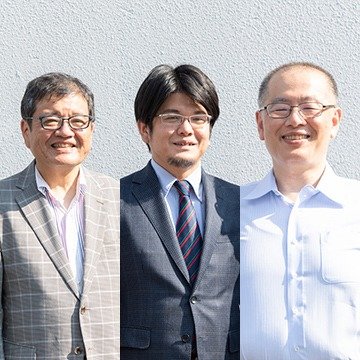緊縮財政を主張するとインテリに見える!?
森永:10月から消費税率が10%に引き上げられます。消費税増税の議論が表面化したとき、消費増税に否定的なMMT(現代金融理論)に注目が集まりました。MMTを支持する層は「緊縮財政は必要ない」と主張していましたが、飯田先生はどうお考えですか。
飯田:関西学院大学の朴勝俊教授がうまい指摘をしています。MMTとか反緊縮財政がポピュリズム(大衆迎合)なら、緊縮財政はエリート迎合主義。どちらに迎合しているかだけの違いというわけです。緊縮財政を主張すると「インテリですね」と褒められるので、政治家や評論家やタレントは支持しがちだけど、なるべく公的なお金を使わず(公的社会サービスを削減し)、税金は(富裕層の負担が増えないように)消費税の形でフラットに集め……といっためちゃくちゃ金持ちに有利なことを難しく語っているだけという主張もあります。
森永:確かにそうかもしれないですね。
飯田:MMTにも疑問があります。MMTのコア部分になる「ジョブ・ギャランティ・プログラム(JGP)」は、働く気があるのに、仕事がない人に政府が最低賃金を保障して必ず職を提供するという考え方です。すると民間の賃金水準も自動的にJGPレベルまで引き上げられる。景気が上向くと、JGPの賃金よりも高い民間雇用の賃金を求めて労働力が移動するので「ビルトイン・スタビライザー(景気変動を自動的に調節する機能)」が働くというわけです。しかし、これは人の良心に期待しすぎでしょう。絶対にクビにならない職場で、真面目に仕事をするというのは難しい。サボりますよ。さらにこのJGPの職種や仕事内容を管理する機構は膨大な物になるでしょう。それに提供する職も不明瞭です。MMT論者のニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授に「JGPではどんな職を想定しているのか」と聞いたら、介護とか保育とか言う。
森永:介護や保育は素人にできる仕事ではないし、法律上も無理。そこの議論が抜けていますね。
飯田:社会学者の吉川徹先生が10年以上前の本で、「日本は二つの国に分かれている」と書いている。お金に無頓着、人的資本の蓄積にも無頓着というグループ――つまり真面目に勉強したり働いたりして経験を積んでスキルを積み上げて出世してというプロセスに頓着しない人たちと、子どもはお受験して私立、マイホームは都心ならタワーマンション、郊外なら庭付き一戸建て、結婚でも子育てでも全部合理的、全部完璧にしなくてはいけないという生きづらそうな人たちです。前者は気楽な一方で、金がない。
森永:ハイスペックな方々は、お金がない人は自己責任だと主張しています。まるで他人事という捉え方ですが、僕はその考え方はあまいと思っていて、格差の拡大を放置していた結果、行き着くところはディストピア(ユートピアの反対の世界)だと思います。生きる希望を失うと世の中が混乱してテロが起こるかも知れない。自分だけが豊かになればいいという考え方ではなく、社会全体として豊かになることを考えるべきだと思う。その議論はほとんど行われていませんが、たまに見かけるのが最低限必要な所得を無条件に給付する「ベーシックインカム」という制度です。
飯田:ベーシックインカムには、社会主義寄りから出てきたものと、新自由主義的な究極の自己責任論として出てきたものの二系統がある。社会主義寄りのほうは、生存に対して賃金を支払うべきという考え方。逆の新自由主義的なほうは、複雑な官僚機構を必要とする社会保障制度をやめてベーシックインカム給付に統一するにするという意図がある。新自由主義の理論的支柱であるミルトン・フリードマンも負の所得税というベーシックインカムに似たシステムを主張しました。私も一部ベーシックインカムを導入してもいいと思っています。それは老人向けベーシックインカム。今の年金制度は半分以上公金で支えられているのに、一定期間掛け金を払った人しか受け取れません。公金を入れているのなら70歳以上(65歳支給は無理筋だと思う)の全員に払うべきでしょう。
実施時期が悪すぎる
森永:角川書店『キミのお金はどこに消えるのか 令和サバイバル編』では消費増税がテーマの一つになっていますが、飯田先生は消費増税賛成派ですか。
飯田:10%までは正当化できなくもないですね。消費税は安定財源であること、徴税コストが低いことが理由ですが、10%を超えると直間比率が間接税に寄りすぎるので微妙になる。
森永:消費税は10%で止まるのでしょうか? 今後も数年おきに少しずつ上げるような気がします。
飯田:10%に引き上げたら次は固定資産税だと思います。課税方式は所得課税と資産課税と物品課税に分けられます。消費税導入前の日本は所得課税の比重があまりにも高く、いびつな税構造でした。そこで、物品課税を売上税、大型間接税、消費税と名前を変えて導入しようとしたのです。だから次は手つかずの資産課税。固定資産税でも相続税でもどちらでもいいのですが、固定資産税は地方税、相続税は国税なので、分配の原資にするのなら相続税のほうがしっくりきます。固定資産税にすると、地方はまちづくり、まちおこしに積極的になる。英国は市町村の収入に占める固定資産税の割合が高いので、地域の価値を高めて地価を維持することにやっきになっています。
森永:消費増税による景気への影響はどうでしょう。直近の様々なデータを分析しましたが、消費はかなり冷え込むと見ています。日本チェーンストア協会が発表したチェーンストア販売統計をみると、全国10,000店舗余りの主なスーパーの7月の売上高は1兆73億円となっており、4カ月連続で前年同月比マイナスの伸びとなっています。長雨と低気温が続いた影響もあって、前回の消費増税(8%へ引き上げた2014年4月)の駆け込み需要の反動減があった2015年3月以来の大きなマイナスです。増税の前なのに駆け込み需要すら起こらなかった。
飯田:まったくその通りで、日本百貨店協会は2019年7月の全国百貨店売上高を前年同月比2.9%減と発表しています。「長梅雨による日照不足や低温多雨の影響から盛夏アイテムが不振だった」というのですが、いやいや冷夏といっても半袖は着るでしょうと(笑)。今年の百貨店は、真夏にまだ夏物のセールをやっていた。お盆を過ぎたら秋冬物商戦なのに、夏物が売れ残っているのです。
森永:毎日閉店セールをやっている靴店は別にして(笑)、モノが売れないのに、10%になるともっと売れなくなりそう。なぜなら980円の8%を暗算で出すのは難しいけれど、10%なら誰でもわかる。それに1万円の商品に対する消費税が1000円だと、1万円札に加えて、もう一枚お札(千円札)を出さなければならない。その心理的なインパクトは大きい。
飯田:私たちは飲み会の会費は3000円、スーツの値段は5万円、ランチは800円までといった、自分の中の不思議なリミッターを持っています。メンタルアカウンティング(心理会計)の一種ですが、増税になったからといってこの心のリミッターをその分上昇させる人なんていない。前回の増税の時もしっかり税抜き価格で3%分の消費が減っている。今回も2%減るでしょうね。
森永:20年スパンで増税するのなら現役世代が入れ替わるので駆け込み需要も都度発生するのかなと思いますが、数年おきに増税されると、みんなただ買い控えをするだけですよね。
飯田:大愚策だと思います。
森永:よりによって世界的に景況感が悪化しているタイミングで実施ですからね。
座学で泳ぎが学べないように相場も張らなければ分からない
森永:日銀はアベノミクスの最大の貢献者だとみていますが、今後何かが起きた時、日銀には中央銀行として出来ることが何か残されていますか。
飯田:やるべきことは一通りやったといってよいでしょう。これからの日銀に求められているのは、低金利の状態が長く続きますよという将来期待に関してのメッセージを強化することです。返す返すも残念なのは、2008年の段階でアベノミクス(と同様の経済政策)を始めていれば、2008年から2012年までの米国のとんでもない急回復の波に乗れた。当時日銀が手を打たなかったせいで取り残されたこと。今後は金融政策単独でもそれなりには効くでしょうが、財政出動との組み合わせがいいでしょうね。
森永:おっしゃるとおりで、ここまで金融緩和をしきってしまうと、ポリシーミックス(複数の政策を組み合わせて実施)しか手がない。つまり財政が動かないと刺激になりません。
飯田:そうですね。財政も単発ででかいモノを出すよりも中長期計画、特にインフラ改修に関する中長期計画を作り、それにあわせて財政を出すと効果的でしょう。かつては10年区分くらいでインフラ整備計画を立てる「全総」――「全国総合開発計画」がありました。全国総合開発計画 (全総)から第四次全国総合開発計画 (四全総)まで。五全総に相当する「21世紀の国土のグランドデザイン」はありますが、小泉内閣以降整備計画というより縮小計画になってしまった。困ったのは土木・建設業。将来の見通しが立たなくなったので、ビジネスを縮小させた。そのせいで、東京五輪特需が発生しても対応できないし、工賃も異常なほど値上がりしました。
森永:個人の投資レベルまで目線を落とすと、投資の世界に踏み出せないという人には財政出動とか金融政策の内容を理解していないと損をするという誤った認識があり、勝手にハードルを上げています。
飯田:相場を張らずに相場を勉強する方法はないと思うのです。プールには行きたくないけれど、泳げるようになりたいというのは無理(笑)。
森永:僕はプロ野球が好きなので、選手のプレーに対して偉そうにコメントするのですが、じゃあやってみろと言われると困りますね(笑)。たぶん空振りとエラーばかりでしょう。だから、実践することが大事なのです。お金を投じるのがいやなら、ショッピングポイントを使って投資ができる会社もあるので、それでやってみるといい。身銭を張ると相場の「上がった下がった」に一喜一憂して感情が振れていきますが、そのうち感情が振れるのを抑えたいから必然的にリスクヘッジを勉強する。座学がまったく不要とは言わないけれど、やってみることが大事だと思う。僕が金融教育ベンチャーを立ち上げたことで、「資産運用を始めるには何から勉強をすればいいのですか?」と聞かれることが多くなりました。「まずは経済学を勉強すればいいですか?」とか聞かれます。資産運用だけの観点では、勉強したほうがいいけれど、そこから入るのはどうかと思う。しかし、一方でいまの日本には資産運用を学ぶためのパッケージがあるわけでもない。
飯田:座学→投資の順ではなく、投資→座学の順。投資を始めたいという人には、典型的なポートフォリオを5つくらい提示して、とりあえず始めてもらい、相場が動いたことで損をしたり得をしたりする経験を積むことが大事です。
紹介書籍のご購入&試し読みはこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
▷井上純一『キミのお金はどこに消えるのか 令和サバイバル編』
▷森永卓郎・森永康平『親子ゼニ問答』