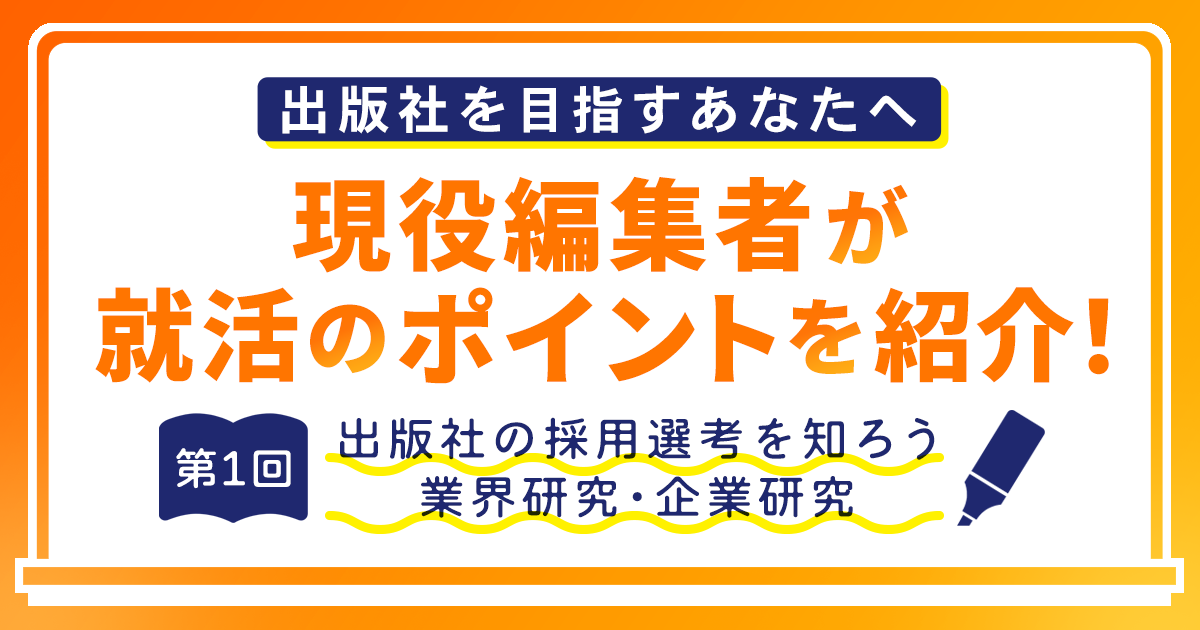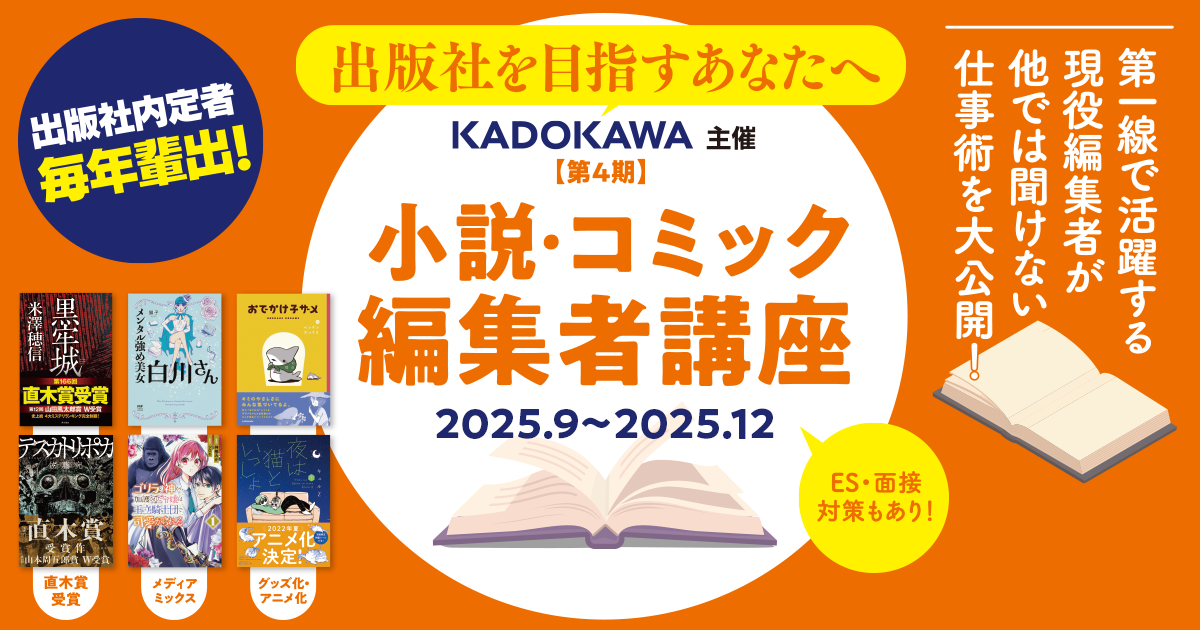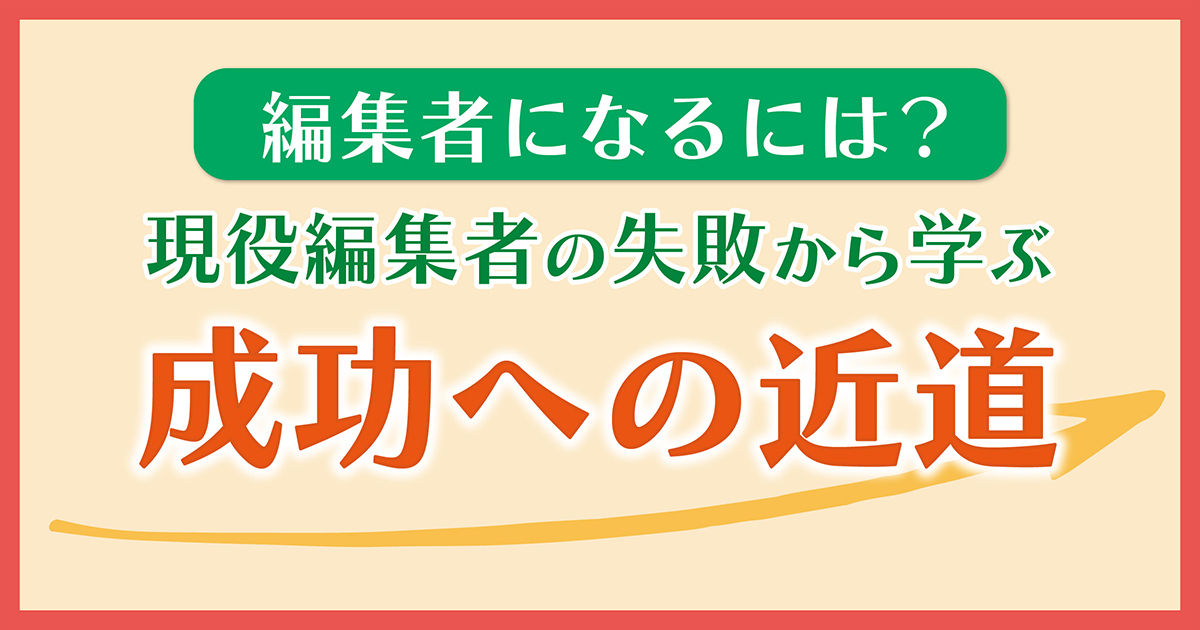編集者という仕事に興味はあるけど、就職のために何から始めればいいのかわからないという方も多いと思います。
本記事ではそんな出版社就職を目指す大学生に向けた「小説・コミック編集者講座」を運営するKADOKAWAの現役編集者が講座でお伝えしている出版社就活のポイントを4回に分けて特別に少しだけご紹介します。
第2回では編集者の仕事内容の紹介と企画立案についてお伝えします。
▼ 前回の記事はこちら
第1回 出版社の採用選考を知ろう 業界研究・企業研究
https://kadobun.jp/feature/readings/entry-123462.html
【第2回】編集者の仕事を知ろう 企画立案~書籍ができるまで
編集者の仕事内容と求められるスキルとは
就職活動において志望職種の仕事内容を把握しておくことは重要です。自分がその会社で働くイメージを具体的に持つことができますし、自身の持つ経験、スキルが仕事のどの部分で役に立つのか就活でのアピールポイントを考えるうえでも役に立ってきます。
編集者の仕事を一言で表すと、それは1冊の本を作り上げるプロジェクトマネージャーになるかと思います。書籍を1冊作って売るためには、作家、イラストレーター、写真家、デザイナー、校正、印刷所、営業、宣伝そして実際に店頭で本を販売してくださる書店員の方々など、様々な人たちの協力が必要です。編集者はそれらの人々をつなげる役割を担っています。
具体的な例として1冊の小説ができるまでの大まかな流れとそこに関わる人を挙げてみます。
① 企画立案
② 執筆依頼~原稿アップ(対作家)
③ 校正~改稿(対校正者、対作家)
④ カバー、帯などの制作(対イラストレーター、対デザイナー、対印刷所)
⑤ プロモーション(対営業・宣伝、対書店)
コミックの場合はここにセリフの写植などを行うDTP(デスクトップパブリッシング)会社が関わってきますし、実用書の場合は専門家に監修をお願いすることが多いです。
他にも作品が映像化やグッズ化された場合はそれぞれの担当部署と監修などのやりとりが発生することもあります。
上記の例だけでも、書籍制作に関わる人はとても多いということが伝わったかと思います。編集者は書籍制作というプロジェクトの責任者として、各関係者と打ち合わせや仕事の発注、スケジュール管理などを担うことになります。
また、作品の資料集めや取材のアポ取り、権利関係の許可取り、原稿料などの支払処理といった裏方仕事も編集者の大事な仕事です。
それでは、編集者に向いている人の特徴とは何なのでしょうか。編集者になるために必要な資格は特にありませんが、以下に選考の際に出版社が意識する編集者に求められるスキルの例を挙げてみます。
① 企画力
編集者の仕事は企画を作ることから始まります。企画が出せないとその編集者に仕事はありません。編集者にとって一番大事なスキルといっていいでしょう。また、その企画をプレゼンする能力も求められてきます。
企画の立て方やプレゼン方法に関しては別の項にて説明します。
② 文章力
書籍のあらすじ作成、帯キャッチ作成、リード文作成など様々なところで編集者は文章力を求められます。採用選考の中に作文試験があるのはこのためです。
③ コミュニケーション能力
前述のとおり、編集者は数多くの人とのやり取りが求められます。常に同じ人とだけ仕事をするわけではなく、企画のためには面識のない作家や新しいデザイナーにも仕事のお願いをしなければなりません。やはり仕事においてコミュニケーション能力は大事です。
④ マネジメント能力
作家の執筆モチベーションを上げたり、スケジュール管理を行ったりといったマネジメント能力も編集者に必要なスキルです。
⑤ 事務処理能力
地味かもしれませんが、書類提出や伝票整理、諸々手続きの申請業務なども編集者の仕事です。一つの手続きミスが大きな事故をもたらすこともありますので堅実な事務処理能力はぜひとも身に着けてほしいです。
もちろん上記の能力すべてを備えた完璧超人であることが求められているわけではありません。ただ、編集者に求められるスキルを知っておくと、選考の中でプレゼンするべき自身のアピールポイントの方向性が見えてくるはずです。
編集者の大事な仕事、企画の立て方について
さて、前項でも触れた編集者に必要なスキル「企画力」についてもう一歩踏み込んだ説明をさせていただければと思います。
よく出版社のESで志望動機や、志望部署でやりたい仕事として、「読んだ人を幸せにするような書籍を作りたい」「有名作家の新作を担当したい」などと書く人がいますが、これは企画としては0点です。
もちろん編集者を志す原点や就活の軸としてその想いを持つことは大事ですが、具体性のないふんわりとしたものは企画とは呼べません。
ESを通過したとしても面接で間違いなく「読んだ人を幸せにする書籍って具体的にどんな内容? その本は売れるの?」「その有名作家には具体的に何を書いてもらうの? その企画はその作家でないとダメなの?」といった質問が飛んでくるはずです。
そもそも企画とは「誰(著者)に、何(テーマ)を、誰(ターゲット)に向けて、何のために書いてもらうか」まで具体的に考えてつくるものです。とはいえ、いきなり良い企画を作れというのは高いハードルに感じてしまうかもしれません。
そこで皆さんに企画の立て方のヒントを一つ紹介します。
① 今流行っているもの、話題になっていることと、その理由を分析する
② 視点を逆にする、別のジャンルと組み合わせるなど構図をひねってみる
といったことを意識して企画を立ててみると、流行りものかつ斬新な企画が生まれてくるかもしれません。
もちろん企画の立て方は一つではありません。打ち合わせの中で作家が書きたいテーマを膨らませて企画にするのが得意な編集者もいれば、編集が作りたいテーマが先にあってそれから作者を探すタイプの編集者もいます。企画の立て方は編集者によって個性が出る部分でもあるのです。
企画は立てて終わりじゃない、企画会議を通過させるためには
企画立案に関してもう一つ大事なこと、それはどれだけ企画を立てようが社内の企画会議を通過しないと書籍は作れないという点です。
出版社に所属して書籍を作るということはすなわち、会社からお金を出してもらって書籍を作るという事です。当然ながら用紙などの原材料費、原稿料、運送費などは編集のポケットマネーではなく、出版社から支払われます。
つまり企画会議とは「この書籍を作るために製作費を出してください」と会社(=決裁者)にプレゼンをする会議なのです。
それでは企画会議を通過するための企画書の作り方、プレゼン方法とはなんなのでしょうか。答えはシンプルです。「この書籍は製作費以上の売り上げが見込めます、つまり会社に利益をもたらします」という根拠を示せばいいのです。
もちろん書籍が売れるかどうかなんて売ってみないとわかりません。それでも会社が「これは売れそうな気がする」と思える説得力がないと会社は企画にOKを出すことができないのです。企画書・プレゼンに必要な要素としては以下になるでしょうか。
① 内容の面白さ(最低条件)、テーマ、ジャンルの時代性=なぜ今出すのか
② 著者実績(SNSフォロワー数なども)・類書実績=これくらい売れます
③ ターゲット層に向けた宣伝施策=売り上げを伸ばすためにやること
④ その他映像化、グッズ化などの付加価値
このような内容をなるべく具体的に示すことが重要です。
そのため、編集者は企画立案の時点で様々な要素を分析する力も求められているのです。
皆さんも企画を考える際に「企画会議を通過させる」ところまで意識できるようになると、周りの人との差をつけられるはずです。
小説・コミック編集者講座(第4期)について
「小説・コミック編集者講座」では直木賞受賞作の担当編集者や、アニメ化もされた人気作品の漫画編集者がゲスト講師として登場します。スター編集者の企画立案方法などの仕事術や作品作りの裏話などが聞ける貴重な機会になります。また、実際に企画書作成や企画会議プレゼンを行ってもらう実践形式の講義も用意しています。
企画立案の詳細を知りたい方はぜひとも受講をご検討ください。
▼「小説・コミック編集者講座」の詳細・お申込みはこちらから!
https://kadobun.jp/special/editor-class/