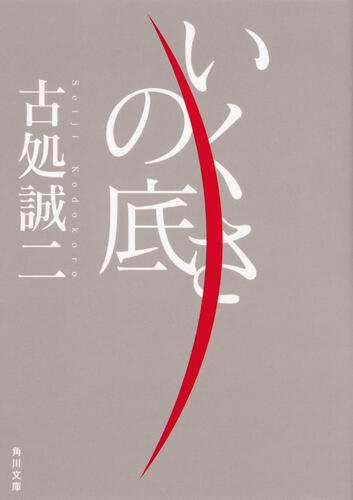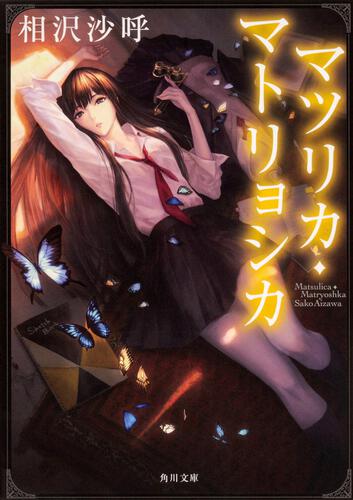来る5月11日(金)に第18回本格ミステリ大賞の受賞作が発表されます。今年の小説部門の候補作にはなんとKADOKAWA刊行の単行本が5作中4作品もノミネート! 火花散らす編集者たちに思う存分自分の担当作をガチンコアピールしてもらおうではないか、ということで急きょ立ち上がった本企画。KADOKAWA候補作の担当編集者によるバトルロイヤル開幕です。
〈参加メンバー紹介〉
K:編集者歴の長いベテラン。貴志祐介さん『ミステリークロック』を担当。クールに見えるが実は大変情熱的な人で、担当作について語らせると止まらない。
Y:単行本副編集長であり、古処誠二さん『いくさの底』を担当。ミステリ読みというわけではないので、なぜ自分がここにいるのか正直わかっていない。
M:ミステリ系の作品を多く担当する編集者。相沢沙呼さん『マツリカ・マトリョシカ』を担当。押しの強い編集者にひきつつ、マツリカ愛と著者の変態性を大いに語る。
T:入社したばかりの新人編集者。似鳥鶏さん『彼女の色に届くまで』を担当。社歴は短いですが作品への愛は負けないぞ、と血気盛んに参戦。
F:新人Tが先輩編集者にいじめられないか心配で急きょ参加。似鳥鶏さんの連載担当として原稿をいただいていました。Tのことは私が守る!
A:この企画を考えつい(てしまっ)たもうひとりの単行本副編集長。ジャイアン気質。別に誰の担当というわけでもないのにノリノリでやってきた。ちゃんと全部読んだから今日は言いたいこと言うぞ!
司会:中堅くらいの編集者。4作品中2作品を読了していたために、編集Aに「あなた司会をやって、なんとなく原稿をまとめなさいな」と言われて「イエスマム!」と返した社畜。
――というわけで、第1回編集者バトルロイヤルを開幕いたします。各編集担当の皆様には自分の担当作こそ世界で一番おもしろいぞ、というアピールをしていただければと思います。記事をまとめたら『屍人荘の殺人』を担当されている東京創元社Hさんにコメントをいただく予定です!
A:まずは各候補作を読んでいない方も多いと思うので、各担当編集者から自分の作品の紹介をしてください。ここで面白いこと言えなかったらすべてが終わるくらいの覚悟でどうぞ。それでは古処誠二さんの『いくさの底』のご紹介をどうぞ。ファイッ!

Y:では僭越ながら一番手をつとめます。著者の古処誠二さんは長く戦争小説を書いてこられた作家さんで、本作も第二次世界大戦中期のビルマを舞台としています。中国軍・ビルマ軍・日本軍がせめぎあっている三すくみの状況下で、日本軍の部隊を率いていた少尉が殺害されるというショッキングな事件から物語は始まります。誰が、なぜ、という部分が物語の中心の謎ではありますが、戦争が引き起こす村の分断や心理劇も読みどころです。
――古処さんはメフィスト賞のご出身ですが、「ミステリ」と大きく打ち出される作品は珍しいですよね。
Y:実は刊行した時から、これは「ミステリ」と言っていいものなのかが心配でした。ホワイダニットの物語ではありますが、他の候補作のようにトリックに主眼をおいていたわけではなかったので。そもそも、著者も私も「ミステリ」ということを意識して作った作品ではありませんでしたし……。
A:え、意識してないの!?
Y:ないです、ないです。「ミステリ的な側面もあるので、ミステリと言ってしまおう!」と著者とご相談して、「帯にも戦争ミステリと入れちゃえ〜!」って。私自身、ミステリに詳しいわけではないので、ミステリ通の方が読んだときに情報の出し方がフェアであるかも不安でした。なので、様々なミステリランキングで高く評価していただけたことは望外の喜びです。
K:犯人が明かされる部分の衝撃は素晴らしかったですし、ものすごく納得感もありました。全体を通して淡々描かれていくのが、とても良いですよね。
A:もしかしたら濃いミステリ読みの人は、犯人はこの人なんじゃないか、と早い段階で気づくかもしれないけど、その動機は読み終えるまではわからないと思う。しかも改めて読み返すと、最初から全ての要素がきちんと埋め込まれているのが本当にすごいよね。それにしても、結果としてミステリになっただけとさっき話していたけど、その発言を聞いたら多くの編集者たちが血の涙を流すと思うよ……。
F:本当ですよね。嫉妬の炎が燃えあがりそうです。
A:ミステリ書くぞー、という強いお気持ちがないままで、これだけの強度のある動機……!? 震えるね。
>>古処誠二『いくさの底』インタビュー 「戦争という大状況より、戦地での小状況にこだわり続ける」
――続いて、似鳥鶏さんの『彼女の色に届くまで』です。こちらはアートをテーマにしたミステリですね。謎解きの主題にアートを持ってくるというのが、面白い試みでした。
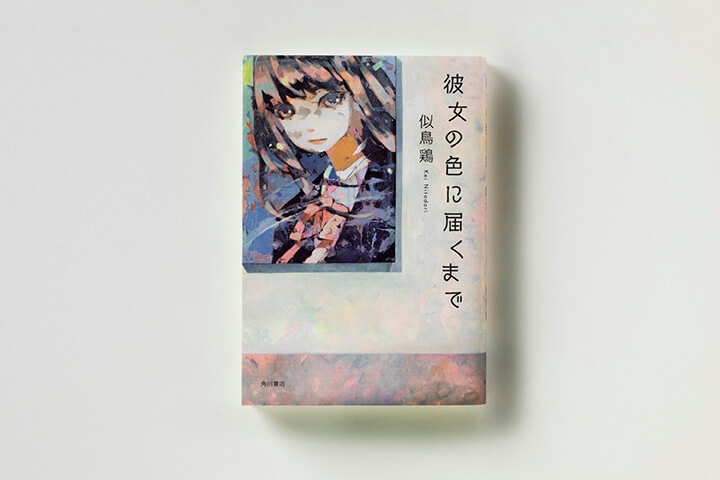
T:ルネ・マグリットやジャクソン・ポロックなど、有名絵画の特徴やモチーフが謎を解く鍵になる。このアイデアは私もとてもユニークだと感じています。著者の似鳥さんは絵がお好きで画廊などにもよく行かれるそうなので、その実体験に基づく小ネタも面白さのひとつだと思います。ひとつひとつのトリックも大変重厚なものであり、収録されている一編「極彩色を越えて」(雑誌掲載時タイトル:鼠でも天才でもなく)は第70回日本推理作家協会賞の短編部門の候補にもなりました。
――それと同時に、大変爽やかで読み心地のいい青春ミステリの側面も強いですね。
T:主人公の緑川礼は画廊の息子で幼い頃から画家を目指していますが、その才能は周囲から認められていません。あるとき高校で起きた絵画損壊事件の犯人と勘違いされた緑川は、同級生の千坂桜に窮地を救われます。無口でミステリアスな一方で絵の才能に溢れる千坂に緑川は惹かれていきますが、それは彼の千坂の才能に対する嫉妬と葛藤の日々の始まりでもありました。高校から社会人まで長いスパンで2人を描いているので、才能に葛藤する少年少女の成長を感じることができる青春ミステリの決定版です!
A:キャラクターものの連作短編としての醍醐味を感じた作品ですね。何者になれるのかもわからない、けれど何者かになれなければ自分に存在価値はない。そう思っている主人公たちと謎を解くこそ切実さがね、本当に見事でした。
F:私は連載担当として各話の原稿をいただく立場だったんですが、本作は一冊にまとまった時にはじめて完成する本だったと思います。一編ずつの謎は短編ごとに一応の決着がついているのですが、一冊を通して繋がる大きな謎が仕掛けられていて。最後まで読むと世界が反転するような終わり方になっていて、そこに主人公の葛藤がリンクしているのが本当に素晴らしいんです。ミステリ読みの方にはもちろんですが、普段ミステリに慣れ親しんでいない方にもぜひ読んでもらいたい。悩める人々の葛藤と成長の物語としても大変読み応えのある作品です。
――『屍人荘の殺人』については後程全員でお話しするとして。相沢沙呼さん『マツリカ・マトリョシカ』のご紹介をお願いします。
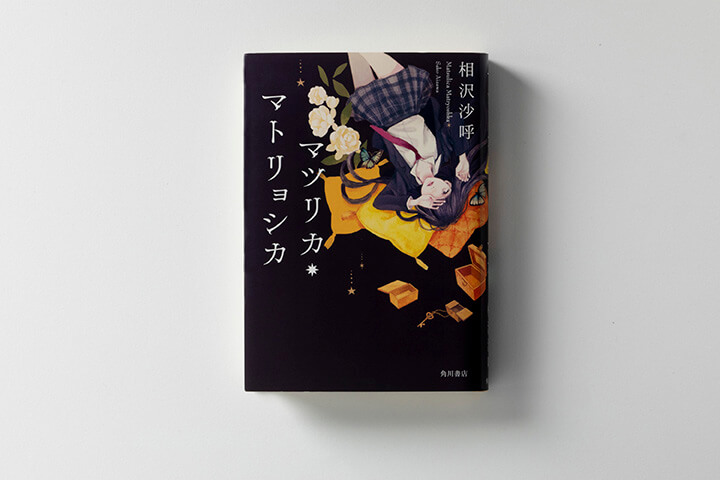
M:本作は高校2年の柴山祐希と、彼の通う学校近くの廃墟ビルに住む謎の美女・マツリカさんの2人が謎を解く「マツリカ」シリーズの第3弾にあたります。柴山が1年生の女子から「開かずの扉の胡蝶さん」という2年前に起きた密室事件のことを聞き、その調査に乗り出すと同様の密室が現在にも現れるというふたつの密室が鍵となる物語です。シリーズ初の長編で著者の意欲作です。
――学園ものでの密室、というのはなかなか難しいですよね。
M:「マツリカ」は人が死なないミステリなので、密室を作ることとそれに意味を持たせることが本当に大変でした。作中の密室では死体の代わりに制服をきたトルソーが転がっているのですが、結果的には映像的な効果が出て事件がより鮮やかに読者に伝わるようになったと感じています。開かずの扉を柴山が開けた時に、目の前に密室の状態が伝わるような感覚になるんですよね。そういった描写の部分にも著者の力を感じる作品です。
A:ふたつの密室に対して登場人物たちがある種の推理合戦のようなものを繰り広げる部分が、とても面白かったですし魅力的。私、こういう多重推理もの大好きなんだよね。
M:推理が錯綜する中で、探偵役の柴山が犯人と疑われるなど、二転三転する多重解決ものとしての面白さもありますね。現在の密室と過去の密室、それぞれを各キャラクターたちが解かなければいけない理由付けも明確なので、必然性が伝わるのだと思います。多重推理ものでありながら、読みやすく、コンパクトにまとまっているところも相沢さんの本領が発揮されています。
T:キャラクターひとりひとりが魅力的ですが、特にマツリカさんは他の方には生み出せないですよね。悔しいです。しかも今回は多重解決ものにすることで、マツリカさんの凄さがより際立っていました。
A:無慈悲なマツリカさんが、一般人たちの推理を蹂躙していくプロセスね。ゾクゾクするよね。あとは似鳥さんの物語にも通じるところがありますが、青春の屈託のようなものが鋭くて痺れます。『マツリカ・マトリョシカ』のほうは決定的に失ってしまったものがある人が描かれていますけど、今作では謎を通して彼らが再生していく姿がほんとに愛おしい。
K:似鳥さんも相沢さんも鮎川哲也賞のご出身ですが、この世代の方は青春ミステリの素晴らしい書き手が本当に多いですよね。皆さんそれぞれの青春に対する屈折があり、それが僕は大好きです。
M:ありがとうございます。登場する少年たちはみんな何かしらの悩みを抱えていて、それでも前を向いて謎に向き合っています。おとなが読んでもグッとくる青春小説になったのは、そういった弱々しいけれど歩みをやめない少年たちの姿がとてもリアルだからだと思いますね。
――では、最後に貴志祐介さんの『ミステリークロック』を……。
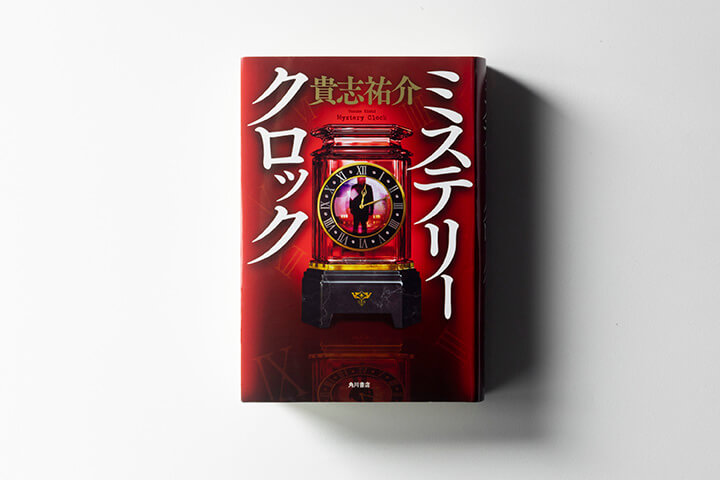
K:アドリブで話すのがとても苦手なので、メモを作ってきました!
A:Kさん、やる気満々じゃないですか!(笑)
K:皆さんご存知、ドラマ化もされた防犯探偵シリーズの第4弾です。今回も防犯コンサルタントで泥棒の榎本径と弁護士・青砥純子のペアが、タイプの異なる4つの密室殺人事件に挑みます。どれも切り口の異なるミステリで読み応えは抜群ですが、特に表題作の「ミステリークロック」は貴志祐介さんの意欲作です。時計に囲まれた山荘で起こる女流作家殺人事件なんですが、これだけでも長編がかけるくらいのボリューム感があり重厚感は抜群です。文字通り時間に縛られた時の密室を解いていく鮮やかさは、華麗としか言いようがありません! あと、セールスポイントとしては貴志祐介さんのエンターテイナーとしての気配りと遊び心ですね。
――どういうことでしょう。
K:本格ミステリには陥りがちな問題点がふたつあると思っていて、ひとつはトリックが複雑化しすぎて「読者が理解するのを諦めてしまう問題」。表題作の「ミステリークロック」のトリックはいつも以上に複雑で、貴志さんの執念がにじみ出ている作品ですが、読者に読むことを諦めさせない工夫が随所にちりばめられています。事件の過程やキャラクター同士の関係性など、さりげなく書いているようで全てが綿密に計算されているんですよ。きちんと作中の人間ドラマに読者が入り込むことで、トリックが複雑だったとしても読者の「なぜこうなったのか最後まで見届けたい」という気持ちを刺激するのだと思います。
A:筆致やキャラクター性はとても軽快ですが、そこだけによらないのがすごいよね。トリックや謎解きは純粋な小説力で納得させるという貴志さんの剛腕ぶり。ちなみに、もうひとつの問題点というのは?
K:そんな複雑なトリックを使うくらいなら「サクッと殺したほうが早いんじゃねーの問題」です。
F:確かに「どう考えても普通に殺したほうが良い」と思ってしまうケースは稀にありますよね。今回で言うと4本目の「コロッサスの鉤爪」はものすごく大きな仕掛けでした。
K:「コロッサスの鉤爪」は深海で起きた殺人事件で、普通の人間ではたどり着くことができない深海でどうやって殺したのかが物語の鍵になっています。かなり大掛かりなトリックなので、その動機とのバランスはものすごく重要で、ちょっとやそっとの理由では読者に納得してもらせないと思いました。けれど、貴志さんはきちんとそのハードルを越えていらっしゃって、人間ドラマの裏側に強い動機を潜ませているんです。これ、本当にすごいので皆さん動機はぜひ読んで確かめてください。
――さて、ここまででKADOKAWAの候補作4作品の紹介が終わりましたので、最大のライバルとも言える今村昌弘さんの『屍人荘の殺人』(東京創元社)のお話に移りたいと思います。本作は第27回鮎川哲也賞受賞作であり、デビュー作ながらこのミス2018年版・週刊文春ミステリーベスト10、2018年本格ミステリ・ベスト10で1位と前代未聞の三冠を獲得しています。今日は、この『屍人荘の殺人』の四冠を止めるための戦いですよ! 皆さん、わかっていますか!!
K:そうだ! 『屍人荘の殺人』にKADOKAWA軍として勝つぞー!
――葉村譲と明智恭介のミステリ愛好会コンビが映画研究会の夏合宿に参加した際、とある事件が起きてしまいペンション紫湛荘への立てこもりを余儀なくされます。騒動から一夜明けると、映画研究会の部員の一人が密室で惨殺死体となって発見される……というストーリーです。
>>『屍人荘の殺人』今村昌弘さんインタビュー
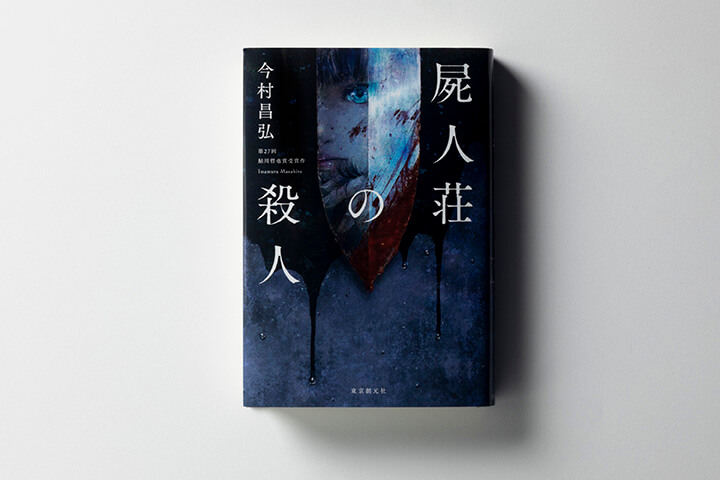
M:トリックやキャラクターが非常に立っていて、デビュー作でここまでの完成度というのは正直驚きました。実は私、作中のキーになるアレがものすごく苦手で……あ、これってネタバレになってしまうんでしたっけ。
――公式的な情報としては出していらっしゃらないので、すべて伏せ字にします。タイトルからわかる方も多いとは思いますが、念のため。
M:やっぱり最初は怖いし読めないなと思っていたのですが、勢いできちんと読めてしまうんですよね。●●●の出し方も非常に効果的で、人的災害として描いているのが素晴らしいアイデアだと思いました。
K:本当は●●●と本格ミステリって相性が良くないはずなんですよね。なんでもありの世界になってしまうので。でもこの作品は●●●の設定をお墓からモコモコ出てくる自然発生なタイプではなく人的災害に描くことで、きちんと設定に制限をかけているんですよね。ギリギリのところでトンデモ話にならないように設定していて、そのバランスが秀逸でした。
A:ある意味で米澤穂信さんの『折れた竜骨』と近いものがあるよね。『折れた竜骨』はファンタジーワールドで、魔法というものに制限とできることの法則性を作ることで大変フェアなミステリ。本作も●●●は出てくるトンデモ設定だったけれど、謎解きの部分はとてもフェア。
T:私は普段あまりミステリを読むタイプではないので、正直なところ●●●が本格ミステリとしてありかなしかというのはわからないんですが……。ただ一読者としてはギリギリの現実的なラインは保っているように思えて、皆さんおっしゃっていましたが、そのバランス感覚が抜群に面白いなと感じました。
Y:私はやっぱり動機が気になってしまいました。先ほどの貴志さんの話ではないですが、本作も結構大掛かりなトリックが使われているんですけど、こんな理由でしかもこんな込み入った方法で人を殺すかなあ……とついつい思ってしまいました。少し腑に落ちなかったです。
K:いや、僕はわかるなぁ、殺したくなる気持ち、わかります。
A:人間性の差、ここに極まれり(笑)。Yさんの言うように、たしかにこれほどのことを起こす動機というのは、描くのはかなり難しいとは思います。まあ、今回の物語はそのホワイダニットが主眼ではないと思うので、それはそれとして。
F:本格の密室トリックは出尽くしたという印象をもっていたんですけれど、限界はないんだということを感じた作品でした。発想の逆転と言いますか、ハウダニットはもちろんのこと状況設定の作り方が新しく、着眼点が本当に素晴らしいと思います。
A:ミステリというのは知の遊戯だという、その根本的な楽しさがとても出ている作品ですよね。殺人現場に残されている、「いただきます」「ごちそうさま」というメッセージが最高に悪趣味でいやらしいですよね。俗世の倫理から外れて遊び倒すというまさにエンタメ、ミステリだからできることを見せつけられちゃいましたよ。だが、我々はこれと戦うのである!
――そのとおりです!(笑)というわけで、最後に皆さんには「私の担当作品のこの部分が、他の候補作よりもはるかに優れているぞ!」というアピールをしていただければと思います。では、最初とは逆の順番で。
K:『ミステリークロック』は、ハウダニットを徹底追求して作られた本格ミステリであり、とにかくすべてが高いレベルで完成している作品です。そして何より貴志祐介さんの創作者としての狂気が溢れている作品だと思います。あ、ここは太字にしておいてくださいね。
T:マッドネス!(笑)
K:担当編集ながら、いつも貴志さんの思考には驚かされることが多いです。たとえば、「コロッサスの鉤爪」は最後まで犯人がわからなくて、連載時はタイトルの通りダイオウイカが犯人じゃないかと不安になってきて。「まさかイカじゃないですよね!?」と確認してしまったほどです。ちなみに犯人はダイオウイカではないですよ(笑)。普段ミステリを読み慣れていない方にも、逆に読みまくっている方にも満足していただける作品だと思っています。そしてその裏に見え隠れする貴志祐介さんのミステリ作家としての矜持を堪能していただきたいです。これぞ本格ミステリ大賞にふさわしく、かつエンタテインメント!!
M:『マツリカ・マトリョシカ』は人を殺さずに密室を作り上げている、ということがミステリとしての読みどころのひとつですね。人を殺さなくても密室は作れるし、その面白さを皆さんにも堪能していただきたいです。また、とにかく探偵役のマツリカさんのキャラクター性ですね。先ほど貴志さんの狂気のお話をされていましたが、相沢さんの太もも愛といいますか変態性は、ある意味で他の候補作を圧倒していると私は思っています(笑)。
――相沢さんの描くキャラクターの思春期感のリアルさは凄まじいですよね。変態性でいうと相沢さんはガチだ、と思いながら読了しました。褒めていますよ!
M:嬉しいです。謎を絡めて思春期の少年少女たちの葛藤と成長を見守っていただけたらと思います。
T:キャラクターの成長感という部分で言うと、似鳥鶏さんの『彼女の色に届くまで』も負けていないと思っています。物語の謎自体に「才能」というものをどう考えるかが関わっているので、謎そのものとキャラクターたちの成長がものすごく密接なんですよね。説明の入れ方、わかりやすさ、エンタメとしての読みやすさを追求している作品です。ミステリが苦手、私のように登場人物を覚えられないわ、という方にこそ読んでいただきたいです。面白いと思っていただけると自信を持って言えます。
Y:皆さんのお話を聞いていて、ここにいていいのかしら……とアウェイ感満載なんですが(笑)。ただ、絶対に負けない、というのは、やはり物語の強度の部分で、「自分だったらどうふるまうか。本当にこういうことがあってもおかしくない」と思っていただける作品だと思います。楽しいだけではなく、読み終えた時に深く心に何かが残る文学作品だと思います。
A:5冊ともそれぞれミステリとしてのあり方が全然違うので、全部が本当に美味しゅうございました。どれが受賞しても納得ですが、KADOKAWAの本・4冊も候補に入ってるんだから、1冊くらい(いや2冊でもいいんだけど)受賞させてくれたっていいよね? てか、するよね!? けど、何よりもこれをきっかけにたくさんの方に候補作を読んでいただけたら嬉しいよね。
――装丁も5冊それぞれ美しく、作品ならではのものになっているので是非お手に取っていただけたらと思います。お忙しい中、今日はありがとうございました!
後日このトークバトルの原稿を、『屍人荘の殺人』の担当編集者である東京創元社のH氏に「挑戦状だ!」と送りつけたところ、以下のようなコメントをいただきました。
---
初めましてこんにちは。『屍人荘の殺人』担当の東京創元社のHです。候補作一覧を見たとき“東京創元社”の漢字5文字が浮いて見えました(笑)。他社さんの想いも背負って「ぐっ、一太刀浴びせたり!!」と。とはいえ、今村昌弘さんがデビューされた鮎川哲也賞の先輩である似鳥さん、相沢さんも候補で、東京創元社としては嬉しい限りです!(背後から「原稿お待ちしておりますよ~!」という各担当の声が……)
今村さんは密室を書くぞという出発地点から例のアレで人々を閉じ込める着想に至ったそうです。アレがクローズド・サークルの装置としてだけでなくトリックと不可分で、余すところ無く物語に寄与しているところが個人的に大好きです。またミステリ初心者であった今村さんが、国内外のミステリ作品を読み、勉強していく過程で感じた「こうだったらいいのにな」を詰め込んだ作品です。絶対に解けない謎ではなく、手がかりをフェアに提示しよく読めば真相に辿り着きそうな、でも少しだけ読者の先を行くようなラストは衝撃です! ちなみに真相に辿り着く解法はAルートとBルートの2つのパターンを用意してあるんです。
KADOKAWA軍の猛攻を受けておりますが、三冠達成はダテじゃない! 四冠いただいちゃいます!!
---
>>『屍人荘の殺人』書誌情報(東京創元社)
勝手に企画を立ち上げた挙句、突然原稿を送りつけ、「コメントをください!」というお願いに、寛容なご対応をいただきましたこと心よりお礼申し上げます。Hさん、本当にありがとうございました!
だが、この栄冠は渡さぬぞ!!!! 本格ミステリ大賞の発表は5月11日(金)です!!