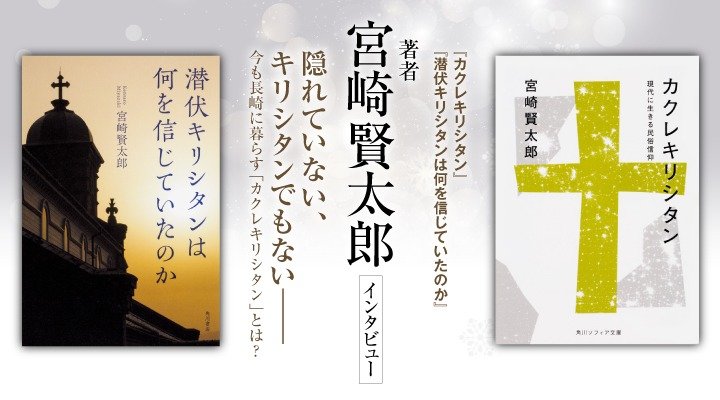信仰の自由が認められている現代ですが、長崎県下には今なお、潜伏時代の信仰を守る人々、「カクレキリシタン」がいることを知っていますか。著者の宮崎さんは数十年にわたり、その信仰世界をフィールドワークしてきました。マリア観音やキリシタン神社、口伝でのみ伝えられる唱文など、その信仰世界はキリスト教とは大きく異なり、日本独自の民俗宗教ともいえるものでした。秘蔵の像や行事の様子など貴重な写真も多数掲載された角川ソフィア文庫『カクレキリシタン』、そして単行本『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』を上梓された宮崎先生に、お話を伺いました。
── : 宮崎賢太郎さんの著書『カクレキリシタン』は2001年に長崎新聞社から刊行されました。私はこの本で初めて、今も長崎県には、潜伏キリシタン時代の信仰を守って暮らす人々がいることを知りました。これ自体、多くの人が耳を疑う事実だと思うのですが。
宮崎: 大半の人にはそうかもしれませんね。長崎県では折に触れて報道されていますのである程度の方は知っていると思います。
── : まず聞いたときに、「信教の自由があるのになぜ隠れているの?」と思ってしまいます。
宮崎: もちろん、隠れていませんよ。『カクレキリシタン』という言葉の中に『カクレ』が入っているからそういう誤解を生んでしまいますよね。今も潜伏時代の信仰を受け継ぐ人々のことを、便宜的に『カクレキリシタン』と呼んでいるのです。 彼ら自身、自分たちの呼び名は統一されていません。潜伏時代はお互いに行き来できませんから、古ギリシタンだったり、辻の神様だったり、しのび宗、元帳、古帳などさまざまです。外部の人は、隠れキリシタン、納戸神と呼ぶことが多いようです。 もっとも多く用いられているのは『隠れキリシタン』ですね。ただ、この表記は、隠れているわけではなく誤解を呼びますので、『カクレキリシタン』とすることにしました。それでもやはり耳で聞いたときには隠れていると思ってしまいますから、ほかにいい呼び方があればと思うのですが、今のところこれが最良かと思っています。
── : そして、キリシタン、キリスト教でもないのですよね。潜伏時代から200年以上にわたって信仰を受け継いできているのですが、その信仰世界には度肝を抜かれました。
宮崎: キリシタンといいますから、信仰しているのも当然キリスト教であり、キリストやマリヤを祀っているのだろうと思われるでしょうが、彼らの信仰世界はキリスト教とは大きく異なります。丸や様、出臼(父なる神デウス)様、肥料(フィリョ=イエス)様などという言葉がオラショ(祈りの言葉)の中にでてきますが、唱えている彼ら自身、その神様が誰だかはわかっていません。現代に生きる私たちは、デウス、マリア、キリストのことだろうとわかりますが、誰だかわかっていない以上、彼らはデウスやマリアに祈りをささげていたということはできないのではないでしょうか。 誰だかはわからないけれど、先祖がありがたくこれまで祀ってきた神様だから、引き続き大切にする、というスタンスです。 そもそもイエスやマリアを信仰するのであれば、信仰の自由が保障されるようになった明治以降、キリスト教徒になることを選ぶこともできました。実際、そうした信者もいます。ところが多くの潜伏キリシタンたちは、キリスト教徒になることを選ばず、地域ごとにカクレの神様を祝う行事などを続けてきたのです。
── : 祭壇などもキリスト教をイメージするものと違い、どこの家にもある仏壇のようです。
宮崎: 宣教師たちが運んできた当初は正真正銘のカトリックだったのでしょうが、200年以上にわたる潜伏期を経て、日本の土着の宗教と深く融合した姿がそこには見られます。マリア観音などはその最たる例ではないでしょうか。

生月島の南端にある祠に祀られているタンジク(地獄)様のお掛絵。中央がジゴクの弥市兵衛、右がマリヤ、左がその子のジュアンといわれている
── : そもそも、なぜ、カクレキリシタンの研究をしようと思ったのですか。宮崎さんは長崎県出身ですが、東京大学で宗教学を専門にされています。
宮崎: 実は私は父も母も先祖が潜伏キリシタンでした。また浪人時代に遠藤周作の有名な『沈黙』を読み、迫害され、殉教したキリシタンたちに興味を抱きました。この殉教者は、いうまでもなくキリスト教のために命を捧げたに違いないと誰しも考えていることですが、必ずしもそうではないことに気付きました。それはまた後ほど述べたいと思います。 とにかく日本の潜伏キリシタンたちの迫害と殉教をテーマにして、大学卒業後はイタリアに留学して400年前の古文書を虫眼鏡で解読するような暮らしをしていました。 研究の気晴らしで、長崎に戻ってきたときにカクレキリシタンの島として有名な生月島に行ってみたところ、今も潜伏時代の信仰を守っている人々がいることに改めて気づき、文献で過去の歴史をたどるのではなく、今、この人たちの信仰の姿から遡ってキリシタンの歴史を探ってみようと思い立ったのです。 思い出してみれば、大学院の課題で、一つの宗教教団について調査する、というものがあり、長崎市近郊にある外海を調査したことがありました。それが最初でしたね。
── : 資料との一対一からフィールドワークへ。思い切った転換ですね。地元の人に警戒されませんでしたか。
宮崎: それがそういうことはなくて、1、2の例外はありましたが、最初からほとんどの地区で歓迎されました。研究者といった意識ではなく、同じキリシタンの血につながる仲間のひとりとして入っていったのがよかったのでしょうか。ほかの地区の組織のことを話したりすると自分たちとは〇〇が違う、などと話が盛り上がりましたね。帰るときは、『今度いつ来るね?』と声をかけてもらっていました。 当時は各組織で年間に少ないところでも10回、多いところでは30回を超えるカクレの行事があり、儀式の後は直会が盛大に行われていました。カクレの奥さんたちがたくさんのごちそうを作ってくれます。もちろんお酒も入るのですが、行事参加者全員から歓迎の印として盃を受け、何度も返杯を受けますから、それが大変でしたね。東大出版会の会報誌『UP』に、『酒飲まぬ者にカクレの調査はできぬ』などと書いたこともありました。
── : 10を超える行事というのはどんなものですか。
宮崎: たとえば、元旦の御前様参詣にはじまり、餅ならし(正月の神様へお供えした餅を切り、信徒仲間にわける)、オマブリ切り(お守りとして十字架の形の紙を切る)、野立ち(野山の悪霊祓い)、家祓い(全信徒の家のお祓い)、上がり様(復活祭に相当するが何の行事か不明)、盆の終い、先祖様の盆、ジビリア様(意味不明)、田祈祷、12月末頃に「御産待ち」、「御誕生」(クリスマスに相当)など、多くの行事がありました。
── : お正月を祝ったり、お盆で先祖に祈るなど、キリスト教とは思えないですね。
宮崎: 潜伏時代は約230年間、人間の世代でいえば7代にわたります。仏教を強制されていましたので、オラショや教義の伝達は文書にできず、口伝でした。一人も指導者、宣教師がいない中で、キリシタン信仰は時代とともに少しずつ変容し、日本の土着信仰と融合していったのですね。 ただ多くの民衆層が、キリシタンに改宗した当初から正しく教義を理解できていたとは思えません。一神教のキリスト教を受け入れるということは、仏教や神道を邪教として捨てることです。そうではなく、日本の多神教の世界の中にキリスト教の神が仲間のひとりとして受け入れられたというのが実際のところでしょう。そうなると多神教のキリスト教ということになるのですが。
── : 外部の人には見せない秘密の儀式や秘仏などを見せてもらったりもしたのですか。
宮崎: 何度も繰り返し訪ねていると、『先生になら見せましょう』と言って、秘蔵の観音像を見せてもらったり、今まで一度も開けたことのないという『開けずの壷』を一緒に開けてみたりもしました。またカクレの仲間でも見ることが許されない『戻し方(葬式)』も、そばでそっと見ることを許されたこともあります。 ただ生月島はわりとオープンですが、生月以外は、外に出したがらない、儀式を見せたがらないですね。組織によっては今でも見せないところも多いです。
── : 秘密主義なのですか。
宮崎: といいますか、これまで隠してきたのだから自分たちの代で公にするのは申し訳ない、という気持ちではないでしょうか。加えて、ある種の困惑というか、自分たちも何をやっているかわからないので、何か質問されても困る、盛んだった行事も廃れ信徒も少なくなり、世間にその姿をさらすのが恥ずかしいといったような心情もあるようです。

各地区のカクレキリシタンの組織は次々と解散している。新たな試みとして、地区の共有地に「御堂(ごどう)」と呼ばれる礼拝施設が建てられた。左は辻という地区の御堂、右が小場という地区の御堂
── : 私は初めてこの本を読んだとき、本当におどろき、興味を覚えたのを覚えています。今回、角川ソフィア文庫として刊行させていただき、本当にうれしく思っているのですが、ただその中にとても気がかりなことが加筆されていました。文庫化するに当たり、この十数年の変化も大幅に書き加えていただきましたが、ほとんどの組織が消滅寸前だと……。
宮崎: 今の信者はほとんどが60代以上です。平均年齢は80歳に近いでしょう。すでに90%以上の組織が消滅し、わずかに残っている4~5カ所の地域でも、本来、役職者は三役があったのですが、以前のようにそろっているところはひとつもありません。帳方あるいはオヤジ様といった最高の役職者と、わずかな数の信徒が残っているだけです。洗礼も行われなくなって久しく、それらの組織もあと何年続けていけるのか、すでに秒読みの段階に入っています。
── : 風前の灯という感じなのですね。なぜ解散が相次いだのですか。
宮崎: まずは地域の過疎化で、役職の後継者がみつからないというのがもっとも大きな原因です。かつてはこういった信仰組織のなかで、行事の折に人々が集って親睦を深め、助け合う、そんな地域のつながりがあったのでしょう。楽しみも限られていた時代には、行事で振舞われるお酒を信仰仲間と酌み交わし、ごちそうを食べるのはなによりの娯楽でもあったことでしょう。 現代は、個人個人がそれぞれの楽しみを持つ時代です。地域で助け合わなくとも、さまざまな手段でサービスを受けられますし、おいしいものも食べることができます。組織としての必要性が薄れてしまいました。 また、直会の食事の準備は女性たちの大きな負担でもあったのです。行事数を減らしたり、複数の行事をまとめて一日で済ませたり、食事も簡素化したりして何とかやってきていましたが、それも限界となり、解散せざるを得なくなったのです。
── : 時代と合わなくなったとはいえ、200年以上も受け継いできた信仰の灯が今まさに消えようとしている……そういう意味でも、本書の内容は貴重ですし、多くの写真には思わず見入ってしまいます。
宮崎: 私が研究していた1980年代以降の写真も多く掲載しています。儀式の様子や祭礼道具、直会の食事風景など、解散して儀式自体執り行っていないものがほとんどですから、今となっては貴重ですね。

祭壇の前で祈願のオラショを唱えるカクレキリシタン。祭壇のしつらえなどに日本の民俗宗教との融合が感じられる
── : この『カクレキリシタン』と同時に、単行本『潜伏キリシタンは何を信じていたのか』が刊行されました。こちらは何をテーマにしたのですか。
宮崎: 先ほど少し話したのですが、キリシタンといえば厳しい迫害を受け、多数の殉教者がでたが、それにもかかわらず仏教や神道を隠れ蓑としてその信仰を守り通したという、美しい夢とロマンにみちたイメージを思い描いている人が多いのではないでしょうか。ただ私はあるときからこの点に疑問を抱くようになりました。 そもそもほとんどの一般民衆は、キリシタン大名の命令によって、キリスト教のことはほとんど何も知ることなく、集団改宗によって洗礼を受けさせられました。信仰の問題ではなく、政治の問題だったわけです。 そのような経緯で、それまで拝んできた仏教や神道をそれほどたやすく捨て、先祖崇拝をやめることができたのでしょうか。宣教師たちのたどたどしい日本語で、現代人にも容易とは言えないキリスト教の神の三位一体の意味を理解できたのでしょうか。疑問を持たざるを得ません。それであれば、『命がけでキリスト教の信仰を守り通した』という定番のストーリーは、史実とは程遠いと考えられます。
── : 言われてみれば確かにそうですね。ただ天草四郎など、実際に殉教した人も多くいますよね。
宮崎: もちろん、強い信仰を持つ人もいたでしょうし、本当に殉教した人もいます。ただそれは例外的だったのではないでしょうか。例外的な事例を普遍化はできません。また、殉教者といわれる人が多数存在したのは事実ですが、問題はその殉教者と言われる人たちが本当にキリストのために命を捧げたのかどうかという点です。別の何かに命を捧げたのではないでしょうか。その何かとは何だったのでしょう。 私はこれまでに述べてきたように、現在のカクレキリシタンたちをフィールドワークしてきました。そこにはキリスト教の残像はほとんど見えません。それに、禁教後、キリスト教に留まる人は限られていましたし、今も組織解散後、キリスト教からの勧誘もあるようですが、カトリックにいく人はほとんどいないのです。
── : 本書では、キリスト教の研究者や信者の間で大きな議論を呼びそうな考察が述べられています。その内容についてはぜひ本書を読んで確かめてほしいと思います。
宮崎: この論点が日本のキリスト教史の正しい理解のために極めて重要なポイントであると考えるようになったのはここ数年のことです。夢とロマンのベールを取り去り、虚心坦懐に日本におけるキリスト教受容を考えたときに、ハッと気づいたのです。 ただ一つ、誤解しないでいただきたいのですが、私は潜伏キリシタンたちの信仰を貶めるつもりは一切ありません。むしろ、日本の民衆の信仰と自然に融合したその姿を美しいと思っているのです。一人の研究者として、歴史の事実をありのままに見つめたいと思ってきたのです。
── : 今年の夏には世界遺産登録も予定されています。
宮崎: 『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』ですね。ホームページを見ると、潜伏キリシタンたちの信仰の強さや迫害の厳しさがくり返し述べられていますが、実際はどうだったのでしょうか。皆さんもぜひ本書を読んで、考えていただけたらと思います。
── : 今日はありがとうございました。

長崎にはキリシタン神社がいくつかある。写真は五島列島の有福島にある頭子(つむりこ)神社。地元のカクレキリシタンの人々が、殉教者をお祭りしているという。かつて殉教者の漂っていた首を祀ったという