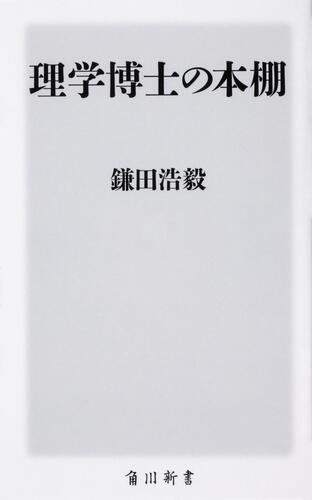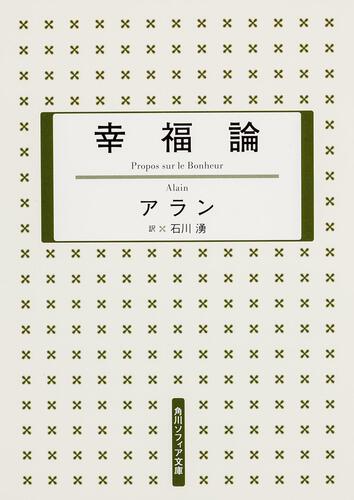京都大学大学院人間・環境学研究科教授で火山学者の鎌田浩毅さんは、地学の啓蒙のため、地球科学系の著書を次々と上梓する一方、書物にまつわる著書も多い方です。その中の新著『理学博士の本棚』(角川新書)では、厳選した中古典の名著12冊を紹介していますが、これらの本は実は鎌田さん自身を形成してきた本でもあります。刊行を記念して鎌田さんにとっての読書の魅力を存分に語っていただきました。
◆ ◆ ◆
――本書の執筆のきっかけは?
鎌田:10年ほど前に、アランの『幸福論』(角川ソフィア文庫)の解説を引き受けたのですが、その際に、いずれ『幸福論』を含めて中学生や高校生に読んでもらいたい本について書いてほしいと編集担当から言われたので、ずっと温めていたんです。
僕は角川書店の創業者の角川源義が作った「角川文庫」が好きで、当時はハトロン紙(グラシン紙)のカバーでしたが、中学生の頃からよく読んでいました。だから、やはり古典とか中古典といったら角川と決めていたんです。
そのあと「角川oneテーマ21」という新書シリーズが登場して、今は「角川新書」になりましたね。僕は手軽に読めることを大事にしたいので、新書という判型は僕の希望とも合致するものでした。
――10年越しの企画ということですね。しかし、読者対象は若い人とは限らないようですね。
鎌田:そうです。読者対象は2世代あります。まずは中学生、高校生に読んでもらいたいと思って、僕が昔読んで感動した本を選びました。若い人の本離れが問題になっているので、紙の本への応援団、読書の応援団としての目的です。
一方で、振り返ってみると僕は今年で65歳。来年は大学を定年退官になるんですね。
僕らは新書とか文庫とか、それこそ岩波文庫など、ハトロン紙の文庫を読みつづけてきた世代で、その世代が60を過ぎてから次々と定年になり、第二の人生、第三の人生がスタートします。そのときにもう一回若いときに読んだ本を読み直そうよ、というメッセージを込めて、プレミアエイジ向けにも選びました。
だから、若い人が初めて知る本や、プレミアエイジが振り返って昔こんな本があったなって思うタイトルも入っています。たとえば畑正憲(はたまさのり)なんて、若い人はきっと知らない人が多いでしょうけど、プレミアエイジならみんな知っているはずです。
――12冊を選ぶには悩みましたか?
鎌田:そうですね。悩むというより、うれしい悩みというか。この本では、僕のエピソードをガンガン語ろうと思ったんですよ。
というのは、世の中には古典本の解説がいろいろありますけど、たいてい「こういうことが書いてある」というクールなガイド。その人がなぜそれを選んだのか、理由が見えないものが多いんです。
やっぱり本の内容が人に伝わるというのは、俺はこう読んだ、こんなに感動した、ぜひ読んでみて、というエピソードがあって初めて生き生きと伝わるものだと思うんです。
そういう意味では今回、自分にとって読書遍歴のエピソードが多い本を選んだと思っています。
――1冊目が寺田寅彦で、最後が勝海舟ですね。
鎌田:寺田寅彦は僕の専門分野ですが、寺田の『天災と国防』に始まり、勝海舟の『氷川清話』で終わっているのには、実はわけがあるんです。
ひとことで言うと、地球科学を社会に還元するということですね。寺田寅彦は「アカデミーの洞窟を出て」という言い方をしたのですが、そのアカデミー、すなわち学問の世界から飛び出て、広く世間、社会へ向けて貢献すべきである、と。
それは勝海舟がやったこととも結びつくと思うんです。そういう意味で勝海舟はトリの本だなと思っていました。
勝海舟が生きた時代は、幕末の動乱期です。勝自身、直心影流(じきしんかげりゅう)免許皆伝の剣の達人というだけでなく、オランダ語の辞書を2冊筆写するぐらい教養がある人。彼はその武術と教養を活かして大きく社会貢献をしました。
現代も平安時代以来1000年ぶりの「大地変動の時代」を迎えていますから、学問の分野からの社会貢献がとても大事だと思うんです。寺田は文理融合で両刀使いでしたから、そういう意味では文理両道の寺田と文武両道の勝っていうのが、最初と最後の位置付けとしてふさわしいように感じたわけです。
あとのラインナップは僕の生い立ちというか、人生の流れに沿った順になっています。3冊目に立花隆を紹介しているのは、『青春漂流』にはたくさんの青春のエピソードがあって、若い人がいちばん不安で未来が見えなくて、でもエネルギーが溢れているというときに最初に知ってほしい本だからです。
この本は、立花が集めた類いまれなエピソードの集合体なんですよね。インタビューの仕方もすごい。僕の立花イチ押し本はこれなんです。
そして、4冊目の畑正憲(『ムツゴロウと天然記念物の動物たち』)は、東京大学理学部の先輩ということもありますが、僕が影響を受けた本ということで取りあげました。やっぱり畑という人も僕らの世代では、輝いていたんです。
本当は畑が出た理学部生物学科動物学課程に行きたかったけど、僕は成績が悪くて留年もした。でも、それが地学科に進むきっかけとなり、その迷いの時期に自分の中で人生を決める羅針盤になったんです。そういう意味で、4冊目にあげたわけです。
――そのあとは、サリンジャー、ミヒャエル・エンデと続きます。気づいたのは、アメリカ人作家が一人で、エンデのほかトーマス・マン、ヘルマン・ヘッセとドイツ人作家が3人です。
鎌田:あ、そうか、でも特段の意味はないんですよ。言われてみてちょっと思うのは、ドイツのシュトゥルム・ウント・ドラング(文学革新運動)ですよね。本書にも書いたけど(青春時代の)疾風怒濤って、本人には辛くてちっとも明るくない時期じゃないですか。
ドイツって情念の国でしょ、ブラームスやシューベルトみたいなね。だからそういう意味ではトーマス・マンとヘッセが出てきたのは、自分なりになるほどなと納得しているんです。
『トーニオ・クレーガー』も『車輪の下』も名作だけど、結構暗い話でしょ、暗い青春にはぴったりなんです。
実は、これまで僕の本で紹介した作品には、明るい話が結構多かったんですよ。『世界がわかる理系の名著』(文春新書)でもジェームズ・ワトソンの『二重らせん』とかアインシュタインの『相対性理論』とか、ああいう突き抜けた天才の話が多かった。でも僕も「中二病」にしっかりかかっていたし、そのエピソードを書くならやっぱり、『トーニオ・クレーガー』と『車輪の下』だろうなと思っていました。
――サリンジャーはいかがですか?
鎌田:サリンジャーはもうちょっと上で高校生ぐらいの感じ。昔は野崎孝訳しかなかったけど、村上春樹が訳してさらに面白くなりましたね。
最初は『ライ麦畑でつかまえて』で原稿を書いていたんだけど、後で村上訳の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んで、すごく「翻訳」の妙味について考えさせられましたね。村上の人生観が出たような翻訳というかな、そんなことをちょっと書きました。
――サリンジャーの章で、「大人になっていない度」を測るという記述もありましたが、鎌田さんは?
鎌田:僕なんか、大人になっていない代表じゃないですかね(笑)。普段はスカジャンみたいなのを着て、学問のいちばん端っこにいて学生や若い人に向けて何かを発信したいという。学生とつるんでばかりいて、全然成長しないんですよね。
でも、それはある意味僕のアイデンティティ、クリエイティビティの源泉でもある。20代の連中に感化されると、教授でも常識を簡単に打ち破れるんですよ。だからもうホントに京大生は好きですね。
――8冊目に登場する伊丹十三さんが亡くなったのは64歳で、奇しくも今の鎌田さんと同じ年でした。
鎌田:野口晴哉(はるちか)も64で亡くなっているんですよ。あんなに健康の本質を考えた人も、決して長生きじゃないんですね。寺田寅彦も50代で亡くなってます。佳人薄命というけど、才能がある人もそうなんですよね。才能がない僕としては、しっかり長生きして、南海トラフ(地震)と富士山噴火と首都直下(地震)を見届けるまでは死ねないぞ、というのはありますね。
それはけっこう本音でもあるんだけど、ちょっと脱線させてくださいね。日本を揺るがす南海トラフ巨大地震の発生は2035年プラスマイナス5年です。どんなに遅くても2050年までには確実に起きますが、2050年になると僕は95歳なんです。
それから、富士山は今、噴火のスタンバイ状態で、いつ噴火してもおかしくない。けれど、今から30年ぐらい休んでも全然不思議ではない。首都直下地震も同じで、今日、明日、起きるかもしれないし、30年後かもしれない。
そういう意味では、地球科学者として3つの大災害を迎え撃つには元気でなければいけないし、ちゃんと頭がクリエイティブで活動的でなきゃいけない。だから、やっぱり64で死んでられない、って思っています。
――ところで、「カドブン」では若い世代へ向けて、小説の楽しみ方だけでなく、人生の役にも立つという側面も伝えられたら、と思っているのですが、その点についてはいかがですか?
鎌田:たとえば、本書でも取りあげたエンデの『モモ』は、児童書だけどとても深い内容なんです。それこそお父さんが子どもに読み聞かせていたら、お父さん自身が深く考えこんでしまう、ということがありますね。
そういうフィクションが、これから伸びるジャンルではないかと思うんですよ。大人向けのフィクションだけ好きな人がいたり、売れる作家の本ばかりよく売れたり、それはそれでいいんだけど。
でも、小学生のときに「本は面白いな」という体験をすることで、大人になって小説を読む、ということにつながっていくと思うんですね。だから児童書と小説をどうつなぐかがポイントじゃないか、と僕は思っています。
もう一つは漫画。この本で紹介しているものだと、手塚治虫の『火の鳥』は、哲学書というか地球科学書というか、すごく大きなドラマです。文明論と言ってもいい。
こういう漫画の古典が文庫になって、大人も子どもも気軽に読める。特に小学生、中学生が、(読書が)自分の趣味になる、人生の一部になるということが大事だと思います。
――たとえば、鎌田さんの場合は、『モモ』を読むことで、どんな副次的な効果がありましたか?
鎌田:『モモ』は時間論のファンタジーですから、時間についていろいろ振り返って考えることになります。この本で語られているもう一つの要素は、コミュニケーションなんですね。どうやって大人と女の子が丁々発止と議論していったか。そこには生きる戦略とたくましさがあって、たくさんの知恵が詰まっていると思うんですよ。
でも柱は、やっぱり人間だれにも等しく与えられた時間をどういうふうに生きるかなんです。僕は「活きた時間」といつも学生に言っていますが、資本主義と科学技術が時間をひどく変質させてしまった。それに対して、我々の生きる時間をどうやって取り戻すか、という問題なんです。
これは、もしかしたら、子どもたちよりプレミアエイジのほうがインパクトを受けるんじゃないかと思っています。だからぜひ今回カドブンでも配信してほしいなと思いますね。
――紹介された本から何を読み取るべきかまで言ってもらわないと、自分一人では到達できない人も多いと思いますが。
鎌田:確かにそうですね。どういうふうに示唆すればよいか、ブックガイドする側にも工夫が必要です。それには、「エピソード」と「レポート」と、伝えたい内容を分けるのです。
エピソードは自分の個人的体験を語ること。それに対してレポートは、「こう読んだらいいよ」とか「世の中にこういうことがあるよ」ということを抽出して伝えることです。
よってフィクションを取りあげるときも、自分の私的なエピソードと、世界の成り立ちを説明するレポートの両方が入るとがぜん面白いんですよ。
――なるほど。普通、小説を紹介するときは個人的エピソードで伝えることが多いですよね。
鎌田:そうです。それに加えて、小説の成り立ちを語ってみると、立体的に小説を読むことができます。たとえば、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』の面白さは、実は小説の「構造」にあるんです。
そうした古典の舞台裏を、専門家と素人が対談しながら解き明かす、とかね。
――エピソードとレポートという二面から語ると、確かに立体的に紹介できますね。ところで、話は『理学博士の本棚』に戻りますが、この本、私は若い頃に読みたかったです。
鎌田:僕もです(笑)。タイムマシンで中2の自分に会いに行けたら、きみこれ読みたまえ、って言いますね。それは僕の本だからということではなく、ブックガイドとしてこういうふうに読んだ奴がいるんだよ、って中2の僕に知らせたいと思う。
――この本は、読んでいると元気が出てきます。
鎌田:ある学者の友人が、この本ほど自己肯定感にあふれた本はない、全部、鎌田は鎌田でいいと書いてある、って言ってました(笑)。なんて答えていいかわからなかったのですが、その通りかもしれません。
――その本が鎌田さんの人生を作って来たわけですから。そういう印象を受けるのは当然かもしれませんね。
鎌田:そうですね、今さら変えられないし。ずっとこれで行きます(笑)。
▼鎌田浩毅『理学博士の本棚』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321903000120/