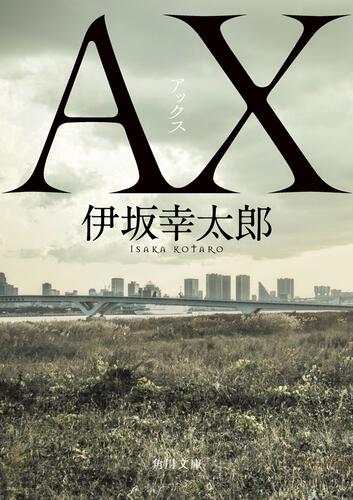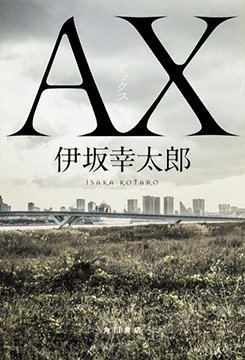『グラスホッパー』『マリアビートル』に続く伊坂幸太郎の代表作〈殺し屋シリーズ〉の第三弾、『AX』が刊行される。
今回のインタビュアーは、KADOKAWAの文芸単行本編集長・三宅信哉。
ちなみに、作中で明かされる殺し屋ネーム「兜」の本名は、「三宅」。……これは偶然か必然か!?
── : 『AX』は累計二二〇万部突破の〈殺し屋シリーズ〉、およそ七年ぶりとなる新作です。主人公は、シリーズ初登場となる殺し屋の「兜」。彼は殺し屋でありながら恐妻家でもある、という点が読みどころですね。この設定を着想した経緯を教えていただけますか。
伊坂: きっかけは今、僕に質問してくれている三宅さんとの雑談です(笑)。「AX」(第一編)の冒頭で、兜が檸檬と蜜柑(シリーズ前作『マリアビートル』に登場した殺し屋コンビ)を相手に「恐妻家は夜食で何を食べるか?」という話をしますよね。カップラーメンは包装しているビニールを破るところから食べるところまで意外と音がうるさいから、寝ている妻に怒られる。「最後に行き着くのは、魚肉ソーセージだ」と。あのエピソードって、三宅さんから聞いた話ですからね。「究極的には、魚肉ソーセージなんですよ!」って言われて、可笑しくて。あっ、実体験ではなく、想像ですか?
── : もちろんです。実体験のはずがありません。
伊坂: 実体験としか思えない迫力で語ってくれたそのエピソードに、ものすごく感動したんですよね。その場で盛り上がって、僕が「恐妻家の殺し屋がいたら面白いですよね」とノリで喋ったら、本当に書くことになっちゃった。
── : まずは短編を一本ということで、若い編集者が正式に依頼しました。伊坂さんから「もっとエピソードが欲しい」というリクエストがあり、僕のほうで恐妻絡みのエピソードをメモにしてお送りしました。
伊坂: 「三宅メモ」と呼んでいました(笑)。当時は震災のすぐ後だったし、楽しいものしか書きたくないなと思っていたからちょうど良かったんですよね。単に殺し屋の話だとキツいけど、魚肉ソーセージの話は楽しいし誰も傷つけないじゃないですか。あと、三宅メモがすごくいいなと思ったのは、「私は妻に怒られないよう家ではこういう言動をしています」といったことが告白調の文体で書かれてあるんですけど、読んでいると「奥さんの悪口を言いたいわけじゃない」ってことが分かるんですよね。自虐的ではあるけれども、いい話なんですよ。
── : 想像です……。
伊坂: この小説を書いているときも、奥さんが本当に「怖い人」とか「悪い人」だと、駄目になっちゃうなあ、と思ったんです。あくまでも「夫が気を使い過ぎている」となったほうが楽しいじゃないですか。だから全体の雰囲気は、シチュエーションコメディっぽくなった。とりあえず、兜を主人公にして、続きの短編も書くことにしたんですが、最初の三作まではコメディの雰囲気が強いと思います。
── : おっしゃる通りですよね。妻に「夕飯はトンカツにするね」と言われてトンカツを食べる気満々になったところで、「やっぱりそうめんにするね」と。兜が「俺も、そうめんくらいのほうがいいように思っていたところなんだ」と即答する場面は、我がことのように身につまされて……いえ、笑いました。
伊坂: 「妻の話を聞いていないと思われないように、オーバーリアクションで聞くが良し」とか(笑)。三宅メモに加えて、まぁ僕自身の経験も入っていますからね。妻に対しては何事も「大変だね」ってねぎらうことが大事だなって……あっ、僕も想像ですけど!
── : でも、今出たエピソードって過剰ではあるかもしれないけど、人づきあいの基本でもありますよね。
伊坂: そう思うんですよ。この小説で書いていることって、恐妻家と妻の関係に限定されることではなく、人と人とのコミュニケーションの問題だと思うんです。あまり踏み込まない、表層的なやり取りって大事ですし(笑)。
── : これ以上は誤解を招きそうですから、具体的な内容について詳しく伺わせてください(笑)。
省略している部分に 書き手の個性が出る
── : 兜は、昼は文房具メーカーの営業として働き、休みの日は庭にできたスズメバチの巣を退治する。殺し屋の仕事を仲介するのは医師で、病院の診察室で依頼を受ける場面もありますよね。これまで以上に、日常が描かれる度合いが多かったんじゃないかな、と。これは意識されていたんでしょうか。
伊坂: 恐妻家の設定を決めた時点で「家族」の話が多くなるから、必然的にそうなっちゃったんですよね。「BEE」(第二編)に関しては、当時ぜんぜんネタがなくて。たまたま床屋さんから庭のスズメバチを退治したという話を聞いて、本人の了承を得て使わせてもらったんです(笑)。ただ、そのエピソードからどう恐妻家の方向に持っていくかは結構悩みました。
── : 妻はハチの巣を一刻も早く退治してほしいと思っているのか、少し時間がかかってもいいから業者に任せようと思っているのか、本心はどっちなんだろうと兜が言葉の裏を読みまくるんですよね。
伊坂: 奥さんが兜に「頼むから、ちゃんと区役所に連絡してね」と言った後で、「あなたが刺されちゃったら大変だから」と。「心配」とか「つらい」じゃなくて、奥さんが「大変」という言葉を選んでいるところの微妙なニュアンスは、自分でも書いていてくだらなくていいなぁと思いました。
── : 兜は殺し屋として優秀なわりに、敵よりも妻を恐れたりパパ友を強烈に欲したりと、少しとぼけたところもあります。そういった性格設定は、どのように作っていったのですか?
伊坂: 敵よりも奥さんのほうが怖い、というのは典型的なギャグ、というか、くだらない感じを狙っているだけなんですよね。他の部分に関しては「君はどういう人なんだ?」って想像しながら、書きながら作っていった感じですね。「Crayon」(第三編)は兜がパパ友を作ろうとする話ですけど、この人にとって「友達を作る」というのはこんな感覚なんじゃないかなぁと、想像しながら書いていきました。まあ、常に立ち返るのはやはり、究極の恐妻心理としての魚肉ソーセージですけどね。
── : 一方で兜は、殺しの依頼を受けた相手がどんな人間で、なぜ殺さなければならないかという事情にはまったく興味がないようですね。
伊坂: そこは単に、僕の好みかもしれないです。今までの作品もそうなんですけど、「そこはどうでもいいなあ」「省いたほうがいいなあ」というところが結構あるんですよ。そういう部分はもう考えもしないで、あえて空白にしておきたい、というか。でも、意外にそこが大事だと思う人もいて「なぜ書かれてないんだ?」と怒られることがあるんですよね。でも、僕は僕の好きなように書くしかないから、「ほんと、ごめんなさい」と謝るしかない感じで。ただ、たぶん省略している部分に作家の個性が出るんだと思うんですよね。
四年の間に熟成された、 何かを残せたらという思い
── : 大前提として、兜は奥さんのことが好きですよね。息子の克巳のことも好きだし、家族というものを大事にしている。そういった底に流れている感情が、読み進むにつれて少しずつ上に出てきます。書き下ろしの二編(第四編「EXIT」と最終第五編「FINE」)では、その先へ向かおうという思いがあったのでしょうか?
伊坂: 三宅さんはよくご存じですけど、最初の三本を書いてから後ろの二本を書くまで、だいぶお待たせしてしまったんです。
── : 最初の三編の原稿は、二〇一三年にはそろっていましたね。
伊坂: 一本一本は気に入っていても、同じ流れでもう二本書いて一冊にまとめることには抵抗があったんです。『マリアビートル』は自信作というか、いまだに僕の代表作だと思っているから、〈殺し屋シリーズ〉の新作がこれだと、読者をがっかりさせちゃうんじゃないかな、と。最初の三本と同じような短編を二本書いて、まとめたところで、殺し屋の話に「恐妻家あるある」を入れた軽い短編集と思われたかもしれない。でも、担当編集者が「モチベーションが上がるまで待ちますよ」と言ってくれたんですよ。編集者もサラリーマンだろうし、申し訳ないな、と思いつつもそれに甘えてしまい。でも、時間を置いて考えることができたおかげで、書き下ろしの二本がこういう形になったんですよね。個人的にはかなりぐっと来る話になったし、「短編集ではなくて、長編です」と謳っても大丈夫なくらい、頭から一本の流れがきちんとできました。
── : ポイントとなるのは、兜と息子との関係ですよね。伊坂さんも息子さんがいらっしゃいますが、ご自身と息子さんとの関係を反映している部分はありますか?
伊坂: 克巳は思春期の高校生ですけど、うちの子はまだ小さいので、こういう男の子になってほしいなという憧れのほうが強いのかもしれないですね。親子関係というか。自分の味方で、友達関係でもあるような。ただ、父としての兜が息子に何を教えるかというところになると、「フェアでいようね」とか、自分の子どもに教えたいことが出てきちゃいますね。
── : それを言っているのが殺し屋、というのがいいですよね。
伊坂: 説教臭くないというか、ダイレクトに来ない感じがいいのかもしれないですね。「殺し屋のお前が言うなよ!」と突っ込めますしね(笑)。
── : 最初の三編を書いた頃からだいぶ時間が経ったことで、伊坂さんご自身と息子さんとの関係が変わり、兜と息子の関係の見え方が変わったということはありませんか?
伊坂: ああ、それはすごくありました。子どもに「何かを残そう」と思ったことはないですけど、「残せたらすごいだろうなあ」という気持ちはあるから、最後の「FINE」はそういう話になったのだと思います。後半の展開も、たぶん読者によってはマイナスの感じになっちゃうかもしれないですけど、僕としては、ああなるしかなかったという思いが強いんですよ。もし四年前に書いていたら絶対、こうはなっていないですよね。そういう意味では、原稿を急かしちゃ駄目だってことかも!
── : そこですか(笑)。本作は恐妻家のシチュエーションコメディの面もありつつ、殺し屋モノとしてのアクションもあり、描写や語りなどの実験精神も盛り込まれていて、鮮やかなどんでん返しで楽しませるミステリーとしての完成度も高い。終盤で迫り上がってくる「家族」「夫婦」「父と子」といったテーマも、多くの読者の胸に響くと思います。最後に、読者へのメッセージをお願いできますか。
伊坂: ないんですよね、読者にメッセージ。
── : いつもそうおっしゃいますよね。
伊坂: 「みんな、健康に気をつけましょうね」くらいですかね。ふざけているわけじゃなくて、本当に。「日々の生活を乗り切って、お互いまた、作品で会いましょう」と。
── : 〈殺し屋シリーズ〉のさらなる続編も楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。