インタビュー 「小説 野性時代」2015年4月号より
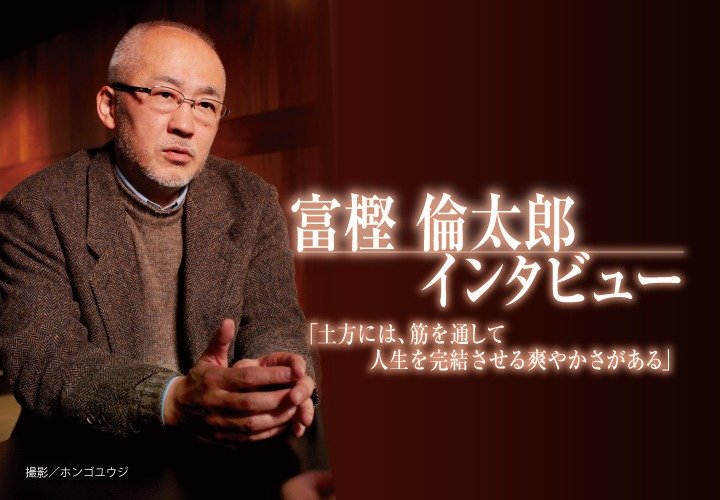
土方には、筋を通して人生を完結させる爽やかさがある
撮影:ホンゴユウジ 取材・文:末國 善己
富樫倫太郎さん『土方歳三』が角川文庫より文庫化されました。混迷の時代を明るく、前向きに駆け抜けた土方の実像に迫った本作について、土方という人物の魅力についてお話を伺いました。
富樫流「土方」に挑戦
── : 富樫さんは、〈土方歳三 蝦夷血風録〉三部作を発表されています。今回、土方歳三を正面から描いたのは、満を持してという気持ちがあったのでしょうか。
富樫: 司馬遼太郎先生にはかなわないという思いがありましたから、あまり他の方が書いていなくて、自分の故郷でもある函館(箱館)を舞台にして土方を書きました。ただ、ここ数年、他の方がお書きになっていても、違う見方をすれば違う物語が書けると考えるようになったので、土方歳三に挑戦してみました。それでも、やはり他の方と同じ題材を書きたくなかったので、土方の生涯でもよく分かっていない子供時代などに力を入れました。
── : 新選組の中でも、なぜ土方に魅かれているのでしょうか。
富樫: 動乱の戦国と幕末は、歴史小説作家には魅力的な素材です。例えば関ヶ原の合戦は、始まる前から謀略で勝負が決まっていたので、悲劇でもあり喜劇でもあります。幕末も同じで、長州征伐の頃までは幕府を恐れていますが、維新の一、二年前になると幕府は負けるという見方が広まり、雪崩を打ったように寝返っていく。その中で筋を通したのが、戦国でいえば石田三成や真田幸村、幕末でいえば土方歳三です。五稜郭で戦死した幹部クラスは土方と中島三郎助くらいで、他の人は生き残って明治政府で出世しています。その意味で、土方には自分の人生を完結させる爽やかさがあって、汚さを感じないんです。
── : 後半には、榎本武揚が、最後まで土方と行動を共にする同志として出てきますが、それも同じ理由でしょうか。
富樫: 榎本は、五稜郭で生き残って、明治政府で大臣になっていますから裏表があると考えていたのですが、調べると彼なりに首尾一貫していて、すっきりしていました。書きながら気に入っていったので、近藤勇亡き後、土方の相棒になりました。
── : 土方は、前半は吉原の遊女・桃若と、後半は京の医師の娘・佐和と恋に落ちます。このあたりはフィクションだと思いますが、富樫さんは史実とフィクションの関係をどのように考えていますか。
富樫: デビューして十六年になりますが、ようやく自分が史実を書くのが得意でないと分かってきました。デビューして数年は、史実をつないで物語を作っていましたが、最近は逆に、史実の空白を埋める気持ちで小説を書いています。今回一番困ったのが日誌に何年何月に何をしたのかが書いてある土方の新選組時代でした。逆に、どのように近藤勇と知りあったかは分かっていないので、子供時代は楽しく書くことができました。
── : 土方をはじめとする試衛館のメンバーは、幕末の動乱に乗じて出世を目指しています。これは、〈軍配者〉シリーズや『北条早雲』などの戦国青春小説にも通じる面白さがありました。
富樫: 東日本大震災の影響もあると思うのですが、〈軍配者〉の頃からテーマを意識するようになりました。〈軍配者〉のテーマは、僕が子供の頃に読んだ「少年ジャンプ」のスポ根と同じ、努力と友情と希望です。試衛館のメンバーは、同じ釜の飯を食って夢を語っていました。でも実際に出世をするとすれ違いも出て、山南敬助を切腹させるなどしています。その中で土方だけは、子供が玩具を与えられたように組織作りに熱中して、希望を失わず箱館まで転戦します。テーマを声高に主張したつもりはありませんが、意識しないうちに当てはまりました。
書くほどに深まる「土方」の魅力
── : 新選組が大きくなると、近藤勇をはじめとする幹部は変わっていきますが、土方だけは金にも、地位にもこだわりません。これも〈軍配者〉シリーズなどと共通するテーマで、現代の競争社会や拝金主義への批判のようにも思えたのですが。
富樫: 歴史小説を書いていると、金と権力を握った人間は、みんな同じ方向に崩れていくのがよく分かります。典型的なのが、若い頃は人を殺さなかったのに、晩年は簡単に人を殺し、成金趣味に走った豊臣秀吉です。今、『北条早雲』を連載していますが、早雲は面白い人物で、大名になっても相変わらず節約して、年貢を絞り取らないようにしています。お金や権力を欲する方向にぶれないのは、土方も同じです。近藤は偉くなると遊女の身請けに新選組の金を使っていますし、原田、永倉も妾を囲っています(笑)。新選組で最後まで変わらなかったのが土方と沖田総司です。沖田は病弱だったので、浮世離れした子供みたいなとらえ方をすると分かりやすいのですが、土方だけはよく分からない。そこが逆に面白いのかもしれません。
── : 佐幕派は、新政府軍の新兵器と火力に連敗し、自信を失っていきますが、土方は『英国歩兵練法』を熟読して、新政府軍に対抗する手段を最後まで考えようとしています。これは再チャレンジが重要というメッセージのようにも思えたのですが。
富樫: 新選組は、だんだら羽織を着て、髷を結って都大路を闊歩していましたが、土方は鳥羽伏見で負けて江戸に帰ってくると、髷を落として、洋服を着ています。おそらく敵の服装を見て、動きやすそうだから取り入れたのでしょうが、その変わり身の早さはすごいですよ(笑)。土方は一種の合理主義者で、戦国武将でいえば、織田信長に似ているかもしれません。土方は、味方が負け続けて肩を落としているのに、常にどうすれば勝てるかを考えています。こうした前向きさは、教えられて備わるものではありません。何がこんなに面白い人間を作ったのかと思うのですが、書き終わってもよく分からないです。
── : 土方が魅力的なのは、分からないところが多いからかもしれないですね。
富樫: 早雲の前半生には、何をしていたか不明な期間も多いのですが、土方は子供時代を除けば空白期間がありません。子供時代に、人生観を変えるような大事件に遭遇したとは考えにくいので、今でも何が土方を作ったかよく分からないですね。
── : 近藤が切腹ではなく斬首されたと聞いた土方は、新政府軍は武士の礼節も知らないと言って激怒し、それが北海道まで戦うモチベーションになります。ここにも勝った人間だけが得をする現代の風潮への批判があったように思えたのですが。
富樫: 幕末で最後まで戦ったのは、生まれた時からの武士ではありません。土方も本当の武士でないから、武士の礼節に忠実に生きようとした。死が美しいとは思いませんが、生にしがみつかないと俗世間の垢が抜けて、分かりやすい生き方ができるのだと思って書いていました。痛快な土方が、親友が斬首されてからは、僕が考えなくてもかっこよく動いてくれました。
── : 最後に読者へのメッセージをお願いします。
富樫: 僕は土方が好きなので、土方のかっこよさをさらに伝えようと思って書きました。今回はあまり取り上げられない土方の子供時代から新選組までと、新選組解散以降を重点的に書いたので、そのあたりを読んでいただければ嬉しいです。
<単行本刊行時に「小説 野性時代」2015年4月号に掲載されたインタビューを「カドブン」に再録しました>




















