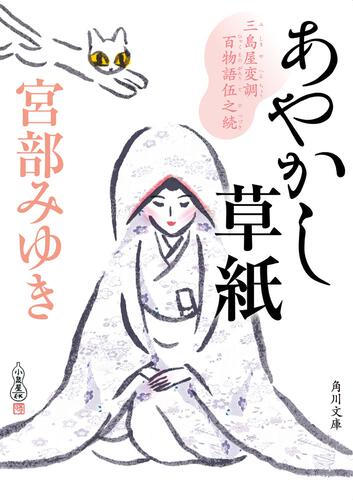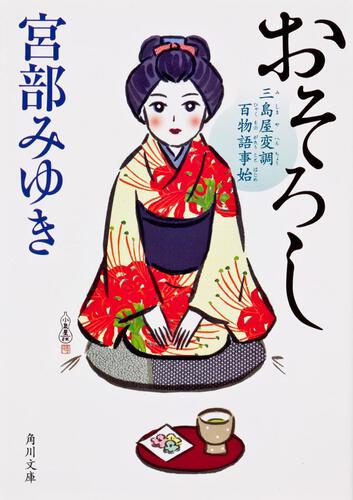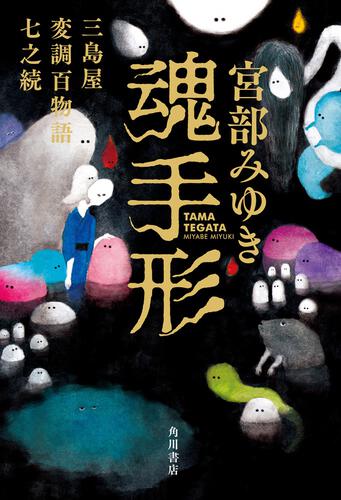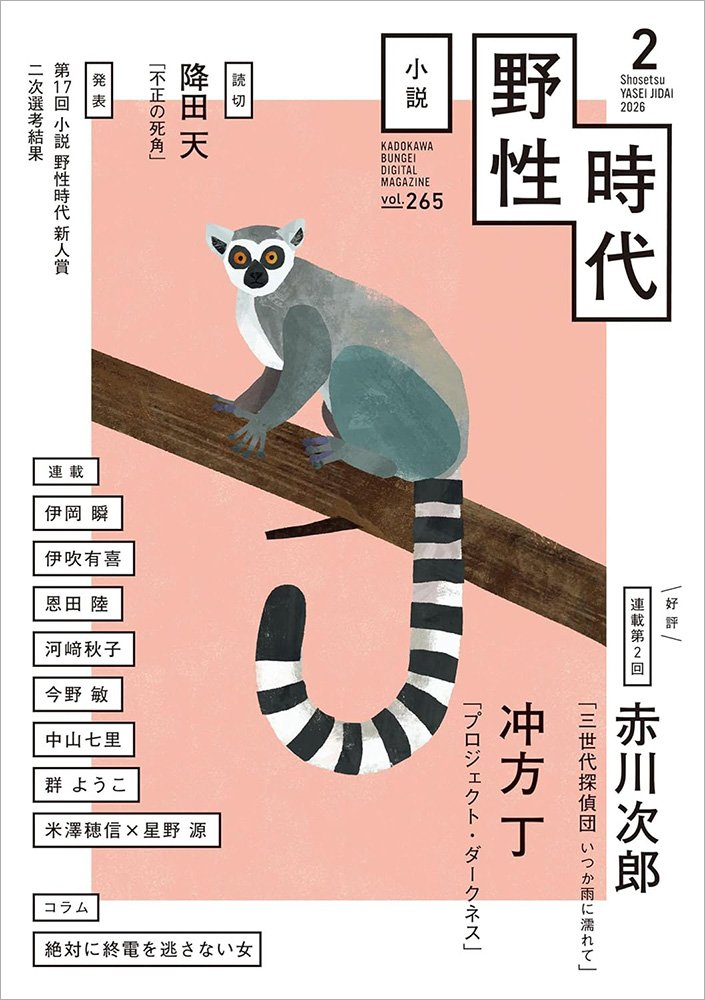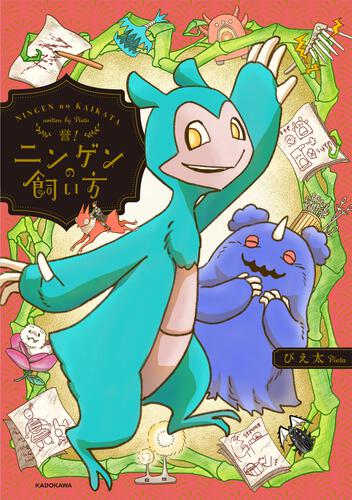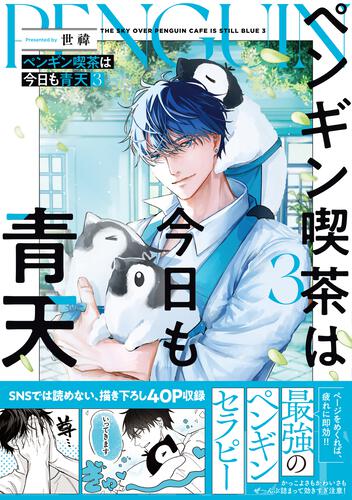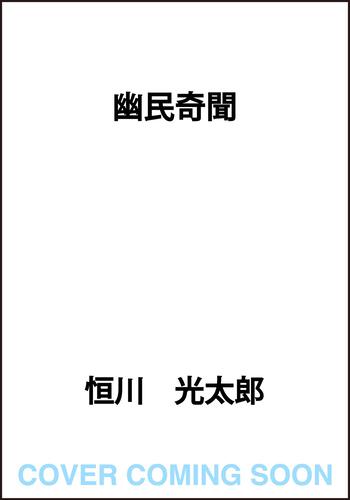対談 「本の旅人」2018年5月号より

《『あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続』刊行記念対談 宮部みゆき×若松英輔》稀代のストーリーテラー宮部みゆきのライフワークにして江戸怪談の真骨頂!
撮影:ホンゴ ユウジ 取材・文:朝宮 運河
江戸で人気の袋物屋・三島屋でくり広げられる〈変わり百物語〉。訪れる客たちは胸に秘めた不思議な話を、聞き手のおちかに語り出す——。宮部みゆきさんのライフワークにして江戸怪談の傑作「三島屋」シリーズ。その第五弾となる『あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続』が刊行されました。シリーズの大きな転機となった表題作など、珠玉の五作品を収録したこの新作について、批評家・若松英輔さんと宮部さんがたっぷり語り合いました。
読んでいて羨ましかった
宮部: 若松さんとは『読売新聞』の読書委員で二年間ご一緒していましたが、こうして自作についてお話しするのは初めてですよね。
若松: 送っていただいた『あやかし草紙』を真夜中に読んだんです。眠れなくなるんじゃないかと心配でしたが、読み終えてみるとまったく怖くありませんでした。文字は怖いことを追っていても、心は違うものを感じている。この作品も表層は怖いことが描かれていますが、底を流れる物語はじつに温かいですね。
宮部: ありがとうございます。怪談なのでまず怖いことは大切ですが、ただ怖いだけのシリーズにはしたくないなと思っています。
若松: 途中から今日の対談を忘れるくらい物語に引き込まれていました。宮部さんは書いていて、自分を物語が「通過」するという感覚はありませんか?
宮部: 締め切りが迫ってきて、どうしよう、何も浮かばない、と悩んでいる時に、すーっと何か降りてくる感じを受けることはありますね。
若松: 「書く」という行為は、大別すると言葉を「宿す」か言葉を「使う」かだと思うんです。宮部さんは明らかに前者のタイプだと思いました。この物語では人が思わぬ形で生かされたり命を落としたりする、世界のありようそのものです。そのありさまを描く作家は多くいます。しかし、その理というべきものを表現できるのは一握りの作家だけです。ここに宮部さんが多くの読者の心をとらえている秘密があるのだとあらためて思いました。
宮部: 私の好きなミステリやホラーは、ジャンルの歴史が長いので、物語の器がすでに整っているんです。そこにアイディアを盛っていけば、駆け出しの新人でもひとつの世界を作れる。そういうジャンルでデビューしたことも大きいのかもしれません。
若松: もうひとつの世界にふれることで、人は新たに生まれ変わります。これは「三島屋」のテーマそのものですよね。おちかが未知の世界にふれて生まれ変わるような体験が、現代人にも必要なのではないでしょうか。また、宮部さんはそういう言葉による新生の契機を提供する、という仕事をしているんだ、と今回あらためて気がついて、つくづく羨ましかったんです。
宮部: そんなに褒めていただけるなんて(笑)。今日は嬉しくて眠れません。
凝っていたものが現れる瞬間
若松: この作品では「聞く」という行為が重要な意味を持っています。おちかは三島屋にやって来た客の話を、毎回ただ座って聞く。どうしてこういう設定が生まれたのですか。
宮部: 百物語の枠組みを借りた小説というのは、岡本綺堂をはじめ、先例がいくつもあります。ただ聞き手に聞かなければならない切実な理由があるという作品は、これまで多分なかった。過去を背負ったおちかという主人公は、そうした発想から生まれました。
若松: 怪談を聞くごとにおちかの心が癒えていく、という展開もじつに興味深いです。
宮部: ある種のセラピーですよね。江戸時代、百物語は娯楽であると同時に、見聞を広めるための教養講座でもあったそうなんです。当初はずっとおちかに聞き手をさせておくつもりだったんですが、幸い成長してくれて(笑)、このまま続けさせるのも無理があるので、この巻で一区切りということにしました。

若松: 発信の機会が増えている反面、現代人は聞くことがとても苦手になっている気がします。相手がいて場所があれば、対話が成り立つというわけではない。聞くにはそれなりの準備や心構えが必要です。その微妙な間合いを、この作品は見事にとらえている。
宮部: 本題を語り出すまでには、お茶を飲んだり雑談をしたり、といういくつかの段階を踏まないといけない。どういう形で怪談に入ろうかという部分で、毎回工夫しがいのあるシリーズです。
若松: 胸にしまわれた言葉を宮部さんは「凝った」と表現している。この感覚にはっとなったんです。人は自分が話したいように話しているつもりでも、その奥に「凝った」ものが潜んでいて、それは語ることでしか現れない。意図できないものなんですね。
宮部: 夜中タクシーに乗っていて、どうしてこんなに深い話を、運転手さんにしているんだろう、と思うことがありますよね(笑)。凝ったものが溶け出す瞬間っていうのは、私たちの日常生活のなかでも実際にある。このシリーズは私たちにとって「語る」ということがどんな意味を持つのかを描いているのかな、と思います。
若松: それと全編を通じて、見えないものが大きな働きをしていますね。見えるものは表層に過ぎなくて、その向こうには人を動かす力がある。第一話「開けずの間」がまさにそうで、当人のあずかり知らぬところで不幸にされたり、守護されていたりする。
宮部: 怪談ですからなるべく理に落ちないように、ということは意識しているんです。分からないことは分からないまま、解釈はつけない。「開けずの間」に出てくる行き逢い神にしても、三話目の「面の家」のお面にしても、神様なのか物の怪なのか分からない。人間に分かるのはここまで、というラインが、当時はあった気がするんですね。
現代人が失ってしまったもの
若松: 語られた出来事が正しいのか、間違っているのか、登場人物たちは判断しません。そこも重要なポイントだと思いました。昨今はこれが正しい、こうすべきだという正論が世間を覆っていますが、この作品にはそれがない。すべてが存在を許されている。
宮部: その曖昧さこそが江戸怪談の面白さであり、日本文化の懐の深さだと思います。当時、物の怪と神様は近しい存在で、神様の中にはそそっかしい奴も、ずる賢い奴もいる。これは京極夏彦さんの作品で読んだのですが、昔の人は、イケニエを要求するような悪い神のことを「猿神」と呼んだんだそうです。お猿さん程度の神、というニュアンスですね。そういう日本的な宗教観は、なるべく尊重していきたいと思っています。
若松: 江戸時代に比べると、現代はずっと便利で進歩していると人は思い込んでいます。でもその分失ったものもたくさんある。たとえば第二話「だんまり姫」には、あやかしを呼ぶ不思議な声が出てきますね。
宮部: 「もんも声」ですね。物の怪が寄って来てしまうので、その声を発する少女は集落にいられなくなってしまう。
若松: 日常の言語が絶対だと信じている人には、「もんも声」なんて価値を見いだせないでしょう。でもそれが見えない世界への扉になっている。僕らはその扉をなぜ手放してしまったのか、真剣に考えないといけません。
宮部: お姫様がなぜ口を利かないのかという謎解きものにするつもりが、なぜか語り手の女性の一代記になっちゃって(笑)。どんどん長くなるなあと思いつつ、架空の藩や漁村を作りあげていくのは楽しい作業でした。
若松: この本の五篇には、死んでも人は終わらない、思いは残り続けるという豊かな世界観が共通して描かれています。それを取り戻すことができれば、現代人の生き方は大きく変わるはずです。よく小説は作りものだから不要だという人がいますが、とんでもない話です。真の物語は、思想や哲学では扱えないものを私たちに届けてくれている。むしろ、現代はあまりに思想を重んじ過ぎました。
宮部: ここ数年、物語に触れる喜びがやや伝わりにくくなっている気がして残念です。物語に日常的に触れることで、心にちょっとしたゆとりや張りが生まれるんだけど、その楽しさがなかなか伝わらない。ネットに物語的なものがたくさんあって、次々と更新されてゆくので、ホントの「作り話」の面白さが伝わりにくくなっているのかもしれません。
大きな絵を鑑賞している感覚
若松: 『あやかし草紙』を読んでいて、巨大な絵の一部分を鑑賞しているような気がしたんです。これまで書いてきた作品が繋がっているという感覚はお持ちですか。

宮部: 昨年デビュー三〇周年で既刊本をずらっと並べてもらったんですが、やっぱりひとつのお店だな、という気がしました。よく「時代小説と現代小説ではどう切り替えるのか」とお尋ねを受けるんですが、切り替えるという意識はないんです。恋をする切なさや、親しい人と別れるつらさは、現代でも江戸時代でも変わりはないだろうと。最近だと時代小説の方が、むしろ現代的なテーマを扱えたりという面もありますし、時代を超えて繋がっているんでしょうね。
若松: 描かれる時代や題材は違っても、それが大きな絵に結びついていく感覚がある。これを感じさせる作家を一流と呼ぶような感じがしています。海外でいうとドストエフスキーやバルザックがその典型です。
宮部: あわわわわ(笑)。冷や汗が出てきちゃう。
若松: 冗談じゃなく、これこそが今と共にある文学だと感じました。「あやかし草紙」「金目の猫」の二篇でおちかに転機が訪れますが、シリーズは今後どうなっていきますか?
宮部: 百物語の聞き手が交替して、次巻からは富次郎タームに入ります。富次郎は三島屋の次男坊で、将来を決めかねているモラトリアム青年。そんな青年が聞き手になることで、進むべき道を見つけていくという展開になる予定です。先日シリーズ五冊をあらためてふり返って、あら、意外とバラエティ豊かじゃないと、再発見したんですよ(笑)。まさか九九話書くことになるとは夢にも思っていませんでしたけど、なんとか古希を迎えるまでに到達できたらいいなと思っています。今後もゆるゆると書き継いでいくので、気長にお付き合いください。
若松: もちろんです。すでに四分の一を過ぎましたからね。到達したら、ぜひお祝いさせてください。