本日より配信開始の「文芸カドカワ」2018年5月号では、土橋章宏さんの新連載『いも殿さま』がスタート!
カドブンではこの新連載の試し読みを公開いたします。
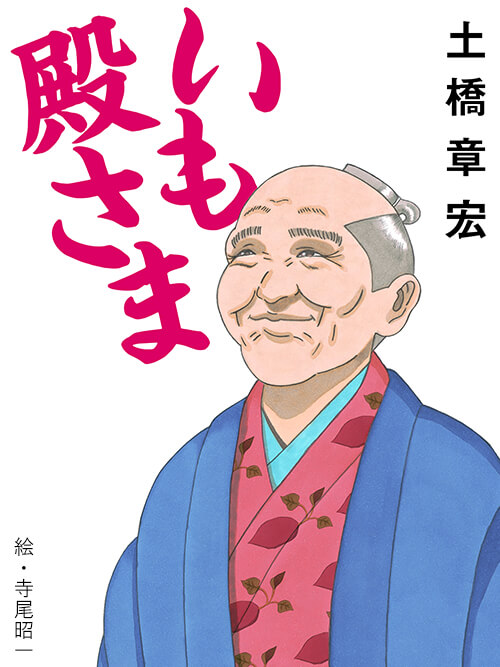
困窮にあえぐ銀の産出地、石見の新代官に就任したのは無類の菓子好きのそろばん名人・井戸平左衛門。甘党代官による地方改革が始まる!
一
享保十六年(一七三一年)、夏――。
勘定所で勤めを終えた井戸平左衛門は、江戸城をくだったあと、神田明神のほうに向かってのっそり歩き出した。小太りの両肩の真ん中に乗った丸顔は春風駘蕩たる穏やかさに満ちている。あたりに発する威圧もなく、目立つところもまるでない。争いごととはまず無縁の相である。
その後ろを歩いているのは井戸家用人の尾見藤十郎であった。こちらは主人に比べ落ち着きがなく、いかにも早く帰りたいといった顔をしている。
「殿。今日も行かれるのですか」
「うむ。いい旬菜が入ったらしい」
「……そうですか」
日も暮れてやっと涼しくなってきた風を頰に感じながら、二人は半刻(約一時間)ほど歩き、下町の曲がりくねった路地に入ると、その奥に食事処〈松葉〉はあった。
「今日も頼むよ」
「へい、いつものですね」
平左衛門が一番端の、なじみの席に腰を掛けると、板前の手が動き始める。その日出す料理は、遠州出身の板前が客の顔色とその日入った旬のものを考え合わせて決めるらしい。
「どうぞ」
板前はごとっと深皿を置いた。丸い皿の真ん中に里芋が鎮座し、脇にいんげんが添えられている。
「ほう。里芋の煮っ転がしか」
井戸平左衛門はつぶやくと、里芋を箸で崩した。一瞬、ほわっと湯気が上がる。芋を煮汁に浸し、平左衛門は口に運んだ。
「よい出汁だ」
崩れた里芋がほろりと汁に溶け、花のように開いていた。
「鰹節のいいのが入りましてね」
答えた板前があるかなきかの口の動きで微笑む。きっと、食材よりも出汁を褒められたほうが嬉しかったのだろう。藤十郎には味が薄すぎてよさがよくわからない。もっと塩味が強いほうがよかった。
店の他の客は町人ばかりである。武家の平左衛門は異色の存在だったが、みな気にもとめていなかった。威張ったところがまるでないし、この好々爺が何か事を荒立てるとも思えないのだろう。
平左衛門のほうも、城での勤めが終わったあと、うまい店で夕餉を取るのがなによりの楽しみなのである。騒がすつもりもない。唇に微笑みをたたえ、行儀よく芋を口に運んでいた。
(早く食べればいいのに)
若い藤十郎はもっと揚げ物の多い、若い女中のいるような賑やかな店に行きたかったが、そこは用人たるゆえ、主人に付き添わねばならない。平左衛門はもう還暦の年寄りなので、脂の多いものはあまり好まない。
早く帰って水茶屋にでも行きたい――。
看板娘たちがそろっているだろうし、場所によっては連れ出し料を払って給仕の女を外へ連れ出すこともできる。若い藤十郎の体はむずむずしていた。
そんな気持ちも知らず、平左衛門はにこにこと里芋を少しずつ口に運んで大事そうに頰張っている。栗鼠が頰袋にどんぐりをためているかのようだった。
藤十郎は早々と鱚の煮物を食べ終え、酒杯を重ねている。
「こうして何度も嚙んでいるとな、味がもう一度変わるのだ。喉の奥でほのかな甘みが出てくる」
「へえ、そうでございますか」
早く飲み込めばいいのに、あなたは牛ですか、と思いながら待っていると、平左衛門はようやく最後のものを注文した。
「亭主。そろそろあれを」
「へい。今日はこれで」
知らぬ人が聞いたらなんだかわからないようなやりとりのあと、皿に載った餅のようなものが出てきた。薄茶色の濁った餡がかかっている。
「なんだこれは」
平左衛門が嬉しそうに目を光らせると、
「餡大福にございます」
と板前は答えた。
「ほう、大福か。なるほど」
平左衛門は待ちきれないといったようすで、箸で切り取り、口に運ぶ。
「ほうううう……。これは甘いな」
「高松の砂糖を使っております」
「たまらぬ」
平左衛門は大きく顔をほころばせた。
(大福なんてただでさえ甘いのに、餡がかかってるのか)
辛党で酒が好きな藤十郎は少し胸が悪くなった。だが平左衛門は大福をぺろりとたいらげ、出された熱いほうじ茶を味わうように飲んだ。
「このしめの茶もいい」
感慨深げに目を閉じている。
「殿、そろそろ」
藤十郎が言うと、平左衛門は頷き、
「勘定を頼む」
と、財布を出した。
「毎度ありがとうございます」
平左衛門の身元を知らされている小女が、やや緊張して釣りを返す。しまりのない顔の平左衛門とはいえ、勘定方でも地位のある幕臣がこんな下町の店に来ているのだから、無理もない。
「これ」
平左衛門がふと言った。
「なんでございますか」
北国生まれなのか、頰の赤い小女が蚊の鳴くような声で答える。
「釣りが二文、多い」
「あっ……」
「うまかったぞ」
にっこり笑うと平左衛門は銭を返し、財布をしまって立ち上がった。
「ありがとうございました」
小女が嬉しそうに言う。照れたのか頰はさらに赤くなっていた。
(まったく……。お人好しなんだから)
二文の釣りなんか、もらってしまえばいいのに、と思う。
だが、それが平左衛門であった。勘定方で三十年以上勤め上げたそろばんの腕はまず右に出る者がない。将軍吉宗から日頃の勤勉さを讃えられ、褒美に黄金二枚をちょうだいしているほどである。
だが、出世にはまるで縁がなかった。勘定方から上にあがるには、上役や茶坊主、位の高い旗本、奉行などにあらゆる付け届けや挨拶がいる。しかし平左衛門はまったく無頓着で、誘われた宴会もすべて断っていた。
「一生のうち食事をする機会は限られている。そのうちの一度をわざわざ人まかせのものを食べ、愛想笑いをするのはどうも気が進まない」とのことである。
しかし人の世のつきあいというのはある。藤十郎は何度も忠告した。うまく振る舞えば奉行になるのも夢ではない、と。
だが、決まって言うのは、
「私はそろばんが好きだ。一日中、そろばんだけ弾いていればよい。それこそが勤めよ。なのに上に行けば行くほど、よけいな気苦労が出てくる。そろばんにも触れられなくなるかもしれない。そんな勤めはたくさんだ」
ということだった。
仕える者にとってはなんとも甲斐がない殿である。
こんな無欲な年寄りの、たった一つの楽しみが食道楽であった。
とくに、甘いものに目がない。
すでに江戸中の菓子屋はすべて回った。饅頭に団子、大福餅に柏餅、白雪煎餅に長飴、落雁に白玉と白子、汁粉にぜんざい、甘酒、干し柿、甘葛、きなこ餅まで甘いものはすべて賞味し尽くした。
江戸にない菓子は、つてを頼って取り寄せたりもする。
「わしはな、甘いものさえあれば何もいらない」
と、平左衛門はよく言う。
そろばんを弾いて、うまいものを食う――。
なんとも単純だが、単純なだけに力強くもあった。
だがこの日の帰り際、平左衛門はふいに告白した。
「藤十郎」
「はい」
「わしも還暦だ。そろそろ勤めを辞め、隠居しようと思う」
「えっ。まだまだ勤められると思いますが」
藤十郎は意表をつかれた。幕臣の中には八十を超えてなお、のんびりと勤める者もいる。あまりにも勤めの評判が悪いと遠回しに上から隠居の勧告が来るが、そうでなければ引退は各自の判断である。
平左衛門はなにか重い荷を下ろしたような、清々しい顔をしていた。
「おつむは大丈夫なのだがな。足が弱っておる」
「足でございますか」
藤十郎は平左衛門の足を見つめたが、歩みは別におかしくない。
「城へ通うのはよいが、旅は厳しくなろう」
「旅、と申しますと?」
「わからぬ奴だな。自らの足で旅をしたいのだ。全国津々浦々の甘味処をな」
平左衛門が嬉しそうにくっくっと笑った。
(このつづきは、「文芸カドカワ」2018年5月号でお楽しみいただけます。)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
「文芸カドカワ」最新号は毎月10日配信です。
関連書籍

書籍週間ランキング
熟柿
2026年2月16日 - 2026年2月22日 紀伊國屋書店調べ
アクセスランキング
新着コンテンツ
-
試し読み
-
試し読み
-
文庫解説
-
試し読み
-
試し読み
-
特集
-
連載
-
連載
-
特集
-
文庫解説


























