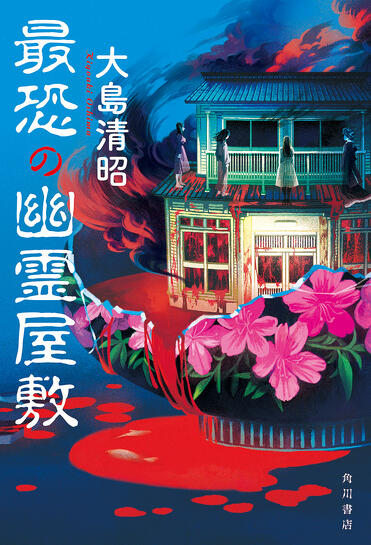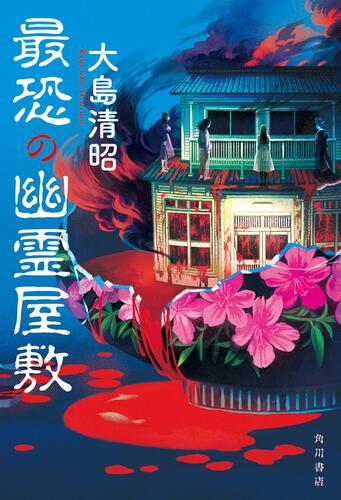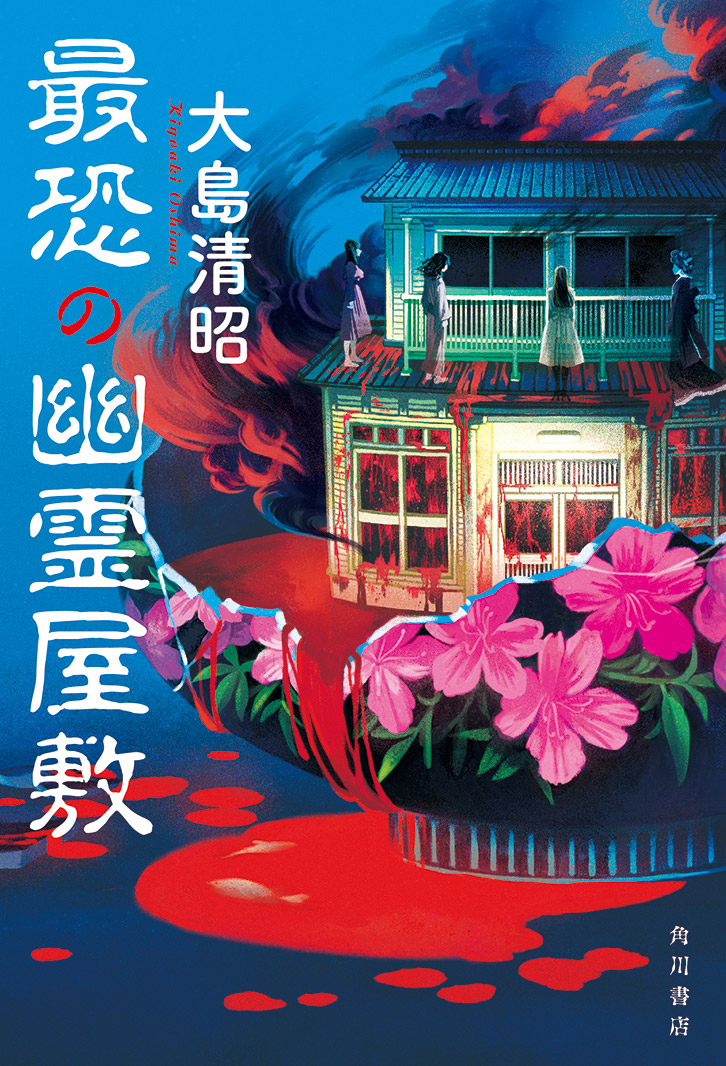取材・文:編集部
転落が止まらない、ジェットコースター級事故物件ホラー長篇『最恐の幽霊屋敷』が刊行された。著者は、背筋が凍る怪異譚にミステリの要素を絶妙なバランスで組み込んだ作風で注目される作家、大島清昭氏。小説作品としては4作目となる本書は、「家で読みたくないホラーミステリ」と呼ぶべき一冊になっている。本書やご自身について、担当編集者が著者にお話を伺った。
幽霊、妖怪、ホラーのそれぞれにある別の魅力
『最恐の幽霊屋敷』大島清昭インタビュー
――本作は、「最恐の幽霊屋敷」という触れ込みで貸し出された一軒家で相次ぐ不審死の調査を、探偵が依頼される場面から始まります。テーマやストーリーの着想はどこから得られましたか。
えっと、ご質問にストレートにお答えしてしまうと、完全にネタバレになってしまいますので、遠回りにお話しさせていただきます。
『最恐の幽霊屋敷』のプロットを考える直前、私は『
また、全体の着想は小学生の頃から好きだったカプコンのアクションゲーム『ロックマン』シリーズの影響を強く受けています。恐らくこの答えを聞いてもよくわからないと思いますが、作品を読んでいただくと私のお話ししていることがご理解いただけるかと思います。
――舞台となる栃木県は、大島さんご自身が生まれ育った土地でもありますね。知っている場所を舞台にホラーを書くことには、どのような良さや効果がありますか。
私は全く知らない場所を書くのは苦手ですので、自分の故郷やフィールドワークを行った地域、観光で訪れた場所などを舞台にすることが多くあります。というのも、あらかじめその土地のことを知っていれば、気候や地理的な状況、言語、生業、交通、信仰など細かな情報を調べる手間が省けるからです。例えば、『最恐の幽霊屋敷』に登場する幽霊屋敷の裏庭には稲荷の社がありますが、これは東北から北関東に見られる屋敷神の信仰で、現在でも目にすることができます。
――知っている場所を舞台にすることで困ったことはありますか。
知っている場所を舞台にして困ったことはないのですが、よく知っている場所だからこそ、フィクションを描く時に、現実的な縛りが出る場合があります。私は栃木県を舞台にしても、しばしば架空の市や町を登場させるのですが、実在する市町村との位置関係や規模などで悩むことがあります。登場人物が車で移動する際に、現実の栃木県と物語の中の栃木県では移動距離が微妙に異なるので、時間の経過を計算するのが厄介ですね。
――各章では、結婚間近の女性やオカルトライター、心霊番組のディレクターや元アイドル、ホラー映画監督など、さまざまな人物が主人公として登場します。仕事柄、怪現象に慣れている人物がいたり、周囲の誰よりもおびえている人物がいたり、怖がっていた人物が次第に怪現象に慣れていってしまったりと、人それぞれの感覚で怪現象を受け止めていく過程も読みどころだと思います。とくに思い入れのある人物はいますか。
非常に難しい質問です。というのも、特にどの人物にも思い入れがないからです(笑)。ただ、強いて挙げるとすれば、探偵事務所の事務員「
――大島さんのこれまでの作品では、『影踏亭の怪談』『赤虫村の怪談』に登場する「
特にありません。私は細かいキャラクターづくりやストーリーについては書きながら考えるので、登場人物の言動や思考については、ほとんど無意識に書いています。
――作中で登場するルポ『最恐の幽霊屋敷に挑む』には、数多くの怪異譚が書き連ねられています。ひとつひとつのエピソードが恐ろしいですが、すべてが「創作」なのでしょうか。なかにはご自身が体験したりこれまでに蒐集したりした「実体験」もあるのですか。
『最恐の幽霊屋敷に挑む』の内容だけではなく、作中で書いた怪異の起源に関するエピソードは「創作」です。しかし、作中で起こる怪異や幽霊のデザインについては、自分の体験やこれまでに様々な方から蒐集した「実体験」を参考にしています。例えば、作中には真夜中に玄関チャイムが鳴るのに外に出ると誰もいないという怪異や「ウズメさん」と呼ばれる特徴のある幽霊が登場しますが、これらは皆、身近な「実体験」が元になっています。
――本作では「最恐」を謳う幽霊屋敷が舞台となり、それがタイトルにもなっています。大島さんご自身も、家にまつわる恐ろしい体験をしたことはありますか。
家の中で不可思議なことが起こるのは日常茶飯事なので、「恐ろしい」とは思いません。
――大島さんはこれまで幽霊や妖怪の研究を続けてこられ、小説家としての作品はすべてがホラー作品です。幽霊や妖怪、ホラーといえば、多くの人が「恐ろしい」と感じるものですが、大島さんにとってその魅力は何でしょうか。
私にとっては、幽霊、妖怪、ホラーは、それぞれ全く別の魅力を感じます。
まず幽霊は研究の対象として魅力的です。死者が生前の姿で出現する現象は、世界中で見られます。それを文化として研究するか、実在の有無について研究するかは、文系理系などそれぞれの立場によって異なりますが、どちらにしても興味深いものです。日本では、民俗学、宗教学、歴史学、文学、社会学など、様々な分野からのアプローチがあり、これまで多くの先行研究が存在しています。近年では小山聡子さんと松本健太郎さんの編集された『幽霊の歴史文化学』(思文閣出版、2019年)といった優れた成果もあります。
次に、私にとって妖怪の最大の魅力は、種類の多さです。カウントの基準にもよりますが、その数は日本だけでも3,000種目以上です。しかも「肉吸い」のような恐ろしいものから「豆腐小僧」のような滑稽なものまで、幅広く存在しています。私は幼い頃からとにかく妖怪が大好きですが、それは博物学的な興味が大きかったと思います。あの頃は「妖怪図鑑」と「恐竜図鑑」にあまり差はありませんでした。
ホラーについては、恐怖を描くために、日常では忌避される闇の部分に真摯に向き合っている姿勢が魅力だと思います。それに斬新なネタやオチのある作品に触れると、全身が震えるような感動があるのも、魅力の一つですね。
――「最恐のホラー作品」と聞いて、思い浮かぶ作品はありますか。
う~ん、ホラー作品は好きですが、怖いとは思いません。現実に耳にする怪異の方が遥かに怖いので。ですが、ご質問を受けてぱっと思い浮かんだのは、スティーヴン・キングの『IT』です。私は小尾芙佐さん翻訳の文春文庫で読みました。『IT』が思い浮かんだのは、小学生の頃の体験が影響しています。当時、父親がよく洋画をレンタルビデオ店で借りてきて、家族で視聴していたのですが、その冒頭の作品紹介の時、トミー・リー・ウォーレス監督のテレビドラマ版『IT/イット』(1990年)の映像が何度も流れたのです。子供心にピエロのペニーワイズの映像が衝撃的で、その印象がずっと忘れられずにいます。
――本書『最恐の幽霊屋敷』の一番の読みどころを教えてください。どのような人に読んでほしいですか。
やはり最後に探偵が謎解きをするシーンです。とはいえ、本書はどちらかというとホラー色が強めなので、普段はミステリを読まない方々にも楽しんでいただければ幸いです。
――今後書きたい作品やテーマ、題材などがありましたらお聞かせください。
これからもミステリを書き続けていきたいと思います。以前に別のインタビューでも申し上げたことですが、いつか幻想文学とミステリを融合したような作品が書いてみたいですね。それから、特撮が本当に好きなので、許されるのならば怪獣文学にも挑戦したいです。
――ありがとうございました。
書籍紹介
最恐の幽霊屋敷
著者 大島 清昭
発売日:2023年07月21日
転落が止まらない、 ジェットコースター級の事故物件ホラー長篇!
「最恐の幽霊屋敷」という触れ込みで、貸し出されている一軒家がある――。
幽霊を信じない探偵・獏田夢久(ばくたゆめひさ)は、屋敷で相次ぐ不審死の調査を頼まれる。婚約者との新生活を始めた女性、オカルト雑誌の取材で訪れたライターと霊能者、心霊番組のロケをおこなうディレクターと元アイドル、新作のアイデアを求める映画監督とホラー作家。滞在した者たちが直面した、想像を絶する恐怖の数々と、屋敷における怪異の歴史を綴ったルポ。そのなかに、謎を解く手掛かりはあるのか?
幾多の怪異と死の果てで、獏田を待ち受けるものとは――。
詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/322212001341/
amazonページはこちら