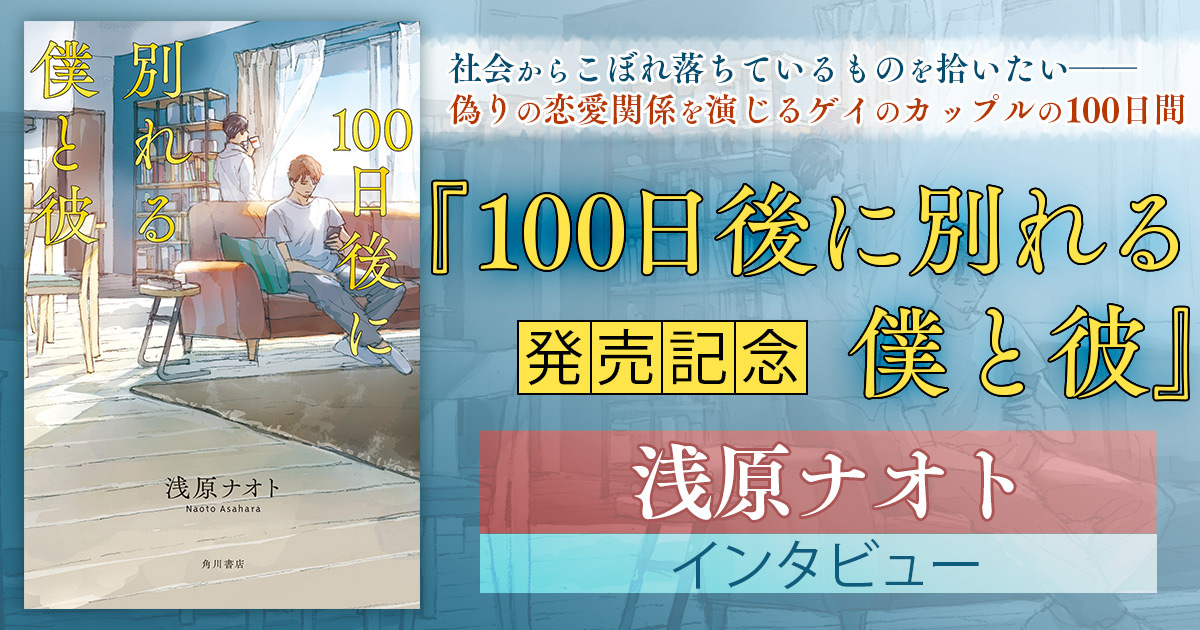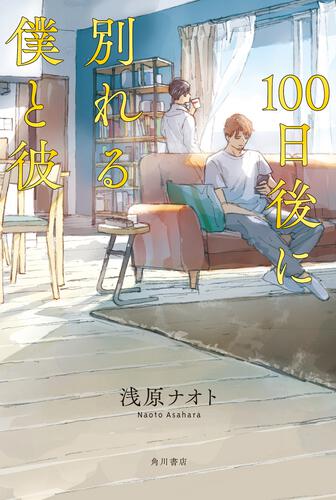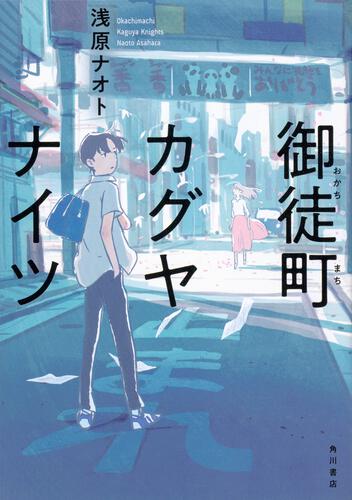取材・文:甲斐荘 秀生
2016年にカクヨムで発表した『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』が2018年に書籍化されてデビューし、その後も『御徒町カグヤナイツ』『#塚森裕太がログアウトしたら』など多彩な作品を発表してきた浅原ナオトさん。5月19日(5/17搬入以降順次発売)に発売の最新作『100日後に別れる僕と彼』では、すでに関係が終わっているゲイカップルと、それを知らずに彼らのドキュメンタリーを撮影する女性映像ディレクターの撮影を通じた交流が描かれます。浅原さんに、本作への思いを伺いました。
社会よりも、個に向けて書きたい
――浅原さんが小説を書く上で大切にしていることを教えていただけますか?
浅原:私は「社会に向けて」ではなくて「個に向けて」小説を書きたいですし、社会のことではなくて個のことを書きたいんです。昨今では社会のことを書くと偉いみたいな風潮があるけれど、社会を書こうと思って社会を書くと、絶対に何かがこぼれ落ちる。ですから今作に限らず、執筆している時には「こぼれ落ちているものを拾いたい」という意識がどこかにありますね。
この物語でも、書いているうちにやはり「社会を相手にすることで、こぼれ落ちる個」というのは中心的なテーマになっていきました。
映像ディレクターの茅野志穂は、はじめのうち春日佑馬と長谷川樹を「ゲイカップルという属性」として撮っていきます。でも「ゲイカップル」と一括りにしても、一人ひとりにはそれぞれの考えがあって、個性がある。ゲイカップルである前に人であるわけですが、もしかしたら撮られる側である佑馬にもそれが見えなくなっている。そのさまを描くことは本作の強いテーマの一つになりましたね。
――今作の「すでに関係が終わっているゲイカップルを取材したドキュメンタリー」というアイデアは、何がきっかけで生まれたのでしょうか?
浅原:これはアホすぎて恥ずかしい話なんですが、『Mr.&Mrs. スミス』という映画がありますよね。僕はなぜかあれを「もう別れているカップルが、無理やり仲のいいカップルのふりをする」という話だと勘違いしまして、「それの同性愛バージョンをやったら面白いんじゃないか」というのがそもそもの発想なんです。
だから、本作を読んで真面目な印象を持つ読者の方は多いと思うのですが、はじめに僕が持っていたイメージではもっとコメディ寄りだったんです。「取材中に相方が嫌そうな顔をしたら、見えないところからつねる」みたいなシーンが入ってきたりとか(笑)。
――なるほど。コメディタッチのイメージでスタートした作品が、文芸的なある種のテーマ性を持った作品へと変わっていったのはなぜだったのでしょうか?
浅原:そこは「同性愛の」という設定だけで、自然となんらかのテーマが乗ってしまいますよね。さらに「偽りのカップル」を演じないといけない物語上の都合を考えた結果「ドキュメンタリーの撮影」という設定になったので、その時点でもう社会的なテーマが乗ることは確定します。
だったら、「人を〝属性〟で判断する多様性」と「人を〝個体〟で判断する多様性」の噛み合わなさを書きたいな……ということで最終的に作品になったプロットが出来上がりました。
――普段から「○○の同性愛バージョン」という発想をすることは多いんですか?
浅原:例えばお医者の兼業作家さんは何人もいますが、そういう人が何か小説を読んだときにはきっと「これが医者だったら面白いな」という発想をすると思うんです。書店員だったら、「これが本屋で起きたら面白いな」と考えてみたり。
同じように、自分はゲイなので、何らかの作品に触れたときに「これがゲイだったら面白いな」って考えてしまうんですよね。ただ「○○+ゲイ」と設定を足しただけだと面白くなくて、「これ、イケるな」と感じるのは組み合わせに必然性が出てきた時です。本当に面白くなりそうな組み合わせってそんなに見つからないですけどね。
――本作は小説サイト「カクヨム」で連載されていましたが、Webで連載した原稿から書籍化するにあたり、どんな観点で加筆・修正しましたか?
浅原:この小説は荒唐無稽なシチュエーションではありますが、「それはねえよ」と読者に思われてしまったら全体の読み口が変わってしまいます。ですから編集さんと話し合いながら、不自然だったところを削ったり、強引感があるところをうまくつないだりと、リアリティを出すために細かいところに配慮して仕上げていきました。
それと、この作品に限った話ではないですが、私はどうしても語りすぎる傾向があるのでそういった部分を削っています。書いている時は登場人物に憑依しているので、彼らの心理を逐一文章で説明してしまったり、頭の中のイメージが伝わっているかを気にしすぎて、あまり必要ない描写を入れてしまうので、初稿ではどうしても冗長になるんですよね。
ですから今作では、Web連載では先出し優先で書いて、後から冗長な部分を削っていくような作業をやりました。そういうプロセスができるので、Webで一回書くのはすごくいいと思います。
――自分の作品を客観視するタイミングが得られるわけですね。逆にWeb版より膨らませたところはありますか。
浅原:志穂の先輩である尚美の描写はWeb版より膨らませています。Web版での尚美は、物語が始まった時点で産休に入っていて、志穂たちが赤ちゃんを見に行く時にはじめて登場します。それだと展開として唐突なので、書籍にするにあたり、物語のはじめのほうで一度登場させて会話させることで、尚美のキャラクター性を明らかにしています。Web版の尚美の赤ちゃんを見に行くことになるくだりは僕も「ちょっと強引かな」と思っていたんですが、編集さんからも「違和感がある」とコメントをもらえたことは、作品を仕上げる上で非常に良かったと思います。
3つの視点から描かれる物語
――本作は基本的に、撮影されるゲイカップルの片割れ・春日佑馬の立場と、彼らを撮影する映像ディレクター・茅野志穂の立場のふたつから描かれています。さらに撮影が始まってからは、各章の冒頭に、物語の最後で放映されたのであろう「映像作品の視点」が加わります。
この3つの視点から物語を描いたことには、どんな意図があったのでしょうか?
浅原:単純に本作は、視点がスイッチしていったほうが面白くなると思ったんです。「仲睦まじそうなゲイカップルが、本当はすでに関係が終わっている」というシチュエーションは、「表」と「裏」の両方から見えないと面白くないですよね。
「裏側」に関しては撮影されている佑馬の視点から簡単に見えますが、「表側」をどう書こうと考えた時、外側に「カメラ」の役が必要になります。「外側のカメラ」をどう設定しようかと考えて思いついたのが、映像ディレクターである志穂というキャラクターです。
――しかし物語の中で、志穂は徐々にふたりの本当の関係を知っていくことになります。
浅原:そうですね。志穂の視点が表から裏へと移っていくのは予定通りです。ただ予定外だったこととして、樹が最初の撮影から結構ふてくされてしまいました。書き始めてみると、樹が「俺たち、ラブラブカップルでーす」みたいに演技するの違うよな、と思ってしまったんですよね。なので「仲むつまじいゲイカップルを演じるふたり」がそもそもあまり見られず、二人の偽りの姿を捉えるカメラとしての志穂の役割はそこまで機能しませんでした。
――なるほど。佑馬と樹の実際の関係を知るにつれて、志穂が表の視点から裏の視点へとシフトしていったから、ずっと表で固定されている「映像作品の視点」が必要になったわけですね。
浅原:結果的には各章の初めに入る「映像作品の視点」が表を書き、その裏を志穂と佑馬それぞれの視点から書く形式になりました。それは樹が思ったより演技をしてくれなかったことに加え、志穂の背景をいろいろ考えると自然と人間味が出てカメラに徹することにはならなかったというのもあります。ただ、志穂が「カメラに近い視点から徐々に裏側へと入っていく」感覚はちゃんと書けたと思います。最初から最後まで表と裏が分かれたままだと物語として何の意味もないので、最後には「映像作品の視点」も含めて表も裏も何もない感じにしたかったのですが、その流れも上手く作れたと思います。
――その他、書いていて楽しかったシーンはありますか?
浅原:「野良猫と通り雨」と題したラストの部分ですね。僕自身も一番好きなシーンですので、ぜひ読んでもらいたいです。次点は、「101日目」にあたる日に佑馬がある決着をつけるシーンで、こういった決着のシーンは基本的に好きです。
小説は基本的に、後ろにいくに従って、読者の共通理解が出来ているから説明が要らなくなっていきます。はじめのほうはどうしても「樹はこういう人間だよ」「このふたりはこういう関係だよ」ということをどう入れるかを考えないといけないので、ある種工業製品を造っている感覚があって、少し楽しさが薄れる。だから後のほうが書いていて楽しいですし、楽にもなっていきます。
――本作が書店に並び始める5月17日は、国際的な「多様な性にYESの日」でもあります。多様性をめぐる社会の流れについて、自身もゲイであることを公表している浅原さんは何を感じていらっしゃいますか。
浅原:いま世間で言われている「多様性」は、「属性差」のことだと思います。いろいろな種類の魚が集まって水族館ができたから、この水族館は「多様性」があるよね、という形で語られていますよね。
そこで見逃されがちなのは、多様性には当然「個体差の多様性」もあることです。個体差がある以上は、属性差だけで考えていったら絶対に取りこぼしが出てくる……ということはぜひ伝えたい。
属性に対する配慮は、属性の「あるべき姿」を定義しないと絶対できません。「子供はピーマンが嫌いだよね」という前提があるから、「給食からピーマンを抜こう」みたいな話になるわけですが、そうすると今度はピーマンを食べたい少数の子が悲しむ。
そういうことが世の中のいろいろなところで起きているし、特にいわゆるLGBTに関する話ではすごく多いんです。
――なるほど。今作の中でも「暑がりな熱帯魚」という比喩が印象的でした。
浅原:属性のあるべき姿を定義して、そこに合わせた配慮をすることが必要ないとは言わないし、逆にそういう形をとらないと「配慮する」こと自体がきっと不可能なのでしょう。でもその上で、結果的に取りこぼされてしまう人や、全然別の方向を向いてしまっている人は必ずいる。
だから「属性ばかり見ていると、原理的に絶対に取りこぼす」ということ、属性として扱う限り「誰一人取りこぼさない」というのは嘘だということを、分かった上で発言や行動してほしい。「30人中28人の子供が喜ぶから、給食からピーマンを抜く」という選択肢はあり得るでしょうが、その時に「けれども、残りの2人が悲しんでいる」ことは忘れないでほしいんです。
『100日後に別れる僕と彼』の登場人物はそれぞれの道を歩みますが、だからこそこの物語には意義があるのだと私は思っています。この物語を読んだ読者の方も、誰の意見が正しいかを考えるより先に、まずはただ「色々な考え方の人間がいる」ということを受け止めてもらえると嬉しいです。
プロフィール
浅原ナオト(あさはら・なおと)
2018年、同性愛者の少年とオタク女子の交わることのない恋愛を描いた青春小説『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』でデビュー。同作は「腐女子、うっかりゲイに告る。」のタイトルでドラマ化、また「彼女が好きなものは」のタイトルで映画化され話題となる。他著作に『今夜、もし僕が死ななければ』『余命半年の小笠原先輩は、いつも笑ってる』など。
書籍情報
100日後に別れる僕と彼
浅原ナオト
四六判・上製・272頁
定価:1,870円(本体:1,700円)
発売日:2023年5月19日(※5/17搬入以降順次発売)
愛を撮る者、愛を偽る者、愛を捨てきれない者、様々な想いが交錯する100日間。
自治体に導入されたパートナーシップ制度を利用したことで受けたインタビューの様子が萌えるとSNSで広まり、世間の注目を集めることになった春日佑馬と長谷川樹のゲイのカップル。一躍時の人となったふたりに、映像制作会社のディレクター・茅野志穂が、性差別問題啓発のドキュメンタリー制作のため、のべ100日間にわたる長期取材をすることになった。ところが、佑馬と樹の関係はすでに破綻していた。しかし佑馬はドキュメンタリーの意義を感じ、あえて取材を受けることにしたのだった。当初取材を渋っていた樹だったが、佑馬に説得され、二人はカメラの前で仲のいいカップルを演じることに。一見、順調に進む取材。しかし、隠しきれなくなったふたりの溝が徐々に姿を現し始め、取材は破綻に向かい……。「私は何を見ていたのか、何を撮っていたのか」、志穂はカメラを通し彼らと向き合ってきた己の姿勢に重大な間違いがあることに気づき、もう一度カメラを向けることを決意するのだった……。
https://www.kadokawa.co.jp/product/322211000098/
amazonページはこちら
こちらもオススメ
▼WEB小説サイト「カクヨム」の活用術を語った姉妹記事。
https://kakuyomu.jp/info/entry/beforedebut_interview_vol.3