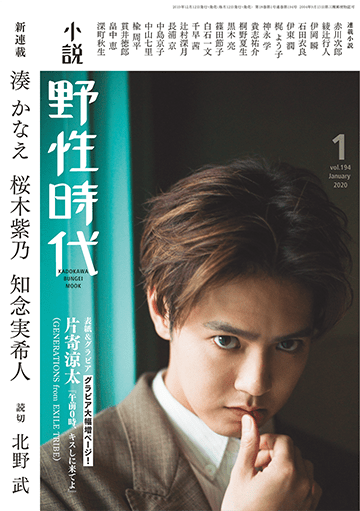著者である桜木さん自身が、「『砂上』は、書けても恥、書けなくても恥でした」とコメントを寄せた本作。作家デビュー十周年記念作品であり、書くことに取り憑かれ、作家へと変貌を遂げていく女性の物語とあって、どこか桜木さんご自身を重ね合わせてしまいます。桜木さんが自らをさらけ出し描いた渾身の一作について、お話を伺います。
―― 新作『砂上』は、小説を書く女性が主人公ですね。北海道・江別に住む柊令央は四十一歳。一人で倹しい生活を送る彼女の元に、東京から小川乙三という編集者がやってきます。乙三は令央が応募した原稿を読んだといい、彼女に小説を書くように勧める……。この物語の出発点はどこにあったのですか。
桜木:KADOKAWAさんから二〇一一年に『ワン・モア』という小説を出しましたが、その頃からずっと担当者と「次は長篇で何を書こうか」と話していたんです。そのなかで、「これは実話なのではないかと読者に邪推されてもいい話はどうか」となりました。二〇一三年、『ラブレス』で島清恋愛文学賞をいただいた頃に、「そろそろ私たちの鬼子をやろう」ということで連載の準備を始めたんです。
――確かに桜木さんのプロフィールを知らない方が読んだら、これは作者の自伝的小説なのかと思いそうです。それにしても、小説家が小説家を書くというのは大変だったのではないですか。自分の方法論を晒すことにもつながりますし。
桜木:そうですね。しかも、これはデビューする前の話なんですよね。書き手が出てくる小説は今後も書くかもしれませんが、デビューするかどうかという話は一生に一度しか書けない気がします。
――令央は父の顔を知りません。三年前に離婚して実家に戻り、母ミオと一緒に暮らしていましたが、ミオは一か月前に死去。令央には二十五歳の妹、美利がいますが、実は彼女は令央が十代の頃に密かに産んだ娘。令央は生前のミオとも、現在の美利とも、良好な関係であるとはいえませんね。
桜木:女の人の話を書きたかったんです。ただ、女三代の話ということはあまり意識していませんでした。最初、美利が令央の娘だということは物語の最後のほうで明かそうかとも思ったんです。でも、令央自身がその事実に惑わされる人ではないので、手持ちの札は早めに切ることにしました。あいかわらず感情の薄い人たちの話になっていますね。
――令央が応募した原稿は、母との生活が書かれたものでした。乙三はそこに「この人は書かなきゃいけないものを持っている」と目をつけたわけです。
桜木:実は、連載の時には母と娘の憎しみあいや葛藤も書いていました。単行本にする際にそこをもっと際立たせるという案もあったんですが、私自身が面白く書けない気がして。これはそういう母娘関係の話ではないんだと思い、改稿しました。女同士の確執といった話は、私の中でリアルではなかったんです。 令央が小説を書いているのも、大きなことを言いたいわけじゃないんです。それは私が小説を書く時も同じです。ただ、人間に対しての考え方が間違っていないかどうかを知りたいだけなんです。こういう場合にこう考えて、こう行動するのは間違っていないかどうかを知りたい。
――つまり令央が小説を書くのは、無意識のうちに母との関係をよく考えたいという衝動があったからなのかもしれませんね。この柊令央とは、どういう人物をイメージしていましたか。
桜木:鈍いんでしょうね。小説以外のことには鈍い、ということです。書くことに意識がいってしまっているから、生活においても、人の気持ちを思いやるという点においても、あまり得意とはいえないと思うんです。私も人の気持ちを考えるのが苦手です。ひとえに鈍いから書き続けられたのかもしれません。小説のことしか考えていなくて、生きることに鈍感。すごく幅の狭い人間です。原稿を書けなくなったらどうしようということしか考えていなくて、「もっと他に考えることがあるだろう」と、人から指摘されなければ分からないんです。
――令央はビストロで働く僅かな収入と、元夫から振り込まれる慰謝料で、合わせて月十一万円ほどの倹しい生活を送っています。カツカツですよね。
桜木:原稿を読んだ他の編集者からも、「こんな収入で暮らせるんですか」と訊かれましたが、令央には母が遺した家があるので暮らせます。カツカツではあるんでしょうけれど、令央は気に病めない。それも鈍いからなんでしょうね。
――他の人物にも奥行きがありますね。美利は精神的にも自立している。美人ですがそのことを鼻にかけている様子もない。令央の元夫やその新しい相手が令央の存在を鬱陶しく思っているのも生々しく伝わってくるし、他にもビストロの店主とその母親の言動も人間臭くて……。
桜木:登場人物に名前と性格を与えた時、物語の中で間違いのない言動を書きたい。元夫の嫌な感じは、書いていて楽しかったですね(笑)。美利に関しては、令央が浮世離れしているぶん、生活力のある人になりました。この環境で育ったら、こういう人になるだろうなという、ひとつのケースです。宝塚の男役っぽくて、店長として勤務しているカラオケ店ではお客さんの女子高生に「キャーッ」と言われるような存在ですが、本人は気に病めない。彼女は令央に「被害者面している」「お花畑にいる」などと厳しいことを言いますが、自分も彼女にそういうことをはっきり言われたいです(笑)。
編集者と 小説家の卵との応酬
――令央が小説を書く過程も丁寧に描かれます。乙三のアドバイスが印象に残りますね。「ひとりよがりの一人称」ではなく「三人称一視点で」書けとか、「大嘘を吐くには真実と細かな現実が必要」「フィクションにできなければただの自己憐憫です」などなど。
桜木:それらは、書きながら指摘されながらで覚えたものです。勘もあります。この虚構の中できちんと成り立っていればいい、と思っていました。 でもやはり、乙三の言うことには私の考えも交じっているんです。書きながらいつも「自己憐憫になっていなければいいな」「ちゃんとフィクションになっていればいいな」と思っています。 令央には「これが三人称なのか」と気づく瞬間が訪れますが、私もひとりよがりにならないように気をつけるとどうしても三人称になりますね。主人公一人に偏るのではなく、登場人物の誰を中心に据えても一本の小説にできる状態でないといけない。たとえば令央の別れた夫を中心にしてもお話ができるように、そこにちゃんと光を当てられる状態にしたい。そうでなければ、どこか物語の都合のいいように登場人物を動かしてしまうところが出てくるような気がします。
――乙三はアドバイスは的確ですが、愛想がなく、言い方がものすごく厳しいですよね。強烈です(笑)。
桜木:自分自身もこうしたことを、はっきり言われたいという感覚があります(笑)。はっきり言われないと道を誤ってしまいそうです。 でも、乙三って優しいと思います。これだけ熱意を持ってくれて、逃げずにいてくれる編集者だから、令央のように鈍い書き手にも化学変化が起きる。この二人は砂上という物語において相性がよかったんでしょうね。その過程でどんな闘いがあっても、二人で力を合わせてひとつのものを作り上げた時の喜びというのはとても大きいのでは。
――ここまで小説のことを分かっていて、自分の中に物語を持っている乙三自身も、小説が書けるんじゃないかと思いました。
桜木:いえ、ここまで待つことのできる人は書かないと思います。待てない人が自分で書く。書き手がいいか編集者がいいかと訊かれたら、迷いますけど。編集者って考え方の幅が広いんですよね。視野が広い。私も令央と同じで視野が狭いから、組織に足場を置ける社会性のある人間にあこがれます。書きながら私も乙三に、自分にないものをずっと指摘されていた気がします。
母娘三代 それぞれの生き方
――後半では、柊ミオの波瀾万丈な人生も浮き彫りになってきて、胸を打たれました。
桜木:登場人物はみんな特にモデルはいなくて、ミオについても、書いているうちに「こういう過去があったのか」と分かって自分でもびっくりしました。あの時代にいてもおかしくない人物として書けていればいいんですけれど。ミオの人物造形も、改稿した時に変わったんです。そこに一本通ったものを感じて、やっと一冊の本として刊行できると感じました。母娘の葛藤をもっと際立たせるという案を採っていたら、ミオはもっと嫌な女になっていたかもしれない。それでは私自身が読み返すのが嫌じゃないかと思いました。
――確かに他者との大きな葛藤を乗り越えていくというよりも、令央が自分の内部と向き合って自分自身を獲得していく流れが痛快でもありました。四十歳を過ぎても、人はまだ変わることができるんだ、と思えるのもよかった。
桜木:そうです、人は変われるんです。今回、「人に評価されたいうちは、人を超えない」という言葉を書きましたが、それは私が子ども二人を育てている時に何度も言ってきた言葉ですし、自戒も込めています。今回はその一言が、説教っぽくなく、虚構の中に落とし込めていればいいなと思います。
――これは主体性のなかった令央が、書くということにおいては主体性を獲得していく話でもありますね。
桜木:そうですね。乙三との出会いがもたらしたことですよね。そう思うと、編集者って子どもを育てているみたいですね。小説家は、最初はよちよち歩きだったのが、ようやく一人で立てるようになって……。
―― では桜木さんは、今、小説家としては何歳くらいですか。
桜木:えっ。そんな難しい質問をいきなり(笑)。そうですねえ……。作家になって十年経ったから十歳というわけではないですね。この本の担当編集者の上の息子さんが今三歳で、自作の歌を歌って踊っている動画を見せてもらったんです。自分の思ったことをようやく言葉で表現できるようになった頃。私も今、それくらいかな。ということは、もうすぐイヤイヤ期? 現在、自由にのびのびさせてもらっていますが、編集者はこの後が大変かも(笑)。
――(笑)。ところで、『砂上』というタイトル、最後まで読むとしみじみと意味を噛みしめることになりますね。
桜木:タイトルは先にあったんです。「砂丘が出てくる話がいいよね」という話をしたのがきっかけでした。『砂上』にしたのは、砂の上に先人が遺した跡があって、そこを歩いて行く決意みたいなものが描けたらと思ったからです。ミオも令央も美利も、「私は誰から生まれたとしても私だ」という生き方を、三代そろって選んでいるんですよね。母には母の人生、娘には娘の人生があり、その娘にも娘の人生がある。みんなそれぞれでいい。型にはめずに自分の生き方を選べたら、楽になれると思います。
――今回の作品を書いたことで、新たな達成感があるのではないですか。
桜木:最近、出会った言葉に、〈人は空の下に広がる風景を眺めつつ、過ぎ去った時間に人の世と時代の罪を思ったりするものだ。〉というのがあって。人の世をこの短さの中に盛り込んでくる恐ろしいまでの文の力を感じました。今回の小説は、「空の下に広がる風景」を書けたなと思うし、「過ぎ去った時間」も書けた気がします。ただ、「時代の罪」には大きく触れていない気がするので、いつかそこも感じられるような話を書きたいですね。