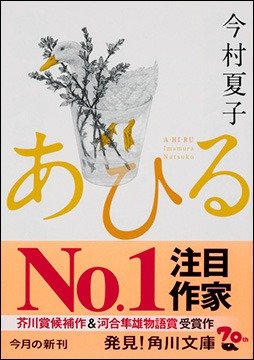6/10(日)より配信開始の「文芸カドカワ」2018年7月号では、西崎憲さんの新連載『ヘディングはおもに頭で』がスタート!
カドブンではこの新連載の試し読みを公開いたします。
大学受験に失敗しアルバイトをして暮らしている松永おんは、ある日、フットサルに出会う。
1 ダンサー・イン・ザ・コート
――なんてことのない、ほんとにおとなしそうなそいつは、けれどコートのなかで宇宙の秩序みたいに動いていた。ボールは自分のほうからそいつの足に向かって走り、理解のできない線を描いて宙に静止し、つぎの瞬間、視界全体が歪むくらいの速さでネットに刺さっていた。目だけになって見ていた自分の頭のなかで、何千人もの人間が拍手した。もちろん自分も一緒に拍手した。そのとき自分は一生そいつみたいにはやれないことを確信した。けどなんだろう、誰かが言ってるような気がした。おまえもやってみろよ。おまえもあそこで踊ってみろよ、と――
鳥はばかだ。
壁がガラスのようになっているビルがあると、そこが空ではないことに気がつかないで、全速力で突っこんで、そのせいで死んでしまう。
ばかだ。鳥のくせに犬死にだ。死ぬ必要がないのに死んでしまうなんて。ゆっくり飛べばいいんだ。
松永おんは弁当屋のアルバイトを終えて、ドトールの縦長の空間の一番奥、トイレの横の席で、レタスドックを食べていた。席はそこしか空いていなかったのだ。そしてそんなことを食べながら考えていた。
鳥の話が頭に残ったのは、それじゃちょっとやりきれないなと思ったからだ。鳥だって親がいて、子供時代があって、兄弟や姉妹がいて、餌のうまいまずいとか、はじめて飛んだ日とか、はじめて交尾した日とかの感動があるはずだ。なのにそんな理由で死んでしまうのはおかしい。
視力が弱い、つまりそういうことなのかもしれない。けどたぶん世のなかには壁が空を映すビルがあって、いつものスピードでそこにぶつかると死ぬってことを鳥が知らないのが問題なのだ。そしてそれを誰も教えてくれないことが。
まったく悲劇的だ。つまりそこには良くなる見こみというものがない。これから未来永劫、鳥にそのことを教える者は現れない。ずっとそういうふうに無駄に死んでいく。
スクールは七時からなのですこし間があった。
永田町のフットサルコートが主催するスクールに通いだして四か月近くになっていた。
スクールは毎週月曜開催で、月に三回は行くので、もう十回以上は通っているはずだった。しかしうまくなっている実感は全然なかった。あいかわらず無駄に興奮してボールを追いかけるだけで、犬や幼児とあまり変わらなかった。ドリブルはできず、速いシュートも打てなかった。
けれどそれはどう考えても当たり前で、何かがうまくなるには時間と努力が必要なのだ。まったくの未経験者が四か月やっただけで人が感心するほどうまくなったらそのほうがおかしい。けれどそうだとしても何か手応えのようなものが欲しかった。自分の手元にはまだ何もなかった。
永田町のスクールには初心者でない人たちもきた。そういう人たちはメニューのあいまにリフティングをしていた。手を使わずに爪先で浮かせてリフティングに入るのが魔法みたいで、でも顔を見るとものすごく普通の人で、特別な才能があるようには見えなかった。自分も間違いなく普通の外見のはずだった。自分はなんでできないんだろう、とおんは思った。
しかしフットサルスクールというのはなんだか特殊なところのように見えた。いままでいたどんな場所にも似ていなかった。何かを習うところというのは、おんは学校しか知らない。経済的な理由でおんは塾にすら行ったことがないし、ピアノを習ったり、英会話を習ったりということもなかった。そのせいで特殊に感じられるのかもしれなかったが、どうもそれだけではない気がした。教えるのがフットサルであること、それに場所が永田町であるというのが、もしかしたらそう感じる原因なのだろうか。
コートは国会議事堂前の駅から歩いて五分ほどの距離の、五階建てビルの屋上にあった。そこは「東京deフットサル」という、どこか無理のある名前の会社が経営しているフットサルコートのひとつで、ほかに五反田や銀座などにあり、おんはそれをインターネットの検索で知った。
四か月というのは短い期間のような気がしたが、そのあいだに色々なことがあった。スクールで経験したことのなかで一番大きかったのは、三回目か四回目にあったことだった。
一回の授業は二時間で、最初の一時間半は基礎的な練習にあてられる。左右の足の内側で小さくキャッチボールするようにして前に運ぶドリブル、ボールの頭をシューズの裏で舐めながら運ぶフットサル特有のドリブル、インサイドつまり足の内側で出す対面パス、足の裏で止める練習。そういう地味な練習がつづく。そして最後の三十分は参加者を五人ずつにわけてのゲームだった。
なんと言ってもゲームが楽しみだったので、おんはとにかくその時間は集中した。まだ何もできなかったけれど、集中の度合いだけは深かった。そしておんはその時間にそれまで知らなかった自分を発見した。
ボールをラインの外に出してしまうと、ボールは相手チームのものになってしまう。その場合はラインのボールが通った位置に相手の選手がボールを置き、蹴りいれて、試合が再開される。位置しだいではゴールに直結することもあるので、どちらがボールを外に出したかはとても重要だった。
自分よりすこし上くらいの女の人とライン際でボールの取りあいになった。ボールは外に出た。コーチが審判を務めるけれど細かい判断を下してくれるわけではなく、どっちがボールを出したかなんてことについては何も言わない。それは自己申告だ。
おんは外に出たボールを拾ってラインの上に置いた。競りあった女の人は怪訝な表情を浮かべておんの顔を見て、口を開きかけた。おんはそれを無視して、ボールを味方に向かって蹴った。
ボールを外に出したのはおんだった。だからボールは当然相手のものだった。けれどおんはそれを知っていて、自分のチームのものにしてしまった。
それほど意識的に不正を働いたことはいままでなかった。
もちろんそれまで正しくないことをした経験がなかったわけではない。親戚の家から従兄弟のおもちゃを持ってきてしまったこともある。友達と一緒に学校の備品を壊したこともあるし、中学生のときには友達と一緒に万引きさえした。けれど高校生になってから正しくないと思われることをしたのは一度もなく、自分は不正なことはしない人間だと思っていた。
しかし違った。自分は最後にボールに触ったのが自分であることを認めず、相手の正当な抗議も無視することのできる人間だった。間違いをごまかして無理矢理押し通せる人間だった。
中学と高校にはいじめがあった。いじめられていたやつを助けはしなかったけれど、加担することはしなかった。だからいままで自分という人間はだいたい正しくて、いい人間だと思ってきた。
けれど、ボールにかんして不正なことをしたとき、それまで思っていた自分の像が、違っていたことに気がついた。決定的に気がついた。
親戚の家からおもちゃを黙って持ってきたとき、自分は明確に盗むということを意識していた。備品を壊したのは友達が一緒だったからではなく、壊すことが楽しかったからだ。何人かで万引きしたときは規則に縛られないことが快感だった。いじめを黙って見ていたのは結局そいつがどうなってもよかったからだ。自分はつまり最初からそういう人間だったのだ。
それに気がついたことでおんは思ったより苦しみ、ラインを割ったボールの件は、心のどこかに常駐するものになった。
フットサルスクールに行くことによって、自分について知ったのがよかったのかどうか、おんは考えた。
フットサルを習うだけのつもりだったし、ただ恥ずかしくないくらいの技術を身につけたかっただけなので、そんなことは望んでいなかった。けれど、それはどちらかと言えばいいことのような気がした。しかしそのとき、もしかしたら正しい人間や正しいことというのは完璧な形では存在しないのではないかとも思った。直感みたいなものがそう言っていた。
女の人が自分を見たときの目は忘れられなかった。もちろんそれは非難の目だったのだけれど、非難だけだったらそんなにはこたえなかったかもしれなかった。目のなかには薄く諦めもあって、その諦めはあとでじわじわと食いこんできた。その人はそれから二度ほど見かけただけで来なくなった。たぶん一生会うこともないだろう。あの人にとって自分はずっと不正にボールを奪った人間になったのだ、とおんは思った。もちろんそれは楽しい考えではなかった。
ただ深刻に悩むまでにはいかなかったこともたしかで、遊んでいて熱中しすぎてそうなっただけだ、という気持ちもどこかにあった。フットサルはただの遊びだからという声が。
(この続きは単行本『ヘディングはおもに頭で』でお楽しみください)
※2020年10月1日発売