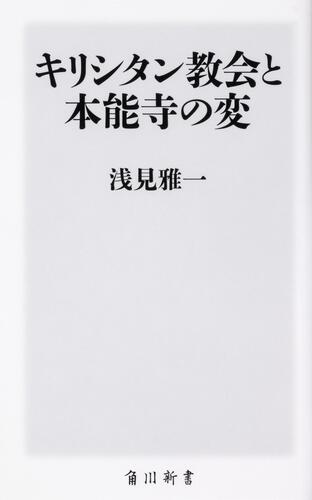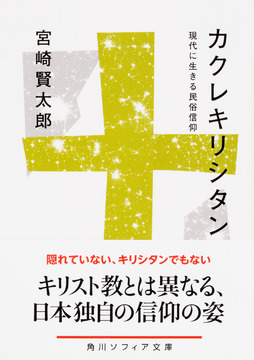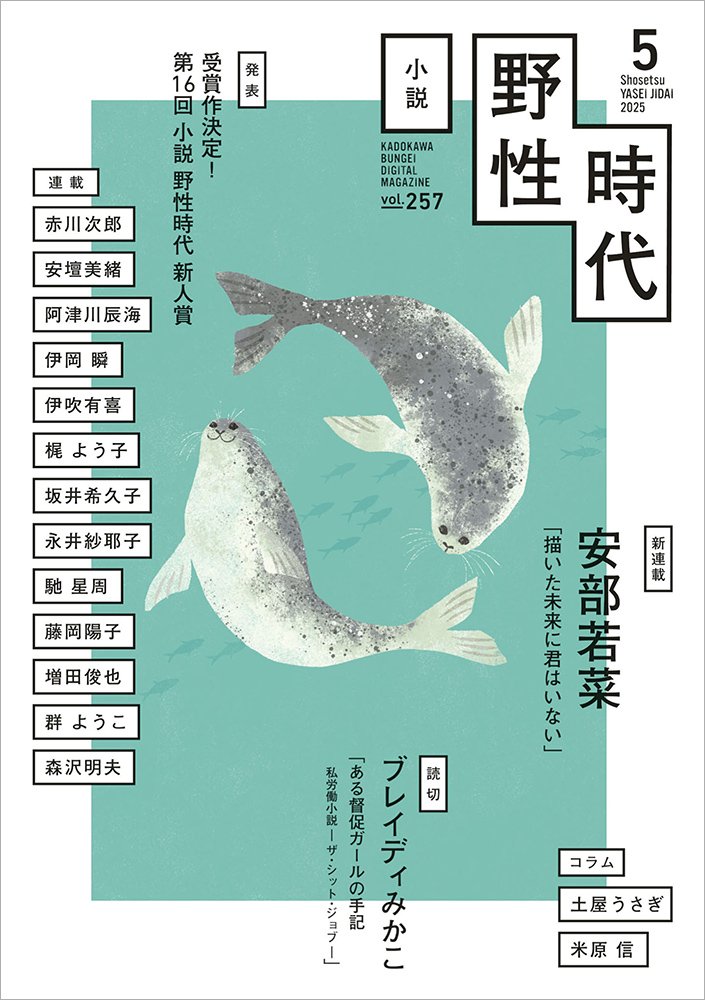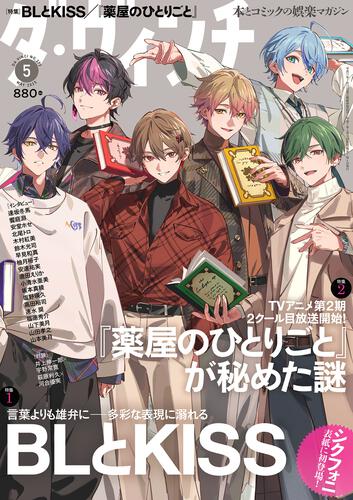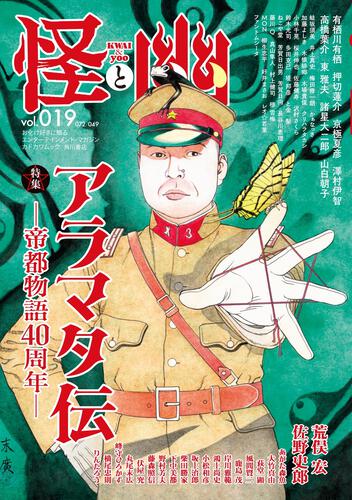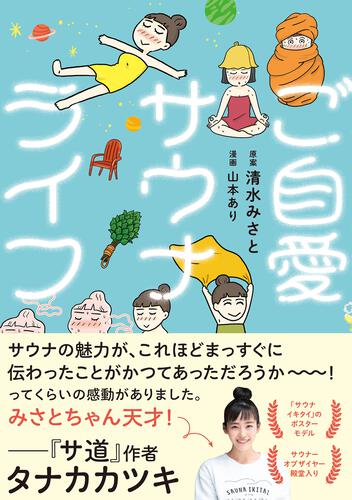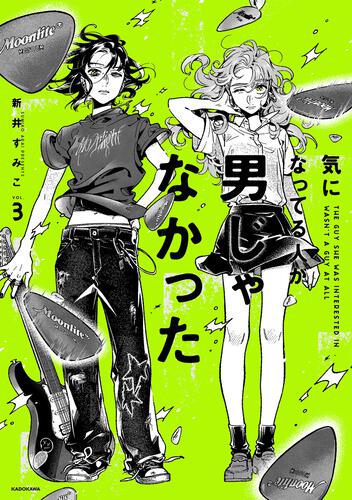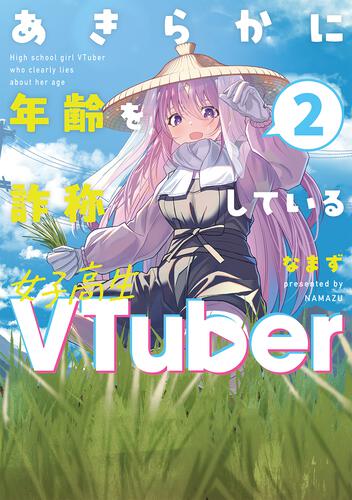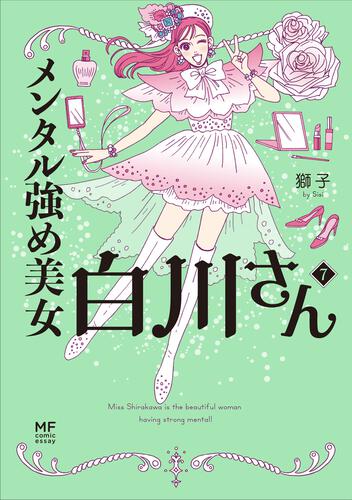日本史における最大のミステリーのひとつが「織田信長はどうして殺されたのか」であることについては、おそらく異論をまたない。2020年5月に刊行された本書『キリシタン教会と本能寺の変』でも、キリシタン史を専門とする著者・浅見雅一が、キリシタン教会側の史料をもとに一説を述べた。
数多い日本側の史料では、裏切り者で謀反人である明智光秀について中立的に書き残すことが難しい。しかし、国内にあってひとつの外国であったキリシタン教会は必ずしもそうではなかった。その史料を再検討することで、著者は光秀が“本能寺の変”を起こした理由は、明智家の存続可否がひとつのカギであるという確信に至った。野心でもなく、怨恨でもない。光秀には確かな危機が存在していたのだ。
では、その危機とは何だったのか。
刊行後、他の研究者と対話する中で、著者は更なる推測を得た。
光秀の謀反を呼び起こしたのは、信長の、ある政策転換だった――
『キリシタン教会と本能寺の変』は、イエズス会のルイス・フロイスが執筆した「信長の死について」(史料編として収録)の分析を通して、本能寺の変に迫ることを試みたものである。同文書からは、キリシタン教会、とりわけニェッキ・ソルド・オルガンティーノと明智家の密接な関係を読み取ることができる。その結果、光秀自身の個人的な問題からではなく、主君信長との関係から明智家の存亡に関わる問題であると光秀が認識し、信長の殺害に至ったものと考えた。このことから、本能寺の変の要因を探るためには、謀反を起こした光秀だけでなく討たれた信長の事情を考察することが必要ではないかと指摘した。
それでは、信長の事情とはいったい何なのか。
「信長の死について」には、信長が最晩年に安土で自己神格化を試みたことが述べられているが、この記事は事実を反映しているものと考えられる。本書で述べたように、信忠の記事との連続性を考慮するならば、信長の自己神格化の記事は当時京都にいたフランシスコ・カリオンの執筆記事を基にしていると考えられる。日本側の史料に同様の記述が確認できないとしても、それだけでこの記事がフロイスの創作であると見なすことは難しい。
同文書には、光秀が低い身分の出身であったにもかかわらず、信長の重臣にまで取り立てられたことが述べられている。周知のように、信長は、家臣に対して実力主義を採用し、出自に関係なく実力次第で取り立てていた。ところが、本能寺の変の直前、信長は、それまで放置に近かった三男の信孝に四国を与えると言って遠征軍の司令官に任命している。このことは実は重要な意味を持つ。信長が親族優遇を始めた兆しがここに見られるのである。光秀が実力主義によって信長に取り立てられたこと、信長が実力主義から親族優遇策に転換したこと、そして信長が自己神格化を試みていること、同文書には、これらの要素がすべて見出されるのである。
「信長の死について」において、信長は、全国統一後に大艦隊を編制して中国大陸の征服に赴き、領地を自分の息子たちに分割支配させるつもりであると述べている。信長自身が親族優遇策への転換を端的に述べているのである。親族優遇策に政策を転換させることは、つまりは織田家の血を引く者を優遇することである。それを人々に納得させるためには、信長自身が天から選ばれた特別な存在でなければならない。自身の親族を重用するためには、織田家の血統が高貴で特別なものであると人々に言明することが必要となる。信長が最晩年に安土で自己神格化を推し進めようとしたのは、その前提であったと考えられる。信長の自己神格化が事実であると判断しない限り、彼の政策転換は説明できないのである。
光秀は、信長の政策の変化をすぐには見抜くことができなかったのであろう。光秀の妹で信長の側室の「御ツマキ」が本能寺の変の前年に病死したことによって、光秀には有力な情報源が消滅してしまったことがその背景にはある(勝俣鎭夫『中世社会の基層をさぐる』山川出版社)。
信長が親族優遇策を進めるためには、それまで功績のあった重臣たちを徐々に排除していく必要がある。その標的となり得る筆頭は恐らく光秀と秀吉である。しかし、天正4年(1576)、秀吉は、信長の子の於次丸を養子に迎えている。のちの羽柴秀勝である。この結果、秀吉は、信長が親族優遇策に移行する以前に信長の親族に連なる形になっていた。他方、光秀には二人の息子がいたので、信長の息子を養子に迎えることには繋がらなかったのであろう。
光秀が、信長の政策転換が自身の排除に繋がると認識したならば、信長と信忠の父子が同時に警備の手薄な状態で京都に宿泊することは、光秀にとって謀反を起こす千載一遇の機会であったことは明らかである。信長は、政策を転換しつつあったとはいえ、重臣たちの処遇は内に秘めておいたつもりであったのだろう。信長が自ら無防備に京都に宿泊したことは油断であったとしか説明できない。
織田家家臣の筆頭であった柴田勝家と滝川一益が信長の政策転換をどのように捉えていたのかは明確ではない。両者ともに信長の親族には連なっていないが、排除される危険性を認識していなかったこともあり得る。
秀吉は、信長の妹の市との結婚を望んでいたが、信長の没後に実際に彼女を娶ることができたのは柴田勝家であった。婚礼は清洲会議後に取り決められたと考えられている。彼女は美人の誉れ高い女性であったが、山本博文氏が指摘するように、秀吉が望んだのはそれだけでなく信長の血統であったと考えられる(山本博文『信長の血統』文春新書)。秀吉は、市の長女の茶々を側室としているが、恐らくそれ以前に信長の娘の三の丸殿を側室としている。
家康は、本書で述べてきたように、光秀に恩義を感じていたと見られる。本能寺の変後、光秀は、家康が直前に京都から堺に移動していたのに彼を追わずに見逃したからである。しかし、実際にはそれだけではない。家康は、長男の松平信康を信長の長女の徳姫と結婚させているが、天正7年(1579)、彼女の訴えによって信康を切腹させることになってしまった。家康には信長の親族に連なる機会が完全に失われていたのである。信長の親族入りを果たすためには婚姻だけでは不安定であったことがわかる。なお、同文書において、家康が信長の義弟とされているのは両者の同盟関係を示すものであろう。
信長が実力主義の官僚制のような形態から自身の周辺を親族で固める方向に転換したとしても、信康を切腹させてしまった家康にはもはや対応する術がない。それどころか、光秀が信長の家臣団から排除されたならば、次の攻撃対象とされる可能性さえある。当時の家康には信長に太刀打ちできるだけの軍事力はない。光秀が信長を討ってくれたおかげで、家康は命拾いしたことに後に気づいたのであろう。
家康は、信長の親族に連なることはできなかったが、実は信長の没後もそれを完全に諦めたわけではない。秀忠は、市の三女の江と結婚している。信長の家臣たちは、彼の死後も織田家の血統を求めているのである。
戦国大名たちは自分たちが清和源氏の流れを汲むことが証明できないので、織田家の血統が新たなブランドになっていたのである。信長の血統は自身の家の存続のために、万一の場合には身の保証になり得るという意識がどこかにあったのかも知れない。こうして、織田家の血筋は支配の正当性を主張できる材料となるだけでなく、新たに生み出された高貴な血筋として定着していったのである。
本書の出版後、知り合いの研究者の方々からご意見やご教示を頂いたことで、本能寺の変について、ある程度まで要因を推測できると考えるに至った。とりわけ、敬愛大学教授の小山幸伸氏と東京大学史料編纂所准教授の松澤克行氏との議論を通して上記を結論づけるに至った。両氏に謝意を表したい。
(2020年6月23日著者執筆)
▼浅見雅一『キリシタン教会と本能寺の変』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)
https://www.kadokawa.co.jp/product/321906000895/