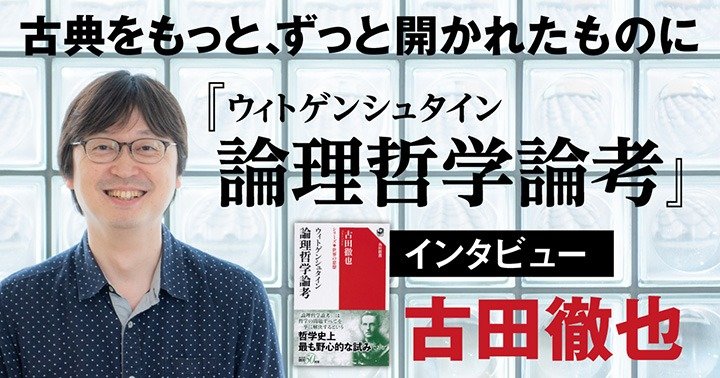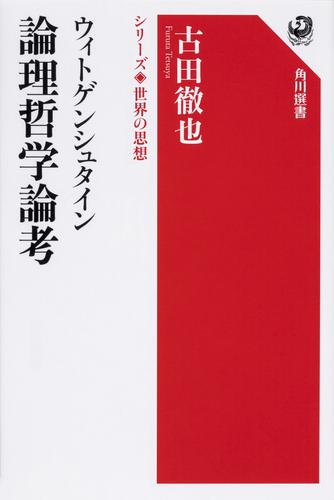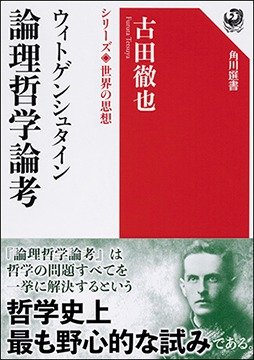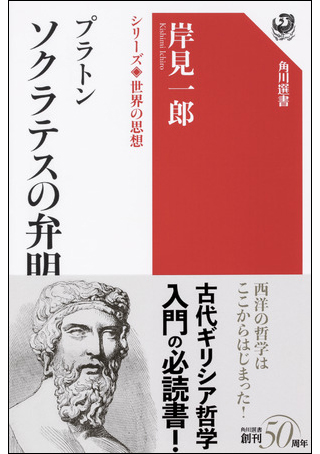哲学の問題すべてを一挙に解決するという、哲学史上最高度に野心的な試み『論理哲学論考』。現代哲学を代表する必読の書とされる一方で、その本文は非常に難解であると言われています。
そこでオススメしたいのが、発売後すぐに「解説が丁寧」「わかりやすい」と大きな評判をよんでいる『ウィトゲンシュタイン 論理哲学論考』。
このたび、この画期的な入門書を書かれた古田徹也先生に、本書の執筆においてどんな苦労や工夫があったのか、さらに、『論理哲学論考』の魅力についてもうかがいました。
(構成:斎藤哲也)
『論理哲学論考』はなぜ難しいのか
――ウィトゲンシュタインの『論理哲学論考』(以下『論考』)は、20世紀以降の哲学に圧倒的な影響を与えた本として知られています。今回古田さんは、原文に即して『論考』を解説する本を書かれたわけですが、どういう読者をイメージしていましたか。
古田:ウィトゲンシュタインの哲学に馴染みがないだけじゃなく、哲学そのものに対してあまり馴染みがない人も読者として想定しました。 「はじめに」にも書いたように、『論考』は、現代哲学の最重要文献に数え入れられる書物です。その知名度もあって、これまでさまざまな人たちが関心を寄せてきた。でも想像するに、『論考』を手に取ってみたけれど、読んですぐに挫折してしまったという人は大勢いると思います。きっと死屍累々の山でしょう。
この本はそういった人たちに向けて書こうと思いましたし、そのイメージがあったからこそ、扱わない部分も明確にすることができました。まずは、この豊かな古典を広く長く開かれたものにしたかった、みんながずっと読めるものにしたかったんです。
――哲学に触れたことがない人が、いきなり『論考』を読むのは難しいんでしょうか。
古田:それは無理だと思います。なぜかというと、『論考』は読むための前提条件が多すぎるからです。まず、フレーゲ以降の新しい論理学の知識をある程度持ってないと正確には読めない部分がけっこうあります。ただ、それを知らなくても、『論考』全体の趣旨を理解することはなんとかできますので、今回の本では扱うのを諦めました。
加えて、構成面の難しさもあります。『論考』は特異な形式で書かれていて、順番に読んでわかるようになっていないんです。たとえば、ある箇所を理解するには、後のほうに出てくる内容を踏まえないといけない。つまり、議論の筋道が一直線ではなく、前後を行ったり来たりしています。
といったって、まずは最初から読むしかないんですが、ともかくいったん最後まで読み、何度も読み返さないと、全体像が見えてこない。『論考』には、そういう独特の読みにくさがあります。
――古田さんの解説パートでは、後の内容を先取りして紹介している箇所が随所にありました。
古田:そうですね。なんとか最初から読んで、見通しがつくようにしたかったので、この本では、かなり後の内容を先取りしたり、前の内容のくわしい解説を後回しにしたりしています。そういう工夫をして、どうにか通常の本を読むのに近い体験ができるように試みたんですけど、実際に書いてみるとほんとに辛かった(笑)。
頭でぼんやり考えてる見通しと、実際に書いて見えるものはずいぶん違う。それが物を書く最大の楽しみではあるものの、この本の場合はやはり誤算の連続でしたから。
――実際にこの本を読んで、いまおっしゃったことも含めて、解説の手さばきに感動しました。抽象的な主張に対する具体例の出し方もすばらしくて。
古田:ありがとうございます。いままで書いた本でも、具体例は意識的に多く出そうとしてきました。それはいくつか考えるところがあって、大学の授業で抽象的な概念の議論だけをしていると、どんどん話が空中戦になって、学生がスーッと引いていくんです。どこかで議論を地上に降ろさないといけない。同時に、哲学の研究者である自分自身も、抽象的な概念の操作をしているとわかった気になってくるんですよね。
でも、哲学的な議論を深く咀嚼しているなら、日常に根づかせて概念を説明することが本当はできるはずです。もしそれができないとしたら、本当に自分がわかっているのかと、怪しんだほうがいい。だから、具体例を多く出すのは読者のためであるだけでなく、自分自身が考えるためでもあるんです。
ただ、『論考』の場合、そもそも具体例の提示自体を拒む概念があるのが難しい。そこは解説する上でも苦労しました。
ガイドの重要性
――執筆する際、どういうスタンスで書こうと考えましたか。
古田:読者が、『論考』全体の構成を理解しながら読み進められる点には配慮しました。そのためには、一貫した筋書きが必要です。だから、『論考』の議論を批判的に検討するというよりも、ウィトゲンシュタインの考えていることを、自分の思う限りの豊かさで汲み取って説明しようとしています。そこが他のウィトゲンシュタインの入門書と最も違う点かもしれません。
――本の冒頭では、前半の内容を理解するまでが一番苦しいと書かれています。「前半部の坂道が最も急で険しく、その後はむしろ緩やかな登りが続く」と。
古田:昨年に九州大学の集中講義で、この本の基本構想を講義しました。そこでもやっぱり、前半の内容を咀嚼してもらうところが難所でした。『論考』はいったい何を議論しているのか、という取っ掛かりがなかなかつかめない。出席してくれた学生と何度もやりとりをしました。
――たしかに『論考』の前半を解説するパートでは、いまどのあたりまで登ってきたか、というコメントが随所に挟まれています。こういうコメントがあると、読者は励まされますね。
古田:それは、編集を担当していただいた麻田さんのアドバイスなんです。初期の原稿では、そういうコメントはもっと少なかったんですよ。
――そうだったんですか。じゃあ、アドバイスに従って後から加筆したんですね。
古田:ええ。増やしてよかったと自分でも思います。私は『論考』をそれこそ何十回も読んでいるので、いまどのあたりまで登ってきたかは自明になってしまっているんですね。でも、はじめて読む人は、いきなり急な坂道が続いて息切れしそうになっているわけですから、いまどのへんまで来ているのか知りたい。
――登山のガイドさんみたいな感じですね(笑)。
古田:正直に言うと、最初はおせっかいじゃないかと思ったんです。ただ、古典を読破する入門書では、ああいうガイドはけっこう大事なんだと認識をあらためました。届いた感想や反応を見ても、つけてよかったと感じています。
ウィトゲンシュタインの魅力
――古田さんにとって、ウィトゲンシュタインを読むことの魅力はどういう点にあるんでしょうか。
古田:大学時代、最初にウィトゲンシュタインを読んだのは、後期の主著とされている『哲学探究』でした。それまで自分がぼんやり考えていたさまざまな問いが大まじめに扱われ、鋭い洞察が書かれている。ちょっとおかしくないかと疑問を持つと、次の節にはその疑問に答えるような内容がある。
読んでいくと、ウィトゲンシュタインと疑似対話している感覚になってくる。それまでとはまったく違う読書体験でした。
『論考』も、『哲学探究』とはスタイルが違いますが、自分の思考が揺さぶられる点では同じです。一節一節にさまざまな意味合いが込められている。それを自分で受け止めて、周囲の節との関係も含めて考えていく。そうやって問いをもって考えることを促してくれるのがウィトゲンシュタインなんです。
――『論考』と『哲学探究』の両方を読んだほうが……
古田:おもしろいと思いますよ。一貫して変わらないところもわかるし、はっきり変わっている点もわかる。
それは、単にウィトゲンシュタイン個人の思想を理解することにとどまらないんですね。二冊を読むと、私たちの世界の捉え方がどういう方向に向かいがちか、ということが理解できる。また、そういう世界像のよさと悪さの両面が見えてくる。
今回の本をKADOKAWAさんにツイッターで宣伝していただいたとき、「一生役立つ知識が身に付きます」とあって、最初はうわっと少し引いたんです。
――「役立つ」とか、簡単に言ってくれるなと。
古田:そうそう。哲学系や人文系の人は「役立つ」という言葉に対するアレルギーがあるじゃないですか。役に立たないのがいいことなんだとか。
でもしばらくして、「一生役立つ」でいいんじゃないか、むしろそう言うべきじゃないかと思い直しました。その都度その都度、ノウハウ的に解決する方法じゃなくて、一生という範囲で文字通り役に立つ。先程申し上げたように、ウィトゲンシュタインを読むと、世界の捉え方の落とし穴もわかるし、意味とか、倫理とか、規範とか、あるいは自分自身とか、一生ずっとついてまわる問題に自分で向き合うための本当に大事なヒントや支えを得られる。それはまさしく一生役立つものなんです。