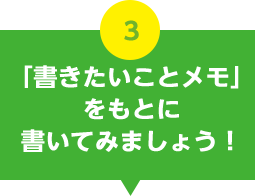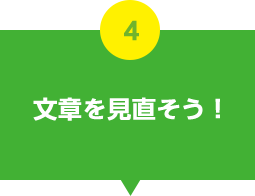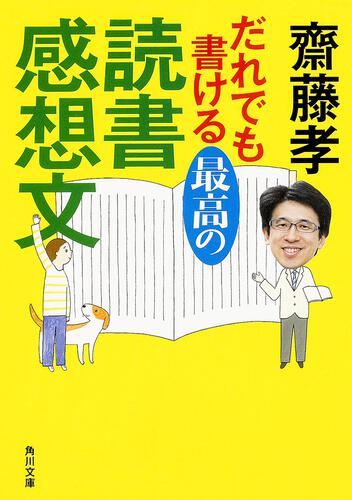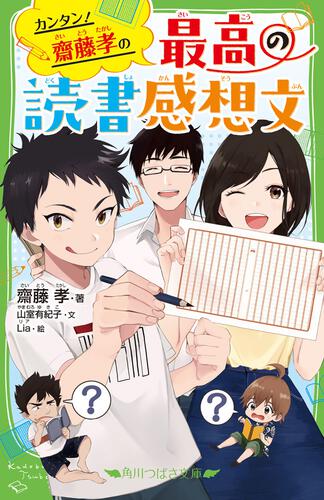超簡単!!
読書感想文をすらすら書く方法
読書感想文なんて簡単だ!
私は国語を専門とする教育学者として、読書の魅力をいたるところで語ってきました。
「本は読んでも読まなくてもいいものではなく、読まなければいけないもの」
「読書なくして人生なし、NO BOOK, NO LIFE!」
私自身はこう強く思っています。
でも、このサイトにきた人には、とにかく本を読むのがニガテだという人、あるいは本は読むのは好きでも、文章の書き方がわからないという人もいるかもしれません。
そんな人たちのためにこのページでは『だれでも書ける最高の読書感想文』(角川文庫)から読書感想文を書くためのヒントをいくつか紹介します。
むずかしい本を選ぶ必要はないし、隅から隅まで読まなくても大丈夫。
感想文は、何をどう書くかだけわかれば、すぐに書けるようになります。
ぜひ本選びから、感想を書くときのポイントまで参考にしてみてください。
そして読書感想文をきっかけに、読書の楽しさ、感想を語る楽しさに気づいてくれるとうれしいです。
「超簡単!! 読書感想文をすらすら書く方法」簡単4ステップ
❶本を選びましょう!
好きなもの、興味があるものが一番!
まずは自分を「その気にさせる」本を選ぶことが大事です。
特別な指定がなければ「好き」や「興味がある」ものを選びましょう。読書感想文の第一歩はとにかく読み通すこと。 スポーツやクラブ活動に参加している人は、それをテーマにした作品を選ぶのもオススメです。主人公、親友、ライバル……登場人物のだれかには感情移入しやすいため、あきずに読むことができるし、自分の体験と重ねあわせながら感想を書くことができます。
短編なら文豪の「名作」を
またとにかく長いものを読むのがニガテ、という人は文豪と呼ばれる大物作家の書いた、短編の「名作」がベストです。長く、多くの人に読まれ続けているものだからハズレがないし、ちょっと難しくても挑戦する意義もあります。
とりわけ日本の文豪ということでは夏目漱石。ぜひ読んでほしいのが『夢十夜』です。全部で文庫本三十ページちょっとしかありませんが、十の夜のほんとに短い不思議な物語が書かれていて、想像力が膨むため感想が書きやすいでしょう。
小説の短編集やエッセイ集を選ぶというのもオススメです。中をパラパラ見て面白そうと思った箇所を重点的に読み、さらにその中のトップ3ぐらいに絞ってなぜ面白いと感じたかを書いてみましょう。
読書感想文におすすめの作品はこちら!
❷「書きたいことメモ」をつくりましょう!
「グッとくるいい言葉」をさがす
感想文を書くためには、読みながら、自分の心にグッときた言葉を拾い出すことが欠かせません。
「この言い方カッコいいなあ」「このセリフ、ジーンときた」と感じたところや、「この文章すごくいいな」と思ったところをさがして、チェックしていきます。本に書き込みをしながら読むのがオススメです。書き込みをするためにも、読書感想文を書くときは図書館の本ではなく、自分で本を買うようにしましょう。
まず箇条書きのメモをつくる
本を読み終わったら、グッときたところをはじめ、気になった箇所をどんどんメモに書き写していきます。そして書き出しながら、思ったこと、感じたこと、書きたいとちょっとでも思ったことをどんどんあげていく。順番は気にせずどんどん書いていく。
全部あげきったら、自分がこの感想文で伝えたいことは何かを考えます。 「感想文に何を書いたらいいかわからない」というのは、何を伝えたいかがはっきりしていないから。そこを考えた上で、抜き出した箇所に①②③と優先順位をふっていきます。
①まず、自分が書きたいことをどんどんあげる。
②その中でもいちばん伝えたいことは何かを考える。
③大事だと思うことに優先順位をつける。
この三つのステップが終わったら六割ぐらいは書けたも同然。
あとはつなげて話の順序を考えていきましょう。
書きたいことは三つに
優先順位をつけるうえでは、伝えたいことや、とりあげたいグッとくる言葉を三つに絞り込むのも大事です。
あれもこれも書きたいとなるとどうしても文章が散漫になって、感想文を読んでくれた人に伝わらないものになってしまいます。
三つに絞るというのは短い感想文でも、長く書くときでも同じ。そしてスピーチなど、人前で話をするときも同じです。ぜひ三を意識して読書に取り組んでください。
❸「書きたいことメモ」をもとに書いてみましょう!
「なぜ」から始めるとスイスイ書ける
読書感想文の書き方に正解はありませんが、いくつかの型はあります。
とりわけ書き出しの一文に悩んでしまうときは、「なぜこの本で感想文を書こうと思ったか」から始めるのがオススメです。
「なぜ○○なのか」「どうして○○なのか」という疑問を自分につきつけて、それに答えていくやり方を「問いを立てる」といいます。文章を書き進めていくときに、問いをたてながら書くと推進力が出てどんどん書けていきます。
まずは「なぜこの本を読もうと思ったのか」「なぜこの本を買おうと思ったのか」そこからはじめてみましょう。
「ビフォー」「アフター」の変化に着目する
どう思ったかだとひとことしか書けない……という人にやってほしいのは、読む前と読んだ後で「自分の心がどう動いたか」「どう変わったか」にポイントを置く書き方です。
人は「くらべる」とものが言いやすいんですね。たとえば一枚の絵があったとして、「これどう思う?」と聞かれてもなかなか答えるのが難しい。けれども、二枚見て「どっちが好き?」「どう好き?」と言われると、どう違うかを元に感想を話すことができます。
・読む前はどういう印象があったか
・読んでみてどうだったか
・ターニングポイントはどこ、あるいは何か
この三段構えを意識すると感想がきちんと書けるようになります。
❹文章を見直そう!
冷めた頭で見直す
文章を書き終えたら終わりではなく、推敲(きちんと見直して日本語の間違いを直したり、より的確な表現をさがしたりすること)は欠かさないようにしましょう。
感想文はあくまで人が読むもの。相手が読んで意味が伝わるか、嫌な気分にならないか……人が読むと言うことを考えながら、いったん頭をクールダウンさせて、冷静なもうひとりの自分の目で読みなおしてみることが必要です。
とくに読書感想文で推敲する時のポイントは三つ。
・感情的になりすぎて、自分にしかわからない表現をしていないか
・だれかを傷つけるような内容になっていないか
・日本語の文章としての誤りはないか
上手な文章が書けなくても、こういうところに注意が払われていれば、まちがいなく良い感想文になります。
-
中高生必見! 読書感想文の課題で困っていませんか?
だれでも書ける最高の読書感想文
-
著者 齋藤孝
-
発売日 2012年6月22日
-
定価 770円(本体700円 + 税)
-
-
もう、読書感想文の宿題だってこわくない!
カンタン! 齋藤孝の 最高の読書感想文
-
著者 齋藤孝文 山室有紀子絵 Lia
-
発売日 2020年6月12日
-
定価 792円(本体720円 + 税)
-
著者プロフィール
齋藤 孝
1960年静岡県生まれ。東京大学法学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士課程等を経て、明治大学文学部教授。専門は教育学、身体論、コミュニケーション論。著書に『だれでも書ける最高の読書感想文』『三色ボールペンで読む日本語』『呼吸入門』(以上、角川文庫)、『語彙力こそが教養である』『三色ボールペン活用術』『不機嫌は罪である』(以上、角川新書)、『原稿用紙10枚を書く力』(だいわ文庫)、『大人のための書く全技術』(KADOKAWA)など多数。